村上春樹「ノルウェイの森」
(5年ほど前に書いた文章です。)
姫路市の西郊に生涯学習大学というのがあって、3年前から、私はそこで「現代文学」の講座を担当している。
年間20コマ、1年生と2年生があるから年間40コマ、これを1回120分ずつ講義するのであるから、結構ハードである。
今年度の2年生のカリキュラムには、1月に、新しく村上春樹「ノルウェイの森」を加えた。
村上春樹は、今や東アジアを加えた、世界の村上春樹であり、ノーベル賞にいちばん近い作家として注目されている。
新しくカリキュラムに加えたのは、こんな重要な作家を講義せずに卒業していただくのは、講師の怠慢だと思ったからである。
なかでも「ノルウェイの森」は、今から20年ほど前、1987年に上下2巻で刊行されて、日本だけで450万部、売れた。
私がはじめて読んだのも、そのときである。
数ある村上春樹作品から、あえてこの長い作品を選んだのは、この作品が最も村上春樹的であり、その文学の本質を明瞭に語っていると考えたからである。
今回、講義の準備のために再読してみると、作品が少しも古びていないどころか、ふたたび、あのときのみずみずしい感動が噴き上げてくるのを経験して、よい気分になった。
それでは、この作品のどこがいいのか。
単行本で刊行されるとき、村上春樹みずから「100パーセントの恋愛小説」とキャッチコピーを選んだ、という。
確かにこの作品は、恋愛小説だといっていい。しかし単純な構造の恋愛小説ではない。
主人公の〈僕〉は17歳のとき、つまり高校生のときに、親友のキズキに死なれた。死の原因はわからない。裕福な家に生まれたキズキは、何一つ不自由なものはなかったはずだった。その彼が車に排気ガスを引きこむという方法で、遺書もなくあの世に行ってしまう。
キズキの恋人が直子で、〈僕〉らは、しばしば3人で一緒に時を過ごした。3人でいる方が気が楽なんだよ、とキズキはいった。
東京の大学に来て、偶然に中央線の電車で直子と〈僕〉は再会する。ふたりは四谷駅で降り、市ヶ谷まで歩きながら話す。
これを機に、2人はデートを重ねる。そして彼女の20歳の誕生日、ケーキを持って彼女のアパートを訪ねた〈僕〉は、彼女と結ばれる。
キズキと直子の仲は長かったから、当然、直子はキズキと寝ているものと〈僕〉は思いこんでいた。ところが直子は、そのときが初めてだった。
直子の話の中に、忘れることのできぬものがある。それは野井戸の話しである。どこかの広々とした草原に、その井戸はある。縁石も何もない井戸で、深い草に覆われているから、誰もそこに井戸のあることに気がつかない。そして落ちてしまう。
落ちたら最後、白骨になっても、誰にも発見されることはないのだ。
この挿話が全編を覆うテーマのように私には思われる。
まもなく直子は心身のバランスを崩して、〈僕〉の前から姿を消す。必死で直子の元の住所――それは、神戸を思わせる海辺の瀟洒な街だ――に手紙を書きつづける彼のもとに、やっとのことで直子から返事が来る。
彼女は、京都の郊外にある深い森の中の療養所で暮らしているのだった。そこで野菜を栽培したり小鳥を飼ったりして、原始生活のような共同生活をしながら、精神の回復を待っているのだった。
直子にはルームメイトがいて、40代のレイコさんという女性だった。彼女もまた深い精神の傷を癒すためにこの療養所に入っているのだが、彼女はかつてピアニストを目指していただけあって、今もギターを弾いたり教えたりしている。
その療養所を〈僕〉が訪れて3人で過ごす日々は美しい。
レイコさんは直子のよきパートナーであり、先輩であり、しかも彼女自身、自分の傷を抱えて生きているのだ。
東京に帰った〈僕〉は、頼まれたまま、せっせと二人に手紙を書く。そしてその手紙は、確かに2人の精神生活をよい方に導いた。
にもかかわらず、最後に直子は決然と死を選ぶのだ。
その死のあと、レイコさんは療養所を出て、北海道の旭川で生き直そうと決心し、途中、東京の〈僕〉を訪ねる。
その夜、レイコさんはある限りの曲をギターで弾き、それの終わった後、〈僕〉とセックスする。これも、とても美しく描かれている。人生に1度でも、このようなセックスを経験すれば、それを力に、そのあとの人生を生きていける、というような、みちたりたものだ。
この作品には、私立大学で演劇学を学ぶ〈僕〉と講義で一緒になる、ミドリという面白い女性も登場して、読者を愉快にしてくれる。彼女はセックスについて奔放な考えを持っていて、それをいちいち口にするのだ。女の子の話を素直に聞き入れる〈僕〉は、悲惨な家庭状況にあった彼女をも救いだす。
このほか、東大法学部に学ぶスーパーマンのような長沢さんという先輩と、その恋人ハツミさんなど、魅力的な人物が登場して物語を豊かなものにしてくれる。
しかし結局のところ、〈僕〉は直子を愛しながら、彼女を救いだすことはできなかった。この物語は、深い喪失感を抱えた人たちの、回復をもとめる物語であるといえるだろう。
村上春樹は今や、中国においてさえその作品名「海辺のカフカ」という喫茶店が出現するほどに読まれ、圧倒的に支持されているという。
村上作品の登場人物たちは、1面で、団塊の世代の、醒めた、アメリカナイズされた生活――着るもの、食事、アルコール、性についての自由な意識――の実践者でもある。筆者など、この世代とわずかに5、6歳ちがうだけだが、まったく彼らを新しいと思う。
そのような新しいライフスタイルや風俗をも自然に描きこんでいるので、それが世界中の若者たちに受け入れられるのだろう。
もう1つの要因は、主人公がやさしく親切だ、ということだろう。こんなによく気がつき、女の子にやさしい言葉をかけてくれる男の子は、村上春樹作品のなか以外では、そうお目にかかることができないと思われるからである。
(5年ほど前に書いた文章です。)
姫路市の西郊に生涯学習大学というのがあって、3年前から、私はそこで「現代文学」の講座を担当している。
年間20コマ、1年生と2年生があるから年間40コマ、これを1回120分ずつ講義するのであるから、結構ハードである。
今年度の2年生のカリキュラムには、1月に、新しく村上春樹「ノルウェイの森」を加えた。
村上春樹は、今や東アジアを加えた、世界の村上春樹であり、ノーベル賞にいちばん近い作家として注目されている。
新しくカリキュラムに加えたのは、こんな重要な作家を講義せずに卒業していただくのは、講師の怠慢だと思ったからである。
なかでも「ノルウェイの森」は、今から20年ほど前、1987年に上下2巻で刊行されて、日本だけで450万部、売れた。
私がはじめて読んだのも、そのときである。
数ある村上春樹作品から、あえてこの長い作品を選んだのは、この作品が最も村上春樹的であり、その文学の本質を明瞭に語っていると考えたからである。
今回、講義の準備のために再読してみると、作品が少しも古びていないどころか、ふたたび、あのときのみずみずしい感動が噴き上げてくるのを経験して、よい気分になった。
それでは、この作品のどこがいいのか。
単行本で刊行されるとき、村上春樹みずから「100パーセントの恋愛小説」とキャッチコピーを選んだ、という。
確かにこの作品は、恋愛小説だといっていい。しかし単純な構造の恋愛小説ではない。
主人公の〈僕〉は17歳のとき、つまり高校生のときに、親友のキズキに死なれた。死の原因はわからない。裕福な家に生まれたキズキは、何一つ不自由なものはなかったはずだった。その彼が車に排気ガスを引きこむという方法で、遺書もなくあの世に行ってしまう。
キズキの恋人が直子で、〈僕〉らは、しばしば3人で一緒に時を過ごした。3人でいる方が気が楽なんだよ、とキズキはいった。
東京の大学に来て、偶然に中央線の電車で直子と〈僕〉は再会する。ふたりは四谷駅で降り、市ヶ谷まで歩きながら話す。
これを機に、2人はデートを重ねる。そして彼女の20歳の誕生日、ケーキを持って彼女のアパートを訪ねた〈僕〉は、彼女と結ばれる。
キズキと直子の仲は長かったから、当然、直子はキズキと寝ているものと〈僕〉は思いこんでいた。ところが直子は、そのときが初めてだった。
直子の話の中に、忘れることのできぬものがある。それは野井戸の話しである。どこかの広々とした草原に、その井戸はある。縁石も何もない井戸で、深い草に覆われているから、誰もそこに井戸のあることに気がつかない。そして落ちてしまう。
落ちたら最後、白骨になっても、誰にも発見されることはないのだ。
この挿話が全編を覆うテーマのように私には思われる。
まもなく直子は心身のバランスを崩して、〈僕〉の前から姿を消す。必死で直子の元の住所――それは、神戸を思わせる海辺の瀟洒な街だ――に手紙を書きつづける彼のもとに、やっとのことで直子から返事が来る。
彼女は、京都の郊外にある深い森の中の療養所で暮らしているのだった。そこで野菜を栽培したり小鳥を飼ったりして、原始生活のような共同生活をしながら、精神の回復を待っているのだった。
直子にはルームメイトがいて、40代のレイコさんという女性だった。彼女もまた深い精神の傷を癒すためにこの療養所に入っているのだが、彼女はかつてピアニストを目指していただけあって、今もギターを弾いたり教えたりしている。
その療養所を〈僕〉が訪れて3人で過ごす日々は美しい。
レイコさんは直子のよきパートナーであり、先輩であり、しかも彼女自身、自分の傷を抱えて生きているのだ。
東京に帰った〈僕〉は、頼まれたまま、せっせと二人に手紙を書く。そしてその手紙は、確かに2人の精神生活をよい方に導いた。
にもかかわらず、最後に直子は決然と死を選ぶのだ。
その死のあと、レイコさんは療養所を出て、北海道の旭川で生き直そうと決心し、途中、東京の〈僕〉を訪ねる。
その夜、レイコさんはある限りの曲をギターで弾き、それの終わった後、〈僕〉とセックスする。これも、とても美しく描かれている。人生に1度でも、このようなセックスを経験すれば、それを力に、そのあとの人生を生きていける、というような、みちたりたものだ。
この作品には、私立大学で演劇学を学ぶ〈僕〉と講義で一緒になる、ミドリという面白い女性も登場して、読者を愉快にしてくれる。彼女はセックスについて奔放な考えを持っていて、それをいちいち口にするのだ。女の子の話を素直に聞き入れる〈僕〉は、悲惨な家庭状況にあった彼女をも救いだす。
このほか、東大法学部に学ぶスーパーマンのような長沢さんという先輩と、その恋人ハツミさんなど、魅力的な人物が登場して物語を豊かなものにしてくれる。
しかし結局のところ、〈僕〉は直子を愛しながら、彼女を救いだすことはできなかった。この物語は、深い喪失感を抱えた人たちの、回復をもとめる物語であるといえるだろう。
村上春樹は今や、中国においてさえその作品名「海辺のカフカ」という喫茶店が出現するほどに読まれ、圧倒的に支持されているという。
村上作品の登場人物たちは、1面で、団塊の世代の、醒めた、アメリカナイズされた生活――着るもの、食事、アルコール、性についての自由な意識――の実践者でもある。筆者など、この世代とわずかに5、6歳ちがうだけだが、まったく彼らを新しいと思う。
そのような新しいライフスタイルや風俗をも自然に描きこんでいるので、それが世界中の若者たちに受け入れられるのだろう。
もう1つの要因は、主人公がやさしく親切だ、ということだろう。こんなによく気がつき、女の子にやさしい言葉をかけてくれる男の子は、村上春樹作品のなか以外では、そうお目にかかることができないと思われるからである。












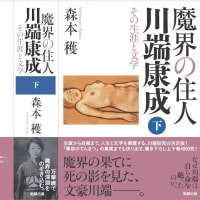
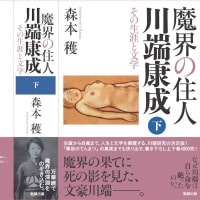

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます