愛のゆくえ「雪国」 その11
「天の河」の構想
「雪中火事」の続編「天の河」は、それから8ヶ月たった1941(昭和16)年8月に、『文藝春秋』に発表された。
「雪中火事」の終わりでふと2行、天の河が描かれる。
「天の川、きれいねえ。」と駒子はつぶやきながら、また走り出した。
島村は空を見上げたまま立つてゐた。
「天の河」は、これを受けて書き出されている。
康成がおそらく渾身(こんしん)の力をこめて観察したに違いない天の河の描写が、描かれる。
ああ、天の河と、島村も振り仰いだとたんに、天の河のなかへ體(からだ)がすつと浮き上つてゆくやうだつた。天の河の明るさが島村を掬(すく)ひ上げさうに近かつた。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このやうにあざやかな天の河の大きさであつたか。裸の天の河が夜の大地を素肌で巻かうとして、直ぐそこに降りてきてゐる。恐ろしい艶(つや)めかしさだ。
康成はここで、芭蕉が佐渡を詠んだ一句の大きさを思い出している。
荒海や佐渡に横たふ天の河
荒海を前景として、眼前に黒々と横たわる佐渡の島。その海と島のすべてを巻くように、全天に拡がる冴えわたった天の河――。
康成が島村に託して描いた、巨大な、荒々しい、それでいて艶めかしい天の河こそ、卑小な人間世界と対比される自然の広大さであった。
「ねえ、あんた私をいい女だつて言つたわね。行つちやふ人がなぜそんなこと言つて、教へとくの? 馬鹿。」
女のあたたかい哀しみが島村を絞めつけた。
「泣いたわ。離れるのこはいわ。だけどもう早く行きなさい。言はれて泣いたこと、私忘れないから。」
人間の世界の、小さな、だが何と一生懸命な、美しい言葉だろう。
この篇は、次の行によって終わりを告げる。
島村も新しい火の手に眼を誘はれて、その上に横たはる天の河を見た。天の河は静かに冴え渡つてゐた。豊かなやさしさもこめて、天に広々と流れてゐた。
ここで「天の河」、すなわち追加された「雪国」は結ばれる。素人にも、平凡すぎる終幕と思われる。
「雪国抄」「続雪国」
以上2編が発表されたのは、まだ太平洋戦争開戦以前の1940、41(昭和15、16)年のことであった。
それから5年後の1946(昭和21)年、戦争も終わった敗残の国土のなかで、康成は三たび筆をとって、「雪国」の続編を新しく書き直して発表した。
「雪国抄」は、『暁鐘』1946年5月号に発表された。
「雪国抄」の、冒頭は、『北越雪譜』を踏まえて、「雪中火事」と、ほとんど同文である。ただ途中から、引用部分を大幅に削って、引き締まった文章となっている。
また「雪中火事」で引用した、作品の核となる部分は、彫琢(ちょうたく)されて、珠玉のような名文へと変貌している。
妻子のうちへ帰るのも忘れたやうな長逗留だつた。離れられないからでも別れともないからでもないが、駒子のしげしげ会ひに来るのを待つ癖になつてしまつてゐた。さうして駒子がせつなく迫つて来れば来るほど、島村は自分が生きていないかのやうな呵責がつのつた。いはば自分のさびしさを見ながら、ただぢつとたたづんでゐるのだつた。駒子が自分のなかにはまりこんで来るのが、島村は不可解だつた。駒子のすべてが島村に通じて来るのに、島村のなにも駒子には通じてゐさうにない。駒子が虚しい壁に突きあたる木霊に似た音を島村は自分の胸の底に雪が降りつむやうに聞いた。このやうな島村のわがままはいつまでも続けられるものではなかつた。
こんど帰つたらもうかりそめにこの温泉場へは来られないだらうといふ気がして、島村は雪の季節が近づく火鉢によりかかつてゐると、宿の主人が特に出してきてくれた京出来の古い鐵瓶(てつびん)で、やはらかい松風の音がしてゐた。(中略)
島村は鐵瓶に耳を寄せてその鈴の音を聞いた。鈴の鳴りしきるあたりの遠くに鈴の音にほど小刻みに歩いて来る駒子の小さい足が、ふと島村に見えた。島村は驚いて、最早ここを去らねばならぬと心立つた。
そこで島村は縮の産地へ行つてみることを思ひついた。この温泉場から離れるはずみをつけるつもりもあつた。
島村は汽車に乗って、さびしそうな駅に降りる。そうして雁木(がんぎ)の連なる、昔の宿場町らしい町通りを歩いて、また汽車に乗る。もう1つの町に降りる。寒さしのぎにうどんを1杯すすって、また汽車に乗り、駒子の町に帰ってくる。
車に乗って宿に帰ってゆこうとすると、小料理屋菊村の門口で立ち話をしている一人が駒子だった。
駒子は徐行した車に飛び乗って、窓ガラスに額を押しつけながら、「どこへ行った? ねえ、どこへ行った?」と甲高く叫ぶ。
「どうして私を連れて行かないの? 冷たくなつて来て、いやよ。」
突然擦り半鐘(すりはんしょう)が鳴り出した。
二人が振り向くと、
「火事、火事よ!」
「火事だ。」
火の手が下の村の真中にあがつてゐた。
「雪国抄」は作品が長くなって、「雪中火事」では、火事の発端だけだったのが、もう少しつづけて書いてある。
作品の終わりに、作者の言葉がある。
――10年前の旧作「雪国」は終章を未完のまま刊行し、折節気にかかつてゐたが、ここにとにかく稿を続けてみることにした。既稿の分も改稿して発表し得たのは本誌編輯者の雅量による。作者――
「続雪国」の新展開
つづけて、1年あまりを経た1947(昭和22)年10月、『小説新潮』に最終篇「続雪国」が発表された。
火事のつづきである。繭倉(まゆぐら)で映画のあったことがわかって、駒子のあとを追って島村も繭倉の方へ駆け出す。
「天の河。きれいねえ。」という駒子の声に誘われて、島村は空を見上げる。
1941(昭和16)年の「天の河」と同じく、芭蕉の見た天の河を連想する。
しかし次がこれまでと異なる。
あつと人垣が息を呑んで、女の體が落ちるのを見た。
やがて、それが失心(ママ)した葉子だとわかる。
――10年を経て、康成は葉子の失心と墜落という、物語の新しい展開、物語のフィナーレを思いついたのだ。
葉子はあの刺すやうに美しい目をつぶつてゐた。あごを突き出して、首の線が伸びてゐた。火明りが青白い面の上を揺れて通つた。
幾年か前、島村がこの温泉場へ駒子に会ひに来る汽車のなかで、葉子の顔のただなかに野山のともし火がともつた時のさまをはつと思ひ出して、島村はまた胸が顫へた。一瞬に駒子との年月が照し出されたやうだつた。なにかせつない苦痛と悲哀もここにあつた。
「幾年か前」という表現に注意したい。島村が葉子を初めて見たのは、2度めの旅、12月だった。3度めの旅は、それから10ヶ月後の10月から、この冬まで。長逗留で、今が1月とも2月とも判別しがたいが、いずれにしても、葉子を初めて見てから今まで、1年とちょっとである。
「雪国」の正確な年立(としだて)という問題からみれば、ここは明らかに作家の錯誤である。
だが、そうだろうか。
この濃密で緊張感にみちた島村と駒子の愛を読んできた読者には、ふたりの仲は3年にも4年にも、あるいは5年にも感じられる。
その読者の錯誤を考えると、ここは正確に「一年ちょっと前」と書いてはならないのである。「幾年か前」と朧化(ろうか)されることによってはじめて、島村と駒子の、のっぴきならぬ愛情の積み重ねが読者に納得させられるのだ。
もう1つ大切な部分は、「一瞬に駒子との年月が照し出されたやうだつた。」とある一行である。
「雪国」という作品にとって、葉子は重要な存在である。3度めの旅の紅葉の季節には、葉子は「東京に連れて行つてください」と島村に頼み、島村もこの「得体の知れない娘と駆け落ちのやうに東京へ帰る」ことは、駒子への最大の謝罪だと考えた瞬間もあった。
そのように葉子は、島村と駒子のあいだにあって、駒子と島村の愛の成り行きを、刺すような美しい目で、じっと観察する存在としても考えられた。
島村はいま、失心した葉子を見ながら、初めて葉子と会ったとき、汽車の夕景色の流れの中に映った、葉子の顔のなかにともったともし火を思い浮かべている。あれからの歳月、それは駒子と過ごした歳月でもあったのだ。
島村の内部に「なにかせつない苦痛と悲哀」が湧き上がるのに、何の不思議もない。
葉子の失心と墜落というアイデアが、駒子との歳月を写し出す鏡のような葉子の役割を、ふたたび思い出させたのである。
「この子、気がちがふわ。気がちがふわ。」
さう言ふ声が物狂はしい駒子に島村は近づかうとして、葉子 を駒子から抱き取らうとする男達に押されてよろめいた。
さあつと音を立てて天の河が島村のなかへ流れて来た。
康成は、最後に推敲して単行本にするとき、この最後の部分を、次のように改変した。
「この子、気がちがふわ。気がちがふわ。」
さう言ふ声が物狂はしい駒子に島村は近づかうとして、葉子を駒子から抱き取らうとする男達に押されてよろめいた。踏みこたへて目を上げた途端、さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるやうであつた。
この最後の場面は、長い物語の終焉として、まことに劇的なものであろう。
駒子の愛の高まりと、それを受けとめる島村の追いつめられた意識が、物語の最後近くで、どうにも身動きできない状況になる。
島村が、この雪国を去るしか、とるべき道は残されていないのである。
物語のフィナーレに火事が起こり、その火事という非日常的な出来事の喧噪をはるかに見下ろすように、すべての人々を包み込むような壮麗な天の河が天空いっぱいに広がる。それに気づいた島村に流れ落ちるかと思われて、物語は結ばれる。
伊藤整は、新潮文庫『雪国』の解説(1947〈昭和22〉・7・16)において、次のように作品の終幕の必然性を説いている。
生きることに切羽つまつてゐる女と、その切羽詰りかたの美しさに触れて戦(をのの)いてゐる島村の感覚との対立が、次第に悲劇的な結末をこの作品の進行過程に生んで行く。そしてその過程が美の抽出に耐へられない暗さになる前でこの作品は終らねばならぬ運命を持つてゐるのである。
――11年間にわたる、康成の格闘がここに終わった。
この「雪国抄」「続雪国」の2編にさらに彫琢を加えて、1948(昭和23)年12月25日、創元社から〈決定版『雪国』〉が刊行される。
「天の河」の構想
「雪中火事」の続編「天の河」は、それから8ヶ月たった1941(昭和16)年8月に、『文藝春秋』に発表された。
「雪中火事」の終わりでふと2行、天の河が描かれる。
「天の川、きれいねえ。」と駒子はつぶやきながら、また走り出した。
島村は空を見上げたまま立つてゐた。
「天の河」は、これを受けて書き出されている。
康成がおそらく渾身(こんしん)の力をこめて観察したに違いない天の河の描写が、描かれる。
ああ、天の河と、島村も振り仰いだとたんに、天の河のなかへ體(からだ)がすつと浮き上つてゆくやうだつた。天の河の明るさが島村を掬(すく)ひ上げさうに近かつた。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このやうにあざやかな天の河の大きさであつたか。裸の天の河が夜の大地を素肌で巻かうとして、直ぐそこに降りてきてゐる。恐ろしい艶(つや)めかしさだ。
康成はここで、芭蕉が佐渡を詠んだ一句の大きさを思い出している。
荒海や佐渡に横たふ天の河
荒海を前景として、眼前に黒々と横たわる佐渡の島。その海と島のすべてを巻くように、全天に拡がる冴えわたった天の河――。
康成が島村に託して描いた、巨大な、荒々しい、それでいて艶めかしい天の河こそ、卑小な人間世界と対比される自然の広大さであった。
「ねえ、あんた私をいい女だつて言つたわね。行つちやふ人がなぜそんなこと言つて、教へとくの? 馬鹿。」
女のあたたかい哀しみが島村を絞めつけた。
「泣いたわ。離れるのこはいわ。だけどもう早く行きなさい。言はれて泣いたこと、私忘れないから。」
人間の世界の、小さな、だが何と一生懸命な、美しい言葉だろう。
この篇は、次の行によって終わりを告げる。
島村も新しい火の手に眼を誘はれて、その上に横たはる天の河を見た。天の河は静かに冴え渡つてゐた。豊かなやさしさもこめて、天に広々と流れてゐた。
ここで「天の河」、すなわち追加された「雪国」は結ばれる。素人にも、平凡すぎる終幕と思われる。
「雪国抄」「続雪国」
以上2編が発表されたのは、まだ太平洋戦争開戦以前の1940、41(昭和15、16)年のことであった。
それから5年後の1946(昭和21)年、戦争も終わった敗残の国土のなかで、康成は三たび筆をとって、「雪国」の続編を新しく書き直して発表した。
「雪国抄」は、『暁鐘』1946年5月号に発表された。
「雪国抄」の、冒頭は、『北越雪譜』を踏まえて、「雪中火事」と、ほとんど同文である。ただ途中から、引用部分を大幅に削って、引き締まった文章となっている。
また「雪中火事」で引用した、作品の核となる部分は、彫琢(ちょうたく)されて、珠玉のような名文へと変貌している。
妻子のうちへ帰るのも忘れたやうな長逗留だつた。離れられないからでも別れともないからでもないが、駒子のしげしげ会ひに来るのを待つ癖になつてしまつてゐた。さうして駒子がせつなく迫つて来れば来るほど、島村は自分が生きていないかのやうな呵責がつのつた。いはば自分のさびしさを見ながら、ただぢつとたたづんでゐるのだつた。駒子が自分のなかにはまりこんで来るのが、島村は不可解だつた。駒子のすべてが島村に通じて来るのに、島村のなにも駒子には通じてゐさうにない。駒子が虚しい壁に突きあたる木霊に似た音を島村は自分の胸の底に雪が降りつむやうに聞いた。このやうな島村のわがままはいつまでも続けられるものではなかつた。
こんど帰つたらもうかりそめにこの温泉場へは来られないだらうといふ気がして、島村は雪の季節が近づく火鉢によりかかつてゐると、宿の主人が特に出してきてくれた京出来の古い鐵瓶(てつびん)で、やはらかい松風の音がしてゐた。(中略)
島村は鐵瓶に耳を寄せてその鈴の音を聞いた。鈴の鳴りしきるあたりの遠くに鈴の音にほど小刻みに歩いて来る駒子の小さい足が、ふと島村に見えた。島村は驚いて、最早ここを去らねばならぬと心立つた。
そこで島村は縮の産地へ行つてみることを思ひついた。この温泉場から離れるはずみをつけるつもりもあつた。
島村は汽車に乗って、さびしそうな駅に降りる。そうして雁木(がんぎ)の連なる、昔の宿場町らしい町通りを歩いて、また汽車に乗る。もう1つの町に降りる。寒さしのぎにうどんを1杯すすって、また汽車に乗り、駒子の町に帰ってくる。
車に乗って宿に帰ってゆこうとすると、小料理屋菊村の門口で立ち話をしている一人が駒子だった。
駒子は徐行した車に飛び乗って、窓ガラスに額を押しつけながら、「どこへ行った? ねえ、どこへ行った?」と甲高く叫ぶ。
「どうして私を連れて行かないの? 冷たくなつて来て、いやよ。」
突然擦り半鐘(すりはんしょう)が鳴り出した。
二人が振り向くと、
「火事、火事よ!」
「火事だ。」
火の手が下の村の真中にあがつてゐた。
「雪国抄」は作品が長くなって、「雪中火事」では、火事の発端だけだったのが、もう少しつづけて書いてある。
作品の終わりに、作者の言葉がある。
――10年前の旧作「雪国」は終章を未完のまま刊行し、折節気にかかつてゐたが、ここにとにかく稿を続けてみることにした。既稿の分も改稿して発表し得たのは本誌編輯者の雅量による。作者――
「続雪国」の新展開
つづけて、1年あまりを経た1947(昭和22)年10月、『小説新潮』に最終篇「続雪国」が発表された。
火事のつづきである。繭倉(まゆぐら)で映画のあったことがわかって、駒子のあとを追って島村も繭倉の方へ駆け出す。
「天の河。きれいねえ。」という駒子の声に誘われて、島村は空を見上げる。
1941(昭和16)年の「天の河」と同じく、芭蕉の見た天の河を連想する。
しかし次がこれまでと異なる。
あつと人垣が息を呑んで、女の體が落ちるのを見た。
やがて、それが失心(ママ)した葉子だとわかる。
――10年を経て、康成は葉子の失心と墜落という、物語の新しい展開、物語のフィナーレを思いついたのだ。
葉子はあの刺すやうに美しい目をつぶつてゐた。あごを突き出して、首の線が伸びてゐた。火明りが青白い面の上を揺れて通つた。
幾年か前、島村がこの温泉場へ駒子に会ひに来る汽車のなかで、葉子の顔のただなかに野山のともし火がともつた時のさまをはつと思ひ出して、島村はまた胸が顫へた。一瞬に駒子との年月が照し出されたやうだつた。なにかせつない苦痛と悲哀もここにあつた。
「幾年か前」という表現に注意したい。島村が葉子を初めて見たのは、2度めの旅、12月だった。3度めの旅は、それから10ヶ月後の10月から、この冬まで。長逗留で、今が1月とも2月とも判別しがたいが、いずれにしても、葉子を初めて見てから今まで、1年とちょっとである。
「雪国」の正確な年立(としだて)という問題からみれば、ここは明らかに作家の錯誤である。
だが、そうだろうか。
この濃密で緊張感にみちた島村と駒子の愛を読んできた読者には、ふたりの仲は3年にも4年にも、あるいは5年にも感じられる。
その読者の錯誤を考えると、ここは正確に「一年ちょっと前」と書いてはならないのである。「幾年か前」と朧化(ろうか)されることによってはじめて、島村と駒子の、のっぴきならぬ愛情の積み重ねが読者に納得させられるのだ。
もう1つ大切な部分は、「一瞬に駒子との年月が照し出されたやうだつた。」とある一行である。
「雪国」という作品にとって、葉子は重要な存在である。3度めの旅の紅葉の季節には、葉子は「東京に連れて行つてください」と島村に頼み、島村もこの「得体の知れない娘と駆け落ちのやうに東京へ帰る」ことは、駒子への最大の謝罪だと考えた瞬間もあった。
そのように葉子は、島村と駒子のあいだにあって、駒子と島村の愛の成り行きを、刺すような美しい目で、じっと観察する存在としても考えられた。
島村はいま、失心した葉子を見ながら、初めて葉子と会ったとき、汽車の夕景色の流れの中に映った、葉子の顔のなかにともったともし火を思い浮かべている。あれからの歳月、それは駒子と過ごした歳月でもあったのだ。
島村の内部に「なにかせつない苦痛と悲哀」が湧き上がるのに、何の不思議もない。
葉子の失心と墜落というアイデアが、駒子との歳月を写し出す鏡のような葉子の役割を、ふたたび思い出させたのである。
「この子、気がちがふわ。気がちがふわ。」
さう言ふ声が物狂はしい駒子に島村は近づかうとして、葉子 を駒子から抱き取らうとする男達に押されてよろめいた。
さあつと音を立てて天の河が島村のなかへ流れて来た。
康成は、最後に推敲して単行本にするとき、この最後の部分を、次のように改変した。
「この子、気がちがふわ。気がちがふわ。」
さう言ふ声が物狂はしい駒子に島村は近づかうとして、葉子を駒子から抱き取らうとする男達に押されてよろめいた。踏みこたへて目を上げた途端、さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるやうであつた。
この最後の場面は、長い物語の終焉として、まことに劇的なものであろう。
駒子の愛の高まりと、それを受けとめる島村の追いつめられた意識が、物語の最後近くで、どうにも身動きできない状況になる。
島村が、この雪国を去るしか、とるべき道は残されていないのである。
物語のフィナーレに火事が起こり、その火事という非日常的な出来事の喧噪をはるかに見下ろすように、すべての人々を包み込むような壮麗な天の河が天空いっぱいに広がる。それに気づいた島村に流れ落ちるかと思われて、物語は結ばれる。
伊藤整は、新潮文庫『雪国』の解説(1947〈昭和22〉・7・16)において、次のように作品の終幕の必然性を説いている。
生きることに切羽つまつてゐる女と、その切羽詰りかたの美しさに触れて戦(をのの)いてゐる島村の感覚との対立が、次第に悲劇的な結末をこの作品の進行過程に生んで行く。そしてその過程が美の抽出に耐へられない暗さになる前でこの作品は終らねばならぬ運命を持つてゐるのである。
――11年間にわたる、康成の格闘がここに終わった。
この「雪国抄」「続雪国」の2編にさらに彫琢を加えて、1948(昭和23)年12月25日、創元社から〈決定版『雪国』〉が刊行される。












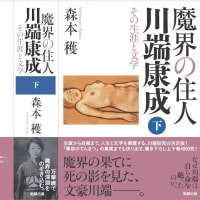
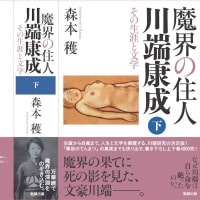

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます