戦時下の川端康成 その8
敗戦と玉鬘(たまかずら)の巻
「かうして私が長物語のほぼ半ば22、23帳まで読みすすんだところで、日本は降伏した」と康成は書いている。
22巻は玉鬘(たまかづら)、23巻は初音(はつね)である。
玉鬘の巻は、54巻のうちでも最も精彩のある面白い章段だ、とわたくしはかつて書いたことがある。
夕顔の遺児・玉鬘は、乳母(めのと)の夫が太宰府の役人になったので、幼いとき乳母に連れられて九州に渡った。玉鬘は大切に養育され、気高く美しい女性に成長したが、大夫監(たゆうのげん)という肥後の国の好色な豪族に婚姻を強要され、すんでのところで虎口を逃れて京に逃げ帰ってくる。
しかし旧知の京の人々も当てにならず、京のうちで流浪する彼女たち一行は、途方にくれて、大和の長谷観音への参詣を思い立つ。
そうして初瀬の椿市(つばいち)の宿で、今は源氏の侍女となっている右近に再会するのである。
右近は、およそ20年前、源氏が夕顔を連れ出したとき、一緒に連れて行った侍女であった。こうして玉鬘は、源氏の壮大な御殿、六条院に引き取られることになる。
この部分は長谷観音の霊験譚(れいげんたん)でもあるが、紫式部は明らかに住吉物語を下敷きにして、玉鬘の物語を書いたのである。大夫監が、住吉物語で姫君を襲おうとした「目うちただれたる70あまりなる翁」を模したものであることは、いうまでもない。
初音の巻は、玉鬘の巻から始まる、玉鬘十帖とも呼ばれる巻の1つで、六条院における源氏の優美な生活と、玉鬘をめぐる皇族貴族たちの鞘当てが描かれる。しかし、さほど劇的な巻ではない。
――敗戦のとき、康成は、54巻の半ばちかくまで読みすすんでいた。
その後、最後まで読み通したことは、1948(昭和23)年12月の『鏡』に「浮舟(うきふね)」を掲載していることによって確認される。宇治十帖の物語をのびやかに語った好短編だ。
生田川(いくたがわ)伝説
源氏物語の掉尾(とうび)を飾る宇治十帖の後半は、源氏の息子・薫(かおる。じつは、女三宮と柏木の密通によって生まれた子)と、源氏の孫・匂宮(におうのみや)という二人の男に愛されてしまった浮舟の悲劇を描いた物語である。
宇治川に身を投げようとした浮舟の苦悩を描いたこの物語は、万葉集巻9では高橋虫麻呂によって語られ、また平安時代には大和物語百47段によって知られる生田川伝説(生田伝説とも)を下敷きにして描かれたものであることは、よく知られているところだ。二人の男に同時に求婚された蘆屋(あしや)乙女(菟原處女(うなひをとめ)とも)が生田川に身を投げる物語である。
この悲劇を、康成は簡潔な文体でみごとな短編に仕上げている。すなわち康成は、敗色の濃くなりはじめた昭和18年の秋ごろから源氏物語を読み始め、戦後3年近くかかって、この長物語を読了したと推測されるのである。
すなわち康成は、昭和18年なかばから、およそ5年をかけて源氏物語を精読しているのである。また、この物語は、短い時間でざっと通読したぐらいでは、その精髄が體に流れこんでこないのである。
湖月抄で読んだ意義
ここで特筆しておかなければならないのは、康成が源氏物語を、「昔の仮名書きの木版本(もくはんぼん)」で読んだ、という事実である。
――わたくしは大学時代、中村俊定教授の国文学演習で、芭蕉が尾張名古屋の俳人たちと巻いた歌仙「冬の日」を読んだ感銘が忘れられない。
このとき、教科書は、江戸時代の木版本の影印本(えいいんぼん)写真でうつしたもの)を使用したのであるが、もちろん江戸時代の変体仮名は現代の仮名文字とはまったく異なり、その判読に苦労したのはひととおりではなかったが、その読みにくい変体仮名を1字1字拾い読みしてゆくと、そこに浮き上がってくる1句1句がまことに鮮烈で、言葉がくっきりとした映像をともなって立ち上がってくるのである。
あれほど鮮明な感動を覚えたことは、学生時代を通じてほかにはなかった。それほどに「昔の仮名書き」の本は、くっきりと一語一語を読者の脳裡(のうり)に焼きつけるのである。
康成は、どこかで、自分は少年時代から変体仮名を読めた、と述べている。だからわたくしたち現代の学生のようなとまどいはなかったであろうが、それでも変体仮名を拾い読みしてゆくのは、普通の読書とはスピードが全然違ったであろう。そして、その遅い分だけ、文章は一つ一つ、くっきりと康成の脳髄に刻まれたはずである。
康成がこの時期に読んだ源氏物語に異常な陶酔を覚えたのは、ひとつにはこの「昔の仮名書きの木版本」で読んだことが大きな要因である。
次に大切なことは、康成が北村季吟(きぎん)の湖月抄(こげつしょう)で源氏物語を読んだ、という事実である。
じつは、現代のように注釈つきの源氏物語が幾種類も刊行されている時代と異なり、戦中戦後のころは、国文学を専攻するごく一部の特殊な人たちを別とすれば、湖月抄でなければ、源氏物語全体を通読することは不可能だったのである。
偶然にも、康成は湖月抄を手にとった。だからこそ、54巻を読みとおすことができたのである。
では、それは、どのような意味なのか。
手順として、先に北村季吟の人間像を最小限、語っておかなければならないだろう。
季吟は、もと近江の国野洲(やす)郡北村の人。寛永元年(一六二四)に、父の住む京の粟田口(あわたぐち)で生まれたらしい。
祖父は医を業とし、かたわら里村紹巴(じょうは)に連歌を学んだ。父もまた医を業とし、里村祖白に連歌を学んでいる。
季吟もまた祖父、父の跡をついで医術を修めた。同時に、十六歳で安原貞室に入門して俳諧を学び、二十二歳で貞室の師である松永貞徳に入門して、貞徳の直弟子となった。
当時の連歌師や俳諧師が、単に歌や俳諧を詠んだばかりでなく、古今・伊勢・源氏など古典文学を当然の素養として学んだことはいうまでもない。
季吟は早くも29歳にして、最初の本格的注釈書『大和物語抄』を脱稿し、翌年に刊行している。以後、『伊勢物語拾穂抄(しゅうすいしょう)』をはじめ、多くの注釈書を刊行し、延宝元年(1673)に『湖月抄』60巻を上版した。
注釈54巻に、発端・系図・表白・雲隠説各1巻、年立(としだて。年表)2巻を付している。
発端の凡例(はんれい)によれば、季吟は箕形(みかた)如庵に師事して源氏物語の講義を聴き、また松永貞徳から桐壺の巻の講義を受けたという。
如庵は三条西公条(きんえだ)・実枝(さねき)から源氏学を相伝した人だから、三条西実隆の『細流抄』を拠りどころとし、また貞徳は九条稙通(たねみち)に従って源氏物語の奥義をきわめたところから、稙通の『孟津抄(もうしんしょう)』を基として源氏物語を解釈した。
季吟はこの両抄を基として、『河海抄』『花鳥余情』の要所を採用し、『弄花(ろうか)抄』『明星抄』などの説も加え、それに師の如庵の説をまじえ、かつ自説を述べて、初心者の助けたるべく『湖月抄』を著作したという。
それにしても、『湖月抄』の画期的なところは、本文の前後に頭注、傍注を加えて、本文を明快に味読する便宜を読者に与えたことである。
源氏物語は難解なので、このような注釈を参考にすることなしには、読みすすめることが不可能な物語なのだ。傍注によって動作の主体や簡潔な語の意味を説明し、頭注によって、難解な語句の解釈を考察し、准拠(じゅんきょ)や故実(こじつ)を説明する。
紫式部は和漢にわたる歴史・文学の膨大な知識を身につけたひとであった。そしてそれらを惜しみなく作品中に取り込んだ。
古今集や後撰集などの和歌は、しばしば本文や会話のなかに引用され(これを「引き歌」と呼ぶ)、それが深い意味をもった。
また、物語のあらゆるところに、准拠や故実が張りめぐらされた。
作品中に描かれている事件や行事は、みだりに創作されているのではない。たとえば巻頭の桐壺帝と桐壺更衣の恋愛が白楽天の「長恨歌」を下敷きにしていることは誰でも知っているし、桐壺更衣の死の一連の場面――宮門を出て里第に帰るのに輦車(てぐるま)を賜わり、里第に帰りつくや否や卒去(そっきょ)し、これを悲しんだ帝が従三位を追贈したことなど――は、『続日本後紀』の仁明天皇の承和六年六月三十日、女御・藤原澤子に対した条を範として書かれていることは、『河海抄』が指摘しているとおりだ。これを准拠(じゅんきょ)という。
敗戦と玉鬘(たまかずら)の巻
「かうして私が長物語のほぼ半ば22、23帳まで読みすすんだところで、日本は降伏した」と康成は書いている。
22巻は玉鬘(たまかづら)、23巻は初音(はつね)である。
玉鬘の巻は、54巻のうちでも最も精彩のある面白い章段だ、とわたくしはかつて書いたことがある。
夕顔の遺児・玉鬘は、乳母(めのと)の夫が太宰府の役人になったので、幼いとき乳母に連れられて九州に渡った。玉鬘は大切に養育され、気高く美しい女性に成長したが、大夫監(たゆうのげん)という肥後の国の好色な豪族に婚姻を強要され、すんでのところで虎口を逃れて京に逃げ帰ってくる。
しかし旧知の京の人々も当てにならず、京のうちで流浪する彼女たち一行は、途方にくれて、大和の長谷観音への参詣を思い立つ。
そうして初瀬の椿市(つばいち)の宿で、今は源氏の侍女となっている右近に再会するのである。
右近は、およそ20年前、源氏が夕顔を連れ出したとき、一緒に連れて行った侍女であった。こうして玉鬘は、源氏の壮大な御殿、六条院に引き取られることになる。
この部分は長谷観音の霊験譚(れいげんたん)でもあるが、紫式部は明らかに住吉物語を下敷きにして、玉鬘の物語を書いたのである。大夫監が、住吉物語で姫君を襲おうとした「目うちただれたる70あまりなる翁」を模したものであることは、いうまでもない。
初音の巻は、玉鬘の巻から始まる、玉鬘十帖とも呼ばれる巻の1つで、六条院における源氏の優美な生活と、玉鬘をめぐる皇族貴族たちの鞘当てが描かれる。しかし、さほど劇的な巻ではない。
――敗戦のとき、康成は、54巻の半ばちかくまで読みすすんでいた。
その後、最後まで読み通したことは、1948(昭和23)年12月の『鏡』に「浮舟(うきふね)」を掲載していることによって確認される。宇治十帖の物語をのびやかに語った好短編だ。
生田川(いくたがわ)伝説
源氏物語の掉尾(とうび)を飾る宇治十帖の後半は、源氏の息子・薫(かおる。じつは、女三宮と柏木の密通によって生まれた子)と、源氏の孫・匂宮(におうのみや)という二人の男に愛されてしまった浮舟の悲劇を描いた物語である。
宇治川に身を投げようとした浮舟の苦悩を描いたこの物語は、万葉集巻9では高橋虫麻呂によって語られ、また平安時代には大和物語百47段によって知られる生田川伝説(生田伝説とも)を下敷きにして描かれたものであることは、よく知られているところだ。二人の男に同時に求婚された蘆屋(あしや)乙女(菟原處女(うなひをとめ)とも)が生田川に身を投げる物語である。
この悲劇を、康成は簡潔な文体でみごとな短編に仕上げている。すなわち康成は、敗色の濃くなりはじめた昭和18年の秋ごろから源氏物語を読み始め、戦後3年近くかかって、この長物語を読了したと推測されるのである。
すなわち康成は、昭和18年なかばから、およそ5年をかけて源氏物語を精読しているのである。また、この物語は、短い時間でざっと通読したぐらいでは、その精髄が體に流れこんでこないのである。
湖月抄で読んだ意義
ここで特筆しておかなければならないのは、康成が源氏物語を、「昔の仮名書きの木版本(もくはんぼん)」で読んだ、という事実である。
――わたくしは大学時代、中村俊定教授の国文学演習で、芭蕉が尾張名古屋の俳人たちと巻いた歌仙「冬の日」を読んだ感銘が忘れられない。
このとき、教科書は、江戸時代の木版本の影印本(えいいんぼん)写真でうつしたもの)を使用したのであるが、もちろん江戸時代の変体仮名は現代の仮名文字とはまったく異なり、その判読に苦労したのはひととおりではなかったが、その読みにくい変体仮名を1字1字拾い読みしてゆくと、そこに浮き上がってくる1句1句がまことに鮮烈で、言葉がくっきりとした映像をともなって立ち上がってくるのである。
あれほど鮮明な感動を覚えたことは、学生時代を通じてほかにはなかった。それほどに「昔の仮名書き」の本は、くっきりと一語一語を読者の脳裡(のうり)に焼きつけるのである。
康成は、どこかで、自分は少年時代から変体仮名を読めた、と述べている。だからわたくしたち現代の学生のようなとまどいはなかったであろうが、それでも変体仮名を拾い読みしてゆくのは、普通の読書とはスピードが全然違ったであろう。そして、その遅い分だけ、文章は一つ一つ、くっきりと康成の脳髄に刻まれたはずである。
康成がこの時期に読んだ源氏物語に異常な陶酔を覚えたのは、ひとつにはこの「昔の仮名書きの木版本」で読んだことが大きな要因である。
次に大切なことは、康成が北村季吟(きぎん)の湖月抄(こげつしょう)で源氏物語を読んだ、という事実である。
じつは、現代のように注釈つきの源氏物語が幾種類も刊行されている時代と異なり、戦中戦後のころは、国文学を専攻するごく一部の特殊な人たちを別とすれば、湖月抄でなければ、源氏物語全体を通読することは不可能だったのである。
偶然にも、康成は湖月抄を手にとった。だからこそ、54巻を読みとおすことができたのである。
では、それは、どのような意味なのか。
手順として、先に北村季吟の人間像を最小限、語っておかなければならないだろう。
季吟は、もと近江の国野洲(やす)郡北村の人。寛永元年(一六二四)に、父の住む京の粟田口(あわたぐち)で生まれたらしい。
祖父は医を業とし、かたわら里村紹巴(じょうは)に連歌を学んだ。父もまた医を業とし、里村祖白に連歌を学んでいる。
季吟もまた祖父、父の跡をついで医術を修めた。同時に、十六歳で安原貞室に入門して俳諧を学び、二十二歳で貞室の師である松永貞徳に入門して、貞徳の直弟子となった。
当時の連歌師や俳諧師が、単に歌や俳諧を詠んだばかりでなく、古今・伊勢・源氏など古典文学を当然の素養として学んだことはいうまでもない。
季吟は早くも29歳にして、最初の本格的注釈書『大和物語抄』を脱稿し、翌年に刊行している。以後、『伊勢物語拾穂抄(しゅうすいしょう)』をはじめ、多くの注釈書を刊行し、延宝元年(1673)に『湖月抄』60巻を上版した。
注釈54巻に、発端・系図・表白・雲隠説各1巻、年立(としだて。年表)2巻を付している。
発端の凡例(はんれい)によれば、季吟は箕形(みかた)如庵に師事して源氏物語の講義を聴き、また松永貞徳から桐壺の巻の講義を受けたという。
如庵は三条西公条(きんえだ)・実枝(さねき)から源氏学を相伝した人だから、三条西実隆の『細流抄』を拠りどころとし、また貞徳は九条稙通(たねみち)に従って源氏物語の奥義をきわめたところから、稙通の『孟津抄(もうしんしょう)』を基として源氏物語を解釈した。
季吟はこの両抄を基として、『河海抄』『花鳥余情』の要所を採用し、『弄花(ろうか)抄』『明星抄』などの説も加え、それに師の如庵の説をまじえ、かつ自説を述べて、初心者の助けたるべく『湖月抄』を著作したという。
それにしても、『湖月抄』の画期的なところは、本文の前後に頭注、傍注を加えて、本文を明快に味読する便宜を読者に与えたことである。
源氏物語は難解なので、このような注釈を参考にすることなしには、読みすすめることが不可能な物語なのだ。傍注によって動作の主体や簡潔な語の意味を説明し、頭注によって、難解な語句の解釈を考察し、准拠(じゅんきょ)や故実(こじつ)を説明する。
紫式部は和漢にわたる歴史・文学の膨大な知識を身につけたひとであった。そしてそれらを惜しみなく作品中に取り込んだ。
古今集や後撰集などの和歌は、しばしば本文や会話のなかに引用され(これを「引き歌」と呼ぶ)、それが深い意味をもった。
また、物語のあらゆるところに、准拠や故実が張りめぐらされた。
作品中に描かれている事件や行事は、みだりに創作されているのではない。たとえば巻頭の桐壺帝と桐壺更衣の恋愛が白楽天の「長恨歌」を下敷きにしていることは誰でも知っているし、桐壺更衣の死の一連の場面――宮門を出て里第に帰るのに輦車(てぐるま)を賜わり、里第に帰りつくや否や卒去(そっきょ)し、これを悲しんだ帝が従三位を追贈したことなど――は、『続日本後紀』の仁明天皇の承和六年六月三十日、女御・藤原澤子に対した条を範として書かれていることは、『河海抄』が指摘しているとおりだ。これを准拠(じゅんきょ)という。












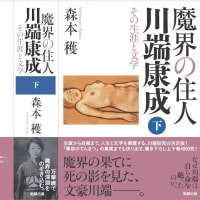
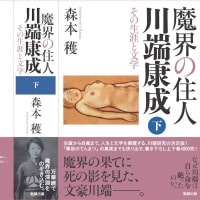

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます