上田 博・木村一信・中川成美編『日本近代文学を学ぶ人のために』 1997年7月20日 世界思想社
川端康成
私の場合、偶然手にとった一冊の新潮文庫『みずうみ』が出発点だった。異様な感動を覚え、その〈美〉に戦慄した。何と怖ろしくて、何と魅惑にみちていることか。このような不思議な〈美〉は、それまで経験したことがなかった。しかもこの〈美〉は、単にそれだけで成立しているのではない。怖ろしいほどに深い主人公の孤独と連動しているようだ。
この〈美〉の正体を明らかにしたい。さらに、この〈美〉のよって来るところ――そのような怖ろしい〈美〉が発想された川端という作家の根底を知りたい。その〈美〉について、何ごとかを語りたい。
――それが私の川端論の出発点だった。
川端康成を研究するとは、そのようなことなのだ。つまり学ぶ人自身が、川端の何かについて語りたいと烈しく願うこと。その衝動が根本にあって、初めて、川端文学を学ぶこと、研究することが出発するのである。
では、この基本的な衝動があって、研究の対象を川端と決めたら、次には何をしてゆけばいいのか。結論的にいえば、一方で自分の考えを深めながら、他方で、これまでの研究成果を学んでゆく、ということにつきる。よい論考は、自分の考えていることに、多大の刺激を与えてくれる。自分の内部に漠として存在しているが、はっきりした形をとっていなかったものを、明かしてくれた論文。それは同時に、自分だったら、もっとこういうことも言いたい、こう考えることはできないだろうか、などと、次々に胸をかきたててくれる。そういうものと対話しつつ、自分の考える論をすすめてゆくのだ。
さて、川端研究は、今日どのように展開し、どのような課題が残されているのだろうか。
ここ20年余のうちに、川端研究はおびただしい進展をみせた。質量ともに膨大な文献が提示され、『伊豆の踊子』『雪国』など、人気作品には論考が集中している。しかし、まだまだ手つかずに近い状態の分野も多い。
手薄な領域として、第1に、作品論が、まだ足りない。有名な作品に偏っていて、よい作品、あるいは意味の深い、示唆にとむ作品でも、深く追究された作品は意外に少ない。なかでも〈掌の小説〉は、ほとんど手つかずといっていい。「川端康成研究叢書」第2巻「詩魂の源流」(教育出版センター、昭52)に論考の集成があるが、玉石混淆である。この領域の研究課題は無尽蔵といっていい。
第2に、戦後作品の検討。〈魔界〉をキー・ワードとして、川端文学の頂点をなす作品群をとらえる方法は、まだ不十分である。私もその一翼をになって理論を提出しかことがある。それなりに、川端文学の本質に迫ることができたと思うが、しかしその後、眼のさめるような斬新な視点は提示されていないように思われる。また、〈魔界〉のキー・ワードだけでは解決しがたい要素が川端文学にはあると痛感させられた。『住吉』連作など、難解だが、それだけに挑戦しがいがあるだろう。
第3に、昭和初期-『禽獣』が書かれるまでの時期は、一種の空白地帯だ。川端の模索時代であっただけに、さまざまな可能性が実験された。川端は何を捨て、何を選びだしたのか。それがどのように『禽獣』や『雪国』に収斂していったのか。そのあたりは、腕力ある書き手の登場が期待されるところだろう。
第4に、『眠れる美女』以降について。〈魔界〉の絶頂期を終えた作家が、その苦しい晩年にめざした新しい境地についての検討。『たんぽぽ』という奇怪な作品を視野に入れつつ、この時期を探っていけば、それは川端文学の全体像への構築にもつながっていくだろう。
第5に、秀抜な批評家でもあった川端の、評論的な分野についての研究。『文学的自叙伝』『末期の眼』『美しい日本の私』など、川端の小説作品を解明するための手がかりとして引用されることは多いが、それ自体を本格的に論じたものは少ない。川端の芸術論、文学観の推移を考究するだけで優に1冊の本は書けそうだ。
――以上は、あくまでも、目安である。基本は、最初に書いたように、自分の内的な関心である。
さて、ここで、私かいま想定している川端論の、1つのテーマについて述べてみたい。それは、『住吉』連作から『千羽鶴』『山の音』 への速続性、という問題である。
この連作から川端の戦後、なかんずく〈魔界〉が始まったとする私の説は、ほぼ定着していると思う。そして連作の3作め『住吉』と踵を接するようにして『千羽鶴』『山の音』が書き出されていることも、厳然たる事実だ。ところがそれぞれ、別々に論じられることはあっても、連作から2作への連統性――内的持続性については、ほとんど論及されていないのだ。行平(ゆきひら)と、菊治、尾形信吾の人間像の、深層における連続性。『千羽鶴』と『山の音』が表裏一体の作として論じられることはよくある。が、行平とこの2人とは、どのような関係にあるのか。
私は、『千羽鶴』を〈夢幻の物語〉と規定したことがある。川端作品の多くは、遠く現実から離れているが、この作品は多くの川端作品の現実から、さらに離れた空間において語られている。『山の音』の尾形信吾の内面深くで夢想される、世俗の倫理を完全に遮断した、夢中の物語なのである。信吾の、より深層の意識のなかで展開される物語なのである。
その菊治の世界とは、父から承け継がれた運命的な資質である。作中にしばしば「暗く醜い幕」「とらわれた」といった類の表現が頻出することに注意したい。菊治は、そのような運命的な、つまり倫理を無視した、おのが裡に流れる官能のおもむくままに行動することを運命づけられた男なのである。その、内なる官能が、父の愛人であった太田夫人としぜんに結ばせ、その娘文子と結ばせる。母の体から娘の体へ「微妙に」「移されてゐる」要素――「2人で1人」の禁断の官能に酔うことを決定づけられているのである。
『住吉』連作のうち、はじめの3部作の根底にあるのが、生みの母と育ての母lどうやら双子であるらしい2人の母への、行平の果てしない思慕であることは言をまたない。そしてその奇怪な願望が、おそらくは行平の父の乱倫による結果、生じたものであることも。
父は、1人の女とのあいだに行平をもうけたのち、その姉妹であるもう1人の女と棲むことになった。うち捨てられた女は死を選んだ。この秘密を、反橋の頂きで告げられたとき、行平の生涯は狂った。
――「私の生涯はこの時に狂つたのでありました」――この1行の恐ろしさこそが文学なのである。こののち行平は、育ての母にたいする〈悪心〉を抱きつつ生涯を歩むことになる。「わがいめちかなし」と知ったとき、同時に〈悪心〉が芽生え、生涯において幾人もの幼い娘を「をかす」ことになった行平。「悪逆と汚辱と傷枯の生涯の果て」に住吉神社へいま1度、おそらくは母との再会、おのが生涯の原点をもとめて訪ねる行平は、まさに私たちの世の中を支配する秩序――公序良俗とは、まったく異なる次元を生きている。
このようなFATALなものこそ、敗戦の深い傷心のなかから川端が生みだした人間像であった。そしてこの行平像が、川端康成の自画像に他ならないことも、留意しなければならないだろう。みずからの意志と関わりなく、いわば運命として、人生の出発点において与えられた実存の条件。肉親関係の極端にうすい家庭で、おそろしいほどに深い孤独のなかで過ごされた幼少年期の、無限にながい時間と空間のなかから川端の官能――「病的な妄想」は育まれたのである。
このように行平(ゆきひら)を川端の自画像としてとらえたとき、いわば倫理のだかをはずされてしまった菊治の内面がたやすく了解されるのである。彼が太田夫人や文子を見る視線は、志野焼を鑑賞する眼と同じである。それは『禽獣』や『末期の眼』に描かれた視線にも重なってくる。人間の社会的関係が最初から喪失されたところに、川端文学は成立しているのである。
『山の音』の信吾はどうか。彼は物語の最初で、山鳴りによって死を告知される。死期を自覚し、ま
た戦後の風俗のなかで自分の人生がもはや終わったと痛切におもう信吾は、いわば〈末期の夢〉として、修一の嫁菊子に思慕をつのらせる。そしてここでも、信吾の思慕を、単なる思慕から隔てているのは、本来は犯してはならぬ〈禁忌〉をはらんでいるからである。
このように『住吉』連作と『千羽鶴』『山の音』に共通する主人公像を見てくれば、第1に主人公が運命的なものに呪縛されていること、第2に、その結果として必然的に〈禁忌〉あるいは〈悪〉につながる思慕が生じていること、第3に、生涯の果てという極限の状況において物語が設定されていること、そして第4に、主人公が限りなく汚辱へと堕落していきながら、他方で、その汚辱を清める存在を求めていること(『千羽鶴』における稲村ゆき子のような)、などの特徴が浮かび上がるのである。
これらの特徴から、この期における川端文学の本質を結論として導き出すのは、さほど困難な作業ではないだろう。
(上田 博・木村一信・中川成美編『日本近代文学を学ぶ人のために』1997年7月20日 世界思想社)
川端康成
森本 穫
最初に、川端文学を学ぶとは、どういうことだろうか? この点を抜きにしては、この稿はすすめることができない。ほんの少しだけ、私の経験を語らせていただきたい。私の場合、偶然手にとった一冊の新潮文庫『みずうみ』が出発点だった。異様な感動を覚え、その〈美〉に戦慄した。何と怖ろしくて、何と魅惑にみちていることか。このような不思議な〈美〉は、それまで経験したことがなかった。しかもこの〈美〉は、単にそれだけで成立しているのではない。怖ろしいほどに深い主人公の孤独と連動しているようだ。
この〈美〉の正体を明らかにしたい。さらに、この〈美〉のよって来るところ――そのような怖ろしい〈美〉が発想された川端という作家の根底を知りたい。その〈美〉について、何ごとかを語りたい。
――それが私の川端論の出発点だった。
川端康成を研究するとは、そのようなことなのだ。つまり学ぶ人自身が、川端の何かについて語りたいと烈しく願うこと。その衝動が根本にあって、初めて、川端文学を学ぶこと、研究することが出発するのである。
では、この基本的な衝動があって、研究の対象を川端と決めたら、次には何をしてゆけばいいのか。結論的にいえば、一方で自分の考えを深めながら、他方で、これまでの研究成果を学んでゆく、ということにつきる。よい論考は、自分の考えていることに、多大の刺激を与えてくれる。自分の内部に漠として存在しているが、はっきりした形をとっていなかったものを、明かしてくれた論文。それは同時に、自分だったら、もっとこういうことも言いたい、こう考えることはできないだろうか、などと、次々に胸をかきたててくれる。そういうものと対話しつつ、自分の考える論をすすめてゆくのだ。
さて、川端研究は、今日どのように展開し、どのような課題が残されているのだろうか。
ここ20年余のうちに、川端研究はおびただしい進展をみせた。質量ともに膨大な文献が提示され、『伊豆の踊子』『雪国』など、人気作品には論考が集中している。しかし、まだまだ手つかずに近い状態の分野も多い。
手薄な領域として、第1に、作品論が、まだ足りない。有名な作品に偏っていて、よい作品、あるいは意味の深い、示唆にとむ作品でも、深く追究された作品は意外に少ない。なかでも〈掌の小説〉は、ほとんど手つかずといっていい。「川端康成研究叢書」第2巻「詩魂の源流」(教育出版センター、昭52)に論考の集成があるが、玉石混淆である。この領域の研究課題は無尽蔵といっていい。
第2に、戦後作品の検討。〈魔界〉をキー・ワードとして、川端文学の頂点をなす作品群をとらえる方法は、まだ不十分である。私もその一翼をになって理論を提出しかことがある。それなりに、川端文学の本質に迫ることができたと思うが、しかしその後、眼のさめるような斬新な視点は提示されていないように思われる。また、〈魔界〉のキー・ワードだけでは解決しがたい要素が川端文学にはあると痛感させられた。『住吉』連作など、難解だが、それだけに挑戦しがいがあるだろう。
第3に、昭和初期-『禽獣』が書かれるまでの時期は、一種の空白地帯だ。川端の模索時代であっただけに、さまざまな可能性が実験された。川端は何を捨て、何を選びだしたのか。それがどのように『禽獣』や『雪国』に収斂していったのか。そのあたりは、腕力ある書き手の登場が期待されるところだろう。
第4に、『眠れる美女』以降について。〈魔界〉の絶頂期を終えた作家が、その苦しい晩年にめざした新しい境地についての検討。『たんぽぽ』という奇怪な作品を視野に入れつつ、この時期を探っていけば、それは川端文学の全体像への構築にもつながっていくだろう。
第5に、秀抜な批評家でもあった川端の、評論的な分野についての研究。『文学的自叙伝』『末期の眼』『美しい日本の私』など、川端の小説作品を解明するための手がかりとして引用されることは多いが、それ自体を本格的に論じたものは少ない。川端の芸術論、文学観の推移を考究するだけで優に1冊の本は書けそうだ。
――以上は、あくまでも、目安である。基本は、最初に書いたように、自分の内的な関心である。
さて、ここで、私かいま想定している川端論の、1つのテーマについて述べてみたい。それは、『住吉』連作から『千羽鶴』『山の音』 への速続性、という問題である。
この連作から川端の戦後、なかんずく〈魔界〉が始まったとする私の説は、ほぼ定着していると思う。そして連作の3作め『住吉』と踵を接するようにして『千羽鶴』『山の音』が書き出されていることも、厳然たる事実だ。ところがそれぞれ、別々に論じられることはあっても、連作から2作への連統性――内的持続性については、ほとんど論及されていないのだ。行平(ゆきひら)と、菊治、尾形信吾の人間像の、深層における連続性。『千羽鶴』と『山の音』が表裏一体の作として論じられることはよくある。が、行平とこの2人とは、どのような関係にあるのか。
私は、『千羽鶴』を〈夢幻の物語〉と規定したことがある。川端作品の多くは、遠く現実から離れているが、この作品は多くの川端作品の現実から、さらに離れた空間において語られている。『山の音』の尾形信吾の内面深くで夢想される、世俗の倫理を完全に遮断した、夢中の物語なのである。信吾の、より深層の意識のなかで展開される物語なのである。
その菊治の世界とは、父から承け継がれた運命的な資質である。作中にしばしば「暗く醜い幕」「とらわれた」といった類の表現が頻出することに注意したい。菊治は、そのような運命的な、つまり倫理を無視した、おのが裡に流れる官能のおもむくままに行動することを運命づけられた男なのである。その、内なる官能が、父の愛人であった太田夫人としぜんに結ばせ、その娘文子と結ばせる。母の体から娘の体へ「微妙に」「移されてゐる」要素――「2人で1人」の禁断の官能に酔うことを決定づけられているのである。
『住吉』連作のうち、はじめの3部作の根底にあるのが、生みの母と育ての母lどうやら双子であるらしい2人の母への、行平の果てしない思慕であることは言をまたない。そしてその奇怪な願望が、おそらくは行平の父の乱倫による結果、生じたものであることも。
父は、1人の女とのあいだに行平をもうけたのち、その姉妹であるもう1人の女と棲むことになった。うち捨てられた女は死を選んだ。この秘密を、反橋の頂きで告げられたとき、行平の生涯は狂った。
――「私の生涯はこの時に狂つたのでありました」――この1行の恐ろしさこそが文学なのである。こののち行平は、育ての母にたいする〈悪心〉を抱きつつ生涯を歩むことになる。「わがいめちかなし」と知ったとき、同時に〈悪心〉が芽生え、生涯において幾人もの幼い娘を「をかす」ことになった行平。「悪逆と汚辱と傷枯の生涯の果て」に住吉神社へいま1度、おそらくは母との再会、おのが生涯の原点をもとめて訪ねる行平は、まさに私たちの世の中を支配する秩序――公序良俗とは、まったく異なる次元を生きている。
このようなFATALなものこそ、敗戦の深い傷心のなかから川端が生みだした人間像であった。そしてこの行平像が、川端康成の自画像に他ならないことも、留意しなければならないだろう。みずからの意志と関わりなく、いわば運命として、人生の出発点において与えられた実存の条件。肉親関係の極端にうすい家庭で、おそろしいほどに深い孤独のなかで過ごされた幼少年期の、無限にながい時間と空間のなかから川端の官能――「病的な妄想」は育まれたのである。
このように行平(ゆきひら)を川端の自画像としてとらえたとき、いわば倫理のだかをはずされてしまった菊治の内面がたやすく了解されるのである。彼が太田夫人や文子を見る視線は、志野焼を鑑賞する眼と同じである。それは『禽獣』や『末期の眼』に描かれた視線にも重なってくる。人間の社会的関係が最初から喪失されたところに、川端文学は成立しているのである。
『山の音』の信吾はどうか。彼は物語の最初で、山鳴りによって死を告知される。死期を自覚し、ま
た戦後の風俗のなかで自分の人生がもはや終わったと痛切におもう信吾は、いわば〈末期の夢〉として、修一の嫁菊子に思慕をつのらせる。そしてここでも、信吾の思慕を、単なる思慕から隔てているのは、本来は犯してはならぬ〈禁忌〉をはらんでいるからである。
このように『住吉』連作と『千羽鶴』『山の音』に共通する主人公像を見てくれば、第1に主人公が運命的なものに呪縛されていること、第2に、その結果として必然的に〈禁忌〉あるいは〈悪〉につながる思慕が生じていること、第3に、生涯の果てという極限の状況において物語が設定されていること、そして第4に、主人公が限りなく汚辱へと堕落していきながら、他方で、その汚辱を清める存在を求めていること(『千羽鶴』における稲村ゆき子のような)、などの特徴が浮かび上がるのである。
これらの特徴から、この期における川端文学の本質を結論として導き出すのは、さほど困難な作業ではないだろう。
(上田 博・木村一信・中川成美編『日本近代文学を学ぶ人のために』1997年7月20日 世界思想社)












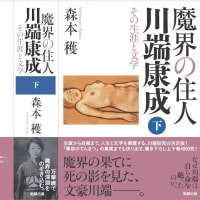
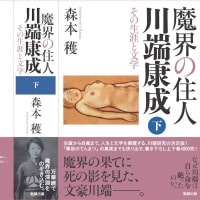

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます