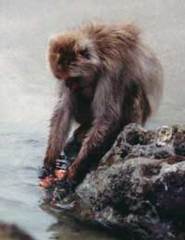
もともと「教育」という行いは文化そのものだったといいたいのです。土地に根ざして営まれていたという意味です。それぞれの作物にふさわしい土壌があるように、その土地に根ざした「教えと学び」のスタイルがあったのです。にもかかわらず<教える>に特化してきたのが日本の近代学校教育でした。国是・国策としての「近代化」はひとえに教育、それも学校教育に頼りきりにならなければ進められなかったと信じられたからです。
国家が創設した大学は、遅ればせの「近代化」をなしとげるエンジンの役割を押しつけられました。そこで教授されたのは、いうまでもなく西欧の文物、つまりは「新知識」だった。大学以下の教育体制が「近代化路線」に強引に参入させられたのは当然でした。
すべての諸学校では中央から持ちこまれた教育内容をひたすら生徒や学生たちの脳髄にたたき込んだのです。それがいまなおつづいて、学校教育の「習い性」となったのでした。
その結果、獲得された成果は「国民国家」という箱船に同乗した身内意識でありましたが、失われたものはその土地に独特の地味であり、風情というものでした。これは土地だけのことではなかったのは無論です。ひとりひとりの存在が独特の土壌だったからです。
またぞろ「卒業式」というおぞましい行事が開かれそうです。今年もまた、「立て!歌え!」という野蛮な怒号が飛びかうのでしょうか。だれのための「式」かと問えば、いうまでもないという答がかえってきそうです。どこの高校だったか、式に参加しなければ卒業証書だか入学証書を発行しないと強弁した校長がいました。そんなものいらないよ、といえ。
無理強いを迫られるとき、いつでも心によみがえる一つの詩があります。
鄙(ひな)ぶりの唄
それぞれの土から
陽炎(かげろう)のように
ふっと匂い立った旋律がある
愛されてひとびとに
永くうたいつがれてきた民謡がある
なぜ国歌など
ものものしくうたう必要がありましょう
おおかたは侵略の血でよごれ
腹黒の過去を隠しもちながら
口を拭って起立して
直立不動でうたわなければならないか
聞かなければならないか
私は立たない 坐っています
(茨木のり子『倚りかからず』所収・筑摩書房)
鄙(ひな)というのは「都から離れた土地。田舎」、つまりは健全な土地・在所という意味です。「それぞれの土」とは、ひとりひとりの分ということ。それぞれが自分の唄(言葉・思想)をもっている、自分に似合った唄をうたいたいというのは一つの態度であり、姿勢です。自分の言葉で自分の思想を紡ぎ、自らの唄を口ずさむ。それが生きるエネルギー。
「私は立たない 坐っています」そんな不敬な態度は認めるわけにはいかぬ、「お前だけを座らせておくわけにはいかない」と生徒も教師も「ものものしくうたう」ことを強いられる。じつに愚弄かつ唾棄すべき風潮ですね。頽廃のきわみだな、と腹の底から思う。
こんな狂気に満ちた風土のなかから、どうして伸びやかで心豊かな青春を育むことができるのか。「生きる力」などとは、悪い冗談だと思う。「鳥かご」や「犬小屋」に閉じこめて、鳥や犬に「さあ、ここで生きる力をつけるのだ」といってみて、さてそれはどんな力なんだろう。飼い慣らされる力ですか。実にグロテスクだというほかない。(馬耳)
国家が創設した大学は、遅ればせの「近代化」をなしとげるエンジンの役割を押しつけられました。そこで教授されたのは、いうまでもなく西欧の文物、つまりは「新知識」だった。大学以下の教育体制が「近代化路線」に強引に参入させられたのは当然でした。
すべての諸学校では中央から持ちこまれた教育内容をひたすら生徒や学生たちの脳髄にたたき込んだのです。それがいまなおつづいて、学校教育の「習い性」となったのでした。
その結果、獲得された成果は「国民国家」という箱船に同乗した身内意識でありましたが、失われたものはその土地に独特の地味であり、風情というものでした。これは土地だけのことではなかったのは無論です。ひとりひとりの存在が独特の土壌だったからです。
またぞろ「卒業式」というおぞましい行事が開かれそうです。今年もまた、「立て!歌え!」という野蛮な怒号が飛びかうのでしょうか。だれのための「式」かと問えば、いうまでもないという答がかえってきそうです。どこの高校だったか、式に参加しなければ卒業証書だか入学証書を発行しないと強弁した校長がいました。そんなものいらないよ、といえ。
無理強いを迫られるとき、いつでも心によみがえる一つの詩があります。
鄙(ひな)ぶりの唄
それぞれの土から
陽炎(かげろう)のように
ふっと匂い立った旋律がある
愛されてひとびとに
永くうたいつがれてきた民謡がある
なぜ国歌など
ものものしくうたう必要がありましょう
おおかたは侵略の血でよごれ
腹黒の過去を隠しもちながら
口を拭って起立して
直立不動でうたわなければならないか
聞かなければならないか
私は立たない 坐っています
(茨木のり子『倚りかからず』所収・筑摩書房)
鄙(ひな)というのは「都から離れた土地。田舎」、つまりは健全な土地・在所という意味です。「それぞれの土」とは、ひとりひとりの分ということ。それぞれが自分の唄(言葉・思想)をもっている、自分に似合った唄をうたいたいというのは一つの態度であり、姿勢です。自分の言葉で自分の思想を紡ぎ、自らの唄を口ずさむ。それが生きるエネルギー。
「私は立たない 坐っています」そんな不敬な態度は認めるわけにはいかぬ、「お前だけを座らせておくわけにはいかない」と生徒も教師も「ものものしくうたう」ことを強いられる。じつに愚弄かつ唾棄すべき風潮ですね。頽廃のきわみだな、と腹の底から思う。
こんな狂気に満ちた風土のなかから、どうして伸びやかで心豊かな青春を育むことができるのか。「生きる力」などとは、悪い冗談だと思う。「鳥かご」や「犬小屋」に閉じこめて、鳥や犬に「さあ、ここで生きる力をつけるのだ」といってみて、さてそれはどんな力なんだろう。飼い慣らされる力ですか。実にグロテスクだというほかない。(馬耳)









