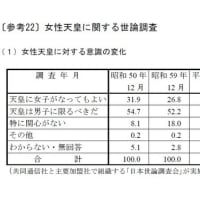○ 皇室の存在意義の捉え方
皇室に対しては、否定的な立場もあり、肯定的な立場もある。
最近は、否定的な立場というのは、昔よりは、減ってきたようにも思われる。
かつて、皇室を敬わないことが進歩的であるかのような雰囲気が、多分にあったのだ。
さて、このような否定的な立場が減ってきたことはいいのだけれど、肯定的な立場といってもいろいろある。
肯定的な立場においても、どうやら、筆者は、かなり少数派なのではないかと、実は、そんなことを思うようになった。
筆者の考えは、日本における皇室の存在意義というものは、皇室の方々の個々のご活動のすばらしさ、それも重要であるが、どちらかというと、皇室は国民の幸福を祈り、国民はそのような皇室を敬うという、そのような皇室と国民との心の絆にこそあるというものだ。
皇室は、125代も続いており、皇室の方々は自然人であるから、人間らしいドラマもあり、抽象的な神様とばかりは言えないところもある。
ただ、改めて考えてみるに、抽象的な理念、神の概念を共同体の価値観とするよりも、そのような、自然人たる皇室との心のつながりを、共同体の理念とするというのは、なかなか現実的であり、健全であるようにも思われる。
少なくとも、人と人との情を大切にする日本人には、ぴったり来るのではないか。
筆者としては、皇室と国民との心のつながりにこそ、皇室の存在意義があったと考えるのだ。
○ 皇室の個人的側面の賛美者
しかるに、皇室についての肯定派において、まず多いのは、皇室の方々の個人としてのすばらしさを褒め称えようとする者たちである。
もちろん、褒め称えること自体は、悪いことではない。
ただ、皇室の存在意義を、皇室の方々の個人としてのすばらしさのみと捉えると、それは、際限のない、ご公務の拡大の要求へとつながると思われる。
また、皇室の方々の在り方について、枠をはめることにもなってしまうだろう。
自然人である以上、様々な得手不得手があるはずであり、対外的なお付き合いで活躍する方もおられれば、静かに国民の幸福を祈られ、それがじんわりとした癒しの効果をもたらされる方もおられるだろう。また、病気やけがで、ご公務ができない場合だってあるかもしれない。
しかし、皇室の存在意義を、個人としてのすばらしさに求めてしまうと、やはり、目に見える形での存在感が必要になるであろうし、病気になれば、存在意義がないというような議論になってしまうのである。
また、皇室の個人としてのすばらしさに着目する場合に問題となるのは、皇室を紹介する人間のエゴである。皇室の無私なるお姿を紹介するに際しては、紹介する者も無私でなければならないだろう。
しかるに、皇室の個人としてのすばらしさを紹介しようとする者は、皇室と直接ふれあう機会を有するものが多いということもあり、どうしても、皇室の方々からよく見てもらいたいという気持ちも働くであろうし、また、皇室と直接ふれあうことのできない多くの国民にとっては、しらけさせることにもなりかねないのである。
○ 皇室の政治利用の問題
また、皇室についての肯定的な立場でも、要するに、何か団体のようなものを作って威張ることが目的であるかのような者もいる。
これは、否定派よりも、むしろ問題であると思う。
団体を作って権力を振りかざすというときに、自分自身の能力、資質のみを根拠とすることは、至難の業である。
しかし、皇室など、既存の価値を利用する場合には、それがごく簡単になる。
単に、自分は、皇室の素晴らしいことを理解しているのだと、声高に叫べばいいからである。皇室のことをよく理解している者と、理解が不十分である者との序列を作り上げ、支配しようというやり方である。宗教団体に多く見られる構造である。
筆者としては、政治家が皇室の大事であることを主張し始める場合には、警戒が必要であると、どうしても思ってしまう。
本当に、皇室の存在意義を理解してでのことか、それとも自らの権威を高めるためなのか、それを見分けるためには、皇室を、何か政治的問題の解決に持ち出そうとしているか、また、自らの考えが皇室の考えと異なることが明らかとなった場合に、素直に間違いを認めることができるか、といったところであろうか。
皇室のことを考えていると、特に現在は、皇室の存在意義が不当に没却されている時代であるから、自分こそが理解しているのだという陶酔に、ついつい陥りがちであるが、皇室を利用しての自らの権威付けは、皇室の方々の嫌うところであり、注意が必要である。
また、皇室のお気持ちというのも、実に計りがたいところがあって、これがお気持ちだろうと勝手に想像すると、実は違っていたということが、しばしばある。後から考えればなるほどと思うのだが、安易に、皇室のお気持ち云々を述べると、恥をかいてしまう可能性大である。
○ 課題
皇室が日本の象徴であるということから、皇室に対して、帝王学の必要性を主張する人は多い。
しかし、「象徴」が、皇室と国民との関係性の上に成り立つ概念であるとすれば、皇室の側にだけ帝王学を要求するというのは、片面的である。
やはり、皇室という存在をどのように捉えるかということの基礎的な教養が、国民の側にも必要ではないだろうか。
それは、日本人という存在を、歴史、文化という面から、捉え直すということになると思う。
現在において、歴史、文化というものは、どうも、人畜無害なイメージがあるように思われる。
しかし、歴史、文化というものは、今現在の自分というものを、まさに形作っているものであり、本来、非常に影響力のある、生き生きとしたものなのである。
あたかも死んでしまったものという思いこみを脱ぎ捨てて、自らの中に息づいている歴史、文化に目覚めれば、日本人としての自分がはっきりしてくるであろうと、また、日本としての本来あるべき姿もあきらかになるかもしれない。
そして、そうなれば、政治家が本物であるか、ニセモノであるか、すぐに見分けがつくようになるはずである。
日本と日本人とが幸せになるためには、自らの淵源というものを知り、目覚めることが大事なのだと思うのである。
皇室に対しては、否定的な立場もあり、肯定的な立場もある。
最近は、否定的な立場というのは、昔よりは、減ってきたようにも思われる。
かつて、皇室を敬わないことが進歩的であるかのような雰囲気が、多分にあったのだ。
さて、このような否定的な立場が減ってきたことはいいのだけれど、肯定的な立場といってもいろいろある。
肯定的な立場においても、どうやら、筆者は、かなり少数派なのではないかと、実は、そんなことを思うようになった。
筆者の考えは、日本における皇室の存在意義というものは、皇室の方々の個々のご活動のすばらしさ、それも重要であるが、どちらかというと、皇室は国民の幸福を祈り、国民はそのような皇室を敬うという、そのような皇室と国民との心の絆にこそあるというものだ。
皇室は、125代も続いており、皇室の方々は自然人であるから、人間らしいドラマもあり、抽象的な神様とばかりは言えないところもある。
ただ、改めて考えてみるに、抽象的な理念、神の概念を共同体の価値観とするよりも、そのような、自然人たる皇室との心のつながりを、共同体の理念とするというのは、なかなか現実的であり、健全であるようにも思われる。
少なくとも、人と人との情を大切にする日本人には、ぴったり来るのではないか。
筆者としては、皇室と国民との心のつながりにこそ、皇室の存在意義があったと考えるのだ。
○ 皇室の個人的側面の賛美者
しかるに、皇室についての肯定派において、まず多いのは、皇室の方々の個人としてのすばらしさを褒め称えようとする者たちである。
もちろん、褒め称えること自体は、悪いことではない。
ただ、皇室の存在意義を、皇室の方々の個人としてのすばらしさのみと捉えると、それは、際限のない、ご公務の拡大の要求へとつながると思われる。
また、皇室の方々の在り方について、枠をはめることにもなってしまうだろう。
自然人である以上、様々な得手不得手があるはずであり、対外的なお付き合いで活躍する方もおられれば、静かに国民の幸福を祈られ、それがじんわりとした癒しの効果をもたらされる方もおられるだろう。また、病気やけがで、ご公務ができない場合だってあるかもしれない。
しかし、皇室の存在意義を、個人としてのすばらしさに求めてしまうと、やはり、目に見える形での存在感が必要になるであろうし、病気になれば、存在意義がないというような議論になってしまうのである。
また、皇室の個人としてのすばらしさに着目する場合に問題となるのは、皇室を紹介する人間のエゴである。皇室の無私なるお姿を紹介するに際しては、紹介する者も無私でなければならないだろう。
しかるに、皇室の個人としてのすばらしさを紹介しようとする者は、皇室と直接ふれあう機会を有するものが多いということもあり、どうしても、皇室の方々からよく見てもらいたいという気持ちも働くであろうし、また、皇室と直接ふれあうことのできない多くの国民にとっては、しらけさせることにもなりかねないのである。
○ 皇室の政治利用の問題
また、皇室についての肯定的な立場でも、要するに、何か団体のようなものを作って威張ることが目的であるかのような者もいる。
これは、否定派よりも、むしろ問題であると思う。
団体を作って権力を振りかざすというときに、自分自身の能力、資質のみを根拠とすることは、至難の業である。
しかし、皇室など、既存の価値を利用する場合には、それがごく簡単になる。
単に、自分は、皇室の素晴らしいことを理解しているのだと、声高に叫べばいいからである。皇室のことをよく理解している者と、理解が不十分である者との序列を作り上げ、支配しようというやり方である。宗教団体に多く見られる構造である。
筆者としては、政治家が皇室の大事であることを主張し始める場合には、警戒が必要であると、どうしても思ってしまう。
本当に、皇室の存在意義を理解してでのことか、それとも自らの権威を高めるためなのか、それを見分けるためには、皇室を、何か政治的問題の解決に持ち出そうとしているか、また、自らの考えが皇室の考えと異なることが明らかとなった場合に、素直に間違いを認めることができるか、といったところであろうか。
皇室のことを考えていると、特に現在は、皇室の存在意義が不当に没却されている時代であるから、自分こそが理解しているのだという陶酔に、ついつい陥りがちであるが、皇室を利用しての自らの権威付けは、皇室の方々の嫌うところであり、注意が必要である。
また、皇室のお気持ちというのも、実に計りがたいところがあって、これがお気持ちだろうと勝手に想像すると、実は違っていたということが、しばしばある。後から考えればなるほどと思うのだが、安易に、皇室のお気持ち云々を述べると、恥をかいてしまう可能性大である。
○ 課題
皇室が日本の象徴であるということから、皇室に対して、帝王学の必要性を主張する人は多い。
しかし、「象徴」が、皇室と国民との関係性の上に成り立つ概念であるとすれば、皇室の側にだけ帝王学を要求するというのは、片面的である。
やはり、皇室という存在をどのように捉えるかということの基礎的な教養が、国民の側にも必要ではないだろうか。
それは、日本人という存在を、歴史、文化という面から、捉え直すということになると思う。
現在において、歴史、文化というものは、どうも、人畜無害なイメージがあるように思われる。
しかし、歴史、文化というものは、今現在の自分というものを、まさに形作っているものであり、本来、非常に影響力のある、生き生きとしたものなのである。
あたかも死んでしまったものという思いこみを脱ぎ捨てて、自らの中に息づいている歴史、文化に目覚めれば、日本人としての自分がはっきりしてくるであろうと、また、日本としての本来あるべき姿もあきらかになるかもしれない。
そして、そうなれば、政治家が本物であるか、ニセモノであるか、すぐに見分けがつくようになるはずである。
日本と日本人とが幸せになるためには、自らの淵源というものを知り、目覚めることが大事なのだと思うのである。