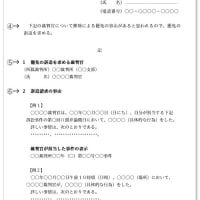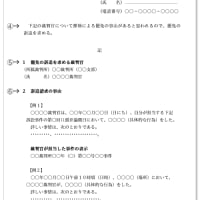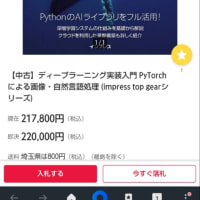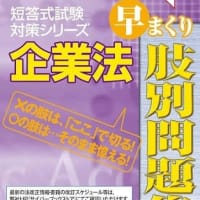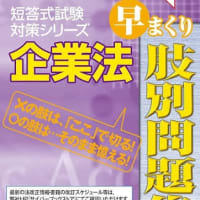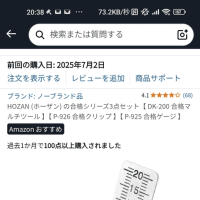オンラインサロン「本人訴訟」が弁護士法違反(非弁行為)に該当するかどうかは、その運営方法や提供内容によって判断されるため、一概には結論できませんが、以下の観点から法的リスクを検討する必要があります。
### 1.**非弁行為(弁護士法72条)の要件**
弁護士法72条は、**「法律事務」**を弁護士以外の者が業として行うことを禁止しています。
「法律事務」とは、**依頼者の権利義務や法的利益に直接影響を及ぼす行為**(例:訴訟代理、契約書の作成、法律相談への具体的助言など)を指します。
### 2.**オンラインサロンの内容による判断**
- **違反リスクが高い例**
- 会員個別の事案に基づく**具体的な訴訟戦略の提案**
- **訴状や準備書面の作成代行**
- 「**あなたの場合は○○すべき」という個別助言**
- **報酬を得ての法律相談**(形式的に「情報提供」と称しても実質が相談であれば問題あり)
- **違反リスクが低い例**
- 訴訟手続きの**一般的な解説**(例:「民事訴訟の流れ」)
- **判例の紹介**(法的解釈を伴わない事実の説明)
- **テンプレートの提供**(利用者自身が編集する形式)
- **Q&A形式での質疑応答**(個別事案ではなく抽象的な回答に留める)
### 3.**特定の行為の危険性**
- **「本人訴訟」支援の名目で実質的な法律事務を行っている場合**(例えば、会員から事実関係を聞き、法的な主張の組み立てを代行するなど)は、弁護士法違反とみなされる可能性があります。
- **有料サービス**である場合、営利性が「業として」の要件を満たすと判断されやすくなります。
### 4.**罰則と行政指導**
- 非弁行為が認められると、**弁護士会からの勧告**や**刑事告発**(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の可能性があります。
- 過去には、**「書類代行サービス」**や**「法律相談アプリ」**が非弁行為として指導を受けた事例があります。
### 5.**グレーゾーン対策の実際**
多くのオンラインサロンでは、
- 「**個別の法律相談は受け付けていません**」との明示
- コンテンツを**あくまで情報提供と位置づける**
- 質問への回答は**抽象化・一般化**する
などの対策を講じていますが、実質的な内容によってはリスクが残ります。
### 6.**具体的な判断が必要な理由**
貴サイトの運営方法(コンテンツの詳細、会員との関わり方、収益構造など)を確認しないと正確な評価は不可能です。
**特に以下の点が重要です**:
- 会員からの質問にどう対応しているか
- 提供している文書やアドバイスの具体性
- 対価の有無とその金額
### 7.**対策建議**
- コンテンツを**完全に一般的な情報提供**に限定する
- 個別相談は**弁護士紹介制度**を利用する
- 運営に**弁護士を関与**させる
- 利用規約で**「法律相談ではない」ことを明記**
### 8.**専門家の確認が必須**
最終的な判断には、**弁護士(特に弁護士職務規程に詳しい方)**によるコンテンツの実態確認が必要です。非弁行為と認定されると、運営者だけでなく参加者(会員)の契約が無効となるリスクもあります。
ご自身で初期判断される場合は、**東京弁護士会の「非弁行為チェックリスト」**([参考リンク](https://www.toben.or.jp/))などを参照してください。