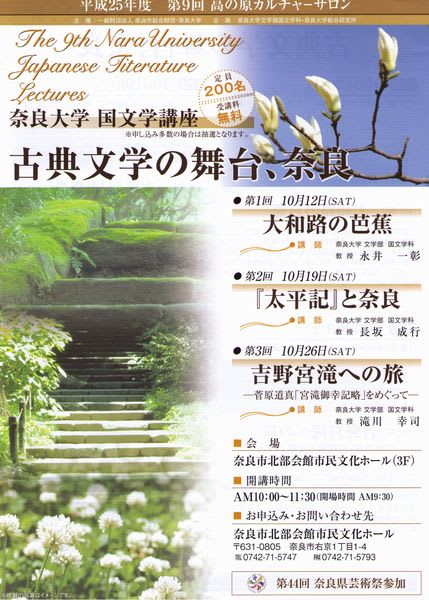2月21日、 浮世絵木版画彫摺技術保存協会研修会のみなさん(15名)が、奈良大学へいらっしゃいました。
永井先生から江戸の板木についてのお話があったのち、板木の実物をみながら、板木について熱い話をくりひろげられました。
実際に浮世絵や木版を彫ったり、摺ったりするプロの方々。彫跡を見て、どの名人が彫ったのか推測するなど、目の付け所が違います。
永井先生から江戸の板木についてのお話があったのち、板木の実物をみながら、板木について熱い話をくりひろげられました。
実際に浮世絵や木版を彫ったり、摺ったりするプロの方々。彫跡を見て、どの名人が彫ったのか推測するなど、目の付け所が違います。