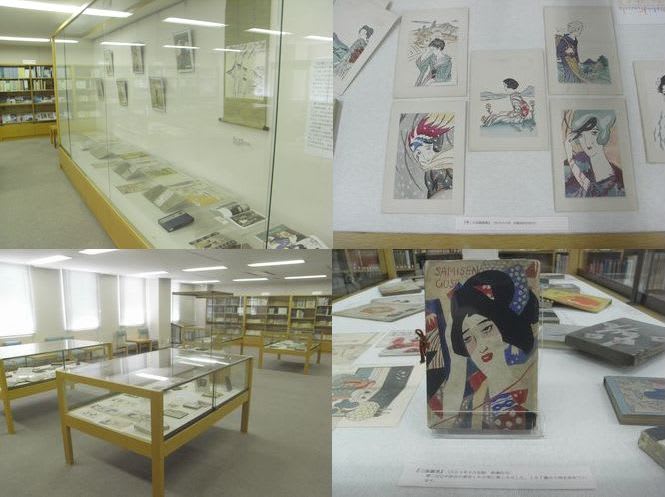上野誠先生が、長編歴史小説『天平グレート・ジャーニー 遣唐使・平群広成の数奇な冒険』(講談社)を刊行されました。
上代研究の確かな知識とエンターテイメント性が見事に融合した作品です。
読んで損なし!
【内容】(同書カバーより)
天平5(733)年の遣唐使は数ある遣唐使のなかでも数奇な運命をたどったことで知られます。行きは東シナ海で嵐に遭い、なんとか4隻すべてが蘇州に到着できたものの、全員が長安入りすることはかないませんでした。それでも玄宗皇帝には拝謁でき、多くの人士を唐から招聘することにも成功、留学していた学生や僧も帰国の途につきました。
しかし……。
4隻の船のうち第1船だけが種子島に漂着、第2船は広州まで流し戻されて帰国は延期、第4船に至ってはその消息は杳として知れません。そして第3船。この船は、南方は崑崙にまで流され、115人いた乗員は現地人の襲撃や風土病でほとんどが死亡、生き残ったのは4人だけだったと史書には記されています。そのひとりが本書の主人公、判官の平群広成なのです。
広成たちはたいへんな苦労の末に長安に戻り、さらに北方は渤海国を経て帰国します。そのとき広成はなぜか天下の名香「全浅香」を携えていたといいますが、それはなぜか?
若き遣唐使の目に世界はどう映じたのか? ふたたび日本の土を踏むまでに何があったのか?
阿倍仲麻呂、吉備真備、山上憶良、玄宗皇帝らオールスターキャストの学芸エンターテインメント。
発行年月日:2012/09/20
ISBN:978-4-06-217864-8
定価(税込):2,625円
上代研究の確かな知識とエンターテイメント性が見事に融合した作品です。
読んで損なし!
【内容】(同書カバーより)
天平5(733)年の遣唐使は数ある遣唐使のなかでも数奇な運命をたどったことで知られます。行きは東シナ海で嵐に遭い、なんとか4隻すべてが蘇州に到着できたものの、全員が長安入りすることはかないませんでした。それでも玄宗皇帝には拝謁でき、多くの人士を唐から招聘することにも成功、留学していた学生や僧も帰国の途につきました。
しかし……。
4隻の船のうち第1船だけが種子島に漂着、第2船は広州まで流し戻されて帰国は延期、第4船に至ってはその消息は杳として知れません。そして第3船。この船は、南方は崑崙にまで流され、115人いた乗員は現地人の襲撃や風土病でほとんどが死亡、生き残ったのは4人だけだったと史書には記されています。そのひとりが本書の主人公、判官の平群広成なのです。
広成たちはたいへんな苦労の末に長安に戻り、さらに北方は渤海国を経て帰国します。そのとき広成はなぜか天下の名香「全浅香」を携えていたといいますが、それはなぜか?
若き遣唐使の目に世界はどう映じたのか? ふたたび日本の土を踏むまでに何があったのか?
阿倍仲麻呂、吉備真備、山上憶良、玄宗皇帝らオールスターキャストの学芸エンターテインメント。
発行年月日:2012/09/20
ISBN:978-4-06-217864-8
定価(税込):2,625円