この前アップした、畑の原の窯詰め。
先週の土日に登り窯の焼成を行いましたよ。
今年も窯焚き監督なので、張り切って活動してきました~。
10月15日(土)10時から火を入れて、最高温度1300度を目指して25時間ほど焼成します。

まずは、胴木間と呼ばれる登り窯の先端から薪を投入して温度をじわじわとあげていきます。
最初は急に温度が上がらないように注意して少しづつ薪を入れていきます。
急な温度変化は陶芸作品が割れる原因になりますので・・・。
だいたい、1時間に70℃くらいをめやすにしてっと。

胴木間から薪を入れ始めて15時間(16日:午前1時)ほどすると、胴木間の次の室(第1室)の温度が1000℃に到達します。
それを目安にして、第1室目の横のレンガを少し外して、そこから薪(松の木)を投げ入れます。
せめ焚きという、窯の内部をわざと不完全燃焼を起こしながら焚いていくので、煤煙がもくもくとでます。
薪の投入口も窯の熱風がでてきて熱いです。
そうやって、だいたい4~5分に1回ぐらいのペースで、温度上昇を見極めながら小割りした待つのタタラ木を10数本づつ投げ入れていきます。
これをずっと続けて、明日の昼まで交代で焚いていきます。

16日の朝から、地元の中学生が薪を入れる体験にやってきました。
交代で薪を投げ入れます。町内にある、国指定史跡をこのように活用できている波佐見町は素晴らしいと思います。
実際に自分の眼で観て、窯の熱を感じながら実体験出来る。
昔の陶工たちがやってきたことを少しでも次世代の子供たちが感じてくれたらいいなって思います。

今回は、薪のコンディションが悪く、雨で湿気ていたり、油分が少なかったりして少々手こずりましたが、なんとか窯焚きも無事に終わりました。
さあ、いよいよ今度の日曜日、朝9時から窯出し作業が行われます。
どんな風に焼き上がっているのか楽しみです。
同会場では、畑の原まつり(昨年の様子)も行われますので、どうぞお越し下さい~。
先週の土日に登り窯の焼成を行いましたよ。
今年も窯焚き監督なので、張り切って活動してきました~。
10月15日(土)10時から火を入れて、最高温度1300度を目指して25時間ほど焼成します。

まずは、胴木間と呼ばれる登り窯の先端から薪を投入して温度をじわじわとあげていきます。
最初は急に温度が上がらないように注意して少しづつ薪を入れていきます。
急な温度変化は陶芸作品が割れる原因になりますので・・・。
だいたい、1時間に70℃くらいをめやすにしてっと。

胴木間から薪を入れ始めて15時間(16日:午前1時)ほどすると、胴木間の次の室(第1室)の温度が1000℃に到達します。
それを目安にして、第1室目の横のレンガを少し外して、そこから薪(松の木)を投げ入れます。
せめ焚きという、窯の内部をわざと不完全燃焼を起こしながら焚いていくので、煤煙がもくもくとでます。
薪の投入口も窯の熱風がでてきて熱いです。
そうやって、だいたい4~5分に1回ぐらいのペースで、温度上昇を見極めながら小割りした待つのタタラ木を10数本づつ投げ入れていきます。
これをずっと続けて、明日の昼まで交代で焚いていきます。

16日の朝から、地元の中学生が薪を入れる体験にやってきました。
交代で薪を投げ入れます。町内にある、国指定史跡をこのように活用できている波佐見町は素晴らしいと思います。
実際に自分の眼で観て、窯の熱を感じながら実体験出来る。
昔の陶工たちがやってきたことを少しでも次世代の子供たちが感じてくれたらいいなって思います。

今回は、薪のコンディションが悪く、雨で湿気ていたり、油分が少なかったりして少々手こずりましたが、なんとか窯焚きも無事に終わりました。
さあ、いよいよ今度の日曜日、朝9時から窯出し作業が行われます。
どんな風に焼き上がっているのか楽しみです。
同会場では、畑の原まつり(昨年の様子)も行われますので、どうぞお越し下さい~。





















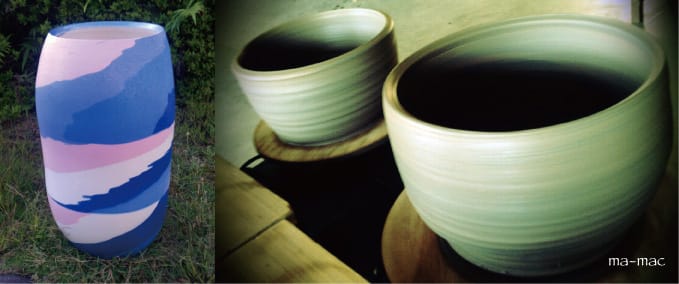

 発表展 ● 長 崎 展 ( 本展 )
発表展 ● 長 崎 展 ( 本展 ) 会期 : 平成23年10月25日(火)~10月31日(月)
会期 : 平成23年10月25日(火)~10月31日(月)


 これを持ち歩くには、体力をつけねばならないっす。
これを持ち歩くには、体力をつけねばならないっす。

