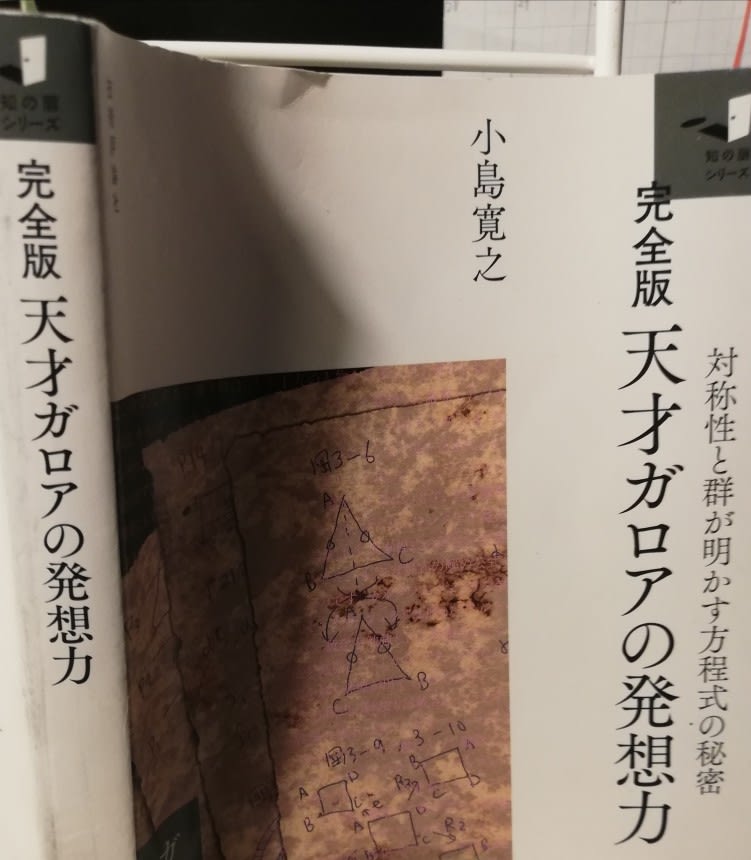
「天才ガロアの発想力」(小島寛之著)を紹介し、第8話目になりますが。
方程式の解法の歴史(その6)とガロア理論に繋がる歴史(その7)をまず述べ、次に2次方程式のガロア理論(その8とその9)と3次方程式のガロア理論(その10からその12)で述べました。
以前、「方程式のガロア群」(金重明著)の紹介では3次方程式の所で躓き、”その5”で長く放ったらかしにしてました。
代数と群を結びつけるというのは非常に抽象的な行為です。故に、色んな本を読み漁り、多方向から眺めるというのも理解する1つの近道かもです。
少し間が開きましたが、前回”その12”ではガロア理論の大きな要である”正規部分群”について述べました。
そいて今日は、群の話からいったん離れ、複素数の話題です。
というのも、虚数という負の平方根の発見こそが、方程式の解法の発見に欠かせないものだからです。
この虚数を全て含むような体を複素数と呼ぶんですが。2次方程式の時代はこうした虚数解(虚根)を”解なし”として済ませてきましたが、3次方程式の解を表記する上では無視できないものとなりました。
負の平方根(虚根)を巡る長い長い歴史
”その6”でも述べた様に、元々、2次方程式は古くは紀元前1600年頃のバビロニアの粘土板にも書かれてあった様に、古代の数学者たちは正の解だけを解と認め、負の解を排除した為に、統一した扱いが出来ませんでした。
負の数を認めたのは、7世紀のインドの数学者プラマグプタでした。彼は”正の数を正で割っても、負の数を負で割っても正である。しかし、正の数を負で割っても、負の数を正で割っても負である”と書いてます。
この負の数を認めたインド数学を積極的に取り入れたのが、イスラム世界です。
9世紀のアル・フワーリズミーは、負数を解と認めていなかったのですが、負の解を導入すれば2次方程式の解の公式が統一できる事には気づいてたらしい。
しかし負の平方根は、例えば”−1の平方根”はずっと長い間認められなかった。
正数の2乗は正数で、ゼロの平方はゼロで、負数の2乗も正だから、負の存在を認めたからとて、2乗して負になる数は認められませんでした。事実、12世紀のインドの数学者バスカラは”負数の平方根はない。負の数は平方ではないからだ”と書いている。
故に、2次方程式の解法を手に入れても、負の平方根の発見には繋がらなかったという事です。
例えばx²+1=0の解は、”−1の平方根”を求める事です。しかし、そんなxは正数にも負数にも存在しないのだから、”解なし”とするしかない。逆を言えば、解なしとすればそれだけで済む事でした。故に、2次方程式の解法にいくら熟達しても、”負数の平方根”を考えるきっかけにはならなかったんですね。
3次方程式がタブーを突破した
しかしこの負の平方根を認める必要に至ったのは、3次方程式の研究からでした。
この3次方程式はイスラムの数学者らも熱心に研究しますが、統一的な解法には至りません。舞台はヨーロッパに移り、16世紀に入ると、”その7”で述べた様に、フォンタナという大天才が3次方程式の解法(公式)を発見します。しかし、当時の数学者たちは奇妙な現象にぶつかった。
”ある3次方程式では解が実数にも関わらず、それを表記しようとすると負数の平方根は避けられない”というものでした。
例えば、x³−6x+2=0ですが。左辺にx=−3を入れると−7で負になるが、−2を入れると+6になり、正負が逆転。故に、xが−3から−2に向えば、左辺の値は途中で0になる筈です。
同様に計算すれば、0と1の間と2と3の間にも解がある筈。図で描けば明らかですが、実数直線上(x軸)に3つの解を持ってますね。
しかし、フォンタナの公式(”その7”参照)で解けば、結果から言えば、解の1つはα=−³√(1+√(−7))−³√(1−√(−7))と得体のしれない数となります。但し、³√は立方根です。
そこで当時の数学者たちは、√(−7)という負数の平方根を何とか消して、実数の形で表そうと努力しますが。当然、敵う訳がない(悲)。
このαの表記から負数の平方根を除くのは原理的に不可能である事が、ずっと後になって証明されます。そして、これがなぜ不可能なのかは、ガロアの定理から本質的に解明される事となります。
この様に、3次方程式の解を表記する上で、負の平方根は避けられない事が判りました。
そこで数学者は負の平方根を無視する訳にもいかず、負数の平方根を”虚数”と名付け、その虚数を全て含む様な体を”複素数”と名付けます。
これも抽象的で判り辛いですが、大まかな歴史の流れだけは掴んどいて下さい。
2万年以上の桁外れの長い歴史を持つ数学という学問は、大きく堅い謎の塊を歴史を1つ1つ紐どきながら砕いていく様な地道な作業の積み重ねです。日本の推理小説の様に、複雑なだけで単純じゃないんですね。
虚数から体を作る
上述した様に、x²+1=0の解は実数ではなく、数直線上には存在しない。しかし、解となる2つの虚数(x=±√(−1))という”お化け”に、(どちらかを基準に)何か名前をつける必要がある。
因みに、実数には四則演算が出来るという他に、”大きさ”という別の性質がある。しかし、x²+1=0の解は実数ではないので、代数的性質しか持たない。
つまり、この2つの解は代数的には瓜2つで全く区別がつかない。しかし、この”双子の虚数解こそが方程式が何故解けるか?”に対するガロアが与えた解答と大きく繋ります。
どんな方程式でも、その解(虚数解)というのは”代数的には”区別がつかない。この事が体の自己同型として現れ、対称性の源となるからです。
結局、当時の数学者たちは、x²+1=0の2つ解のうち、どちらか一方を”虚数単位”と呼び、記号”i”で表す事にしました。
因みに、iとは空想上(imaginary)の頭文字で、当時は虚数を空想上の数字と見下してたんですね。
ここで、x²+1=0の解の片方をiとすると、i²+1=0となり、x²+1=0とi²+1=0を引き算すれば、x²−i²=(x+i)(x−i)=0。故に、x²+1=0の解のもう片方は−iとなります。
しかし、この2つの解±iは、私たちには全く見分けがつかない。
そこで、この虚数(単位)iから体を作ってみます。
”その8”では、有理数Qに√2を加えた体Q(√2)を作りました。体とは四則演算ができる事でしたから、Qに√2を加え四則計算を延々と行い、新しい数ができなくなるまで飽和させた集合がQ(√2)でしたね。
結果、Q(√2)は”有理数+有理数√2”と形の数の集合で、四則演算に関して閉じた集合でした。
これと同じ手続きを虚数iに対して行うんですが、Q(√2)とは異なり、実数Rにiを加え、拡張します。
すると、R(i)は”(実数)+(実数)i”という数の集合で飽和し、この様な数を複素数と呼び、この様な体を複素数体と呼びます。
複素数体の理想郷〜方程式はなぜ解ける?
実は、この複素数体R(i)こそが見事な世界を生み出すんです。
つまり、負数の平方根は全てこのR(i)の中に含まれてますね。虚数という”お化け”はiだけを導入すれば、全て作ってくれる。
例えば、√(−7)はx²+7=0の1つの解で、R(i)の中に全ての解を持つ。
x²+7=x²−7(−1)=x²−7i²=(x−√7i)(x+√7i)=0より、解はR(i)の中の√7iと−√7iになる。故に、−7の平方根は±√7iと定義できます。
同じ様にして、全ての負数の平方根を作る事が出来、必ず複素数体R(i)の中に2つの解がある事が判る。
実は、2次方程式だけでなく、どんなn次方程式でもR(i)の中に全ての解がある事が判っています。係数を複素数にしても、n次方程式は全ての解が複素数体の中に見つかるのです。
これを証明したのが、ガロアが尊敬する”数学の巨人”ガウス(1777−1855、独)でした。
このガウスのお陰で、”複素数は代数方程式について自己完結する”一種の理想郷だという事が判ったんです。この様な集合を”代数的閉体”と呼びます。
しかし、このガウスの発見は一見すると、ガロアの定理と矛盾してる様にも見える。
16世紀にフォンタナが3次方程式の解法を、フェラリが4次方程式の解法を発見し、以降は2つのテーマが問題になりました。
1つは”高次方程式では複素数の解を避けられない筈だが、複素数を許すなら全ての解が保証されるのか?”と、2つ目は”複素数に解が存在するなら、その解を四則とべき根で求める解法は存在するのか?”でした。
そこでガウスは第1の問題に対し、答えを出したんです。つまり、ガウスによって”どんな高次方程式も複素数の範囲なら解の全てが存在する”事が証明されました。
で、次なる問題が、”ならばどうやって解を見つけるのか?”でした。そして、それを解いたのがガロアだったんですね。
そのガロアの模範解答こそが、”5次以上の方程式には複素数解が存在するが、四則とルートで求める手続きはない”というものでした。
勿論、”500年先を行く天才”アーベル(1802−1829)もガロアの6年ほど前に、未完全ながらこの事を証明しました。しかし、ガウスの逆鱗に触れ、アーベルの証明は無視されます。
これを見ても、数学というのが如何に”継承の賜物”かであるかが伺えます。
以上で、代数の立場から複素数(体)というものを多少は理解できましたかね。
でも、複素数も群の様に、何らかの対称性はないのでしょうか?
つまり、複素数の世界が図形で表現でき、四則演算でどうビジュアル化出来るのか?
でないと、複素数を完全に理解するのは不可能です。
次回は、複素数解が作る美しい図形と、"複素数体にべき根を加えた体"がどんな構造をしてるのか?を見てみたいと思います。










そこで若き天才ガロアは虚数解を加えて複素数の体を作り、5次以上の方程式では複素数解は存在するけど四則の計算とルートでは求めることができない事を導いたんだ
でもアーベル様も同じようなこと証明したのよね
なぜガウスの怒りを買ったのかしら?
アーベルは”一般的な解法は存在しない”と漠然と書いてた。それでガウスはキレちゃった。
でも基本理念はガロアと同じで、解の置換にあったんです。その解の置換の陰に隠れてた群論をガロアは新たに展開したんです。
アーベルはそうでもなかったけど、ガロアはガウスの大ファンだったから、ガウスの発見にピンときたんだね。