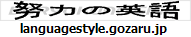女性の呼称が「ミス」という美しい音から「ミズ」というミミズのような鈍い音に変わってしまったのはいつからなのでしょうか。最近の英語教科書では例えば次のような会話例が堂々と登場します。
ミズ(Ms.○○)の歴史と言うのはそれほどあるわけではありません。それはわずが30年ほど前の1975年に遡るにすぎません。
ミセス(Mrs)は既婚婦人の姓(名)の前に付けて、ミス(Ms)は未婚の女性の姓(名)の前につける敬称ですが、最近の中学教科書ではけっこうミズ(Ms)という語を目にします。男性はミスター(Mr)で統一されているのに、女性の場合はなぜミセス(既婚)とミス(未婚)の区別をするのかということで生まれることとなったミズです。1975年、メキシコで開かれた国際婦人年世界会議において初めてミズが使われたのだそうです※1。
ミセスやミスのかわりにミズを使うことをアメリカ議会に提案したのはベラ・アブザグ下院議員です。立法化しようと言うのです。この他にも、女性に未婚・既婚の区別があるように、男性のほうにも区別を設けようという提案もあったといいます。ラッセル・ベイカーがムルム(Mrm)とスルス(Srs)というものを提案したのです。しかし考えてみれば分かるように、新しく区別を作るよりは無くす方が容易です。そのためかベイカー提案は真面目には受け取られなかったようです。ミズ提案のほうはウケが良かったのかどうか知りませんが、現在では「教科書」にまで入り込んできているという点では大成功したと言えるでしょう。いつかは映画の「ミセス・ダウト」が「ミズ・ダウト」になり、ミス・コンテストがミズ・コンテストと呼ばれるようになる日がやってくるのでしょうか。
言語と性の関係には興味深いものがいくらでもあります。例えば、現在、NHKで「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組をやっていますが、プロフェッショナルという語については次のような具体例が挙げられます。次の2文は形式としては同じ形を取っていますが、それが表す意味には大きな違いがあるのです。
「彼はプロフェッショナルだ」と言ったとき、この「彼」は医者や弁護士などのような何か専門職にあることを意味する一方、「彼女はプロフェッショナルだ」と言ったときには専門職は専門職であってもそれは比喩的な意味合いの強い「売春婦」という意味になるということです。なかなか興味深い言語の一面です。
女性からしてみればこのような現実には不満があるところでしょうし、納得のいかないところかもしれません。しかし、このような現実を変えるための運動が行き過ぎると別の問題が出てくることになります。
それはpolicemanには男性もいれば女性もいるのだからpolice officer[person]とするべきだというレベルに留まっている限りには問題はありませんが、stewardに対するstewardessを問題にしたり、女性は男性の付け加えではないという理由からmanにwoをくっつけた形をしているwomanを問題にするなどの事態に発展するとなかなかバカげた世の中になってしまうのではないでしょうか。womanはやめてwomonにしようなどという案が現実にあるわけですから驚きます。関係のないはずの日本語でもスチュワーデスと呼べば差別主義者のように言われる始末です。看護婦さんというのもいけないらしい。よく分からない社会になってると思うのは私だけでしょうか。
加藤周一氏の『真面目な冗談』(1980年、平凡社)に収められている「日本語改革」を紹介しましょう。
womanではなくwomonを人々が使う(あるいは使うべきだと考える)日が来たとしても私はそのような動きには参加しませんし、そのような不細工な歴史(history)に関わりたくもありません。historyもいつの日にかpersontoryになってしまうのでしょうかね※2。
[追記:2007.12.26]
『各種ガイドラインおよび高校英語教科書に見る敬称の問題』によればMsの成立の経緯は次のようなものだといいます。
・ビジネスの場面で使われはじめたという報告がある(1932年)。
・The Oxford English Dictionary, Second Editionによれば1952年が初出。
・Msの一般化は1960年代の米国における雇用差別問題である。
・Msの使用が積極的に推奨されることとなったのは1970年代に台頭した第二波フェミニズム運動がきっかけである。
・Msを表題に掲げた雑誌が創刊される(1972年)。
・国連において女性に対する正式な敬称としてMsが採用(1973年)
※1 こちらやこちらを参照。少し前の1973年のボストン国際フェミニスト会議でミズの使用が公認という情報もあります。いずれにしてもこの頃のこと。なお、国連は1975年を「国際婦人年」とすることにしているのだそうです。
※2 念のために付け加えておくと、historyという語はhis storyとは全く関係のない語であるようです。「彼の物語」、つまりは「男性の物語」という意味が出発点になっている語ではないことは頭に置いておく必要があります。
※ブログランキングに参加しています。よろしければクリックをお願いします。


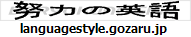
Are you Ms. Green? ―Yes, I am. |
ミズ(Ms.○○)の歴史と言うのはそれほどあるわけではありません。それはわずが30年ほど前の1975年に遡るにすぎません。
ミセス(Mrs)は既婚婦人の姓(名)の前に付けて、ミス(Ms)は未婚の女性の姓(名)の前につける敬称ですが、最近の中学教科書ではけっこうミズ(Ms)という語を目にします。男性はミスター(Mr)で統一されているのに、女性の場合はなぜミセス(既婚)とミス(未婚)の区別をするのかということで生まれることとなったミズです。1975年、メキシコで開かれた国際婦人年世界会議において初めてミズが使われたのだそうです※1。
ミセスやミスのかわりにミズを使うことをアメリカ議会に提案したのはベラ・アブザグ下院議員です。立法化しようと言うのです。この他にも、女性に未婚・既婚の区別があるように、男性のほうにも区別を設けようという提案もあったといいます。ラッセル・ベイカーがムルム(Mrm)とスルス(Srs)というものを提案したのです。しかし考えてみれば分かるように、新しく区別を作るよりは無くす方が容易です。そのためかベイカー提案は真面目には受け取られなかったようです。ミズ提案のほうはウケが良かったのかどうか知りませんが、現在では「教科書」にまで入り込んできているという点では大成功したと言えるでしょう。いつかは映画の「ミセス・ダウト」が「ミズ・ダウト」になり、ミス・コンテストがミズ・コンテストと呼ばれるようになる日がやってくるのでしょうか。
言語と性の関係には興味深いものがいくらでもあります。例えば、現在、NHKで「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組をやっていますが、プロフェッショナルという語については次のような具体例が挙げられます。次の2文は形式としては同じ形を取っていますが、それが表す意味には大きな違いがあるのです。
He's a professional. She's a professional. |
「彼はプロフェッショナルだ」と言ったとき、この「彼」は医者や弁護士などのような何か専門職にあることを意味する一方、「彼女はプロフェッショナルだ」と言ったときには専門職は専門職であってもそれは比喩的な意味合いの強い「売春婦」という意味になるということです。なかなか興味深い言語の一面です。
女性からしてみればこのような現実には不満があるところでしょうし、納得のいかないところかもしれません。しかし、このような現実を変えるための運動が行き過ぎると別の問題が出てくることになります。
それはpolicemanには男性もいれば女性もいるのだからpolice officer[person]とするべきだというレベルに留まっている限りには問題はありませんが、stewardに対するstewardessを問題にしたり、女性は男性の付け加えではないという理由からmanにwoをくっつけた形をしているwomanを問題にするなどの事態に発展するとなかなかバカげた世の中になってしまうのではないでしょうか。womanはやめてwomonにしようなどという案が現実にあるわけですから驚きます。関係のないはずの日本語でもスチュワーデスと呼べば差別主義者のように言われる始末です。看護婦さんというのもいけないらしい。よく分からない社会になってると思うのは私だけでしょうか。
加藤周一氏の『真面目な冗談』(1980年、平凡社)に収められている「日本語改革」を紹介しましょう。
日本語改革 新かな遣いなどはものの数でもない。事は「敗戦」を「終戦」、「占領軍」を「進駐軍」、「後進国」を「発展途上国」というあたりからはじまった。「支那語」はいけないから「中国語」になり、それがたちまち日常身辺に及んで「女中さん」が「お手伝いさん」になった。「女中」は本来身分の高い女にのみ使う言葉で、歌舞伎などでは一種の尊称だが、「お手伝いさん」に歌舞伎を見物する習慣がない以上、そんなことをいってみてもはじまらない。 蔑称はすべて廃止しなければならぬ。「気ちがい」ではなくて「精神障害者」、「片輪」ではなくて「身体障害者」、「めくら」でも「盲人」でもなくて「視覚障害者」――いや、常にそう簡単にゆくとかぎらないのは、視覚障害者が必ずしも「めくら」ではなく、近視、遠視、乱視、色盲、その他多くの障害でもあり得るからだ。「めくら蛇に怯えず」は、「視覚対象の距離光度に係らざる色彩形状識別不能者蛇に怯えず」としなければならない。 いつのころからか「女」が「女性」になった。「性」の一字を加えると、女の格がいくらかあがるだろうと、日本語の語感の鈍い「女性」または「男性」が(もしかするとCIAか)思いついたことであろう。しかしそんなことが長くつづくわけがない。思いきって、男女差別を廃するには、何としても「女」の一字を落とさなければだめだ。いっそ先祖はイザナギ・イザナミだから、「男」を「ナギ」、「女」を「ナミ」という日も、遠くないことであろう。 さてまた大臣や政治家、昔は子分に先生などとよばれてきたけれど、今ではすべてワイロの疑いあまりにも濃く、そのうちこれも一種の蔑称になるにちがいない。本人たちがそれに気づけば、「女中さん」から「お手伝いさん」の流儀で、何とか名前を変える必要があるだろう。たとえば「内外会社献金高額消費者」。 今や日本語改革の運動は、挙世滔々として、とどまる所を知らず、日進月歩して、人事を超え遂に動物畜類にまで及ぶにちがいない。家庭では、もはや「犬」ではなくて、「用心棒さん」、「猫」ではなくて「ねずみとりさん」になる。人はもはや「馬券」を買わず、「高速四足動物さんの番号札」をいただき、当たればもうけ、当たらなければ損をするだろう。しかしそれにしても、とって食われる「ねずみ」の方は、どういう名前でよばれるのかしら? |
womanではなくwomonを人々が使う(あるいは使うべきだと考える)日が来たとしても私はそのような動きには参加しませんし、そのような不細工な歴史(history)に関わりたくもありません。historyもいつの日にかpersontoryになってしまうのでしょうかね※2。
[追記:2007.12.26]
『各種ガイドラインおよび高校英語教科書に見る敬称の問題』によればMsの成立の経緯は次のようなものだといいます。
・ビジネスの場面で使われはじめたという報告がある(1932年)。
・The Oxford English Dictionary, Second Editionによれば1952年が初出。
・Msの一般化は1960年代の米国における雇用差別問題である。
・Msの使用が積極的に推奨されることとなったのは1970年代に台頭した第二波フェミニズム運動がきっかけである。
・Msを表題に掲げた雑誌が創刊される(1972年)。
・国連において女性に対する正式な敬称としてMsが採用(1973年)
※1 こちらやこちらを参照。少し前の1973年のボストン国際フェミニスト会議でミズの使用が公認という情報もあります。いずれにしてもこの頃のこと。なお、国連は1975年を「国際婦人年」とすることにしているのだそうです。
※2 念のために付け加えておくと、historyという語はhis storyとは全く関係のない語であるようです。「彼の物語」、つまりは「男性の物語」という意味が出発点になっている語ではないことは頭に置いておく必要があります。
※ブログランキングに参加しています。よろしければクリックをお願いします。