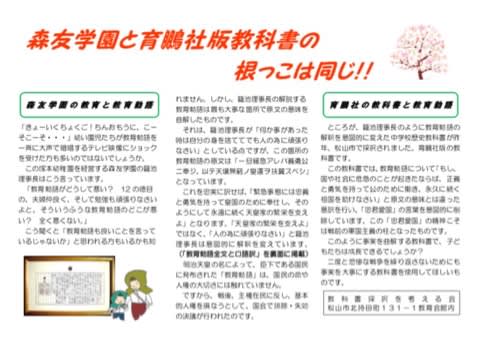8月8日に、松山市教育委員会は「教育出版」を小学校道徳教科書に採択しました。
教育出版は、「国家主義的傾向が強い」として教職員関係団体や市民団体が、県や市町に不採択を請願していたにもかかわらず、
このような結果になり大変残念な思いをしています。
それ以上に、今回の教科書採択では、前回までの採択方法とまったく異なったものになっていたことに驚きを隠せませんでした。
非常に非民主的で独断的なシステムになったと感じています。
***************************************************************************************
[変わった点① 学校現場から希望を聞くことがなくなった]
前回までは、各学校から希望する1位の教科書を報告することになっていた。
ところが、今回は8教科書のよいところのみを書くものをなった。良いところのみ、というのは実質、希望を聞かないということである。
学校報告書をもとにした調査部会からの意見書は出なかった。
[変わった点② 採択委員会が懇話会になり、答申は無かった]
前回まであった採択委員会は、調査部会からの意見書をもとに答申を出していた。
今回は、懇話会となり、話し合った内容を列記したものが教育委員に届けられたのみ。
[変わった点③ 最後は教育委員の独断]
無記名投票を行い、5人の教育委員のうち3人が教育出版に賛成し、決定した。
意見書も答申もない中での決定は、教育委員の独断でしかなかった。明確な教育出版採択の理由説明もなされていない。
*****************************************************************************************
教科書裁判を支える会での学習会(8/21)参加で、教科書採択が教育委員の独断で採択できるシステムに事前につくられたことを知りました。
[いつから?]
2014年3月、「採択委員会規則」を廃止し、「松山市教科用図書採択要綱」を作成・施行して「答申」の制度を廃止。
採択委員会を単なる「懇話会」と位置づけ、そこで話された「協議の内容は、学校教育課が記録を作成し、教育委員会に提出する」という形に変えた。
[なぜ?]
2001年に教科書問題が出てくる。東京と松山市で扶桑社採択が狙われる。答申制を撮っていたため、2011年まで採択できなかった。
2011年、金本教育委員長「採択したいが、現場からの希望が少ないのでできない」と発言。
2015年は、2014年3月にシステムを変えていたが以前のままを踏襲した。しかし、答申には従わず教育委員が4対1で育鵬社教科書に決定。
2017年の教科書採択委員会では、新しいやり方で教育委員の独断で教育出版の教科書に決定。