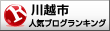養寿院の入口にこの石柱が建っている。

(前略)
禅寺の門の脇によく「不許葷酒入山門」と刻まれた石碑が建っている。よく知られているように「葷酒(くんしゅ) 山門に入るを許さず」と読み、「葷」はにおいの強い野菜、正確にはニンニクやラッキョウ、ネギ、ニラなどのことで、それらの野菜と酒をその先の清浄な場所に持ち込むことを禁止する、という意味の掲示である。
しかしその七字に点をひとつ加え、「不許葷、酒入山門」とすればたちどころに意味が変わって、「葷を許さず、酒は山門に入れ」と読めてしまう。実際にこの句をそう理解して、寺院の中で酒盛りを楽しんでいる破戒僧(はかいそう)もたくさんいるようだ。
厳しい修行を要求される寺院で酒が制限されるのはわかるとしても、なぜ「葷」が禁止されるのだろうか。それはニラやニンニクを食べると若い修行僧が精力旺盛になり、いきおい煩悩がさかんにおこって、修行のさまたげになるからとの配慮なのだそうだ。
たしかに修行の身でニンニクを食べると、あとで困ることになるだろう。僧だけでなくむかしは女性もめったにニンニクを食べなかったようだ。いろいろな女性論を展開する「雨夜の品定め」(『源氏物語』「箒木(ははきぎ)」)に、風邪を引いた女性が「熱き薬草」であるニンニクを食べる場面があるが、その女性は御簾(みす)ごしに話すばかりで恋しい男に会おうとしない。
ニンニクはもともと「大蒜」と書き、「ひる」という名前でよばれていた。いまの「ニンニク」という呼び名は、屈辱に耐えて怒りの感情を起こさないことをいう仏教用語「忍辱(にんにく)」に由来する。なんのことはない、「葷」もちゃんと山門に入っていたのであった。
(阿辻哲次 『故事成語 目からウロコの85話』 青春出版社)