2016年11月29日(火)国宝「信貴山縁起絵巻」で有名な信貴山・長護孫子寺を訪れる
多宝塔・鐘楼堂
 本堂から山の方へ少し登ると紅い塔が現れる。多宝塔です。中には入れないが,平安中期の僧・恵心僧都(えしんそうず)の作とされる大日如来が祀られているそうです。元禄2年(1689)の建立,明治15年(1882)に修復された。
本堂から山の方へ少し登ると紅い塔が現れる。多宝塔です。中には入れないが,平安中期の僧・恵心僧都(えしんそうず)の作とされる大日如来が祀られているそうです。元禄2年(1689)の建立,明治15年(1882)に修復された。多宝塔左の道(空鉢護法堂への参道)を入っていくと行者堂に突き当たる。7~8世紀に活躍した修験道の開祖とされる役行者(役小角)が祀られています。信貴山も修験道の霊場として関係深いことから祀られたものと思われます。


色鮮やかな多宝塔の前に,対照的に黒さびた鐘楼堂が建っている。一丈四方の袴腰の上に鐘を吊るした堂がある。梵鐘には“信貴四郎”の鐘銘が刻まれ,「鐘名信貴四郎は天下に第四番の名鐘なり」と謳われていたそうです。貞享4年(1687)の再建。
これから奥之院へ向かいます。多宝塔を挟み左と右に道が分かれている。左の道は,行者堂を経て信貴山の山頂にある空鉢護法堂への参道です。右の道が奥之院への参道で,入り口に「奥之院毘沙門天王道」の石碑が建つ。
奥之院


奥之院は情報では,多宝塔から約2キロ,30~40分かかるという。参道というより,なだらかな山道といった風です。15分位で大谷池が現れ,何人か釣りをされている。池を過ぎると緩やかな下り道になる。車一台通れるほどの道幅。やがて広い車道が見えてきた。
地図を見れば「フラワーロード」とある。それほど車は走っていないが,この広い車道に遭遇すれば”奥之院”という神秘的なイメージが壊れてしまいます。
「奥之院」といえば,高野山,室生寺を想起します。いずれも神秘的で厳粛な世界に入っていく,又は登っていくという雰囲気に満ちていた。ここの奥之院はどうだろう。広い車道を横切り,民家のある下界に下っていくのです。お寺から下山する感じです。道脇に何ヶ所か置かれていた丁石が,唯一参道らしい趣を感じさせてくれました。


午後1時半、40分かかり奥之院に着きました。寂れたお寺といった風。
山門を潜ると左側に瓦葺の本堂がある。石鳥居や石灯篭が・・・ここは神社か?。この地はわが国で最初に毘沙門天王が出現した霊地され,本堂に御本尊として祀られている。ただしここの毘沙門天さんは「汗かき毘沙門天王」と呼ばれれています。「聖徳太子が守屋討伐の時、毘沙門天王が阪部大臣に化現して先鋒を振われ、御尊像が汗をかかれていたと伝えられております。よって当山は聖徳太子開基の信貴山奥之院、毘沙門天出現最初の地とされ、ご本尊は「汗かきの毘沙門天王」と呼ばれ、御霊験きわめてあらたかです。」と説明されている。

本堂から奥へ進むと空き地があり,その中に「やけごめ」の石碑が建つ。ここの地中から焼き米が湧出するそうだ。その焼き米は,聖徳太子の物部守屋討伐時の兵糧米だとおっしゃっている。毘沙門天王に帰依しこの焼米を頂けばどんな病気も治るそうです。
この奥之院と朝護孫子寺とはどういう関係なのだろう?。朝護孫子寺の境内図には載っているが,朝護孫子寺発行のパンフ「毘沙門天王の総本山 信貴山朝護孫子寺」(p40)には一言も載っていない。山門脇の説明版には「当院は信貴山塔頭なりしも今は奥之院と称す」と意味深な表現をしている。信貴山朝護孫子寺傘下の一寺院なのか,独立寺院なのか判然としない。建物の修理・再建のための寄付金を募集していることから独立しているようにみえるが・・・。

フラワーロードからの眺め。奈良盆地が一望できます。
信貴山の山頂へ(信貴山城址)


奥之院から多宝塔まで引き返し、今度は左の道に入り信貴山の山頂にある信貴山城址と空鉢護法堂を目指します。
約700mの山頂への参道は、かなりの勾配の九十九折りの道だが階段状によく整備されている。参道には多数の朱塗りの千本鳥居が続く。一願成就の願いを込めてか,成就かなっての千本鳥居か。それぞれに献納者の住所・氏名が書き込まれている。所々に丁石も置かれています。

 午後3時、約20分ほどで山頂近くの広場に着く。「信貴山城」の白い幟がはためいている。
午後3時、約20分ほどで山頂近くの広場に着く。「信貴山城」の白い幟がはためいている。信貴山(しぎさん)は、雄岳と呼ばれる北峰(437m)と雌岳と呼ばれる南峰(400m)の二峰からなっている。城跡や空鉢護法堂があるのは雄岳。県境に位置し、西側が大阪府で東側が奈良県。金剛生駒国定公園に属しています。かの昔、聖徳太子が河内側(大阪)の物部守屋を攻めた時、この山で毘沙門天が現れ、その御加護で太子は勝利した。太子が信ずべし、貴ぶべしといったことから「信貴山」と名付けられたと伝わる。
この広場の山頂寄りに「信貴山城址」の碑が建っています。ここには戦国時代に山城「信貴山城」が建ち、大和地方をを睥睨していた。この碑の辺りに二の丸が、少し横の山頂に本丸が建っていたという。
標高437mの信貴山は大和と河内の間にある要衝の地。戦国時代の天文5年(1536)に,畠山氏の家臣・木沢長政により山城が築かれた。長政戦死の後,三好長慶の被官・松永久秀が入り修復・改修し,南北700m、東西550mに及ぶ本格的な城郭に仕上げた(永禄2年1559年)。永禄11年(1568年)筒井順慶と三好三人衆に攻められ窮地に陥るが,織田信長によって助けられる。織田信長に臣従したが,天正5年(1577)信長に謀反を起こし総攻撃を受け50日間籠城の末,落城し久秀は自殺する。この戦で長護孫子寺も焼失してしまいます。
空鉢護法堂(くうはつごほうどう)


信貴山城址碑の横の参道脇に、八体の石仏像が並んでいます。それぞれの仏像には「破軍星」「明星」などの名が付けれ、「星祭り本尊」と呼ばれている。さぞかし星空が美しく見えることでしょう。
星祭り本尊の前は、赤色の千本鳥居が並び、それを抜けると休憩所の様な建物の中を通って空鉢護法堂のある境内に着く。

「空鉢護法(くうはつごほう)」とは,「信貴山縁起絵巻」の「飛倉之巻(とびくらのまき)」からきている。信貴山中興の祖・命蓮上人が法力(飛鉢の法)で貪欲な山崎長者の倉を空鉢に乗せ信貴山まで飛ばしてしまうという逸話です。空鉢には毘沙門天王の侍従神にして八大龍神の最上首・難陀竜王(なんだりゅうおう)の力が備わっていた。
空鉢護法堂には,空鉢護法の神・難陀竜王が祀られている。難陀竜王は龍神即ち蛇の姿をしていおり,一願成就の神様だそうです。拝殿前にはとぐろを巻いた石造の蛇が置かれている。この蛇をなでると一つだけ願いを叶えてくれるそうです。


山頂だけあって空鉢護法堂前からの眺望も素晴らしい。大和平野が一望でき,南には二上山、葛城山の山々の連なりを遠望することができます。
山頂から西の方を見れば山の頂が見える。あれが高安山だろうか?。予定では,信貴山の山頂から尾根伝いに高安山へ登り,そこからロープウェイで大阪側へ降り帰ることにしていた。現在4時前,高安山までの距離も時間も定かでない。その上天候も曇り。高安山は断念した。仁王門近くの信貴大橋バス停まで引き返し、3時50分のバスに乗る。
詳しくはホームページを










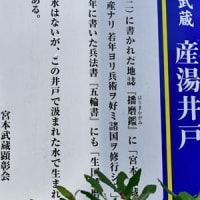









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます