教員はオンライン授業をどのように考えているのだろうか。ニュースネット委員会は、教育学を専門とする神戸大の近田政博教授と生物学と価値創造を専門とするバリュースクールの鶴田宏樹准教授にオンライン授業についてインタビューを行った。近田教授は大学教育推進本部の副本部長を務め、鶴田准教授はバリュースクールの専任教員として、学際教育プログラムの開発を行っている。取材を通して、学生の立場からは見えない、教員の苦労が見えてきた。<笠本菜々美、佐藤ちひろ>

(写真:神戸大本部)
教員も学生もディスプレイを一日中見なければいけない状況
オンライン授業の弊害の一つとして挙げられるのが目の疲れだ。近田教授は、「画面を長時間近距離で見続ければならず、正直に言うとかなり疲れる。自分自身、2020年末に網膜剥離になったが、オンライン授業は無関係ではなかったと感じている」と話す。
教員は授業中、真っ暗な画面にずっと語りかけている
オンライン授業には、大人数講義を行う教員特有のデメリットもある。近田教授は、「授業中、学生は教員が見えるが、教員には学生の顔が見えず、学生の名前だけが表示された真っ暗な画面にずっと語りかけている状態」と話す。このような授業の様子について、「特に最初の一年は、慣れなかった」そうだ。近田教授は、対面授業と比べて「空気感や間の共有などの非言語的コミュニケーションが難しい」ことが、オンライン授業の課題だと考えている。
しかし、通信回線への負担と顔を不特定多数の人に見せることへの学生の心理的抵抗感を考慮すると、Zoomを使用した授業で顔出しを求めるのも難しいという。
オンライン授業が学生・教員間の距離を近くすることも
一方で、オンライン授業(Zoom)でのコミュニケーション方法にはチャットやブレイクアウトルームがあり、そうした機能を使えば教員と学生が授業中に交流できる。近田教授は、オンライン授業での学生と教員の距離感について「対面授業のとき、大教室の後ろの方でスマホをいじっている学生よりは、リアルタイム型オンライン授業の方がむしろ学生との距離感は近いように思う」と話した。
オンライン授業は「一長一短というよりむしろ、多長多短。」
鶴田准教授は、①一方的に話す講義形式の授業と、②グループワークを行い、問題設定をして解決策を考え出す授業の2種類の授業を行っている。オンライン授業をしてみて、「①に関しては、伝える内容は変わらないが、オンラインだと顔が見えず、学生のリアクションや雰囲気など、場の温度的なものが分からない。同じことを伝えるとしても、伝える工夫を考えるのが難しい。②に関しては、SNSなどオンラインでのコミュニケーションに慣れている人は活発に議論できるが、慣れていない人には難しい」と感じたという。
また、「対面で行う場合は黙っているグループのところに行って議論をファシリテートできるが、オンラインだと、すぐにグループに入り込むことができない。ハイブリッド授業の場合は、目の前の学生とオンライン上の学生を同時に見なければいけないため、どうしても目も耳も届かないことが多い。その一方で、どこからでも参加できるというメリットがあるため、他大学との交流が前提で全国から参加者がいる授業の場合にはハイブリッド授業形式は便利である。とはいえ、やはりオンラインだと、すべての学生に同じように接することができないため、講義はできるが、グループワークは難しいのかもしれない。自分たちに話していないと感じ、離脱してしまう学生もいた」ということだ。
近田教授はオンライン授業について、「一長一短というよりむしろ、多長多短」と話し、メリットとして「コロナ禍のような社会状況でも、まがりなりにも授業として成立すること」、「何らかの障がいをもつ学生や教員の負担が減ること」を挙げた。

(写真:ニュースネットのオンライン取材を受ける近田教授 画面下)
分野特性によって適した授業形態は異なり、教員の意見にも差
オンライン授業には、リアルタイム型とオンデマンド型がある。近田教授によれば、「大学が収集したデータを見ても賛否両論ある。知識積み上げ型の授業は教員も生徒もオンデマンド型を好む傾向にある」という。一方で、「人文系など、いろいろな考え方があることを学ぶものは、学生と教員が相互に考えを深めていくものであるので、先生はリアルタイムの議論を好む傾向にある」そうだ。
鶴田准教授も、オンライン授業のメリットに「どこからでも参加できることと、録画ができること(アーカイブが残せること)」を挙げ、デメリットに「対面に比べて内容が伝わりにくいこと」を挙げた。
リアルタイムのオンライン授業はラジオ番組のよう
また、近田教授は、オンラインでリアルタイム授業を行っても、「学生の反応がわかりにくい」という。また、授業を行うのは「ラジオのディスクジョッキーに近い。(Zoomの)チャットはラジオにおけるはがきのようだ。」と話す。さらに、「学生が一日オンライン授業に集中するのが難しいことは理解できる。Zoomが終わったときに退出しない(=授業を聞いていない)のは1割いないくらい。相手が何をしているのか分からない状況は不安感がある」と話した。
「学びのための課題というより確認のためではないか」
ニュースネットが実施したアンケートの結果、オンライン授業で課題の量が多いと感じている学生が多いことを伝えると、鶴田准教授も「不安」という言葉を口にした。「昔は授業の形式を重視する教員ばかりではなかった。いい加減に授業しているという誤解を与えることを避けないといけないので表現が難しいが、今より自由度が高かったので、例えば、休講しても補講や課題だけでなく、臨機応変に学びの内容を担保することがあった。しかし現在では文部科学省の厳しい方針なのか、大学の教員が生真面目になったのかわからないが、授業の理解を「課題」を出すことで測らないといけないような雰囲気はある」とした。
そのうえで、「オンラインでの授業で、先生は学生が理解しているのか不安を感じている側面もある。対面であれば、講義の雰囲気でそれがわかる。真面目な先生は特に、学生が理解しているのかを確かめたくて課題を出す。本当に授業を聞いているのか気になる。(別にそれでも構わないが)オンライン授業は聞き流せる。しかし、それで学生を縛ることになるのはよくないと思う。大学の学びは教科書を読むことだけではなく、さまざまなものを観て感じて考えることも重要だと思う。そこまで学生の時間を奪ってはいけないと考えている。個人的には、(オンライン授業での過重な課題は)学びのための課題というより確認のためではないかと思う時もある。そもそも、オンラインになったからというより、教育そのものが詰め込み型になってしまっているのではないかと感じる。学生には、知識をなぜ得て、どう使っていくのかを考える時間がないのではないか。知識の獲得ができていても、それを使うための考える時間がないということが一番の問題だと思う。ものを考えることが大事なのであって、課題に追われるのはもったいないと思う」と話した。
また、「そのために神戸大学では、“感じて”、“考える”ということに重点を置いた活動を促す「バリュースクール」が作られた。これはどこの大学にもない学びの“場“であり、神戸大学生なら誰でも参加できる。「課題」はこなすだけではつまらない。「課題」そのものを”考える“ことは楽しいことだ」と語った。バリュースクールのサイトは以下のURLからアクセスできる。V.School Kobe 国立大学法人神戸大学バリュースクール (kobe-u.ac.jp)

(写真:バリュースクールの様子。鶴田教授提供)
去年と同じ動画を使い回すのは違和感がある
また、オンデマンド授業について近田教授は、メリットに「分からない所などがあったら繰り返し視聴することができる」点と、「場所・時間に縛られないので、自由度が高まる」点を挙げる。また、単位取得という面でもオンデマンド授業には利便性があるという。近田教授は、「医学部や海洋政策学部は、言語を落とすとカリキュラムの関係で、即留年になってしまう。これはオンデマンド化でカバーできる。つまりオンデマンド授業は落単回避策となり、これは大学運営上のメリットでもある。」と話した。
一方、オンデマンド授業のデメリットには「その場で質問することができない」点があるという。鶴田准教授は、ニュースネットが学生向けに行ったアンケートに寄せられた「昨年度のリアルタイム授業のアーカイブ動画を今年度の授業動画としている講義があり、違和感があった」という意見に関して、「学生と同じく違和感がある。普通教員は教えることは同じでもどんどんよくする工夫をしているため、授業では毎回同じことを話すとは限らない。録画した授業を採用したら、無味乾燥なものになってしまう。」と話した。
このように、リアルタイム型とオンデマンド型の教育効果の大きさは、一概には判断できないようだ。
オンライン授業と対面授業、学生の集中度の変化は
鶴田准教授は、オンライン授業が学生の集中力に与えた影響について「講義型の授業に関しては、一方通行であるため分からない。グループワークに関しては、大きな違いはない。1回生は高校の時からオンライン授業で慣れているが、上回生の中には、黙ってしまう人や、参加していない人をよく見る」と話した。
授業はオンラインなのに、試験は対面なのはなぜか
ニュースネットは、アンケートで「感染対策としてオンライン授業をしていると言っておきながら、試験は対面で行っているから。これは明らかに矛盾している・試験だけ対面は本当に意味がわからない」という学生の意見を得た。これに対して鶴田准教授は、「学生のあたりまえと教員の当たり前のずれだと思う。教員としては、大学に来ることが当たり前であるため、試験くらい来いよという思いがあるのではないか。大学に来るきっかけを作ってあげたいと思っている先生もいるのでは。今までの管理下だと試験は対面になると思う。試験をオンラインで実施するにはシステムの問題がある。すべての成績評価の基準がレポートだと学生は破綻してしまうだろう」と話した。
「教員の仕事は授業だけではない」
先程学生が課題に追われるという問題を取り上げたが、教員もたくさんの仕事を抱えている。近田教授は、授業をするうえで時間管理に気を付けているという。一つの授業を行うのに必要なことは、シラバス入力、授業、試験やレポートなどの採点、成績入力、授業実施の報告レポートなどだ。
「授業は何コマもあるので、一つの授業だけに膨大な労力をかけられない。時間をかけすぎないようにしているが、バランスが難しい。大学はトップダウンではないので、運営の仕方などを会議で決めることが多く、会議で空きコマがつぶれがち。授業以外の見えない仕事はとても多い。それだけでなく、修士論文、博士論文の研究指導もある。トータルの労力を計算し、うまくコントロールしないと崩壊する。BEEF上での採点は、紙の答案を採点するのに比べてとても目が疲れる。学生のことはちゃんと見ていかないといけないが、バランスが難しい。頑張りすぎると自分が潰れる」と近田教授は苦労をにじませた。
最後に、今後の授業形態がどうなっていくのかについて話を聞いた。
開講形態の多様化
近田教授は今後の授業形態について、「大きな流れとして、長い目で考えて、科目や学問分野の特性によって開講形態は多様化していく方向にあるのではないか。これは対面、これはオンデマンドといったように」と話す。
対面授業に戻すのか
近田教授は、「文科省も大学も、昨年4月から対面に戻そうとしていた。しかし、それができる状況ではなかった。今後の授業形態は中長期的に考える必要がある。対面とオンラインの組み合わせはなかなか大変だが、全部オンライン授業、全部対面授業という単純な二分法はよくない」と話した。
一方、鶴田准教授は、「もとの対面中心の授業に戻るのではないかと考えている。オンライン授業と対面授業が共存していくのではないかという考えには賛成であり、一長一短を考えて共存するとさまざまな可能性が広がると思っている。しかし、実際にやろうとするとすごく大変だと思う。全体的なシステムを作らないといけない。理想的だが議論が必要だと思う。議論をするにしても、どのような授業をオンラインすれば良いか、対面とオンラインのバランスをどうするかを考えるための議論である。しかし、オンラインというより技術への不安、授業は対面である『べき』だという根拠が薄い主義主張を語りだすことになっていくのではないか、それを懸念している。オンラインと対面で授業別で完全に分けてしまうと、学生の選択肢を狭めることになってしまうかもしれないので、かなりよく考えないといけない」とシステム構築の難しさを口にした。
オンライン授業と対面授業の共存の仕組みづくりの一環として、鶴田准教授は先ほど紹介した「神戸大バリュースクール」の活用をお奨めしていた。文理農学部キャンパスの南側にあるバリュースクール(http://www.value.kobe-u.ac.jp/#sec3)の1階は、オンライン授業を受けるためのアクセスポイントとして利用できる。さまざまな学生が利用しており、自分と異なる学部の学生などと交流や議論ができる。
ハイフレックス型(ハイブリッド)授業の難しさ「回を追うごとに対面授業に来る学生が減る」
最近新しい授業の形として注目されているのが「ハイフレックス(ハイブリット)型」だ。ハイフレックス型とは、授業の受講形式を対面またはオンラインから選択できるものをいう。ニュースネットが行ったアンケートでも、来年度の授業にハイフレックス型授業の導入を希望する学生は多くいた。
しかし、近田教授は「ハイフレックス型が日本全体の流れとしてあるが、そう単純ではないと思っている。ハイフレックス型は手間がかかる割に、対面授業に来る学生が回を追うごとに減ってしまう。結局学生の反応も確認しにくく、教員のモチベーションも下がってしまう恐れがある」と難色を示した。
「二つの場にいる学生を見るのは大変」
また、ハイフレックス型の授業では教室にいる学生とオンラインで参加し画面上にいる学生の両方に気を配る必要がある。近田教授は「オンラインでの参加者が置いてけぼりになる可能性がある。対面授業の場にいる教員は授業中マスクをしなければいけないが、画面を通して授業を聞く学生は、マスクをしている教員の話を聞き取りにくい」という。
授業の仕方に絶対解はない
コロナ禍でオンライン授業が実施されたことで、授業は、オンラインでも対面でも、またハイフレックス型でも行えるようになった。近田教授は、「特性に合わせ、ベターな解を導くことが大切だ。ベストな解は容易に見つからない。学生に不利益にならないようにすることが大事だ」と話した。
2022年度の授業のシラバスを見ると、昨年に比べ、原則対面の授業が増加したようだ。しかし、オンデマンド授業などのオンライン授業も一定数行われる予定だ。多様化する開講形式を経験する中で、よりよい授業の在り方が見えてくるかもしれない。
関連記事
●コロナ禍の教育と学生生活① オンライン授業を問う=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/8be6ed21c39b9487113e39879034eed4
●コロナ禍の教育と学生生活②「友達0人」と答える2年生も=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/71aa7c63a83c3dec1e21381753a2eb4d
●コロナ禍の教育と学生生活③ 大学、教員から見たオンライン授業=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/7e3118ee09d5cf1db731142829562cb8
▼ニュースネットは本記事に関するご意見・ご感想を募集しています。ご意見及びご感想は以下のフォームからお願いします。
https://forms.gle/7Cgnw83wgATNFBPQ6
了

(写真:神戸大本部)
教員も学生もディスプレイを一日中見なければいけない状況
オンライン授業の弊害の一つとして挙げられるのが目の疲れだ。近田教授は、「画面を長時間近距離で見続ければならず、正直に言うとかなり疲れる。自分自身、2020年末に網膜剥離になったが、オンライン授業は無関係ではなかったと感じている」と話す。
教員は授業中、真っ暗な画面にずっと語りかけている
オンライン授業には、大人数講義を行う教員特有のデメリットもある。近田教授は、「授業中、学生は教員が見えるが、教員には学生の顔が見えず、学生の名前だけが表示された真っ暗な画面にずっと語りかけている状態」と話す。このような授業の様子について、「特に最初の一年は、慣れなかった」そうだ。近田教授は、対面授業と比べて「空気感や間の共有などの非言語的コミュニケーションが難しい」ことが、オンライン授業の課題だと考えている。
しかし、通信回線への負担と顔を不特定多数の人に見せることへの学生の心理的抵抗感を考慮すると、Zoomを使用した授業で顔出しを求めるのも難しいという。
オンライン授業が学生・教員間の距離を近くすることも
一方で、オンライン授業(Zoom)でのコミュニケーション方法にはチャットやブレイクアウトルームがあり、そうした機能を使えば教員と学生が授業中に交流できる。近田教授は、オンライン授業での学生と教員の距離感について「対面授業のとき、大教室の後ろの方でスマホをいじっている学生よりは、リアルタイム型オンライン授業の方がむしろ学生との距離感は近いように思う」と話した。
オンライン授業は「一長一短というよりむしろ、多長多短。」
鶴田准教授は、①一方的に話す講義形式の授業と、②グループワークを行い、問題設定をして解決策を考え出す授業の2種類の授業を行っている。オンライン授業をしてみて、「①に関しては、伝える内容は変わらないが、オンラインだと顔が見えず、学生のリアクションや雰囲気など、場の温度的なものが分からない。同じことを伝えるとしても、伝える工夫を考えるのが難しい。②に関しては、SNSなどオンラインでのコミュニケーションに慣れている人は活発に議論できるが、慣れていない人には難しい」と感じたという。
また、「対面で行う場合は黙っているグループのところに行って議論をファシリテートできるが、オンラインだと、すぐにグループに入り込むことができない。ハイブリッド授業の場合は、目の前の学生とオンライン上の学生を同時に見なければいけないため、どうしても目も耳も届かないことが多い。その一方で、どこからでも参加できるというメリットがあるため、他大学との交流が前提で全国から参加者がいる授業の場合にはハイブリッド授業形式は便利である。とはいえ、やはりオンラインだと、すべての学生に同じように接することができないため、講義はできるが、グループワークは難しいのかもしれない。自分たちに話していないと感じ、離脱してしまう学生もいた」ということだ。
近田教授はオンライン授業について、「一長一短というよりむしろ、多長多短」と話し、メリットとして「コロナ禍のような社会状況でも、まがりなりにも授業として成立すること」、「何らかの障がいをもつ学生や教員の負担が減ること」を挙げた。

(写真:ニュースネットのオンライン取材を受ける近田教授 画面下)
分野特性によって適した授業形態は異なり、教員の意見にも差
オンライン授業には、リアルタイム型とオンデマンド型がある。近田教授によれば、「大学が収集したデータを見ても賛否両論ある。知識積み上げ型の授業は教員も生徒もオンデマンド型を好む傾向にある」という。一方で、「人文系など、いろいろな考え方があることを学ぶものは、学生と教員が相互に考えを深めていくものであるので、先生はリアルタイムの議論を好む傾向にある」そうだ。
鶴田准教授も、オンライン授業のメリットに「どこからでも参加できることと、録画ができること(アーカイブが残せること)」を挙げ、デメリットに「対面に比べて内容が伝わりにくいこと」を挙げた。
リアルタイムのオンライン授業はラジオ番組のよう
また、近田教授は、オンラインでリアルタイム授業を行っても、「学生の反応がわかりにくい」という。また、授業を行うのは「ラジオのディスクジョッキーに近い。(Zoomの)チャットはラジオにおけるはがきのようだ。」と話す。さらに、「学生が一日オンライン授業に集中するのが難しいことは理解できる。Zoomが終わったときに退出しない(=授業を聞いていない)のは1割いないくらい。相手が何をしているのか分からない状況は不安感がある」と話した。
「学びのための課題というより確認のためではないか」
ニュースネットが実施したアンケートの結果、オンライン授業で課題の量が多いと感じている学生が多いことを伝えると、鶴田准教授も「不安」という言葉を口にした。「昔は授業の形式を重視する教員ばかりではなかった。いい加減に授業しているという誤解を与えることを避けないといけないので表現が難しいが、今より自由度が高かったので、例えば、休講しても補講や課題だけでなく、臨機応変に学びの内容を担保することがあった。しかし現在では文部科学省の厳しい方針なのか、大学の教員が生真面目になったのかわからないが、授業の理解を「課題」を出すことで測らないといけないような雰囲気はある」とした。
そのうえで、「オンラインでの授業で、先生は学生が理解しているのか不安を感じている側面もある。対面であれば、講義の雰囲気でそれがわかる。真面目な先生は特に、学生が理解しているのかを確かめたくて課題を出す。本当に授業を聞いているのか気になる。(別にそれでも構わないが)オンライン授業は聞き流せる。しかし、それで学生を縛ることになるのはよくないと思う。大学の学びは教科書を読むことだけではなく、さまざまなものを観て感じて考えることも重要だと思う。そこまで学生の時間を奪ってはいけないと考えている。個人的には、(オンライン授業での過重な課題は)学びのための課題というより確認のためではないかと思う時もある。そもそも、オンラインになったからというより、教育そのものが詰め込み型になってしまっているのではないかと感じる。学生には、知識をなぜ得て、どう使っていくのかを考える時間がないのではないか。知識の獲得ができていても、それを使うための考える時間がないということが一番の問題だと思う。ものを考えることが大事なのであって、課題に追われるのはもったいないと思う」と話した。
また、「そのために神戸大学では、“感じて”、“考える”ということに重点を置いた活動を促す「バリュースクール」が作られた。これはどこの大学にもない学びの“場“であり、神戸大学生なら誰でも参加できる。「課題」はこなすだけではつまらない。「課題」そのものを”考える“ことは楽しいことだ」と語った。バリュースクールのサイトは以下のURLからアクセスできる。V.School Kobe 国立大学法人神戸大学バリュースクール (kobe-u.ac.jp)

(写真:バリュースクールの様子。鶴田教授提供)
去年と同じ動画を使い回すのは違和感がある
また、オンデマンド授業について近田教授は、メリットに「分からない所などがあったら繰り返し視聴することができる」点と、「場所・時間に縛られないので、自由度が高まる」点を挙げる。また、単位取得という面でもオンデマンド授業には利便性があるという。近田教授は、「医学部や海洋政策学部は、言語を落とすとカリキュラムの関係で、即留年になってしまう。これはオンデマンド化でカバーできる。つまりオンデマンド授業は落単回避策となり、これは大学運営上のメリットでもある。」と話した。
一方、オンデマンド授業のデメリットには「その場で質問することができない」点があるという。鶴田准教授は、ニュースネットが学生向けに行ったアンケートに寄せられた「昨年度のリアルタイム授業のアーカイブ動画を今年度の授業動画としている講義があり、違和感があった」という意見に関して、「学生と同じく違和感がある。普通教員は教えることは同じでもどんどんよくする工夫をしているため、授業では毎回同じことを話すとは限らない。録画した授業を採用したら、無味乾燥なものになってしまう。」と話した。
このように、リアルタイム型とオンデマンド型の教育効果の大きさは、一概には判断できないようだ。
オンライン授業と対面授業、学生の集中度の変化は
鶴田准教授は、オンライン授業が学生の集中力に与えた影響について「講義型の授業に関しては、一方通行であるため分からない。グループワークに関しては、大きな違いはない。1回生は高校の時からオンライン授業で慣れているが、上回生の中には、黙ってしまう人や、参加していない人をよく見る」と話した。
授業はオンラインなのに、試験は対面なのはなぜか
ニュースネットは、アンケートで「感染対策としてオンライン授業をしていると言っておきながら、試験は対面で行っているから。これは明らかに矛盾している・試験だけ対面は本当に意味がわからない」という学生の意見を得た。これに対して鶴田准教授は、「学生のあたりまえと教員の当たり前のずれだと思う。教員としては、大学に来ることが当たり前であるため、試験くらい来いよという思いがあるのではないか。大学に来るきっかけを作ってあげたいと思っている先生もいるのでは。今までの管理下だと試験は対面になると思う。試験をオンラインで実施するにはシステムの問題がある。すべての成績評価の基準がレポートだと学生は破綻してしまうだろう」と話した。
「教員の仕事は授業だけではない」
先程学生が課題に追われるという問題を取り上げたが、教員もたくさんの仕事を抱えている。近田教授は、授業をするうえで時間管理に気を付けているという。一つの授業を行うのに必要なことは、シラバス入力、授業、試験やレポートなどの採点、成績入力、授業実施の報告レポートなどだ。
「授業は何コマもあるので、一つの授業だけに膨大な労力をかけられない。時間をかけすぎないようにしているが、バランスが難しい。大学はトップダウンではないので、運営の仕方などを会議で決めることが多く、会議で空きコマがつぶれがち。授業以外の見えない仕事はとても多い。それだけでなく、修士論文、博士論文の研究指導もある。トータルの労力を計算し、うまくコントロールしないと崩壊する。BEEF上での採点は、紙の答案を採点するのに比べてとても目が疲れる。学生のことはちゃんと見ていかないといけないが、バランスが難しい。頑張りすぎると自分が潰れる」と近田教授は苦労をにじませた。
最後に、今後の授業形態がどうなっていくのかについて話を聞いた。
開講形態の多様化
近田教授は今後の授業形態について、「大きな流れとして、長い目で考えて、科目や学問分野の特性によって開講形態は多様化していく方向にあるのではないか。これは対面、これはオンデマンドといったように」と話す。
対面授業に戻すのか
近田教授は、「文科省も大学も、昨年4月から対面に戻そうとしていた。しかし、それができる状況ではなかった。今後の授業形態は中長期的に考える必要がある。対面とオンラインの組み合わせはなかなか大変だが、全部オンライン授業、全部対面授業という単純な二分法はよくない」と話した。
一方、鶴田准教授は、「もとの対面中心の授業に戻るのではないかと考えている。オンライン授業と対面授業が共存していくのではないかという考えには賛成であり、一長一短を考えて共存するとさまざまな可能性が広がると思っている。しかし、実際にやろうとするとすごく大変だと思う。全体的なシステムを作らないといけない。理想的だが議論が必要だと思う。議論をするにしても、どのような授業をオンラインすれば良いか、対面とオンラインのバランスをどうするかを考えるための議論である。しかし、オンラインというより技術への不安、授業は対面である『べき』だという根拠が薄い主義主張を語りだすことになっていくのではないか、それを懸念している。オンラインと対面で授業別で完全に分けてしまうと、学生の選択肢を狭めることになってしまうかもしれないので、かなりよく考えないといけない」とシステム構築の難しさを口にした。
オンライン授業と対面授業の共存の仕組みづくりの一環として、鶴田准教授は先ほど紹介した「神戸大バリュースクール」の活用をお奨めしていた。文理農学部キャンパスの南側にあるバリュースクール(http://www.value.kobe-u.ac.jp/#sec3)の1階は、オンライン授業を受けるためのアクセスポイントとして利用できる。さまざまな学生が利用しており、自分と異なる学部の学生などと交流や議論ができる。
ハイフレックス型(ハイブリッド)授業の難しさ「回を追うごとに対面授業に来る学生が減る」
最近新しい授業の形として注目されているのが「ハイフレックス(ハイブリット)型」だ。ハイフレックス型とは、授業の受講形式を対面またはオンラインから選択できるものをいう。ニュースネットが行ったアンケートでも、来年度の授業にハイフレックス型授業の導入を希望する学生は多くいた。
しかし、近田教授は「ハイフレックス型が日本全体の流れとしてあるが、そう単純ではないと思っている。ハイフレックス型は手間がかかる割に、対面授業に来る学生が回を追うごとに減ってしまう。結局学生の反応も確認しにくく、教員のモチベーションも下がってしまう恐れがある」と難色を示した。
「二つの場にいる学生を見るのは大変」
また、ハイフレックス型の授業では教室にいる学生とオンラインで参加し画面上にいる学生の両方に気を配る必要がある。近田教授は「オンラインでの参加者が置いてけぼりになる可能性がある。対面授業の場にいる教員は授業中マスクをしなければいけないが、画面を通して授業を聞く学生は、マスクをしている教員の話を聞き取りにくい」という。
授業の仕方に絶対解はない
コロナ禍でオンライン授業が実施されたことで、授業は、オンラインでも対面でも、またハイフレックス型でも行えるようになった。近田教授は、「特性に合わせ、ベターな解を導くことが大切だ。ベストな解は容易に見つからない。学生に不利益にならないようにすることが大事だ」と話した。
2022年度の授業のシラバスを見ると、昨年に比べ、原則対面の授業が増加したようだ。しかし、オンデマンド授業などのオンライン授業も一定数行われる予定だ。多様化する開講形式を経験する中で、よりよい授業の在り方が見えてくるかもしれない。
関連記事
●コロナ禍の教育と学生生活① オンライン授業を問う=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/8be6ed21c39b9487113e39879034eed4
●コロナ禍の教育と学生生活②「友達0人」と答える2年生も=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/71aa7c63a83c3dec1e21381753a2eb4d
●コロナ禍の教育と学生生活③ 大学、教員から見たオンライン授業=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/7e3118ee09d5cf1db731142829562cb8
▼ニュースネットは本記事に関するご意見・ご感想を募集しています。ご意見及びご感想は以下のフォームからお願いします。
https://forms.gle/7Cgnw83wgATNFBPQ6
了










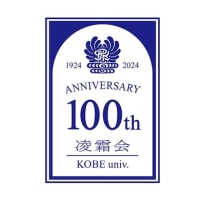


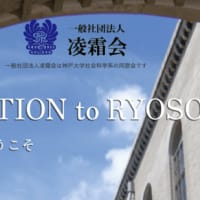
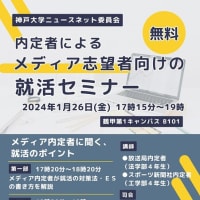





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます