精華町にも多くの神社があるが、この日は3社を回った。相互に比較的近くに建っている神社だ。しかし予想はしていたものの、やはり3社ともに駒札や説明書き等も何もなく、また帰宅してから手持ちの資料やネット情報などもかなり広範囲に当たってみたが、名前だけは出てくるものの神社の由緒などは全く情報なし。大宮神社と天王神社については祭神だけがネット上の記録にあった。若宮神社についてはそれすらない。ということで、ここでは簡単なエピソード的な話と、あとは写真だけで構成することにした。
大宮神社

祭神 崇道天皇 (早良親王さわらしんのう)
誉田別尊 (応神天皇(おうじんてんのう)
近鉄京都線 の木津川台駅が近く、また幹線道路に面しており、わかりやすい場所にある。境内に入ると予想以上に広く、 拝殿も立派な建物だ。全体的によく整備されており地域で大切にされていることがよく分かる。
祭神の崇道天皇は死後に付けられた呼称で、生前は早良親王と言った。彼は謀反に関わったと言うことで捕らわれ、無実を訴えたものの淡路へ流される途中、亡くなる。 もともと平城京の中では東大寺などの大寺院の力が強くなり、藤原種継らが命じられ京都の長岡京へ遷都する事業に携わっていた。
これに対して反対派が種継を暗殺したという事件があった。早良親王がこの事件に関わったということで捕らえられたということだ。そして上記のように淡路へ流される途中に亡くなる。
その後、長岡の都では疫病や皇族関係者の死亡などの不吉な出来事が次々に起こり、暗殺された種継の怨念だと言う噂や、挙句の果てに夜になると、無念の死を遂げた早良親王の亡霊が現れるという噂が広がり、人々は恐れた。その結果、長岡京はわずか10年の短命に終わり、次の平安京造営に繋がる。これらのことが早良親王の祟り話になって、鎭魂の儀式が行われ、親王から天皇へ格上げされた。
これは有名なエピソードで教科書などにも載っている話だ。ただしこれもどこまでが歴史的事実に基づいているのかはよく分かっていない。後に盛られる形で話が大きくなったものかもしれない。
この神社がどういう関わりの中で早良親王を祭神としたのかはわからないが、地理的に見ると、平城京から長岡京への経路の途上にある地になる。当時は平城京と京都を結ぶ経路は木津川東側がメインだった。 しかし長岡へは川の西側が便利だったのだろう。そのような事情から、この神社との関わりがあったのかも知れない。













若宮神社

大宮神社から北へ約100m余り。ちょっとした丘陵地の上に若宮神社がある。
境内に入るとすぐに拝殿が目の前に現れる。これが先ほどの大宮神社の拝殿の建物とそっくり。横に回って本殿を見るが、規模は小さく屋根の方しか見えない。しかし全体的にはなかなか立派な構えの建物だ。
ここもよく整備されていて地元の氏子さんから大事にされていることが伝わってくる。鳥居のすぐ前を近鉄の電車がひっきりなしに走っており、結構騒々しい。残念ながらこれ以上書くことはないので写真をご覧ください。








天王神社

御祭神 建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)
阿智之岐高彦根命(アヂスキタカヒコネ)
2箇所の神社を訪れた後、幹線道路を少し北上し天王神社に寄る。
境内に入るとすぐに拝殿が見えるが、先程とは随分建物の形状は異なる。ここの本殿は比較的小さい方となる。やはりよく整備されていて綺麗に保たれている。
祭神のスサノオノミコトは一般的にもかなり有名だ。もちろん「古事記」「日本書紀」の比較的初期に登場する神であり、「出雲国風土記」にもその名前が見られる。あくまでも 神話とした上での話であり、史実との関係は全く何も分からない。
日本書紀でも日本という国の成り立ちを、恰も神に依るものを出発点とする。その系列が後の天皇という存在につなげられていく。その流れに都合のいいように考えられて、書かれた日本最初の歴史書ということになる。古代史研究の中では数多くの研究者がいるが、また素人の方でも様々な文献を読み込んで研究が進められている。
そんな中で、スサノオノミコトはどのように位置付けられているのか。様々な文献に登場する逸話についても、都合のいいような作り話ではあろうが、神という存在の権威付けに作られているのは確かだろう。ただひょっとしたらそれらの作り話というのは、まだ大和王権が誕生する前に、各地に小さな力を持つ小豪族の大王たちの、小さなエピソードがあちこちで取り入れられ、さらにそれが脚色されて、このような神話物語が書かれたのではないかと思う。
ヤマタノオロチの退治の話にしても、そのまま読んでみれば全くあり得ない話だし、著者がこれを完全に創作したとすれば、なかなかの想像力を持った作家のようにも思える。ひょっとしたら出雲かどこかは分からないものの、ある小豪族の大王がたまたま少し大きめの蛇を捕まえたことが誇張されて各地に広がり、このような話になっていたのかもしれないとも考えられる。
そんな状況下で各地の風土記などの文献が出てくる中で、古事記や日本書紀の記述内容に歴史的事実がある程度、反映されるようになってきたのではないか。ただそうなるのかということも含めた研究が、専門家によってなされ、今ではいくつもの項目についても様々な説が出されている。スサノオノミコトの名前でさえ、斯く斯く然々このような意味を持つというような諸説がいくつもある。
そういうところを見てみると、真相がよくわからない弥生から古墳時代、そして大和王権にいたる古代史というのは非常に興味深い。しかし古事記や日本書紀の、明らかに神話であり作り話であるような記述に対して、何故細かいところにこだわった研究がなされているのか、その意味合いについて私なりに思う所はあるが、もうひとつしっくりこないところでもある。











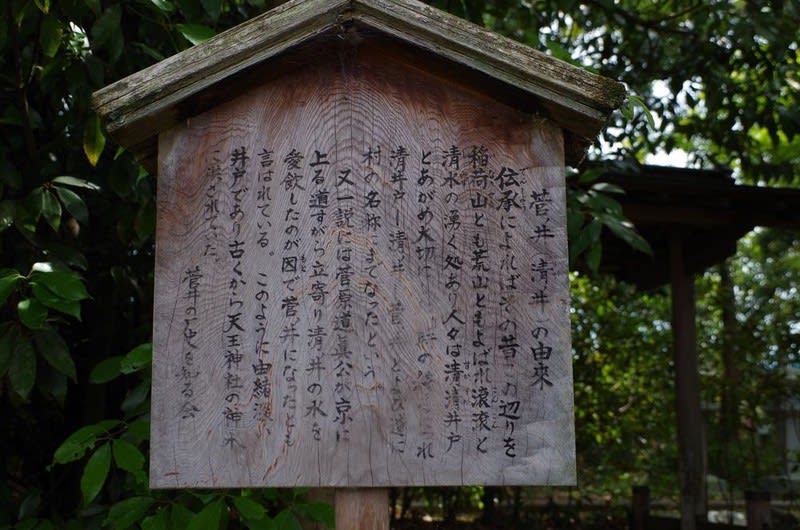


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます