鉄さんはいつも通りゆっくりと茶をすすり微かに体を揺すり、笑みを広げて言った。
「お前がいてくれたら、この家の中にも春が来たようなものだよ」
翌日は漁に出ても、高志は落ち着かなかった。
鉄さんはいつも通りだが、それでもどこか表情が変わっているような気がする。
今頃はあやが昼食の支度をしているだろう。
ふわふわと気持ちが浮き上がり、入江は奥まで昨日とはすっかり違って見える。
春が一気に膨れ上がり、しぶとい冬を包み込んで終わらせてしまった。
山の樹々はまだ固い蕾のままだし、現れた土は昨年の枯草に覆われたままだが、早くも辺りは濃
い春の香に満たされている。
高志は何度も味わった春の訪れなのに、初めての春のように、何をどう言い表して良いのか分か
らない。
ただもう心がわくわくと踊り、自分がどんどん子供に返っていくのを感じる。
鉄さんも時々、ぼんやりと海原の遠くを見ている。
高志は急に鉄さんに尋ねてみたくなった。
具体的に何を尋ねたいのか言葉は浮かんでこなかったが、とにかく何かを尋ねたい思いにかられ
た。
その時、そんな高志の気持ちが通じたかのように鉄さんが口を開いた。
「何で急に帰って来たのかなあ」
言葉には明らかな不安があった。
高志はその言葉に不満を感じる。
「それは鉄さんが倒れたと聞いたからでしょう」










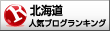

 にご飯を貰えず
にご飯を貰えず








