
2015年5月17日(日)に行われた住民投票によって、大阪府民を二分した『大阪都構想』は僅差で否決されてしまいました。これは大阪府民の自治の問題でしたから、私もこれまでその住民判断を静かに見守ってきましたが、かつて日本維新の会の公認候補として参議院比例代表選挙に立候補した一人の政治家として、とても残念に思っています。
■東京一極集中からの脱却
そもそも『大阪都構想』とは、単に大阪府民の問題なのではなく、日本国における東京一極集中を改め、東京と大阪の二極体制を確立することによって、将来に亘る日本の統治機構そのものに大きな変革を創り出していこうという大きなビジョンに立った構想でした。
戦後復興から高度経済成長を成し遂げるまでの日本の統治機構は中央集権制度で間違いなかったのだと思いますが、バブル経済期にそれまでの経済成長が飽和状態に至り、低成長からデフレ経済が長びく現実の中で、日本国民は日本国の在り方を大きく見直す必要性に迫られているのではないでしょうか。
■”One Osaka”(ひとつの大坂)実現の意義
東京一極集中型の中央集権政治を継続するのか、地方分権を進めて地方主権を確立していくのか。大阪府民が大阪府と大阪市の二重行政を見直して”One Osaka”(ひとつの大坂)を実現するのかしないのか。東京都と並ぶ巨大自治体を創るのか創らないのか。
大阪府民の皆様が、まず自分たちの未来を選択する。東京都と同様に特別区を設置して「大阪都」を実現して、東京と大阪という二大都市(メガロポリス)が二極で新しい日本国を牽引する。そんな未来が開かれていくのか否かが埼玉県民である私の最大の関心事でした。
■「大阪都」は実現しないという傍流の議論~構想失速の原因
ところが議論の早くから、「大阪都構想」に関わる住民投票が仮に通っても、「大阪都」は名称として実現しないという議論がまきおこりました。「大阪都」は名称上のこと。しかし多くの人々が「大阪府は大阪都にはなれない」と理解しました。
大阪府民の皆様の意志として「大阪都構想」が実現すれば、次に「大阪府」の名称を「大阪都」に改める自治法改正案を国会に提案する。単純にそういった手続きを手前から一つずつクリアしていけばいいだけのことでした。「大阪都は実現しない」という誤った認識が大阪都構想を失速させる原因になるのではないかと私は感じました。
大阪府民の皆様が大阪府と大阪市の二重構造をひとつにして大阪都構想を実現していたとしたら、その名称を「大阪都」に改める自治法改正案に誰が反対できるのでしょうか。「東京都」の「都」は「都」(みやこ)という意味であり、「首都」(帝都)の「都」であるから、「大阪府」を「大阪都」に改称することは認めないと国会が最終結論を出したでしょうか。東京都と大阪都の二都が日本の未来を切り拓いていく。名称の議論は大阪都構想の議論の本質ではありませんでしたが、世論を失速させる効果があったことは残念であったと私は思います。
■戦後70年~日本の選択と成果(パイ・セオリー)
今年は日本が太平洋戦争に敗れて70年目の節目の年です。戦後の荒廃から復興し、世界の経済大国にまで登りつめた日本国にとって、国家経営の方針を富国強兵から富国弱兵ともいえる平和国家としての道筋に大転換できたのは、外交的には日米安全保障条約の傘下に入ったからであり、内政的には東京一極集中による中央集権制度を選択したからだと私は考えています。そして結果的に太平洋ベルト地帯に象徴されるものづくりを中心とした急速な工業化によって高度な技術力の開発と蓄積が繰り返されてきました。
戦後、日本人の手元に残されていた小さなパイは、もし政治的に平等に分け合うことを先行して議論したとしても、平等に分け与えられたさらに小さな一切れのパイでは誰も満足することが出来ない。だから日本人はまず、パイを大きくすることを最初に選択したのです。そして高度経済成長期を乗り越え、たとい自分の取り分が最も小さな取り分であったとしても飢えることがない経済大国という大きなパイを築き上げることに成功したのです。
■日本人の気質とコンセンサス社会~今日的な課題と可能性
もともと日本はコンセンサス社会だと言われます。国民が政治的に争わず、合議や合意によって共生社会を維持継続していくのが当たり前の社会。目の前のパイの分け前の大小を争うのではなくて、みんながお腹いっぱいになるために、みんなで頑張る社会。自己犠牲と利他の精神が美徳として根付いた社会。日本が世界を主導していける可能性がここにこそある。私はそう信じています。
しかし一方で、誰でも自分のお腹がいっぱいになると隣の人が食べているものが気になるものです。それが人間の性(さが)なのかもしれません。そのような時代を迎えて、国民の個別的な利害をどうやって調整するのか。国民の多様なニーズをどうやって実現するのか。国家と地方自治体の役割をどうやって分担するのか。変化する世界情勢にどうやって対応するのか。これまで先送りしてきた様々な政治的な問題が少しずつ私たち日本人にとって、現実の問題として迫ってくるようになりました。
だからこそ日本人はもっと積極的に政治に目を向け、政治に参加する必要に迫られているのだと私は思います。これまでのように政治は法律として国会が東京で決め、地方自治体に上意下達で伝達指導するといった中央集権に頼るのではなく、「地域のことは地域で決める」地方主権を確立するために、今こそ、全国民レベルの民主的な論議を始めなければならないと思います。
■「地方自治は民主主義の学校」~大阪都構想の全国民的な意義
今回の「大阪都構想」はその先達となる議論だったのだと思います。大阪府民の皆様の議論が日本全国の地域住民の地域社会に対する関係を大きく動かす力と勇気につながる効果を生み出し、日本の地方自治の在り方を変え、日本を変える。そんな起爆剤になったかもしれない議論でした。
大阪都構想は大阪府民の自治の問題であったかもしれませんが、大阪府民以外の日本国民がもっと積極的に参加していい議論であったかもしれません。結果的に大阪都構想は住民投票によって僅差で否決され、実現しませんでしたが、私たちが忘れてはならないのは、大阪都構想は日本の地方自治の歴史上、最も大きな問題提起であったという事実です。
日本国憲法に第8章「地方自治」が規定されたものの、地方自治がこれほど熱く議論されたことは日本国と日本国民の歴史の中で初めてのことでした。そして、アレクシス・トクヴィルの言葉どおり「地方自治はデモクラシー(民主主義)の学校」なのだとすれば、日本人にとって、地方自治に参加することは主権者として最も尊い権利なのだと思います。
■戦後日本の変貌~戦後復興からバブル経済崩壊まで
日本人はこれまで、戦後復興から高度経済成長期にかけて政治的には中央集権に任せて、経済的には製造業と輸出産業を中心に外貨を稼ぎ、資源を持たざる日本は、資源を輸入に頼って製造を続けてきましたから、加工貿易という造語さえ生まれました。
この間、女性参政権が認められ、女性の社会進出も当たり前のこととなり、急速な経済成長が急速な雇用機会を生み出し、人口は都市部に流れ込み、同時に核家族化が進みました。このような社会変革の末に日本人は、かつてない繁栄を手にする訳ですが同時に、バブル経済の崩壊によって、戦後レジームの終焉と高度経済成長のピークを悟ることになります。
■『ニッポンの底力』を発揮するために
私は『ニッポンの底力』はまだまだ発揮しきれてはいないと信じています。その原動力はこれまで蓄積された高い技術力、商品開発力、国際語にもなった”kaizen”(改善)に向けた飽くなき情熱、”Mottainai”(もったいない)という限られた資源をたいせつにする価値観、”Omotenashi”(おもてなし)という自己犠牲と利他の精神の中にまだまだ大きな可能性として眠ったままの状態なのだと思います。
ですから日本がさらなる経済成長を果たしていく、発展していく可能性は無限大であると私は政治家として確信しています。しかし、そのような未来を切り拓いていくために日本人はこれまであまり議論してこなかった幾つかの問題に真正面から取り組まなければならないと思います。そして国家として、国民として、過去を痛切に反省し、悔い改めるべきものは悔い改め、国際社会からも充分な理解が得られるようなだれにでも公正で平等な全国民レベルの歴史認識の総括をまとめ、内外に発信することによって、日本人としての明確で健全なセルフイメージを確立していく必要があるのだと心からそう思います。
■普選と不戦~日本人が敗戦から勝ち取ったもの
そういった意味で、私は今こそ日本を変える大きなターニングポイントを迎えていると思います。しかしこれが過去の戦争を正当化したり、国際紛争の解決のための武力行使を安易に容認したりするようなものであっては断固としてならないと感じています。
今、やるべきことは「民主的な国民対話」の中で、日本国の在り様や進むべき方向性を決定していくプロセスに最大のエネルギーを傾注すること。その中で、政治家はすべての国民を含んで外交も内政も丁寧に進めていくべきだと考えます。国民も自分たちが日本国を動かしているのだという自覚を強めながら、主権者としての役割にもっと覚醒するべきだと思います。
普選(普通選挙)と不戦(戦力の放棄)
憲政の神様とよばれた尾崎行雄先生のことばどおり、日本人があの厳しい敗戦の歴史から勝ち取った「2つのフセン」を最大限に活かす社会を創り出すことこそが、現代に生きる政治家が持つべき最も基本的な良識であり良心なのだと私は考えています。
■『大阪都構想』の挫折と総括
大阪都構想が一過性の議論で、橋下徹という個性の強い政治家の一時の熱情に過ぎなかったという総括は週刊誌的に可能なのかもしれませんが、これを日本人が初めて直面した地方自治とデモクラシーに関する意義深い歴史的問題提起であったと捉え、ここから日本型デモクラシー発展論が始まったと後世に総括される未来を切り拓いていくのは、日本国の主権者である私たち自身に他なりません。
日本を変える。世界が変わる。
明るく豊かな未来を創り出すために、みんなで対話型の政治を始めませんか。共に力と知恵を併せて参りましょう。
瀬戸健一郎(せとけん)
Ken-ichiro Seto
日本を変える。世界が変わる。
Thinking Globally, Acting Locally
■東京一極集中からの脱却
そもそも『大阪都構想』とは、単に大阪府民の問題なのではなく、日本国における東京一極集中を改め、東京と大阪の二極体制を確立することによって、将来に亘る日本の統治機構そのものに大きな変革を創り出していこうという大きなビジョンに立った構想でした。
戦後復興から高度経済成長を成し遂げるまでの日本の統治機構は中央集権制度で間違いなかったのだと思いますが、バブル経済期にそれまでの経済成長が飽和状態に至り、低成長からデフレ経済が長びく現実の中で、日本国民は日本国の在り方を大きく見直す必要性に迫られているのではないでしょうか。
■”One Osaka”(ひとつの大坂)実現の意義
東京一極集中型の中央集権政治を継続するのか、地方分権を進めて地方主権を確立していくのか。大阪府民が大阪府と大阪市の二重行政を見直して”One Osaka”(ひとつの大坂)を実現するのかしないのか。東京都と並ぶ巨大自治体を創るのか創らないのか。
大阪府民の皆様が、まず自分たちの未来を選択する。東京都と同様に特別区を設置して「大阪都」を実現して、東京と大阪という二大都市(メガロポリス)が二極で新しい日本国を牽引する。そんな未来が開かれていくのか否かが埼玉県民である私の最大の関心事でした。
■「大阪都」は実現しないという傍流の議論~構想失速の原因
ところが議論の早くから、「大阪都構想」に関わる住民投票が仮に通っても、「大阪都」は名称として実現しないという議論がまきおこりました。「大阪都」は名称上のこと。しかし多くの人々が「大阪府は大阪都にはなれない」と理解しました。
大阪府民の皆様の意志として「大阪都構想」が実現すれば、次に「大阪府」の名称を「大阪都」に改める自治法改正案を国会に提案する。単純にそういった手続きを手前から一つずつクリアしていけばいいだけのことでした。「大阪都は実現しない」という誤った認識が大阪都構想を失速させる原因になるのではないかと私は感じました。
大阪府民の皆様が大阪府と大阪市の二重構造をひとつにして大阪都構想を実現していたとしたら、その名称を「大阪都」に改める自治法改正案に誰が反対できるのでしょうか。「東京都」の「都」は「都」(みやこ)という意味であり、「首都」(帝都)の「都」であるから、「大阪府」を「大阪都」に改称することは認めないと国会が最終結論を出したでしょうか。東京都と大阪都の二都が日本の未来を切り拓いていく。名称の議論は大阪都構想の議論の本質ではありませんでしたが、世論を失速させる効果があったことは残念であったと私は思います。
■戦後70年~日本の選択と成果(パイ・セオリー)
今年は日本が太平洋戦争に敗れて70年目の節目の年です。戦後の荒廃から復興し、世界の経済大国にまで登りつめた日本国にとって、国家経営の方針を富国強兵から富国弱兵ともいえる平和国家としての道筋に大転換できたのは、外交的には日米安全保障条約の傘下に入ったからであり、内政的には東京一極集中による中央集権制度を選択したからだと私は考えています。そして結果的に太平洋ベルト地帯に象徴されるものづくりを中心とした急速な工業化によって高度な技術力の開発と蓄積が繰り返されてきました。
戦後、日本人の手元に残されていた小さなパイは、もし政治的に平等に分け合うことを先行して議論したとしても、平等に分け与えられたさらに小さな一切れのパイでは誰も満足することが出来ない。だから日本人はまず、パイを大きくすることを最初に選択したのです。そして高度経済成長期を乗り越え、たとい自分の取り分が最も小さな取り分であったとしても飢えることがない経済大国という大きなパイを築き上げることに成功したのです。
■日本人の気質とコンセンサス社会~今日的な課題と可能性
もともと日本はコンセンサス社会だと言われます。国民が政治的に争わず、合議や合意によって共生社会を維持継続していくのが当たり前の社会。目の前のパイの分け前の大小を争うのではなくて、みんながお腹いっぱいになるために、みんなで頑張る社会。自己犠牲と利他の精神が美徳として根付いた社会。日本が世界を主導していける可能性がここにこそある。私はそう信じています。
しかし一方で、誰でも自分のお腹がいっぱいになると隣の人が食べているものが気になるものです。それが人間の性(さが)なのかもしれません。そのような時代を迎えて、国民の個別的な利害をどうやって調整するのか。国民の多様なニーズをどうやって実現するのか。国家と地方自治体の役割をどうやって分担するのか。変化する世界情勢にどうやって対応するのか。これまで先送りしてきた様々な政治的な問題が少しずつ私たち日本人にとって、現実の問題として迫ってくるようになりました。
だからこそ日本人はもっと積極的に政治に目を向け、政治に参加する必要に迫られているのだと私は思います。これまでのように政治は法律として国会が東京で決め、地方自治体に上意下達で伝達指導するといった中央集権に頼るのではなく、「地域のことは地域で決める」地方主権を確立するために、今こそ、全国民レベルの民主的な論議を始めなければならないと思います。
■「地方自治は民主主義の学校」~大阪都構想の全国民的な意義
今回の「大阪都構想」はその先達となる議論だったのだと思います。大阪府民の皆様の議論が日本全国の地域住民の地域社会に対する関係を大きく動かす力と勇気につながる効果を生み出し、日本の地方自治の在り方を変え、日本を変える。そんな起爆剤になったかもしれない議論でした。
大阪都構想は大阪府民の自治の問題であったかもしれませんが、大阪府民以外の日本国民がもっと積極的に参加していい議論であったかもしれません。結果的に大阪都構想は住民投票によって僅差で否決され、実現しませんでしたが、私たちが忘れてはならないのは、大阪都構想は日本の地方自治の歴史上、最も大きな問題提起であったという事実です。
日本国憲法に第8章「地方自治」が規定されたものの、地方自治がこれほど熱く議論されたことは日本国と日本国民の歴史の中で初めてのことでした。そして、アレクシス・トクヴィルの言葉どおり「地方自治はデモクラシー(民主主義)の学校」なのだとすれば、日本人にとって、地方自治に参加することは主権者として最も尊い権利なのだと思います。
■戦後日本の変貌~戦後復興からバブル経済崩壊まで
日本人はこれまで、戦後復興から高度経済成長期にかけて政治的には中央集権に任せて、経済的には製造業と輸出産業を中心に外貨を稼ぎ、資源を持たざる日本は、資源を輸入に頼って製造を続けてきましたから、加工貿易という造語さえ生まれました。
この間、女性参政権が認められ、女性の社会進出も当たり前のこととなり、急速な経済成長が急速な雇用機会を生み出し、人口は都市部に流れ込み、同時に核家族化が進みました。このような社会変革の末に日本人は、かつてない繁栄を手にする訳ですが同時に、バブル経済の崩壊によって、戦後レジームの終焉と高度経済成長のピークを悟ることになります。
■『ニッポンの底力』を発揮するために
私は『ニッポンの底力』はまだまだ発揮しきれてはいないと信じています。その原動力はこれまで蓄積された高い技術力、商品開発力、国際語にもなった”kaizen”(改善)に向けた飽くなき情熱、”Mottainai”(もったいない)という限られた資源をたいせつにする価値観、”Omotenashi”(おもてなし)という自己犠牲と利他の精神の中にまだまだ大きな可能性として眠ったままの状態なのだと思います。
ですから日本がさらなる経済成長を果たしていく、発展していく可能性は無限大であると私は政治家として確信しています。しかし、そのような未来を切り拓いていくために日本人はこれまであまり議論してこなかった幾つかの問題に真正面から取り組まなければならないと思います。そして国家として、国民として、過去を痛切に反省し、悔い改めるべきものは悔い改め、国際社会からも充分な理解が得られるようなだれにでも公正で平等な全国民レベルの歴史認識の総括をまとめ、内外に発信することによって、日本人としての明確で健全なセルフイメージを確立していく必要があるのだと心からそう思います。
■普選と不戦~日本人が敗戦から勝ち取ったもの
そういった意味で、私は今こそ日本を変える大きなターニングポイントを迎えていると思います。しかしこれが過去の戦争を正当化したり、国際紛争の解決のための武力行使を安易に容認したりするようなものであっては断固としてならないと感じています。
今、やるべきことは「民主的な国民対話」の中で、日本国の在り様や進むべき方向性を決定していくプロセスに最大のエネルギーを傾注すること。その中で、政治家はすべての国民を含んで外交も内政も丁寧に進めていくべきだと考えます。国民も自分たちが日本国を動かしているのだという自覚を強めながら、主権者としての役割にもっと覚醒するべきだと思います。
普選(普通選挙)と不戦(戦力の放棄)
憲政の神様とよばれた尾崎行雄先生のことばどおり、日本人があの厳しい敗戦の歴史から勝ち取った「2つのフセン」を最大限に活かす社会を創り出すことこそが、現代に生きる政治家が持つべき最も基本的な良識であり良心なのだと私は考えています。
■『大阪都構想』の挫折と総括
大阪都構想が一過性の議論で、橋下徹という個性の強い政治家の一時の熱情に過ぎなかったという総括は週刊誌的に可能なのかもしれませんが、これを日本人が初めて直面した地方自治とデモクラシーに関する意義深い歴史的問題提起であったと捉え、ここから日本型デモクラシー発展論が始まったと後世に総括される未来を切り拓いていくのは、日本国の主権者である私たち自身に他なりません。
日本を変える。世界が変わる。
明るく豊かな未来を創り出すために、みんなで対話型の政治を始めませんか。共に力と知恵を併せて参りましょう。
瀬戸健一郎(せとけん)
Ken-ichiro Seto
日本を変える。世界が変わる。
Thinking Globally, Acting Locally












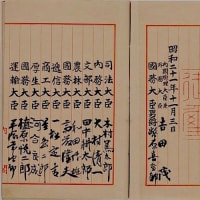
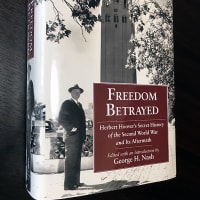


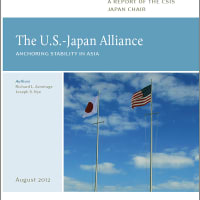
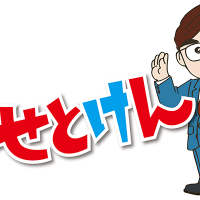

よくも悪くもこんなに盛り上がった住民投票もなかったと思います。橋下市長が大阪市役所の異常な実態にメスを入れようとしました。ここは評価できる点であると思います。
大阪の住民投票も賛成派と反対派がテレビで連日討論を行っていました。
ただし、東京と大阪は財務状況も異なります。同じようにはならないでしょう。首長が改革をしようとすれば、利害関係のあるものは抵抗するでしょう。今井元衆議院議員や木下県議が首長だった頃の草加も似たようなことがございました。その改革が正しかったかどうかは分かりません。
田中市長も、公共施設の老朽化の問題や地方交付金の仕組みが代わり、草加も頑張っていかないと自治体間で格差が生じるでしょう。芝野市議は市庁舎の建て替えについて問題提起をされていました。
どんな街が住んでいる人達にとって幸せなのか。難しい問題だと思います。