
※今日はイースター。日本政治のタブーに挑戦パート2として、少しずつ書きためた記事は「政治と宗教」について。画像はキリストの受難と復活を記念したイースターリリー(てっぽうユリ)です。「ゆりの花のことを考えてみなさい。(中略)栄華を窮めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。」(ルカ12:27)
ブログ記事「政治とカネ~日本政治のタブーに挑戦①」に対するkeikoさんのリクエストにお応えして、「政治と宗教」について、今、思うことをシリーズ第二弾としてアップしておこうと思います。
■「政治と宗教」~瀬戸健一郎のライフワーク。
もとより、政治と宗教というトピックは、これ一本で博士論文が書けるほどの大きなテーマだと私はずっと思ってきました。やがて現役を引退したら、大学院に入って、このテーマに取り組みたいとも考えています。ですから、ここではあくまでさわりの部分ですので、ご了承ください。
また、私はクリスチャンですので、その立場からの見解になりますが、「相互理解なくして本当の和はありえない。」、「多様性の受容こそが本物の愛であり、デモクラシーの根源である。」というのが、私なりの哲学ですから、これについても私の発言の前提として明確にしておきたいと思います。
■八百萬(やおよろず)~多様性を包摂した憲法制定と仏教伝来。
keikoさんが前記事へのコメントで指摘されているように、私も日本人は、その精神性において、八百萬(やおよろず)=英語ではそのまま"eight million gods"(800万の神々)と表現されるように、神様の存在を文字通り万象に感じ取り、それを尊んできたのですから、信心深い国民だと言えると思います。
聖徳太子の「和を以て貴しと為す。」という日本初の憲法の精神が立てられた頃の日本は、おそらく地域ごとに神々を讃える地域信仰、民間信仰が集落ごとに多数点在していて、当時の日本はかなり多極化した状況だったのではないかと私は想像しています。
この憲法の制定と仏教の伝来が、日本に暮らす多様な人々にまさに「和」をもたらし、多様な信仰を包摂しながら、いわゆる日本という国や日本民族という枠組みが形成されて行ったのではないでしょうか。
■権力と権威~統治に必要な2つの力。
統治する=Governとは、政治学の永遠のテーマであると思いますが、一般論として、統治には2つの「力」が必要であると思います。ひとつは「権力」(Power)という力、もうひとつは「権威」(Authority)という力です。
一言で言えば、「権力」とは、「人を従わせる力。」であり、「権威」とは、「人が従おうとする力。」だと、私は説明してきました。
「ローマは3度、世界を征服した。」と言われます。最初は軍事力によって、2度目は法によって、3度目は宗教によって。軍事力は暴力。しかし、その軍事力でさえ、法によって正統化され得るので「権力」(Power)に分類され、その権力は皇帝に集中されていました。ローマ帝国は元老院の権威を借りて皇帝が統治しましたが、『ローマ市民全体を統治するための民主制』(※参照)は確立されていませんでしたから、ローマ領内にかつて迫害したにも関わらず広まったキリスト教の「権威」(Authority)を借りて、神聖ローマ帝国に至ります。
※"Government of the people, by the people, for the people"は、「人民の人民による人民のための政治」と翻訳されていますが、これは「人民を人民が人民のために統治すること」と私は自分のブログ記事で翻訳しています。"Government of the poeple"とは、「人民の政治」という所有・帰属の"of"ではなく、「人民を統治すること」という"Govern"(統治する)目的の"of"なのであり、これがアメリカのデモクラシー(民主制)の根源です。
■宗教の二面性~ルターは何をプロテスト(主張)したのか。
その後、宗教的権威は世界中に広がりましたが、これが純粋に宗教的教義や理念として広まったというより、時の権力者の統治を補完する政治システムとして取り込まれた側面を無視してはならないと思います。純粋に「教理を柱とする宗教」と権力者によって立てられた「制度としての宗教」の二面性を区別することが大事です。
少なくともドイツでルターが宗教改革を提唱するまでは、教会制度は政治権力に取り込まれ、信仰的に純粋ではなくなってきていたことがプロテスタント運動やピューリタン(清教徒)革命の背景にあったことは、神の意思や権威を権力者たちが自分たちの権力基盤を安定化させるために利用しようとした側面が少なからずあったことを連想させますし、事実なのではないかと思います。
十字軍の遠征による西欧諸国の覇権争いは、まさに「キリスト教が巻き起こした血で血を洗う世界史の中の汚点」であると評することが出来るかもしれませんが、隣人愛を説いたイエスの教えがいかなる殺戮も正当化するはずがなく、「キリスト教が」という主語は、正確には「西欧諸国が」と置き換える必要があるのかもしれません。
■産業革命~印刷機の発明と識字率の向上がもたらしたもの。
一部の人たちだけが、ほんの少数の人々だけが、文字を読むことができる。つまり聖書を直接読むことができた。印刷技術も発達していなかった時代には、聖書そのものが限られた人々の手に委ねられ、その教義はすべて口述によって伝えられた時代があったことも忘れてはならないと思います。
だれもが文字が読める。だれもが聖書を手にすることが出来る。そのような環境でこそ、本来のキリスト教信仰の根本である、神と人との個人的な関係が結ばれていく。それぞれの人間に神がどのように関わり、何をなさせようとしているのかが、十分に発揮されてこそ、また、個々人の可能性の開花が阻害されない社会を実現してこそ、すべての多様性を包摂した、相互理解に基づく社会の調和たる「和」が実現するのだと思います。
■人の思惑と神の愛~最後に残るものは神の愛、キリストの栄光。
ここで少しだけ、クリスチャンとしての思いを語らせていただきます。やがて世界宣教という錦の御旗を掲げて繰り広げられた西欧諸国の覇権は衰退し、民族自決権による独立運動が世界中に広がっていきました。世界中の民主化運動の中で、人々が自己の可能性に目覚め開花させた結果、征服者は去っても、イエスがキリストであるという信仰は残りました。
ですから、過去の歴史において、もしくは現代社会において、宗教が人間の行為を正当化するために使われる危険性を排除しない限り、宗教は人を幸せにはしない。しかし、本物の宗教の根底には人を幸せに導く教理が存在している。
それが何なのかを純粋に探究すれば、自分の生命に対する解決が見つかるかもしれません。自己の可能性が開花するかもしれません。すべての人が愛すべき存在に変わるかもしれないと私には思えるのです。
■八百萬(やおよろず)とは、神の臨在の証し?~聖書に見る不思議。
何かまとまりませんが、思うがままに書き進めてきました。ここで、クリスチャンとして、私なりに日本の八百萬(やおよろず)の神とは、神の臨在一つ一つの現象だったのではないかと思わせられた旧約聖書の記述を紹介したいと思います。
【旧約聖書より】
すると主の使いが彼に、現われた。柴の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに柴は焼け尽きなかった。
モーセは言った。「なぜ柴が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。」
主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は柴の中から彼を呼び、「モーセ、モーセ。」と仰せられた。彼は「はい。ここにおります。」と答えた。
神は仰せられた。「ここに近づいてはいけない。あなたの足のくつを脱げ。あなたの立っている場所は、聖なる地である。」
また仰せられた。「わたしは、あなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。」モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて、顔を隠した。(出エジプト記第3章2-6節)
※これは、モーゼの前に神が現れ、モーゼに「わが民を去らせよ。」(Let my people go.)と命じる直前の個所です。出典は旧約聖書に収められている「出エジプト記」という書物で、エジプトに隷属していたヘブライ人たちをモーゼが解放した史実を記録したものです。
■八百萬(やおよろず)~ヘブライ人の信仰と日本人の宗教観。
私がこの記述から思うことは、もしこのようなことが過去の日本に、日本人に起こったとしたら、きっと日本人は「燃える柴神社」をその場所に立てていたに違いないということでした。
ヘブライ人たちの信仰においては「偶像礼拝」を禁じる宗教文化でしたし、後に神が解放したヘブライ人たちのために初めて与えられた戒律である、モーゼの十戒においても、その第一戒として「あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。」(出エジプト記第20章4節)と記されていることから、そのようなことは起きませんでした。
宗教的権威というより、神の権威が正確に人間社会に反映されれば、その社会はパラダイスになるはずであり、この思想は仏教においても「王仏冥合」(おうぶつみょうごう)という大乗仏教の思想であり、これが創価学会が公明党を立党した根拠にもなっているのです。
宗教は本来、人々の価値基準、善悪の区別、行動規範を与えるという意味で「権威」という信じる人々が自ら従おうとする力を持っています。どの宗教を信じているのかが分かれば、その人なりその社会の価値観が理解できるというのは、かなり可能性の高いことだと思います。
■日本人とヘブライ人の宗教観と時間的概念
日本で最初の憲法である十七条憲法が八百万の神々への多様な信仰を前提に、それでも人と人との関係に着目して「和」という秩序を唱えているのに対して、ヘブライ人たちの最初の律法(戒律)であるモーゼの十戒は、万物の創造者であり、唯一完全無欠な一神教の神と人との関係に着目して「信仰」という観点から秩序を唱えています。
信仰上の「和」は日本においては仏教が多様性を包摂することによって形成されていき、それは地域信仰や民間信仰、神道や儒教ばかりではなく、キリスト信仰をも包摂する性質を養っていったのではないでしょうか。その意味で、偶像礼拝を禁じるキリスト教が排他的に見える。
さらに時間的な概念においても、季節がめぐるように生命もめぐるといった農耕民族らしい輪廻転生といった感覚(円)が、命には始まリがあり、終わりが来るといった狩猟民族らしい感覚(線)を、大きな輪(円)の一部として包摂しているかのようにも思われます。この感覚の違いが創造と終末論という思想につながっていると思われます。
■相互理解なくして本物の「和」はありえない。
「あなたの宗教は何ですか?」とか、「あなたは何を信じていますか。」というのは、その人を深く理解したいと考えた時に出てくる質問ですが、日本人はそのようなことは他人には聞くことはほとんどありません。深く相手のものの考え方や価値観を理解しようとすれば、当然の質問なのかもしれません。
これは多分、そもそも日本という国に存在していた多様性が、「和をもって貴しと為す。」といった聖徳太子の十七条憲法と仏教伝来によって、少しずつ大きな枠組みの中で包摂されていき、いわゆる日本という国や日本民族という単一統一の社会が形成された結果を享受している私たちが、そのプロセスを忘れているからではないかとさえ、私は思います。
相互理解なくして本物の「和」はあり得ない。"Harmony without Mutual Understanding is not Real Harmony."(相互理解なしの調和は本物の調和ではない。)とは、私たちの結婚式に駆けつけてくれた私の代母(Godmother)ナンシー(Nancy Ferriman)の言葉です。
■多極共存型デモクラシーは民主的に社会を統一化させる。
オランダ出身の政治学者アーレンド・レイプハルト教授が定義された「多極共存型デモクラシー」(Consociational Democracy)とは、かつて宗派によって三つに分断されていた社会が相互理解に基づく共生社会を構築した結果として社会の統一が実現されたオランダの例を論拠とした学説で、これが現実に多極社会である国際社会(もしくは、グローバル社会)に適応されることによって世界平和や世界国家が実現する可能性を示唆しています。
ちなみに、アメリカ合衆国はしばしば「人種のるつぼ」(melting pot)と称され、その社会は多元社会(Pluralistic Society)と政治学者ロバート・ダール教授らによって定義づけられてきましたが、多極社会(Plural Society)はこれと区別されるべきです。
※ポリアーキー(Polyarchy=多頭制)論は、アメリカのデモクラシーに代表されるリベラル・デモクラシー(Liberal Democracy)とほぼ同義であると思われますが、こちらはロバート・ダール教授の理論です。ポリアーキー(Polyarchy)はモナーキー(Monarchy=君主制)の対語としてダール教授が造語しました。
■日本もかつて多極共存型デモクラシーによって統一された。
日本人は多極社会の民主的な統一化をすでに実現した経験を持つ民族なのかもしれません。日本もかつて多極共存型デモクラシーによって統一された。これが私の日本観です。
しかし、それから多くの歴史が過ぎ去りました。私の歴史観が事実だとしても、その記憶はもはや現代日本人の記憶には残っておらず、完成した「和をもって貴しと為す」社会の維持・継続のために、いつのまにか日本人は「出る杭は打たれる。」という、多様性を受容しないコンテクストを立上げてしまったのだと私は感じています。
日本人はそもそも、多極社会を民主的に統治するために多様性を受容する優れた民族気質を持っていたのだと私は信じています。しかし、これを忘れて、既に、今、目の前に存在する、過去の日本人が完成させた「和」を乱さないために、壊さないために、グローバル化にうまく対応できていないのではないでしょうか。このことについて、私はかつての「鎖国政策」の功罪の大きさを思わされます。
■多様性を受容する相互理解を忘れた統一日本の原罪。
本来ならば、さらに大きな受容性を発揮することで世界への窓が広げられなければならない時代に、日本人は第二次世界大戦に敗北するまで、占領地であるアジア周辺諸国を日本化し、占領地の民族、歴史、言語、宗教の独自性や多様性を認めようとはしませんでした。今もまだそんな感覚が私たちの中に残ってはいないでしょうか。私たち日本人はまず、この原罪を認めなくてはならないと私は思いますが、いかがでしょうか。
戦後復興の中で、多様性を受容しながらまさに「人種のるつぼ」と呼ばれるアメリカ合衆国の統治の下で、日本はもう一度、多極社会を民主的に統治するための日本人の民族気質を思い返し、発揮して、地球的な視野で多くの多様性を受容する社会をめざしてこの国のあり方を決めていかなければならないと私は感じます。
■相互理解のためにこそ宗教をタブー視してはならない。
これには多くの困難が考えられます。相当な覚悟が必要なことでしょう。それぞれが信じるものを持ち寄って、それぞれが信じるものを承認し、受容することがその第一歩だと思います。個人が確立されていることが、成熟した多様性を受容する社会の実現には必要です。
ですから、本論からかなり外れてしまいましたが、宗教は政教分離の思想からタブーとするのではなく、公明党だけでなく、もっと多様な宗教的バックグラウンドを持った政党が出てきてもかまわないと私は思います。宗教をタブー視するのではなく、もっと積極的にあらゆる宗教を学ぶことが大切なのではないかと思えるのです。誤解や反発を恐れずに言えば、自分なりに納得できる宗教を持たないこと、明確な信仰を持たないことが宗教に対する恐れや偏見につながりかねないのではないでしょうか。
個人的に信じる信じないは別としても、グローバル化が進む世界情勢の中で、宗教的背景が国際社会においても「権力」とは異なる、「権威」という大きな「力」を持ち得ることは、今も否定できない事実なのですから。

追伸 なかなかまとまらず、アップするのに時間が実は掛かりましたが、これでアップすることにします。いろいろなご意見やご感想があることと存じますが、どうぞ、いつものように忌憚のないご意見ご感想をお寄せくださいませ。今日は、期せずして、イースターです。キリスト=イエスの復活祭。別にこの日を目指して少しずつ書き綴った訳ではないのですが、これも神様の時なのかもしれません。みなさまに神様からの豊かな祝福があるように祈ります。ハッピー・イースター。
※イースターリリー(てっぽうユリ)は、聖母マリアの印でもありますが、イースターと言えばきれいに色を塗られたイースターエッグです。「死」の殻を打ち破って復活したキリスト=イエスを象徴しています。イースターラビットは、うさぎが一度にたくさんの子どもを産むことから、やはり生命の誕生を意味しています。イースターエッグはイースターラビットが持ってきて隠すとされており、このイースターエッグを探す、イースターエッグハンティングは欧米の子どもたちにとって年中行事であり、大きな楽しみのひとつでもあります。
瀬戸健一郎
Kenichiro Seto
草加市議会議員
Soka City Councilor
ブログ記事「政治とカネ~日本政治のタブーに挑戦①」に対するkeikoさんのリクエストにお応えして、「政治と宗教」について、今、思うことをシリーズ第二弾としてアップしておこうと思います。
■「政治と宗教」~瀬戸健一郎のライフワーク。
もとより、政治と宗教というトピックは、これ一本で博士論文が書けるほどの大きなテーマだと私はずっと思ってきました。やがて現役を引退したら、大学院に入って、このテーマに取り組みたいとも考えています。ですから、ここではあくまでさわりの部分ですので、ご了承ください。
また、私はクリスチャンですので、その立場からの見解になりますが、「相互理解なくして本当の和はありえない。」、「多様性の受容こそが本物の愛であり、デモクラシーの根源である。」というのが、私なりの哲学ですから、これについても私の発言の前提として明確にしておきたいと思います。
■八百萬(やおよろず)~多様性を包摂した憲法制定と仏教伝来。
keikoさんが前記事へのコメントで指摘されているように、私も日本人は、その精神性において、八百萬(やおよろず)=英語ではそのまま"eight million gods"(800万の神々)と表現されるように、神様の存在を文字通り万象に感じ取り、それを尊んできたのですから、信心深い国民だと言えると思います。
聖徳太子の「和を以て貴しと為す。」という日本初の憲法の精神が立てられた頃の日本は、おそらく地域ごとに神々を讃える地域信仰、民間信仰が集落ごとに多数点在していて、当時の日本はかなり多極化した状況だったのではないかと私は想像しています。
この憲法の制定と仏教の伝来が、日本に暮らす多様な人々にまさに「和」をもたらし、多様な信仰を包摂しながら、いわゆる日本という国や日本民族という枠組みが形成されて行ったのではないでしょうか。
■権力と権威~統治に必要な2つの力。
統治する=Governとは、政治学の永遠のテーマであると思いますが、一般論として、統治には2つの「力」が必要であると思います。ひとつは「権力」(Power)という力、もうひとつは「権威」(Authority)という力です。
一言で言えば、「権力」とは、「人を従わせる力。」であり、「権威」とは、「人が従おうとする力。」だと、私は説明してきました。
「ローマは3度、世界を征服した。」と言われます。最初は軍事力によって、2度目は法によって、3度目は宗教によって。軍事力は暴力。しかし、その軍事力でさえ、法によって正統化され得るので「権力」(Power)に分類され、その権力は皇帝に集中されていました。ローマ帝国は元老院の権威を借りて皇帝が統治しましたが、『ローマ市民全体を統治するための民主制』(※参照)は確立されていませんでしたから、ローマ領内にかつて迫害したにも関わらず広まったキリスト教の「権威」(Authority)を借りて、神聖ローマ帝国に至ります。
※"Government of the people, by the people, for the people"は、「人民の人民による人民のための政治」と翻訳されていますが、これは「人民を人民が人民のために統治すること」と私は自分のブログ記事で翻訳しています。"Government of the poeple"とは、「人民の政治」という所有・帰属の"of"ではなく、「人民を統治すること」という"Govern"(統治する)目的の"of"なのであり、これがアメリカのデモクラシー(民主制)の根源です。
■宗教の二面性~ルターは何をプロテスト(主張)したのか。
その後、宗教的権威は世界中に広がりましたが、これが純粋に宗教的教義や理念として広まったというより、時の権力者の統治を補完する政治システムとして取り込まれた側面を無視してはならないと思います。純粋に「教理を柱とする宗教」と権力者によって立てられた「制度としての宗教」の二面性を区別することが大事です。
少なくともドイツでルターが宗教改革を提唱するまでは、教会制度は政治権力に取り込まれ、信仰的に純粋ではなくなってきていたことがプロテスタント運動やピューリタン(清教徒)革命の背景にあったことは、神の意思や権威を権力者たちが自分たちの権力基盤を安定化させるために利用しようとした側面が少なからずあったことを連想させますし、事実なのではないかと思います。
十字軍の遠征による西欧諸国の覇権争いは、まさに「キリスト教が巻き起こした血で血を洗う世界史の中の汚点」であると評することが出来るかもしれませんが、隣人愛を説いたイエスの教えがいかなる殺戮も正当化するはずがなく、「キリスト教が」という主語は、正確には「西欧諸国が」と置き換える必要があるのかもしれません。
■産業革命~印刷機の発明と識字率の向上がもたらしたもの。
一部の人たちだけが、ほんの少数の人々だけが、文字を読むことができる。つまり聖書を直接読むことができた。印刷技術も発達していなかった時代には、聖書そのものが限られた人々の手に委ねられ、その教義はすべて口述によって伝えられた時代があったことも忘れてはならないと思います。
だれもが文字が読める。だれもが聖書を手にすることが出来る。そのような環境でこそ、本来のキリスト教信仰の根本である、神と人との個人的な関係が結ばれていく。それぞれの人間に神がどのように関わり、何をなさせようとしているのかが、十分に発揮されてこそ、また、個々人の可能性の開花が阻害されない社会を実現してこそ、すべての多様性を包摂した、相互理解に基づく社会の調和たる「和」が実現するのだと思います。
■人の思惑と神の愛~最後に残るものは神の愛、キリストの栄光。
ここで少しだけ、クリスチャンとしての思いを語らせていただきます。やがて世界宣教という錦の御旗を掲げて繰り広げられた西欧諸国の覇権は衰退し、民族自決権による独立運動が世界中に広がっていきました。世界中の民主化運動の中で、人々が自己の可能性に目覚め開花させた結果、征服者は去っても、イエスがキリストであるという信仰は残りました。
ですから、過去の歴史において、もしくは現代社会において、宗教が人間の行為を正当化するために使われる危険性を排除しない限り、宗教は人を幸せにはしない。しかし、本物の宗教の根底には人を幸せに導く教理が存在している。
それが何なのかを純粋に探究すれば、自分の生命に対する解決が見つかるかもしれません。自己の可能性が開花するかもしれません。すべての人が愛すべき存在に変わるかもしれないと私には思えるのです。
■八百萬(やおよろず)とは、神の臨在の証し?~聖書に見る不思議。
何かまとまりませんが、思うがままに書き進めてきました。ここで、クリスチャンとして、私なりに日本の八百萬(やおよろず)の神とは、神の臨在一つ一つの現象だったのではないかと思わせられた旧約聖書の記述を紹介したいと思います。
【旧約聖書より】
すると主の使いが彼に、現われた。柴の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに柴は焼け尽きなかった。
モーセは言った。「なぜ柴が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。」
主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は柴の中から彼を呼び、「モーセ、モーセ。」と仰せられた。彼は「はい。ここにおります。」と答えた。
神は仰せられた。「ここに近づいてはいけない。あなたの足のくつを脱げ。あなたの立っている場所は、聖なる地である。」
また仰せられた。「わたしは、あなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。」モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて、顔を隠した。(出エジプト記第3章2-6節)
※これは、モーゼの前に神が現れ、モーゼに「わが民を去らせよ。」(Let my people go.)と命じる直前の個所です。出典は旧約聖書に収められている「出エジプト記」という書物で、エジプトに隷属していたヘブライ人たちをモーゼが解放した史実を記録したものです。
■八百萬(やおよろず)~ヘブライ人の信仰と日本人の宗教観。
私がこの記述から思うことは、もしこのようなことが過去の日本に、日本人に起こったとしたら、きっと日本人は「燃える柴神社」をその場所に立てていたに違いないということでした。
ヘブライ人たちの信仰においては「偶像礼拝」を禁じる宗教文化でしたし、後に神が解放したヘブライ人たちのために初めて与えられた戒律である、モーゼの十戒においても、その第一戒として「あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。」(出エジプト記第20章4節)と記されていることから、そのようなことは起きませんでした。
宗教的権威というより、神の権威が正確に人間社会に反映されれば、その社会はパラダイスになるはずであり、この思想は仏教においても「王仏冥合」(おうぶつみょうごう)という大乗仏教の思想であり、これが創価学会が公明党を立党した根拠にもなっているのです。
宗教は本来、人々の価値基準、善悪の区別、行動規範を与えるという意味で「権威」という信じる人々が自ら従おうとする力を持っています。どの宗教を信じているのかが分かれば、その人なりその社会の価値観が理解できるというのは、かなり可能性の高いことだと思います。
■日本人とヘブライ人の宗教観と時間的概念
日本で最初の憲法である十七条憲法が八百万の神々への多様な信仰を前提に、それでも人と人との関係に着目して「和」という秩序を唱えているのに対して、ヘブライ人たちの最初の律法(戒律)であるモーゼの十戒は、万物の創造者であり、唯一完全無欠な一神教の神と人との関係に着目して「信仰」という観点から秩序を唱えています。
信仰上の「和」は日本においては仏教が多様性を包摂することによって形成されていき、それは地域信仰や民間信仰、神道や儒教ばかりではなく、キリスト信仰をも包摂する性質を養っていったのではないでしょうか。その意味で、偶像礼拝を禁じるキリスト教が排他的に見える。
さらに時間的な概念においても、季節がめぐるように生命もめぐるといった農耕民族らしい輪廻転生といった感覚(円)が、命には始まリがあり、終わりが来るといった狩猟民族らしい感覚(線)を、大きな輪(円)の一部として包摂しているかのようにも思われます。この感覚の違いが創造と終末論という思想につながっていると思われます。
■相互理解なくして本物の「和」はありえない。
「あなたの宗教は何ですか?」とか、「あなたは何を信じていますか。」というのは、その人を深く理解したいと考えた時に出てくる質問ですが、日本人はそのようなことは他人には聞くことはほとんどありません。深く相手のものの考え方や価値観を理解しようとすれば、当然の質問なのかもしれません。
これは多分、そもそも日本という国に存在していた多様性が、「和をもって貴しと為す。」といった聖徳太子の十七条憲法と仏教伝来によって、少しずつ大きな枠組みの中で包摂されていき、いわゆる日本という国や日本民族という単一統一の社会が形成された結果を享受している私たちが、そのプロセスを忘れているからではないかとさえ、私は思います。
相互理解なくして本物の「和」はあり得ない。"Harmony without Mutual Understanding is not Real Harmony."(相互理解なしの調和は本物の調和ではない。)とは、私たちの結婚式に駆けつけてくれた私の代母(Godmother)ナンシー(Nancy Ferriman)の言葉です。
■多極共存型デモクラシーは民主的に社会を統一化させる。
オランダ出身の政治学者アーレンド・レイプハルト教授が定義された「多極共存型デモクラシー」(Consociational Democracy)とは、かつて宗派によって三つに分断されていた社会が相互理解に基づく共生社会を構築した結果として社会の統一が実現されたオランダの例を論拠とした学説で、これが現実に多極社会である国際社会(もしくは、グローバル社会)に適応されることによって世界平和や世界国家が実現する可能性を示唆しています。
ちなみに、アメリカ合衆国はしばしば「人種のるつぼ」(melting pot)と称され、その社会は多元社会(Pluralistic Society)と政治学者ロバート・ダール教授らによって定義づけられてきましたが、多極社会(Plural Society)はこれと区別されるべきです。
※ポリアーキー(Polyarchy=多頭制)論は、アメリカのデモクラシーに代表されるリベラル・デモクラシー(Liberal Democracy)とほぼ同義であると思われますが、こちらはロバート・ダール教授の理論です。ポリアーキー(Polyarchy)はモナーキー(Monarchy=君主制)の対語としてダール教授が造語しました。
■日本もかつて多極共存型デモクラシーによって統一された。
日本人は多極社会の民主的な統一化をすでに実現した経験を持つ民族なのかもしれません。日本もかつて多極共存型デモクラシーによって統一された。これが私の日本観です。
しかし、それから多くの歴史が過ぎ去りました。私の歴史観が事実だとしても、その記憶はもはや現代日本人の記憶には残っておらず、完成した「和をもって貴しと為す」社会の維持・継続のために、いつのまにか日本人は「出る杭は打たれる。」という、多様性を受容しないコンテクストを立上げてしまったのだと私は感じています。
日本人はそもそも、多極社会を民主的に統治するために多様性を受容する優れた民族気質を持っていたのだと私は信じています。しかし、これを忘れて、既に、今、目の前に存在する、過去の日本人が完成させた「和」を乱さないために、壊さないために、グローバル化にうまく対応できていないのではないでしょうか。このことについて、私はかつての「鎖国政策」の功罪の大きさを思わされます。
■多様性を受容する相互理解を忘れた統一日本の原罪。
本来ならば、さらに大きな受容性を発揮することで世界への窓が広げられなければならない時代に、日本人は第二次世界大戦に敗北するまで、占領地であるアジア周辺諸国を日本化し、占領地の民族、歴史、言語、宗教の独自性や多様性を認めようとはしませんでした。今もまだそんな感覚が私たちの中に残ってはいないでしょうか。私たち日本人はまず、この原罪を認めなくてはならないと私は思いますが、いかがでしょうか。
戦後復興の中で、多様性を受容しながらまさに「人種のるつぼ」と呼ばれるアメリカ合衆国の統治の下で、日本はもう一度、多極社会を民主的に統治するための日本人の民族気質を思い返し、発揮して、地球的な視野で多くの多様性を受容する社会をめざしてこの国のあり方を決めていかなければならないと私は感じます。
■相互理解のためにこそ宗教をタブー視してはならない。
これには多くの困難が考えられます。相当な覚悟が必要なことでしょう。それぞれが信じるものを持ち寄って、それぞれが信じるものを承認し、受容することがその第一歩だと思います。個人が確立されていることが、成熟した多様性を受容する社会の実現には必要です。
ですから、本論からかなり外れてしまいましたが、宗教は政教分離の思想からタブーとするのではなく、公明党だけでなく、もっと多様な宗教的バックグラウンドを持った政党が出てきてもかまわないと私は思います。宗教をタブー視するのではなく、もっと積極的にあらゆる宗教を学ぶことが大切なのではないかと思えるのです。誤解や反発を恐れずに言えば、自分なりに納得できる宗教を持たないこと、明確な信仰を持たないことが宗教に対する恐れや偏見につながりかねないのではないでしょうか。
個人的に信じる信じないは別としても、グローバル化が進む世界情勢の中で、宗教的背景が国際社会においても「権力」とは異なる、「権威」という大きな「力」を持ち得ることは、今も否定できない事実なのですから。

追伸 なかなかまとまらず、アップするのに時間が実は掛かりましたが、これでアップすることにします。いろいろなご意見やご感想があることと存じますが、どうぞ、いつものように忌憚のないご意見ご感想をお寄せくださいませ。今日は、期せずして、イースターです。キリスト=イエスの復活祭。別にこの日を目指して少しずつ書き綴った訳ではないのですが、これも神様の時なのかもしれません。みなさまに神様からの豊かな祝福があるように祈ります。ハッピー・イースター。
※イースターリリー(てっぽうユリ)は、聖母マリアの印でもありますが、イースターと言えばきれいに色を塗られたイースターエッグです。「死」の殻を打ち破って復活したキリスト=イエスを象徴しています。イースターラビットは、うさぎが一度にたくさんの子どもを産むことから、やはり生命の誕生を意味しています。イースターエッグはイースターラビットが持ってきて隠すとされており、このイースターエッグを探す、イースターエッグハンティングは欧米の子どもたちにとって年中行事であり、大きな楽しみのひとつでもあります。
瀬戸健一郎
Kenichiro Seto
草加市議会議員
Soka City Councilor












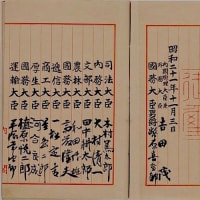
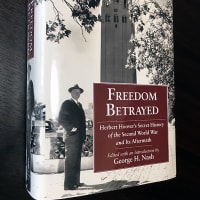


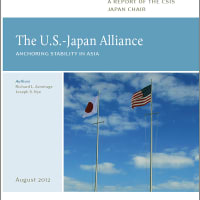
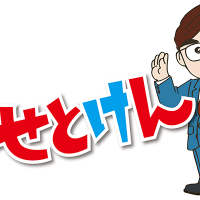

私には瀬戸さんの書いたものを論破するだけの知識も力量もありませんが、これだけの文章を書くというのはどれほど大変かは、よくわかります。また、この分野での返答は難しいだろうと思っていたのに、本気で答えてくれた瀬戸さんの律儀さに頭が下がります。
私には難しすぎて理解できない部分も多々ありますが、理解に努めようという気持ちがないわけではありません。しかし、争いごとが宗教に起因することが多すぎる気がします。自爆テロを認めるイスラム教など、到底認められません。
カルトでない限り、誰が何を信じようと口出しする気もありませんが、「主が小沢一郎を支持する」などと言われると、つい過剰に反応してしまいました。
かなり昔、無神論者であるはずの友達が大感激して、「キリスト教って素晴らしい」と1冊の本を貸してくれました。三浦綾子の「塩狩峠」(ブレーキのきかなくなった列車の乗客を、自分の命を犠牲にして救ったクリスチャンの話)です。作品としては申し分なく、私も泣きながら読みました。
その本を返すとき、「キリスト教だから素晴らしいんじゃなくて、人間の本質には誰でも自己犠牲というものを持っていると思う」と、今にして思えば冷たい感想を述べてしまいました。
実際、現代でも線路に人が落ちれば、反射的に飛び降りて助けようとする人は沢山います。赤の他人のために命を落とすのが、偶然、全員がクリスチャンだったというのなら、これは考えてみる価値があると思います。実際は違うでしょうけれど。
ここからが、瀬戸さんとの決定的な違いになります。つまり、人間の行動の規範というのは、宗教とは関係ないというのが私の主張です。矛盾した表現になりますが、現実的原理主義者と言い換えてもいいかと思います。
評価すべきことは形(宗教)ではなく、その精神であると思います。瀬戸さんが素晴らしいのは、クリスチャンだからではなく瀬戸さんだからです。
レイプ魔の牧師か神父が知りませんが、世の中には存在しますね。最近はローマ法王にまで飛び火しているではないですか。聖職者と呼ばれる人たちだって結局は野獣の顔を隠しているだけの、ただの人間です。
最後になりますが、「人民の人民による人民のための政治」という翻訳が文法的には間違っていても、日本人が誰でも知っている言葉になったのは、この翻訳があってこそです。意訳であっても元に含まれる真意を汲み取った翻訳だと思います。また、これと同じ意味のこととを、もっと深く語ったのは上杉鷹山の「伝国の辞」であり、リンカーンより何十年も前のことでした。
理想論ではすまない現実の問題があります。
宗教とは、個人個人の心のよりどころとなる信仰にもとづくものです。
宗教団体には、一歩間違えれば信者の心をコントロールしかねない要素があります。
それを利用して信者に政治活動を洗脳して政治団体や政党を作って政治活動をしたら、そら恐ろしいものがあります。
また、宗教団体を金儲けの道具にして蓄財している輩も多く、そんな団体が政治活動をしたらもう滅茶苦茶ですよ。