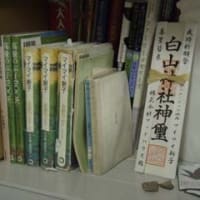2008年10月26日。
アフレコ開始5日前の日曜日。
キャスティングが決定し、主だった配役のうち、大人の男性は山口県出身者で固めてありましたが、女性陣と子どもたちが山口弁に馴染みがありません。
防府から方言監修の森川信夫さんに来ていただき、山口弁のおおよそのルールについて語っていただくことにしました。
松竹本社の会議室に集ったメンバーは、
新子=福田麻由子(中学生)
貴伊子=水沢奈子(中学生)
光子=松元環季(小学生)
シゲル=中嶋和也(小学生)
タツヨシ=江上晶真(高校生)
ミツル=西原信裕 (高校生)
一平=冨澤風斗(小学生)
吉岡さん=喜多村静枝(大人)
初江=世弥きくよ(大人)
メイド=久野道子(大人)
この日はキャストの初顔合わせでもあります。長子の本上まなみさん、諾子の森迫永依さんは、スケジュールが合わず、残念ながら、と欠席。
今日も水沢奈子くんは、名古屋から荷物を引っ張ってきています。
「あ」
福田麻由子くんは、西原信裕君を見つけて挨拶していました。『女王の教室』の共演者どうしだったわけです。
子どもの役は全部、実年齢高校生以下が演じるのですが、どっしり落ち着いた風情の「絵のうまい吉岡さん」だけは喜多村静枝さんに演じてもらうことにしてあります。といっても、喜多村さんの本役はむしろ「バー・カリフォルニアの女」の方なのですが。
新子のおばあちゃん「初江」を演じる世弥きくよさんは、舞台演劇の女優さんです。監督より年下なのに「おばあちゃん」なのはもうしわけないのですが、『カムイノミ』という劇で蝦夷の女長老を堂々と演じておられたのを観て、これはいいかも、と、『マイマイ』一座に引っ張り込んだのです。新子の家は祖父の代までは大地主だったので、地主の奥様だったおばあちゃんには飄々とした落ち着きが残っています。
山口県出身の久野道子さんには、最初のオーディションのときに子役たちのマイク前での面倒を見ていただいて、ひじょうに助かりました。本番では、フロアに入っていただいて細かい方言のニュアンス指導をお願いすることになっています。
「山口では、知らない人以外は皆知っている。森川です」
森川さんは防府市立図書館の職員(現在は館長)なのですが、方言研究家として、山口県では放送に出てそれなりに通った顔です。自己紹介の決まり文句も持っておられます。
山口弁は、東京式イントネーションなのですが、「ヒトシ」「ミツル」「フクダ」のような三文字の名前はだいぶイントネーションが違います。
それから、母音の数が多い。
「『赤い』が『あけー』、『会議室』が『けーぎしつ』」
この「けー」は実際には『か』と『け』の間の音です。標準語より多い母音は「あいうえお」では書き表せません。
ちょっとだけ名古屋弁に似ている気もします。
「名古屋弁の場合は『きゃーぎしつ』。名古屋弁に比べて、山口弁の方が○○」
そういって、名古屋から来ている奈子くんの顔をのぞきこんで、からかいます。
森川さんが口にした例文をみんなで真似して復唱します。
山口弁のツボがわかってきた気がします。
「それぞれ、ご自分の台詞で聞いておきたいことは?」
「はい」と喜多村さん。「この、『ほうたっちょきさんよ』ですが・・・・・・」
「『ほうたっちょきさんよ』。意味は『放って置きなさいよ』」
そんな感じで、みんなで手をあげて質問していく。小中高校生、大人も入り混じった山口弁学校。
「休み時間です。それが終わったら、一度通しで映画を見てみましょう」
一同、ガヤガヤ。
しかし、福田麻由子くんは休み時間もひとりでじーっと台本に見入ってます。競走馬みたいに真剣に役に入れ込んでる。だけど、周りの子たちが気を緩めてる、この休み時間にも?
と、奈子くんが、すっ、と隣に座りました。
奈子「いっしょにお団子食べよ?」
麻由子「え?」
奈子「はじめまして」
麻由子「あ。う、うん・・・・・・」
麻由子くんは、差し出されたお団子の箱に手を延ばしました。
うまくいってるじゃん、このキャスティング。
福田麻由子は、主人公役として、誰よりも前に出て芝居を作り上げなければならない覚悟を携えてここに来ている。
水沢奈子は、福田麻由子よりひとつ年上だけど、4歳から演技の世界にいる福田麻由子のことを先輩としてリスペクトし、友だちとして一緒にやっていこうとしている。
小学生の中嶋和也が、高校生の江上晶真にまとわりついてふざけてる。江上君もちゃんと取り合ってやっている。
芝居すれば大人顔負けの松元環季のふだんの顔は、まったく無邪気な「こども」のままです。
アフレコ開始5日前の日曜日。
キャスティングが決定し、主だった配役のうち、大人の男性は山口県出身者で固めてありましたが、女性陣と子どもたちが山口弁に馴染みがありません。
防府から方言監修の森川信夫さんに来ていただき、山口弁のおおよそのルールについて語っていただくことにしました。
松竹本社の会議室に集ったメンバーは、
新子=福田麻由子(中学生)
貴伊子=水沢奈子(中学生)
光子=松元環季(小学生)
シゲル=中嶋和也(小学生)
タツヨシ=江上晶真(高校生)
ミツル=西原信裕 (高校生)
一平=冨澤風斗(小学生)
吉岡さん=喜多村静枝(大人)
初江=世弥きくよ(大人)
メイド=久野道子(大人)
この日はキャストの初顔合わせでもあります。長子の本上まなみさん、諾子の森迫永依さんは、スケジュールが合わず、残念ながら、と欠席。
今日も水沢奈子くんは、名古屋から荷物を引っ張ってきています。
「あ」
福田麻由子くんは、西原信裕君を見つけて挨拶していました。『女王の教室』の共演者どうしだったわけです。
子どもの役は全部、実年齢高校生以下が演じるのですが、どっしり落ち着いた風情の「絵のうまい吉岡さん」だけは喜多村静枝さんに演じてもらうことにしてあります。といっても、喜多村さんの本役はむしろ「バー・カリフォルニアの女」の方なのですが。
新子のおばあちゃん「初江」を演じる世弥きくよさんは、舞台演劇の女優さんです。監督より年下なのに「おばあちゃん」なのはもうしわけないのですが、『カムイノミ』という劇で蝦夷の女長老を堂々と演じておられたのを観て、これはいいかも、と、『マイマイ』一座に引っ張り込んだのです。新子の家は祖父の代までは大地主だったので、地主の奥様だったおばあちゃんには飄々とした落ち着きが残っています。
山口県出身の久野道子さんには、最初のオーディションのときに子役たちのマイク前での面倒を見ていただいて、ひじょうに助かりました。本番では、フロアに入っていただいて細かい方言のニュアンス指導をお願いすることになっています。
「山口では、知らない人以外は皆知っている。森川です」
森川さんは防府市立図書館の職員(現在は館長)なのですが、方言研究家として、山口県では放送に出てそれなりに通った顔です。自己紹介の決まり文句も持っておられます。
山口弁は、東京式イントネーションなのですが、「ヒトシ」「ミツル」「フクダ」のような三文字の名前はだいぶイントネーションが違います。
それから、母音の数が多い。
「『赤い』が『あけー』、『会議室』が『けーぎしつ』」
この「けー」は実際には『か』と『け』の間の音です。標準語より多い母音は「あいうえお」では書き表せません。
ちょっとだけ名古屋弁に似ている気もします。
「名古屋弁の場合は『きゃーぎしつ』。名古屋弁に比べて、山口弁の方が○○」
そういって、名古屋から来ている奈子くんの顔をのぞきこんで、からかいます。
森川さんが口にした例文をみんなで真似して復唱します。
山口弁のツボがわかってきた気がします。
「それぞれ、ご自分の台詞で聞いておきたいことは?」
「はい」と喜多村さん。「この、『ほうたっちょきさんよ』ですが・・・・・・」
「『ほうたっちょきさんよ』。意味は『放って置きなさいよ』」
そんな感じで、みんなで手をあげて質問していく。小中高校生、大人も入り混じった山口弁学校。
「休み時間です。それが終わったら、一度通しで映画を見てみましょう」
一同、ガヤガヤ。
しかし、福田麻由子くんは休み時間もひとりでじーっと台本に見入ってます。競走馬みたいに真剣に役に入れ込んでる。だけど、周りの子たちが気を緩めてる、この休み時間にも?
と、奈子くんが、すっ、と隣に座りました。
奈子「いっしょにお団子食べよ?」
麻由子「え?」
奈子「はじめまして」
麻由子「あ。う、うん・・・・・・」
麻由子くんは、差し出されたお団子の箱に手を延ばしました。
うまくいってるじゃん、このキャスティング。
福田麻由子は、主人公役として、誰よりも前に出て芝居を作り上げなければならない覚悟を携えてここに来ている。
水沢奈子は、福田麻由子よりひとつ年上だけど、4歳から演技の世界にいる福田麻由子のことを先輩としてリスペクトし、友だちとして一緒にやっていこうとしている。
小学生の中嶋和也が、高校生の江上晶真にまとわりついてふざけてる。江上君もちゃんと取り合ってやっている。
芝居すれば大人顔負けの松元環季のふだんの顔は、まったく無邪気な「こども」のままです。