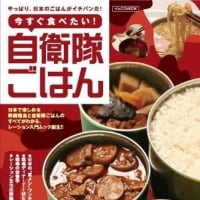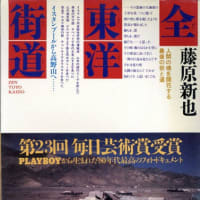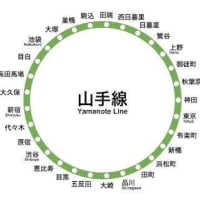(Ⅱ)立憲主義と民主主義
朝日新聞の主張「憲法によって国を治めるのが、近代の民主主義国の仕組みだ。憲法は、別の法律や命令では変えることはできない。つまり、時の権力者でも思うままにはできない。首相は、こうした立憲主義の考え方が、絶対王政時代の遺物だと言いたいのだろうか」は明らかに「立憲主義」の曲解、もしくは、贔屓の引き倒しの類の言説だと思います。
第一に、憲法改正条項(96条)の改正に際しても、安倍総理は現行の占領憲法の諸々の手続を踏んで行おうとされているのだから「憲法は、別の法律や命令では変えることはできない。つまり、時の権力者でも思うままにはできない」という批判は筋違いである。それとも、朝日新聞は立憲主義を根拠に「憲法典の改正規定を遵守したとしても時の権力者なるものは憲法典を変更できない」とでも言いたいのでしょうか。
もしそうなら、それこそ「憲法によって国を治める立憲主義」を否定する主張だと思います(尚、憲法改正条項の改正は「憲法の改正」ではなく法学的意味の革命、すなわち、「新憲法の制定」であるという主張に関しては旧稿「憲法96条--改正条項--の改正は立憲主義に反する「法学的意味の革命」か」をご参照ください)。
第二に、現下の大衆民主主義下の社会において、「時の権力者」なるものは「社会の多数派、および、その社会の多数派を擁する時の立法府と行政府」でしかない以上、「立憲主義」は「社会の多数派の支配」としての民主主義と鋭く対立する法理念だからです。
尚、この、立憲主義と民主主義の交錯と相克に関しては
下記拙稿をご参照いただければ嬉しいです。
・立憲主義を守る<安全弁>としての統治行為論
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/d2b014fb5dcdcb6d9260f7aa8eec3c5f

而して、国家権力を正当化する民主主義という法理念を退ける立憲主義の<神通力>は、ある「権利の権利性」が間主観的にその当該の社会で了解される限り--ある権利の権利性について国民の間に法的確信が存在する限りにおいて--認められるものでしょう。そうでなければ、立憲主義のパーツとしての司法審査を鑑みるに、民主主義的な要素がより濃厚な立法府や行政府といった政治セクターの判断や行為を、つまり、その社会の多数派の要求を、選挙の洗礼も経ていない法テクノクラートが構成する司法府が違憲・無効にできるという根拠は存在しないでしょうから。
加之、アメリカ憲法では「政治問題:political questions」と呼ばれる--日本では「統治行為」と呼ばれている--外交や安全保障、エネルギー政策等の高度の政治性を帯びる問題、あるいは、政教分離原則の射程等のその社会内に歩み寄りが不可能なほど鋭く、かつ、その社会を二分するイデオロギー対立が存在する問題については司法府は司法審査を行うべきではないというルールもまた、民主主義に立憲主義が道を譲るべきとされる類型にほかならない。而して、「政治問題-統治行為」は、社会の多数派に鬱積する不満と怨嗟がついに<暴力>を帯びて現行の実定法秩序と憲法体系を打ち倒すことを防ぐための憲法保障の仕組み、換言すれば、立憲主義を守るための<安全弁>なのだと思います。
すなわち、「立憲主義」とは、逆に言えば、司法審査が可能で妥当な法的紛争の範囲を確定するためのガイドラインであり、極論すれば、そのような司法府を組み込んだ国家の統治機構全体の正当化ロジックである。と、そう私は考えます。ならば、「立憲主義」と「民主主義」を共に「時の権力者」なるものに対する制約原理と解する朝日新聞の理解は完全に間違っているということもまた。
(Ⅲ)硬性憲法を説明するロジックとしての立憲主義
説明するまでもないことでしょうが、その改正に通常の立法手続よりもより厳格な手続を求めている憲法典のことを「硬性憲法」と呼びます。そして、(Ⅰ)「権力者とは誰か--立憲主義の守備範囲」で述べたように、「権利性の認められる権利」を時の社会の多数派からも容易には侵害されないようにするべく、憲法典に権利規定を定め、かつ、司法審査の蓄積の中でその権利の保障を行うだけでなく、その権利規定の改正要件を厳格化することは確かに「立憲主義」の内容の一斑と言える、鴨。
けれども、「立憲主義」の意味内容は、謂わば「硬性憲法を正当化するロジック」に尽きている。なぜならば、実際、現実的にも、また、--「立憲主義」自体が紛争解決を通した権利の保障について具体的な判断基準を備えているわけでもないのだから--法論理的にも、具体的な権利の保障は個々の具体的な案件に際して具体的な権利条項の解釈を巡る司法審査の中で行われるしかないのですから。
蓋し、ならば、ある社会のある時代において、どの程度の憲法改正条項の厳格さが<立憲主義>からみて妥当かどうか。就中、--前節で触れた、立憲主義と民主主義の二律背反の構図を想起するに--どの程度の憲法の硬性性が民主主義の謂わば「受忍限度」や「許容範囲」と言えるかどうかは、これまた「立憲主義」の四文字をいかに睨んでも詳らかにすることは不可能なのです。
畢竟、国会議員による改憲案の発議要件が現行の占領憲法の如く「3分の2以上」なら<立憲主義>に沿っており、「過半数」なら<立憲主義>からは正当化され得ないということはないということ。自民党の改憲案でも憲法改正には国民投票が課されており、それはそれでまた硬性の憲法である--<立憲主義>の精神を踏まえている!--、他方、現行の3分の2以上を4分の3以上に修正する改正案に比べれば、現行の占領憲法は--<立憲主義>の精神を軽視している!--と言えるでしょうから。
何を言いたいのか。蓋し、「立憲主義」を持ち出してする憲法改正条項(96条)の改正批判はそう根拠の確かなものではないということ。すなわち、それは単なる「硬性憲法説明のロジック」にすぎない「立憲主義」を、現行の占領憲法の適切な硬性性--あるべき厳格さの程度--を判定する根拠として用いる誤謬を犯したもの。いずれにせよ、「権利性のある権利の尊重」を要求する法理念として「立憲主義」を捉える場合、直接には、--「憲法を国民の手に取り戻す」こと、つまり、国民の参政権を拡充することを除けば--いかなる権利の侵害とも権利の保障とも無縁な改正要件の具体的な変更の是非を「立憲主義」を基準に判定することなど不可能。と、そう私は考えます。
(Ⅳ)憲法の概念と立憲主義
この社説が陥っている最大の陥穽は、それが憲法の概念または事物の本性と「立憲主義」を二者択一的のものと捉えていることでしょう。「「考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方がある」。それこそ立憲主義である。問題はその次だ。「しかし、それは王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、いま憲法というのは日本という国の形、理想と未来を、そして、目標を語るものではないかと思う」これには、とても同意することはできない」、と。あのー、「国家権力を縛るもの」と「日本という国の形、理想と未来を、そして、目標を語るもの」は矛盾していますか。
第一に、アメリカ憲法にせよフランスの憲法にせよ、なにより現行の占領憲法や旧憲法を紐解くまでもなく、世界の憲法典の中に「国の形、理想と未来を、そして、目標」を語っていないものなど一つも存在しません。それとも、朝日新聞の社説子はアメリカ憲法の前文や現行の占領憲法の前文を読んだことがないのでしょうか。
第二に、政治社会学的に見た場合--近代以降の「国民国家-主権国家」の、かつ、憲法の事物の本性や憲法慣習といった実質的意味の憲法を捨象して形式的意味の憲法(憲法典)に限定したとしても--、<憲法>とは<国家>の実定法秩序に正当性を付与する最高の授権規範であり、すなわち、国民を社会統合するイデオロギー装置である。こう見た場合、例えば、現行の占領憲法の根幹もまた、旧憲法同様、日本の「国の形」を明記した第1章「天皇」であり、また、安倍総理が、憲法とは「国の形、理想と未来を、そして、目標を語るもの」と理解されていることは毫も「不思議」ではなく中庸を得た穏当な憲法理解であろうと考えます。
第三に、繰り返しになりますけれども、「時の権力者でも思うままにはできない」ということが、まさか、「時の社会の多数派、および、その社会の多数派を擁する時の立法府と行政府も憲法を変えることは一切許されない」ということでもない限り、憲法の改正手続に沿った憲法の改正を行うことは民主主義の要請であり、また、そのような立憲的な手続に則った憲法の改正を封じることは立憲主義を根拠にしてできるはずもない。なぜならば、「立憲主義」から導かれるのは「権利性を帯びる権利の尊重」という要請と「司法審査の妥当な範囲の確定」という基準までであり、「国の形、理想と未来、そして、目標」を憲法典に書き入れてはならないなどの規則が<立憲主義>から演繹されることはないのですから。
第四に、夜警国家の時代でもあるまいに、社会権が権利性を獲得して久しい現下の福祉国家を念頭に置くとき--かつ、グローバル化の昂進著しく、国際競争が激化の一途を辿っている現下の人類史において--、憲法は国家権力を縛る側面だけではなく、国家権力からのサービス供給の枠組みを定めるものです。
ならば、単なる権利間の調整原理である「公共の福祉」を超えて--安全保障の側面でも厚生経済政策の側面でも--国家権力が、公益の観点からする私権の制約と富の再配分、そして、国益の観点からする内政外交両面での統一的政策コングロマリットを推進することを憲法は謂わば「動作動詞の現在進行形」で正当化する機能を果たさなければならない。
要は、比喩ではなく社会権とは国家予算、更に言えば、景気動向指数と失業率のパラメーターであり--かつ、郵便ポストの色が赤色である必然性はないように、ルールの内容自体に必然性は乏しいが何らかのルールが定まっていることに社会的な意味と効用があるという事柄、「調整問題」の対象であり--、自由権に比べてもある国のある時点でのその内容を「立憲主義」の四文字から導くことは金輪際不可能でしょう。すなわち、憲法は「立憲主義」の他に「国の形、理想と未来、そして、目標」の規定に飢えているということです。
而して、この認識に異論がある向きにとっても、そのような現下の広大な国家権力の行政サービスの守備範囲を鑑みるに、それに比して、<立憲主義>が「動作動詞の現在進行形」で縛りうる国家権力の活動範囲は--それを司法審査の対象と再定義してみるとき--太平洋に風呂桶1杯分もないことだけは認めざるを得ないのではないでしょうか。再度記しておきますが、要は、国家権力の守備範囲は<立憲主義>の空間的守備範囲を遥かに超えているということです。
ことほど左様に、朝日新聞のこの社説は--「国の形、理想と未来、そして、目標」といった--「憲法の概念」や「憲法の事物の本性」に含まれる意味内容を、それらと無縁とまでは言わないけれど、それらの「真部分集合」にすぎない「立憲主義」という言葉から理解して批判する誤謬を犯している。それ正に立憲主義の無知の爆裂。と、そう私は考えます。
尚、「憲法」の概念を巡る私の基本的な理解については
下記拙稿をご参照いただければ嬉しいです。
・保守主義-保守主義の憲法観
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11144611678.html
・憲法とは何か? 古事記と藤原京と憲法 (上)~(下)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11145667266.html
・天皇制と国民主権は矛盾するか(上)~(下)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11136660418.html 
木花咲耶姫
・ほしのあきさんの<無罪>確定-あんだけ可愛いんだから当然なのです
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/78478ca7d4aebc00f057beebd43f17a4