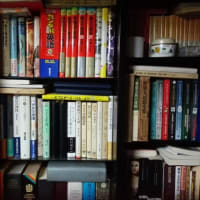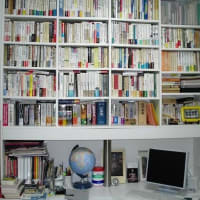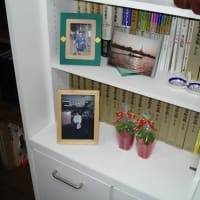2010年04月19日 14時33分56秒
本書、原作・服部武四郎/作画・中城健雄『劇画 教祖(おやさま)物語』(天理教道友社・1991年1月)は、全一巻1113頁の大作、天理教の教祖(おやさま)・中山みき様の伝記(第1部~第3部)と、教祖がお姿をかくされた明治20年2月18日(1887年)以降の天理教の苦難と発展の歴史(第4部・第5部)を描いた漫画です。
些か読みにくい、例えば、『稿本 天理教教祖傳』『稿本 天理教教祖伝逸話篇』(ともに天理教教会本部・1973年10月, 1976年1月)に比べるまでもなく、本書は漫画ということもあり天理教を知る上ではまたとない「入門書」であることは間違いありません。而して、中山みき教祖のお考えに接するという一点では、本書は「入門書」に止まらない水準にあると思います。
蓋し、プロテスタントの牧師が「偽善」に、他方、(「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」と喝破した親鸞聖人の「悪人正機説」の影響でしょうか)浄土真宗の学僧が「偽悪」に傾く傾向がまま見られるとき、「中山みき教祖=おやさま」の「貧に落ち切る」という姿勢に感動した天理教布教拡大に燃える青年達がおうおうにして「貧乏自慢」に走る傾向がなきにしもあらずのことを見れば、本書がバランスよく紹介している教祖の人柄・姿勢・態度・思想は、それら「付け焼刃-形式主義」の信仰とは別次元のものであることが理解できるのではないか。と、そう私は考えます。
【教祖(おやさま)・中山みきプロフィール】
本名:中山 美伎
DOB:1798年6月02日(寛政10年4月18日)
DOD:1887年2月18日(旧暦換算、明治20年1月26日。
明治5年からは日本では太陽暦が採用されている)
POD:大和国山辺郡三昧田村(現在の奈良県天理市三昧田町)
その他:①比較的裕福な農家に生まれた
②少女時代から神仏に帰依する所深く、自身浄土宗の僧侶になることを希望し、
19歳の時には五重相伝を授けられるほどの、浄土宗の熱心な信者だった。
③1810年10月13日(文化7年9月15日)に中山善兵衞に嫁ぐ
④1838年(天保9年)10月23日・10月26日に神のこの世の「依り代=神の社」となる。
信仰の話は、信仰のある方にはする必要が乏しく、ない方には、ブログ程度でしてもあまり意味がない。よって、天理教の信仰以外の点で、私が本書をお薦めするポイントを最後にまとめておきます。蓋し、それは次の三点。
(甲)江戸期から明治中期にいたる庶民の暮らしや思いを知る上で絶好の資料
(乙)江戸期から戦前にかけての日本女性の立場や思いを知る上で絶好の資料
(丙)人生の苦境にあるときに勇気づけられる一書
・宗教と憲法--アメリカ大統領選の背景とアメリカ建国の風景
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3a1242727550e8e31a9133aa154f11bf
この国では、例えば、坂本龍馬の<人気>はあいかわらず高いのでしょうが、その龍馬氏も江戸時代の人であり、彼の言動も、江戸時代の人々の人生観や神仏観を前提にしない限り、実は、彼の「同時代人から見て際立った先進性」も本当は理解できないのではないか。実際、黒船が来航したときから(1853年)、あるいは、明治維新が成し遂げられたときから(1867年)、要は、政治権力が交代した途端に、ほとんどの日本人が、少なくとも、「個人の自立と家制度の矛盾に悩む」エリート青年ががらりと<近代人>に変わったわけではない。明治といえども江戸時代の延長の上にしかない。そのことが本書には、文字通りビジュアルに描かれていると思います。
また、中山みき様の夫、「中山善兵衞」氏は、歴史学的には(逆に、当時としては極端に素行の悪い人物であったとも思えませんが)浪費癖・女性問題等々の点で些か問題のあった人物とされる(例えば、笠原一男『教祖誕生』(日経新書・1968年5月)参照)。よって、中山みき様が教祖(おやさま)になられたについては、素行の悪い夫への不満が爆発した、少なくとも、それが一つの契機になったと言う方もおられる。論証は割愛しますが、私はそのような考えは採用しません。が、しかし、本書が天理教の立場から些か「中山善兵衞」を美化していることは間違いないと思います。
けれども、その若干の美化を通してさえも、本書が描く夫に対する中山みき様の複雑な思い、また、天理教の教えに救いを求める多くの女性たちの叫びや思いを感じることは、江戸期から戦前にかけての日本女性の立場や思いを追体験する上でまたとないテクストではないか。蓋し、
・水田珠枝『女性解放思想の歩み』(岩波新書・1973年9月)
・上野千鶴子『家父長制と資本制』(岩波書店・1990年10月)
・上野千鶴子『ナショナリズムとジェンダー』(青土社・1998年3月、特に、第1部)
と本書を併読されれば、日本における女性解放思想の潮流を、地に足のついた形で血肉化できる、鴨。と、そう私は考えています。尚、上野千鶴子『家父長制と資本制』は、「マルクス主義の有効射程を市場に限定する」帰結として、国家の概念が些か薄かったのですが、上野女史は、例えば、『ナショナリズムとジェンダー』以降、国家をそれなりの独自の運動法則性を持つものとして捉え返しておられます。女性解放思想に関する私の基本的な考えについては下記拙稿をご一読いただければ嬉しいと思います。
・完全攻略夫婦別姓論-マルクス主義フェミニズムの構造と射程(上)
http://kabu2kaiba.blog119.fc2.com/blog-entry-398.html
・完全攻略夫婦別姓論-マルクス主義フェミニズムの構造と射程(中)
http://kabu2kaiba.blog119.fc2.com/blog-entry-399.html
・完全攻略夫婦別姓論-マルクス主義フェミニズムの構造と射程(下)
http://kabu2kaiba.blog119.fc2.com/blog-entry-400.html
・読まずにすませたい保守派のための<マルクス>要点便覧
-あるいは、マルクスの可能性の残余(1)~(8)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11139986000.html
さて、本書は間違いなく「人生の苦境にあるときに勇気づけられる一書」です。この点に関しては是非ご自分でご確認いただければと思います。間違いなく元気になりますよ。ということで、久しぶりに天理市に行きますかね。
ヽ(^o^)丿