
We will engrave in our hearts the past, when Japan ended up becoming a challenger to the international order. Upon this reflection, Japan will firmly uphold basic values such as freedom, democracy, and human rights as unyielding values and, by working hand in hand with countries that share such values, hoist the flag of “Proactive Contribution to Peace,” and contribute to the peace and prosperity of the world more than ever before.
Heading toward the 80th, the 90th and the centennial anniversary of the end of the war, we are determined to create such a Japan together with the Japanese people.
August 14, 2015
Shinzo Abe, Prime Minister of Japan
【Cabinet Decision】
<語彙:S71-S73>
when:関係副詞のwhenですよ, end up:なんだかんだ言っても結局/紆余曲折の末に~ということで事は終わる(end up が 他動詞として目的語に「~になること/~すること」の意味の状態や動作を取る場合、avoid, appreciate, consider, give up, insist on 等々と同様、不定詞(to-V)ではなく、必ず動名詞(Vg-ing)がきます), firmly:しっかりと, uphold:保持する/維持する/上級審が下級審の判決を支持する,
the international order:実定的な国際法秩序(談話前半の(S18)の「the new international order」は、満州事変以降の具体的な日本の行動をなぞりながら、国際聯盟に象徴される第一次世界大戦以降の国際秩序の変化をイメージしていました。ここではより一般的というか本質的な意味で--「すべからく国際秩序なるものとは」とか、例えば、「武士道とは」とか「人生とは」とか級の高い抽象度の質問への解答として--用いられていること。ここの「the international order」の定冠詞 the は総称用法の中でも本質表象型なのです),
(S72)basic values:基本的な価値(basic(基本的な)は語源はL語源の base(底)から。value(価値)のL語源は「健康かつ頑強」、valid(有効な), avail(ある物事が役に立つ), prevail(上回る/普及する)も同系列の語彙), such as A as B:Bという属性・性質を持つA (注意! as や that をともなわず suchが単独で使われる場合には、これまでに述べたことを「さっき話題に出たあれ」と「前方照応型」です),
freedom:自由(である状態。「-dom」は、wisdom(英知), boredom(退屈/倦怠)等、抽象名詞を作る接尾辞), democracy:民主主義(Gr語源「demo-・群衆の」「-cracy・統治」。IE語源[da-・ばらばらに切り分ける]から出たGr語源の[demos-]の原義は「社会を構成する地域組織やその構成メンバー」、後辞のGr語源の[kratos]の原義は「力/発言権」), human rights :人権(この用語は、英語圏では、国際法-国際法学のテクニカルターム。国内法的な意味の、つまり、憲法論的な意味の「人権」は単なる「right(s)」。「human:人間の」「fundamental:基本的な」などの余計な形容詞はつきません。よって、この箇所で安倍総理は、あくまでも、「国際法的な意味の人権」を述べている。少なくとも、これを英文テクストで読む読者はほぼ例外なくそう理解することになります),
unyielding:頑強な/劣化や変形などしない, hand in hand with:~を手を取り合って/密接な関係にある, share:共有する(IE語源の「切る/裁断する」の語義をも残しつつ、G語源の「短めの上着」から「なにかを切り分け各自に小さな部分を分け与える」まで到達。語源の面白さで、shirt(シャツ), skirt(スカート), short(短い)は同系統の語彙です), hoist:旗や帆を巻き上げる(cf. 「~に反対(賛成)という旗幟を鮮明にする」は「make one's position clean against (/for); take a clear stand against t (/for)),
the flag of “Proactive Contribution to Peace” :「積極的平和主義」の旗(proactive(先取りする/先々と手を打つ), contribution:貢献・寄与(L語源は「con-・共に」「tribution・持っていって贈る」)), more than ever before:かってそうあったよりも多く,
(S73)head:(動詞としては、)~に向かう/~を率先する, centennial:百周年の(L語源の[cent-・100の]「ennial・年」から。後の形は英語の annual(年の/年間の), anniversary(例年の/周年の)と同語源、そして、前の「cent-」が「centimeter:センチ」や「century・100年=1世紀」と同じなのは言うまでもない。しかし、この「cent-」とGr語源の[hekaton]と、IE語源段階では同一の語であり、このGr語源系から「hectare:ヘクタール」「hectopascal:ヘクトパスカル」だけではなく「hundred:100」ができたんですよと聞くと、ちと得した気分になりませんか),
determine:決意する(determine は agree, hesitate, manage, prepare, refuse 等々と同様に、動名詞(Vg-ing)を目的語に取ることはなく、必ず、不定詞(to-V)を取る他動詞です), create:創造する(L語源の「成長する/成長の動因」から。creative(独創性のある)は当然として、cereal(穀物の), recruit(新兵を補強する)も同系統の言葉 ), such a Japan:そのような(=今述べたような)日本←これが「前方照応型の such」),
<語彙:おまけ-Giveaway>
Abe:安倍(英語では男性名の「エイフ」(アブラハム(Abraham)の愛称), prime minister:内閣総理大臣(L語源では「臣の中の臣/人臣中の序列第1位の臣民」), Japan:日本(マルコポーロ『東方見聞録:the Travels of Marco Polo』(1300?)の中の、当時の「日本」を表す支那の元(1271~1368)で流通していた言葉[Jihpun]から[Zipangu]になったとかは、実はかなり怪しい話。いえいえ、[Zipangu]→「Japan」は鉄板なのですけれど、[Jihpun]の方が、それに該当する<国>がこの「日本」と同一か不明ということ。日本列島側に[Jihpun]の当時の支那の音声/Jihpun/に該当する地名らしき言葉もないっ、ぽ。なんです),
cabinet:内閣(中英語期に「cabin:小さめの小屋」「-net:小さいもの」が合体して「小さな部屋/密談用の国王の私室」から成立), decision:閣議決定/判断(L語源の[de-・/分離]→「切り離す」から。scissors(はさみ)は派生語、また、動詞形は decide(判断する/決める)ですが、この decideは、expect, feel free, fail, resolve 等々と同様に、目的語には、必ず、不定詞(to-V)を取って動名詞(Vg-ing)は取らない他動詞です)
<読解躓きの石>
▽freedom-libertyの語感
「freedom」の語幹、「free」は固有種の単語で原意は「恋人・友人」。ただ、そんな「恋人・友人」の関係は部族内の自由人仲間に限られるわけで、漸次、「恋人・友人」の属性である「奴隷ではない/拘束されていない/自分のやりたいことはすきにできる」から「自由」の語義が巣立ったらしい。他方、「liberty:自由」の語源原義が「奴隷身分から解放された状態」という客体的なものだったからか、「freedom」が「非拘束状態であることを誇りに感じ、その裏面で、自由を担う責任をも自覚する」、謂わば主体的な色彩が強いのに対して、「liberty」の方は「拘束状態からの解放を喜びつつも、その「状態」が再度失われる恐怖感を引きずる」、謂わば被害者意識が憑依しており、liberty とfreedomの英語での語感はかなり異なる。
例えば、憲法論議の際、英米法の用語としては、権利としての「表現の自由」「信教の自由」は、あくまでも「freedom of speech」「freedom of worship」と「X への自由」型。他方、liberty といえば、「liberty from autocracy:独裁制からの解放」のように「Y からの解放」型。蓋し、freedomが「非拘束状態」を主体的に求めるのに対して、libertyはそれを社会的-状況的に求めるものだから、鴨。
両者をこう捉まえるとき、--夜警国家が絶滅して世界のすべての国家が福祉国家化した、この1世紀あまりの状況の変遷を鑑みるに--逆に、freedom が「よけいなことせんと、ほっとけ!」と「国家権力からの自由」を、また、精神的な自由や表現の自由に力点を置くのに比べて、liberty は経済的保障や差別の禁止等々、「時の権力の強権を使ってでもなんとかしてよ!」と「国家権力への強請」の形を取るのも自然な流れ。ならば、freedom と liberty を共に「自由」と訳すから混乱が生じるのであって、後者は「解放」「強請」とかにすればよい、と、そう私は考えます。
実際、米国の日常生活で「liberty」は--所詮、インテリさん向け外来語だからか--そう多くは使われません。日本語で1月1日を呼ぶ「お正月」と「元旦」の頻度差はある。特に、アメリカでは--フランスから贈られた「自由の女神:the Statute of Liberty」なんかも、普通、保守派も、(日本のリベラル派とは全然違う、アメリカの健全な)リベラル派もともにアメリカ人は「the Goddess of Freedom」「Miss. Freedom」とか呼んでいます(←ちょびっと誇張、でも、嘘ではありませぬ。少なくとも「出羽の守」ではない)。
>自由の主体的な称揚:freedom
>解放の社会的な強請:liberty
OED先生に確認、
・freedom
1) the state of not being a prisoner or a slave
2) the power or right to act, speak, etc. as one wants without anyone stopping one
:protect the freedom of the individual
* * * *
1) 囚人や奴隷ではない状況
2) 他者から制止されることなく、自分のやりたいように行動し、
言論活動を行い、あるいは、その他の活動をする権利もしくは権限:
: 個人の諸権利を護る(←「コロン」以下は、OED先生の使用例ですよ)
・liberty
1) the state of being free from excessive restrictions placed
on one's life by a governing power
2) the right or power to do as one chooses
:They give their children a great deal of liberty.
* * * *
1) 政治的権力が人々の生活に過剰な制約を課してはいない状況
2) 自分の好きなようにする権利や権限
:彼等は自分の子供達には好き放題することを許していた。
▽頻出形容詞の語順の確認-- TOEIC・TOEFL受験者必須
[◎]all the people [×]the all people (その人々全員)
[◎]such a people as the Vietnamese
[×]a such people as the Vietnamese
(ヴェトナム国民のような国民)
cf. a very kind people as the Vietnamese←通常の語順
(ヴェトナム国民のように大変親切な国民)
[◎]most of the people
[×]the most of people
[◎]most people
(国民の大多数<==・・日本では保守派である!)
(上2個のmostは名詞、下は形容詞のmost)
[◎]so pretty a cat
[×]a so pretty a cat
cf. a very pretty cat.←通常の語順
(かなり可愛い猫<==・・KABUんとこの白黒ちゃんも?
cf. the very pretty cat
(正に、それ、その可愛い(とかいう)噂の猫)
↑
うちの白黒ちゃんのことじゃないよな、多分。
The Asahi made the very same mistake.
The Asahi made much the same mistake.
(朝日新聞は(またもや)まったく同じ間違いを犯した)←何回、売国すんねん!
(朝日新聞は(今回も)ほぼ同じ間違いを犯した)←えーかげん、学習せい!
▽副詞の位置-位相差問題
TOEIC・TOEFL対策では前頭の中位、他方、世界のビジネスシーンで使える英語力獲得のための重要度では、調子がよければ(?)小結・関脇も狙える。それが「副詞の位置」。ここでは同じ副詞の位相差による意味の違いを取り上げます。日本人や日本語が母語の日本市民の典型的弱点の一つだから。まずは基本の確認。有名な『ロイヤル英文法』の例文からスタート。
Happily the cat didn't die.
The cat didn't die happily.
(白黒ちゃんは幸いにも死ななかった)←よかった、よかった。
(白黒ちゃんは不幸な死に方をした)←ええっ、可哀想~!
準備運動終わり、
次々行きます。
I met him first; and・・・.
First I met him; and・・・.
(彼が最初で・・==>2番目には彼女に会った)
(彼との面談を済ませたあと==・・>次に山に柴刈りに行った)
This is the most notorious prefecture for its left biased education.
This is the notorious prefecture most for its left biased education.
(北教組(民主党系)によって教育が左側に歪められているという点では、北海道が全国で最悪だ)
(北海道には良いこともある。だが、北教組(民主党系)や道教組(共産党系)によって教育が左側に歪められているという点だけは玉に瑕だ)
a most important problem(かなり重要な問題)
most important problems(かなり重要な諸問題/大部分の問題)
the most important problem (最も重要な問題)
※ a most≒very/=incredibly
cf. the very constitution(それ、正に、その憲法)
cf. a very constitution(なんというか、憲法みたいなもの)
まだ行きます。
①Suddenly Hatoyama stopped his car.
②Hatoyama suddenly stopped his car.
(鳩山は車を止めた、唐突なことだった)→おい、ここはどこだよ?
(鳩山はいきなり車を止めた)→あぅ、むち打ち症は大丈夫かぁー?
最後は、【本編12】の例文を使った確認。これです。
GHQ provided a constitution to the Japanese.
≒GHQ provided the Japanese with a constitution.
(GHQは日本国民に憲法を提供した)
ここで、上のセンテンスに officiously(あつかましく・差し出がましく/横柄・慇懃無礼)を加えるとどうなるか。ここでは一応、文末に置く場合も下③センテンスと意味はほとんど同じとしておきます。そうすると、この二通りになります。③④の意味の違いは?
③Officiously GHQ provided a constitution to the Japanese.
④GHQ officiously provided a constitution to the Japanese.
cf. GHQ provided a constitution to the Japanese officiously. ←(≒④)
③④の意味はこうなる。⑤は対照例文。
③(不当にも、GHQは日本国民に憲法を押しつけた)
④(GHQは日本国民に無礼なやり方で憲法を押しつけた)
⑤Officiously GHQ provided a constitution to the Japanese officiously.
つまり、③では「officiously」はセンテンス全体を修飾(文修飾)するのに対して、④ではあくまでも(語修飾として)述語動詞を修飾をしている。だから、③④で訴えたい不満をともにあなたが言いたい場合は⑤になる。ただ、⑤は、韻を踏んで力強くもあるけれど、やっぱダサ。よって、どちらかの副詞は他の類似の副詞と差し替えしないと教養(intelligence)を疑われる、鴨。このような類義語への差し替えを、確認ですが「Variation」と言います。ここ、【本編10】「パラグラフ-英語の<風呂敷>のお話し」で確認してください。
敷衍します。同じ、--漠然と「差し出がましく」と「横柄」の両極の語義を包摂していた--「officiously」が③では「unreasonably:筋違いも甚だしく」の意味に、そして、④では「arrogantly:横柄かつ居丈高に」の意味に収斂するということ。副詞の位置は、就中、その位相差の論点は、所謂「新テスト」(←変更、2006年5月だよ!)になってからは、TOEICの頻出論点では最早ないと感じます。しかし、パート4や7で<制限時間内>にパッセージの要旨をきちんと把握するためにはかなり重要な知識。
蓋し、
畢竟、
而して、←(英文のパラグラフではこの3語は不要です!)
副詞は、そして、冠詞と前置詞が英語の鬼門、
かつ、英語のワンダーランド・遊園地です。
б(≧◇≦)ノ ・・・冠詞・前置詞・副詞は英語のUSJだぁー!
б(≧◇≦)ノ ・・・英語は、楽しい-!
<日本語原文>
私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります。
終戦八十年、九十年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく。その決意であります。
平成二十七年八月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
【閣議決定談話】
( ..)φ( ..)φ
◆後書き-保守派の同志の皆さま◆
本稿「英語教材として読む安倍談話」はこれで終わりです。以下、
本稿の「余滴」として、「国家」「法」についての語源譚が続きますが、
教材の副読資料にはなっても、些か、社会思想的な色彩が強い。
もし、ご興味があれば、暇なときにでもお寄りください。
ここまででも、しかし、確実に、
あなたの英語力が向上したことを保証します。
と、うにゅ、
>「保証なんてできるのか!」っ、て?
もちろんですとも。
どんな「教材」でも、ちゃんとやれば必ず
効果はあるものですから。
ヽ(^o^)丿
最後まで読んでいただきまして有り難うございました。
日本のため、自分のため、共に闘わん。
<(_ _)> <(_ _)> ←KABUs
<余滴に続く>
最新の画像[もっと見る]
-
 ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
-
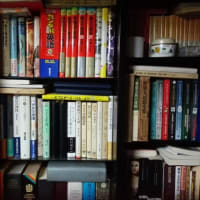 ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
-
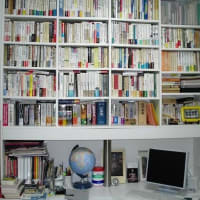 ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
-
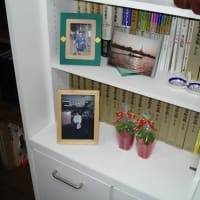 ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
-
 ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
ネットの時代に「本を買うこと」の意味≒それは自宅のストーブでカボチャをじっくり煮ることかも+「古文・漢文」は必要か?
2日前
-
 #自分でも感心したこと↖️英語苦手だったはずなのに米英人の同僚から文法チェック頼まれるようになったとき
7日前
#自分でも感心したこと↖️英語苦手だったはずなのに米英人の同僚から文法チェック頼まれるようになったとき
7日前
-
 #自分でも感心したこと↖️英語苦手だったはずなのに米英人の同僚から文法チェック頼まれるようになったとき
7日前
#自分でも感心したこと↖️英語苦手だったはずなのに米英人の同僚から文法チェック頼まれるようになったとき
7日前
-
 「ベトナムフェスティバル 2024」東京・代々木公園で開催、本場ベトナムグルメが集結⬅️楽しみ。お薦めします❗️
7日前
「ベトナムフェスティバル 2024」東京・代々木公園で開催、本場ベトナムグルメが集結⬅️楽しみ。お薦めします❗️
7日前
-
 「ベトナムフェスティバル 2024」東京・代々木公園で開催、本場ベトナムグルメが集結⬅️楽しみ。お薦めします❗️
7日前
「ベトナムフェスティバル 2024」東京・代々木公園で開催、本場ベトナムグルメが集結⬅️楽しみ。お薦めします❗️
7日前
-
 【再掲】貨幣価値:「あしながおじさん」に出てくる$35は今の**万円なのかしらね🐙
1週間前
【再掲】貨幣価値:「あしながおじさん」に出てくる$35は今の**万円なのかしらね🐙
1週間前
「英文読解 one パラ道場」カテゴリの最新記事
 【再掲】「歴史とは何か」のE.H.カー先生はとっくに見抜いていた? 「個人の尊厳...
【再掲】「歴史とは何か」のE.H.カー先生はとっくに見抜いていた? 「個人の尊厳... 英文読解 one パラ道場:極秘指令「マグナカルタの全貌を公開せよ!」
英文読解 one パラ道場:極秘指令「マグナカルタの全貌を公開せよ!」 [再掲]英文読解 one パラ道場:AKB48 渡辺麻友の最後の総選挙2017スピーチ
[再掲]英文読解 one パラ道場:AKB48 渡辺麻友の最後の総選挙2017スピーチ 資料:英文読解 one パラ道場:英語教材として読む安倍談話(英文全文)
資料:英文読解 one パラ道場:英語教材として読む安倍談話(英文全文) 資料:英文読解 one パラ道場:英語教材として読む安倍談話(英文全文)
資料:英文読解 one パラ道場:英語教材として読む安倍談話(英文全文) 【再掲】英文読解 one パラ道場:AKB48 渡辺麻友の最後の総選挙2017スピーチ
【再掲】英文読解 one パラ道場:AKB48 渡辺麻友の最後の総選挙2017スピーチ one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(4)
one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(4) one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(3)
one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(3) one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(2)
one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(2) one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(1)
one パラ道場-あしながおじさん"Blue Wednesday" de 英文読解(1)















