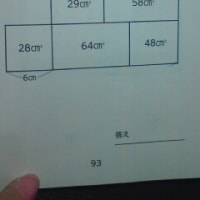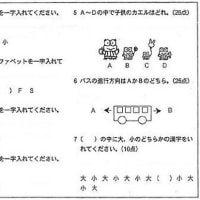| 日の名残り (ハヤカワepi文庫) |
| カズオ・イシグロ | |
| 早川書房 |
ここのところ、職場の試験が続いていて、本はほとんど読めませんでした。まだしばらくこの状態が続きそうで気が重いです。

そんな中で、読んだのがこの本です。
前にこの方の夜想曲集という本について記載した際に、次はこの本を読みたいと書いたのですが、やっと実現したわけです。
前の本は私の分際ではあまり理解できませんでしたが、この本はなかなか味わい深かったと思います。
最初のうちはいささかまどろっこしいのですが、読み進むと考えさせられます。もしかしたら翻訳がうまいのかもしれませんが。
話は、初老にさしかかった大きなお屋敷の執事さんの話です。
お屋敷がイギリスの貴族からアメリカの実業家の所有に移り、居抜きでそのままアメリカ人の執事をすることになった主人公が、お屋敷の人手が足りないために以前女中頭を勤めていた女性にお屋敷で働いてくれないか打診に行く旅に出ます。
女中頭の女性は、結婚してお屋敷をやめたのですが、その後の様子であまり家庭がうまくいっていない感覚を受けたため、主人公はお屋敷に戻ってくれるかも、と思うのです。
結局、女中頭の女性はお屋敷に戻ることはないのですが、旅を通じて、イギリスの執事のあり方や、主人公と女中頭の女性がかつてお屋敷で一緒に働いている間に妙な緊張関係にあったことなどが回想されていきます。
本を読んで改めて思うのは、イギリスの厳然たる階級社会です。
執事は一生執事で、もしかしたら代々執事だったりして、使う側の人間になることはない。それに誰も疑問も抱かず、むしろ誇りを持っていたりするのですが、たぶん下克上の国アメリカや、階級差を異常にいやがる日本からすると、あまり接することのない考え方なんじゃないかと思います。
主人と召使いと思うからなんとなく良い感じがしないのかもしれず、もしかしたら人に仕えるということは、世襲制の芸術家のような職業なのかもしれません。
あと、アメリカ人の主人のいささか下司なジョークに主人公が当惑する場面も少し出てくるのですが、アメリカとイギリスの気質の違いが現れていて面白いです。ある意味、アメリカ風というのは良く言えば率直、悪く言うと「身も蓋もない」ところがありますが、イギリス風は良く言えば婉曲、悪く言えばまどろっこしい感じかな、などと思います。
まずい比喩で恐縮ですが、バックヤードを隠して、お客様にはきれいなところだけをお見せしたいというイギリス風の心意気も立派ですし、所詮中はぐちゃぐちゃなんでしょう?恰好つけるなよ、というアメリカ風のあけすけさも私は好きです。
たぶん、相手と自分との距離、相手の性格や様子、状況などで対応を変えることが、大事なことなのでしょうね。