私は,20代前半に胃潰瘍をして以来,40代前半までそれほど太っていませんでした。
30代の頃はむしろやせすぎていたと思います。
ところがここ5年ほどで,年齢的にもやむを得ないとはいえ,だいぶ太くなってしまいました。
ゴルフのトレーニングや筋トレをしているので,「良い体格」です。
もう年だし多少太くてもかまわないのですが,太くなってイヤだなと思うことは,細かった頃と比べて暑く感じること。特に夏の厳しさは堪えます。
太る原因は何かと考えると,ご飯自体はそれほど食べませんので,私の場合やはり間食だと思います。
基礎代謝は年齢の割に高くて1350ほどあります。
なので,摂取カロリーを1500くらいにすれば,運動しているのでやせるだろうと考えたのですが,なかなかやせません。摂取カロリーを1500に,というのは,とても大変。
外食はNGになりますよね。ファミレスなんかでお昼ご飯食べると1食で1000くらいいっちゃうメニューばかりですし……
そんなこんなでこの本を手に取りました。
この本の著者はお医者さんで,103キロから20キロほどやせて,リバウンドもないということです。
内容は単純で,やせたければ摂取カロリーを減らさなければならないというもの。
そのために邪魔な常識を挙げているのですが,なかなか説得的です。
例として,酒だけ飲むと良くないという常識。
酒とつまみを食べれば,ご飯を2杯食べるようなものだからオーバーカロリーになると言うことは,ああやっぱりねえ,と思います。
あと,1日に30品目食べなさいという常識。
こんなに食べたらオーバーカロリーになるということです。
あと,摂取カロリーを減らすには,1日単位ではなくて1週間単位で考えると,楽に減らせるというような記載もあります。外食はNGといっても,付き合いもあるし,1食1000カロリー食べなきゃなんない宴会もあるでしょうから,これは助かります。前々からとか,翌日節制すれば帳尻が合うというわけですし。
面白かったのは,人の目を気にすると,太るという例として,ケーキ屋さんでケーキを1つ買えるか,という話がありました。ある糖尿病の人の話。
この人,ケーキ屋さんに悪いような気がして,1つ下さいと言えなくて3つ買ってしまい,ダイエットに協力してくれる家族にケーキを食べることを知られたくなくて,内緒で全て食べてしまうということです。これでは駄目ですよね。
身につまされます。この本を読んで,私も少し筋力を落とさないように,以下のように頑張ってみています。
自分のためにお菓子売り場には行かず,ケーキは買わない。
替わりにコンビニで0カロリーゼリー(けっこうおいしい)を買っておく。
甘いものが欲しくなったら,甘い飲み物を飲む。
食べたくないときは無理に食べない。
料理は余分に作らない。足りないくらいで丁度良い。
更年期が収まればやせてくるとは思いますが,とにかく汗かくのも暑いのもイヤなんですよねえ。
やせたい方はご参考に読まれてみては。
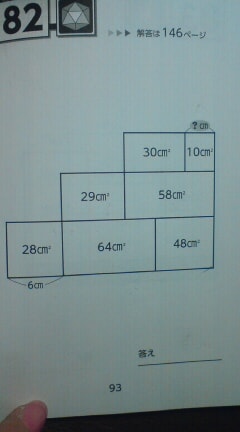

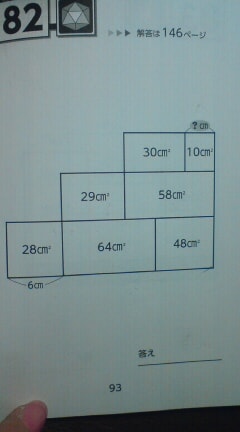


















 」と拍手をしたのですが、日本のエアラインだったら、もっと優しく言うでしょうね。そして客はいつまでもわがままを言う。内弁慶の日本人気質かも知れませんが。
」と拍手をしたのですが、日本のエアラインだったら、もっと優しく言うでしょうね。そして客はいつまでもわがままを言う。内弁慶の日本人気質かも知れませんが。






