
1 はじめに
デビッド・コーエン氏と戸谷由麻氏による共著『東京裁判「神話」の解体 ─パル、レーリンク、ウェブ三判事の相克』に対する読書感想文を書いてみる。
東京裁判に関しては、秦郁彦氏の『南京事件─「虐殺」の構造』(1986年)への反論を書こうと思いつつも、【法律】【国際法】への知識が皆無で、なかなか踏み出せないままであった。
そこで、ぼちぼちと東京裁判での【南京事件】に関する文献を理解する上で、国際法と東京裁判への理解が必要と痛感した。もちろん、冨士信夫氏の『私の見た東京裁判〈上〉』や『「南京大虐殺」はこうして作られた―東京裁判の欺瞞』を読んではいたが、国際法から見た視点が不足している感じがしていた為、南京事件を【事実】として認識している【法曹会】や【国際社会の法曹会】の主張も見る必要があると考えている。
この書籍を読了後、戸谷由麻氏の『東京裁判─第二次大戦後の法と正義の追及』(2008年)も、ついでに読み参考にしている。国際法の書籍類や論文を読み込みながら知識を少しずつ増やしていった結果随分掛かってしまった。
この書籍は、『東京裁判「神話」の解体』の主題は、南京事件ではなく、如何に東京裁判が後の国際刑事裁判所に貢献があったかと、ウェブ判決草稿を用いると【日本軍はヤッパリ戦争犯罪国だ。その指導者は戦争犯罪人だ。】という結果を導けるという主張である。
この書籍の目的としては、1998年に出された国際法学者の佐藤和男氏が監修し、インテリジェンス専門家の江崎道朗氏が著述した終戦五〇周年国民委員会編の『世界がさばく東京裁判』への反論書籍であると考えている。理由はレーリンク判事のA・カッセーゼ氏(国際法学者/国際刑事裁判所判事)が共著した『レーリンク判事の東京裁判─歴史的証言と展望』を用いた東京裁判への批判に対して反論をし、もう一度東京裁判を【肯定】し直し日本人に【加害意識】と【天皇陛下は戦争犯罪人】という意識・認識を醸成することが目的であると考えている。
そして、東京裁判は【勝者の裁き】ではないという主張を【法理学的】に裏づけようとしたコーエン、戸谷両氏によるケンブリッジ大学で出版した【内容】が正当性があると読者に思ってもらいたい意図が見える。さて、どうだろうか。その様に著者達の意図通りの感想になるだろうか。
今回の文章では、当方は別に法学者でも司法関係者ではないので、難しい法律に関して反論などは大先生方達に向かっては到底出来ないので、飽く迄感想を述べていきたいと思う。
2 日本がポツダム宣言受諾
書籍の内容を読み進める順を追って感想を述べていきたいと思う。
この書籍は、『The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence』というお二人の共著の書き下ろし(簡易版)日本語版と言う事、素人にはこの程度で十分理解出来るだろうという有難い内容である。
ポツダム宣言を受諾したことで【裁判憲章そのものを受け入れた】という解釈が通念として現代でも主流となっている。東京裁判(極東国際軍事裁判)は、第二次世界大戦に敗戦間近の日本がポツダム宣言を受け入れたのは、欧米が【現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対して用いられた力に比べ、はかりしれないほど強大なものである。われらの軍事力を最大限使用すれば日本国の軍隊は完全に壊滅し、またそれは日本国土の完全なる破壊を意味する。よって、右の条件をのむ以外の日本国の選択は、完全なる壊滅しかない。(一部を要約)/色摩力夫(元外交官・評論家『日本の死活問題』より P.27)】という【原爆2発】による一般人を含める【陸戦法規違反】の攻撃を用いて【恫喝】と【脅迫】されたことにより日本には受け入れる以外に選択肢が無かったことは考慮に入れるべきでは無いかと少なくとも日本人であるわが身としてはそう思う。
牛村圭氏が篠原敏雄先生追悼講演会「東條英機の東京裁判」と題した講演の中で《この憲章を詳しくみると、第5条「人並ニ犯罪ニ関スル管轄」という項があり、そこには「本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス」という文言があります。以上を考え合わせると、「ポツダム宣言」第10項からは特に捕虜の虐待を主眼に置いた戦争犯罪、そして「極東国際軍事裁判所憲章」からは、「平和に対する罪」を掲げた上での戦争犯罪、これらの審理をおこなう軍事裁判になろうということが、ここではっきりしたことが分かります。》(牛村圭氏が篠原敏雄先生追悼講演会「東條英機の東京裁判」講演レジュメ)
と述べている。
ポツダム宣言の第10項《我々の意志は日本人を民族として奴隷化し、また日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。》(同講演レジュメ)の【日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。】により、裁判が受諾され【刑罰】が与えられる法的根拠となったというのが、東京大学を初めとして、政府の外務省の一般的な受け取り方のようである。
【裁判憲章そのものを受け入れた】という考えが日本の法学者や法曹会、政治家、官僚達に通念とされるようになったのは、東京大学法学部助教授の政治学者の丸山眞男が、戒能通孝東京都立大学教授(後述)から速記録を丸山氏が借りて書いた論考にかかれている「日本ファシズムの矮小性」と捉えた認識が受け入れられていたと考える。それが様々な教育やメディアによる拡散で広がったと考えている。
しかしその丸山眞男の考えは【軍への私怨】から来るものでは無いかと考えられる。
牛村圭氏によると《丸山眞男が記そうとした鮮明な差異ではなく、多くの共通点があった、にもかかわらず丸山は自己の主張に好都合な史料のみを提示し、速記録の引用にさいして操作さえもおこなって、日本人被告を貶めるような議論を展開しようとした》(同講演レジュメ)というふうに丸山は私怨から来る恨み節を考えに載せたと言う事になる。。
本来ならば、主権国家が他の主権国家を裁判で裁くなど当時も現在もあり得ないのだが、当時国際社会でその様な合意が確立しているわけでもない。2021年に国際刑事裁判所(ICC)がイスラエルをパレスチナ国家への戦争犯罪で、挙証し捜査・逮捕する決定をした。主権国家のイスラエルをどの国が捜査し、又関係者を逮捕するのか興味があるところである。実行は別として、このような事があり得るかというと、1998年に国際刑事裁判所の設置とローマ規定の国際社会によるコンセンサスと合意が整ったからでもある。ただし、イスラエルは同規定への加盟はしておらず【法的義務に拘束されていない】ので、ちょうど東京裁判と同じ構図となっている。
別のケースとして、ジェノサイド条約が1948年12月9日国連第三回総会決議260A(III)にて全会一致で採択され、1951年1月12日に発効された。これは日本は批准していないが、中華人民共和国は、中華民国が1949年7月20日に署名し、蒋介石が台湾に逃れたのが1949年であるからおそらく1983年4月18日に中華人民共和国も加盟若しくは批准しているのではないかと。アメリカも1948年12月11日署名し、1988年11月25日に批准している。
この条約は、ジェノサイドの罪を時間を遡って対象ケースを裁くための条約であるが、それを裁く裁判所は、その行為が行われた領域の国の権限ある裁判所又は国際刑事裁判所の管轄権を受諾している締約国については管轄権を有する国際刑事裁判所により裁判を受ける。(この条文は多数の国が留保しているため機能不全に陥っている。)
そして、この罪を背負った国の指導者及び直接間接的に関わった人々の【逮捕】する【権限】を持つ【警察機関】は全く存在していない。
この事は、東京裁判を理解する上では、重要ではないかなと思っている。
3 ウェブ裁判長判決書草稿への評価
この書籍によると、国際刑事裁判史上の基盤となる出来事だったという理解が国際法学者の間で一般化しているらしい。しかも近年国際社会で評価されるようになっているらしい。そしてここ20年ばかりで、国際社会の中でも国際刑事裁判所が1998年に設置されたことで、東京裁判の再評価が進んでいるらしいのだが、その評価書籍に田中利幸の文献も挙げている。Yuki Tanakaという偽名を使って、日本人の人肉食(生肉)やインドネシアのバンカでの日本軍部隊上陸直後での看護師(20名程度)の強姦殺人事件などという【虚偽の情報】を英語論文を使って拡散した人物である。
その評価自体お察しというのだけれど、発端は前述したカッセーゼ氏や佐藤和男氏の文献に対応したものだろうと推測できる。何とか東京裁判を従来通りの肯定したいという目的だろうと考えられるが、実際は、なんともならないので【国際刑事裁判所ローマ規定】へ繋がったということ【ぐらい】しか、評価のしようが無かったとも言える。
東京裁判が近年の国際社会で評価されるようになったか理由として、ジェノサイド罪、戦争犯罪、人道に対する罪、そのほか大規模な人権違反に対する免責をなくすための国際刑事裁判が世界的に重要な役割を果たすようになってきたからであろうと書いているのだが、これを読んだ人は裁判・検察・刑事・弁護士のTVドラマや小説を思い出すべきだろう。
そもそも【誰】が嫌疑を掛けるのか? そして犯罪者又は国家組織への【検挙(逮捕)】は【誰が】するのか?である。
前述して在るとおり、この【罪】の嫌疑を他国から掛けられた国の指導者及び直接間接的に関わった人々の【逮捕】する【権限】を持つ【警察機関】は全く存在していないが、現在でも状況は全く変わっていない。
現在も、国家主権を越えて捜査し、逮捕立件する警察機関組織は国際社会には存在しない。その証拠に2000年ぐらいから持ち上がっている中華人民共和国の中国共産党によるウィグルのジェノサイドの噂に関して、中国共産党の許可無しに新疆ウィグル地区での捜査などは一切できない。
現在でも想であるから、過去の1930年代も同じで、同時代の法律を解説した書籍で、盬谷恒太郎著『分析法理学』でも、国際社会は個々の主権国家の上に存在する権威組織は存在していない。そして現代も国際社会は依然としてアナーキー(無政府状態)である。
この書籍でもう一つの大きな主張である【個人責任論の原則】が、【【始めて】】適用されたのがニュルンベルク・東京裁判所であり、その事をことさら強調して【評価】とされている(P.14)。むしろこの部分しかないと言っても過言ではない。
もう一つは、ウェブ裁判長判決書草稿への評価である。この草稿の評価によって、多数派が為し得なかった【本当の判決】=【日本国犯罪成立と為政者犯罪成立】が行い得るものだとの主張である。
後の国際刑事裁判所の設置と実行においての【歴史的先例】としての評価をことさら強調するのはどうなのだろうか。
4 初期の東京裁判研究者
初期の研究者として、つぎの4名を挙げている。
①戦前から国際法の権威として名高い横田喜三郎(満洲事変以来の中国における日本政府の対外政策を批判し、戦後も法学者としての信用を保ち一九六六年には最高裁判長をつとめた。)、②戦後日本における刑法の分野を定義づけた刑法学者の団藤重光(1974〜83年に最高裁判所の判事をつとめた)、③民法学者として著名な戒能通孝、④英米法を専門とする高柳賢三は、東京裁判における被告人のリーダー格弁護人だった人物(P.16)
①については、補足が必要でWikiをみると、《かつてはマルクス主義の読書会(ベルリン社会科学研究会)に参加するなど親社会主義的な法学者として知られ、軍部に睨まれたこともあった。1931年(昭和6年)の満州事変に際し、自衛権範囲の逸脱だと軍部を批判した[1]。1930年から1931年にかけて、『国家学会雑誌』上でケルゼンの純粋法学をめぐり、擁護する立場から美濃部達吉と論争を行う。極東国際軍事裁判(東京裁判)の法的な不備を認めながらも、裁判自体については肯定的評価を与え、「国際法の革命」と論文で述べた。なお、東京裁判では裁判の翻訳責任者を務めた。その後、東京大学法学部長、日本学士院会員などの地位にあって日本の国際法学会をリードした。》ということで、戦後日本の法学及び法理解の方向性を決定的にした人物でもある。何故なら東京大学の法学部関係は彼の意図が中心かつその後エリート達が日本国の中枢を担う各省庁、各地の大学教官に入っていくことになるからである。
この4名には、【それは、東京裁判が国際法の歴史的発展に積極的な貢献をし、とくに国際犯罪に対する個人責任の原則を認めて適用した、という共通理解である。】としているが、④の高柳健三氏は【個人責任の原則】を認めて居無いので、誤った記述である。
そもそも【個人責任の原則】とは、主権国家の元での【刑法】による【刑事罰】にたいする【原則】と考えるが、法律には様々な【原則】があるので、それらは無視しても良いのかと言う事になる。
東京裁判でほぼ無視された【原則】を挙げると、司法権力の分割の原則、罪刑法定主義(法の不遡及)の原則、推定無罪の原則、主権国家による裁量権の原則(属地主義の原則)、主権平等の原則、基本的人権の原則(被告人の人権の保護)、冤罪防止の原則、誣告防止の原則などがあるが、どれも無視した上で【個人責任の原則】のみを前面に出すのはどうかと考える。基本的に戦後の司法の大きな概念での変更はないはずである。
さらに言えば、制度(システム)が、現在の国際刑事裁判所のようなシステムすらない。【法手続き】も英米法と大陸法では違いがあり、事前にロンドン会議(四ヶ国会議:1945年6月26日から8月8日)で政治的に摺り合わせをしている。
初期の研究家のうち、法曹家たちは軍部に睨まれ、かつ戦時中自由な活動や教え子を戦地に赴かせるような馬鹿な行為をした軍部に対し恨みを持つ人物も居ただろうし、根本思想としてソ連を理想郷としている共産主義を抱えている人物だったかも知れない。
団藤重光氏は裁判判決は冤罪の可能性が絶対ではなく、死刑反対論者に転向した人物が、東京裁判という【冤罪製造場】を肯定したとは考えにくい。もし、肯定した立場ならばダブルスタンダードだろう。
戒能通孝氏は、戦犯被告となった鈴木貞一氏の弁護に当たっている。この人物は満洲事変以来の日本軍の行為を【侵略】と認識していて、かつ『極東裁判』(1953年)の中で、《あらゆる革命には新たに形成された権力を旧支配階級の反革命策動から守るために、革命裁判の実施が必至となる、そうした革命裁判は、従って常に事後法による裁判とならざるを得ない、このように考えると、第二次世界大戦は世界の民主主義勢力のファシズム諸国に対する民主主義革命戦争なのであり、その革命戦争の一部として、東京裁判は事後法による裁判として実施されたのだ、という理解を示している。ここには、戦争責任追及に関する「政治」の優越に対する確信が見られる。(赤澤史朗 論文『戦後日本の戦争責任論の動向』)より》や昭和27年4月25日に行われた日本法社会学会第八回総会の討論会で次のように述べている。《破壊活動防止法が国会を通過すれば、その次の段階にはおそらく再軍備反対あるいはまた徴兵法反対というようなものがほとんど不可能にされて行くであろうということを、ある程度本能的に感ずることは私も同感でございます。私自身も破壊活動防止法は、決して共産党取締法ではない、将来の再軍備反対運動取締法であり、かつまた徴兵法反対運動取締法であるという立場におきまして、あれには心から反対を表明したいと思つておるわけであります。》すこしメモ程度を書くと翌年昭和28年韓国が竹島で漁を行っていた日本漁船を拿捕している。
①の横田喜三郎同様に、この戒能通孝氏もかなり左翼(共産主義・社会主義)傾向の強い方ではないかと思えてくる。余談だが、朝鮮半島人の【金嬉老事件】の弁護人でもある。
私怨に燃える丸山氏に東京裁判の速記録を見せたり、【革命】という言葉を多用し、【共産主義的民主主義】を推進しようとしているように思えてくる。
司法権力の分割の原則について、ウェブ裁判章も問題視していて、東京裁判の記者団に次のように述べている。
《本裁判所には、英米の概念に基づいて、純粋な共同謀議を犯罪とする権限はなく、また各国の国内法において共同謀議とされている犯罪の共通の特徴と認めるものに基づいて、そうする権限もない。多くの国の国内法が、国家の安全に影響を与える純粋な共同謀議を犯罪として取り扱っているかも知れない。しかし国際秩序の安全のために、純粋な共同謀議という犯罪があると本裁判所が宣言することは、裁判官による立法をおこなうことに等しいであろう(朝日新聞東京裁判記者団『東京裁判 下』P.308)。》(終戦五〇周年国民委員会編『世界がさばく東京裁判』P.184 15行目)
5 戒能通孝氏が東京裁判の終了した後の1948年に『歴史評論』発表した論文
さらに、戸谷由麻氏の著作戸谷由麻『東京裁判─第二次大戦後の法と正義の追及』のP304に戒能通孝氏が東京裁判の終了した後の1948年に『歴史評論』発表した論文で、【罪刑法定主義】を東京裁判で無視したことについて、次のような記述をしている。
《革命裁判は常に事後法裁判であり、罪刑法定主義を形式上常に否認する。なぜならば革命者は革命が成就する以前には、常に犯罪人として追及され、その的たる支配階級に追いまくられていたのであるが、革命の達成後初めて合法性を獲得し、自ら制定した法により旧敵の反抗を鎮圧するのは当然だからである。革命者に向かって罪刑法定主義の厳守を求めるのは、まさに論理的矛盾である。彼らは革命の成功以前には、その国の憎むべき犯罪人だった。しかし革命が成功することによって犯罪人が合法的政府の主体となり、彼らを追いかけていたものを、逆に追いかける立場に立つのである。秩序を愛する人の眼からみた場合、革命に基づくこれらの政治的価値転換は、呪うべき混乱とも映るであろう。だが実際の問題は、革命家に革命弾圧処罰権がなかったら、革命は起こり得ないのであって、このことは「革命」の性格上、自動的に由来することである。革命はこの意味に於いて法を知らない(46)。》というまったく香ばしい文章を書いて居られる。何を言っているのか正直誰か教えて欲しい文面である。
第二次世界大戦は、【革命】であり、【革命】はつねに【法を知らない】ので、【罪刑法定主義】を否定しても問題はないという【理屈】なのだろうか?
近年ヴェノナ文書などで、第二次世界大戦が【共産革命】のための【戦争】だったとという推論が事実とされだしていることは確かである。
それにしても、法律家である。この方は革命家だったのだろうか。アメリカの制度が国際社会から犯罪人とされたこともないが.... 日本で革命が起こったわけでもないし、単に戦争に負けただけである。【革命戦争】という行為とは全く違うし、東京裁判は当時日本が複数の他国と結んでいた【条約】が元になっている。何を言って居るのだろうか?
【民主主義革命戦争】などと【革命】を使うのは、共産主義者が民主主義をよく使うので、根本思想的には共産主義者だったかも知れない。
この4者から判断できる感想としては、当時、国際法において【個人責任の原則】が【確立】されていなかったという証左ではないだろうか。
そしてその事は、すなわち【確立されていない原則】で【日本軍人個人を裁いた】という事を言明されてないまでもそういう事実を示していると思える。
そこには、【基本的人権】もあったもんじゃない。
6 パル判事に対する不要な中傷
パル判事が、判決文を公開して以来、日本人としては日本軍の弁護を務めた弁護士達の言及などから、【違和感】を感じていたことは確かであるし、【個人責任の原則】という【主権国家】の元での【刑法】の【原則】が当てはめられたことに強く疑念を抱いたことは当然なのだが、この著作者は、《同判事(パル判事のこと)は、一九五〇年代から一九六〇年代にかけて戦犯受刑者の同志から招待を受け、三度にわたり訪日した。》と書いて、まるで【判決】に手心を加えるために日本の戦犯被告の関係者から接待を受けているかのように記述している。まるで、パル判事に対する嫉妬と憎悪を感じる中傷文面である。
この事は、全く法理学とは関係の無いことなのでパル判事の印象を悪くさせたいという印象操作だと思われる。
【違和感】でいうと、著作者の一人である戸谷由麻氏の著作にもあるのだが、真珠湾攻撃に関して、1907年のハーグ第3条からは攻撃の法的性格を決定するには実用的でない文書だとしてアメリカの主張を退けている。少し引用すると《判決書によると「この条約は敵対行為を開始する前に、明瞭な事前の通告を与える義務を負わせていることは疑いもないが、この通告を与えてから、敵対行為を開始するまでの間に、どれだけの時間の余裕を置かなければならないかを明確にしていない」のであり、そのためこの条約は、「狭く解釈することが可能であり、節操のない者に対して、他方でかれらの攻撃が奇襲として行われることを確実にしながら、右のおうに狭く解釈された義務には従うように工夫する気をおこさせるものである」ということだ。つまりハーグ条約そのものに不備があるため、この文書に拘泥する意味が見いだせないというのだった。(『東京裁判』 P.143)》
しかし、ハーグ条約の不備理由に真珠湾攻撃の違法性を不問した割りには、【不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)】の【侵略】の定義についての不備を勘案しなかった判事たちの判断は、首尾一貫していない感じがする。
外にも共同謀議の論理にしても確立された論理を東京裁判で当てはめたようで、国士舘大学の奥原敏雄氏の論文による共同謀議はそもそも【権利の乱用と防止と救済】【虚偽の告訴する結合(協議・関係)】だというし、【共同謀議】が【顔をつきあわせて】とは関係なく、決められた行動を達成するために行動した場合にも【一方はある行為を実行し、他方は同じ行為の他の部分を実行】すれば【共同謀議】に該当するということは、南京暴虐事件で松石根大将は共同謀議罪の平和に対する罪(訴因:1、27)に該当するはずだが、適用された訴因は【共同謀議罪】ではなく、通常の戦争犯罪にたいする不作為の訴因55だけである。
そもそも【不戦条約】を【不履行】の場合、国家を動かす君主及び為政者個人にその【責任】を負わせて、【誰かが処罰する】という規定が確立されていたのかどうか。
藤田久一氏の『戦争犯罪とは何か』に、第一次世界大戦(1914〜1918)の敗戦国家であるドイツ帝国の国王ヴィルヘルム2世(Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen)とドイツ軍兵士による1906年のジュネーブ条約(傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約)、1907年のハーグ陸戦条約への違反者を【戦争犯罪者】として【処罰】しようとしたが、オランダやアメリカ(第28代大統領、ウッドロウ・ウィルソン大統領)の反対で、処罰は行わなかった。理由は【事後法(罪刑法定主義)】という理由からである。
オランダは当時中立国で、ヴィルヘルム2世の亡命先であったが、戦勝国側が引き渡しを求めた際には、【戦争犯罪人】として裁く事は【罪刑法定主義】に触れるため、今後国際社会で【検討】し、【確立】した場合であったならば、【引き渡す】として要求を拒んでいる。
では、その後戦勝国側は不当として、オランダに宣戦布告しの上、ヴィルヘルム2世を奪還したこともなく、うやむやにしている。
清水正義著『第一次世界大戦後の前ドイツ皇帝訴追間題』」『白鴎法学』第十九号によると、《例えば、オーストラリア首相ヒューズは「彼[前皇帝]には世界を戦争に突っ込ませる完全な権利があるのです。今、我々は勝利をした。だから彼を殺す完全な権利がありますが、それは彼が世界を戦争に突っ込ませたからではなくて我々が勝ったからです。法律違反で彼を訴追するなんて、首相、それはできませんよ」と率直に語り、ロイド・ジョージ(イギリス首相)を牽制すると、軍需相チャーチルも呼応して、「前皇帝を絞首刑にするという道を意気揚々と開始するのは易しいし、大衆の一般的関心をその中に取り入れることもできる。けれど、時が過ぎてやがて大変な袋小路に陥ってしまうことになるでしょう。世界中の法律家たちがこの起訴状はとても支えきれるものではないことに気がつき始めるでしょう」と非常に消極的な姿勢に終始した。》
その後、1928年にパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)などが締結されて、その中で条約を違反または不履行の場合に置いて、【主権国家】における【君主】または【政府高官】に対する【罰則】を明記している内容は存在しない。
国際法上での【国家責任法】が議論及び認識されていくのは寧ろ戦後の話になる。【罪刑法定主義】を無視して【事後法】を認めたのは1951年のジェノサイド条約であり、【国家】と【国家】の間での【公法】としての【刑法】が国際社会でコンセンサスを得ていくのも、東京裁判の50年後のローマ規定からである。言うまでもないが、その間に起こった世界各地での戦闘行為については全く無視である。
忘れてはならないのは、インドネシアでの植民地政策を継続したがったオランダ政府に対する現地住民による独立運動とそれを鎮圧するためにオランダが起こした戦闘がある(事実かどうか判らないが、60万人もの尊い命が失われたと言われている)。これに関するオランダ政府への【戦闘行為】に対する【パリ不戦条約】や【ハーグ陸戦条約】に関するお咎めがない。また、著者達も全く【無かった】事のようになっている。
そのほかにも、中国大陸内での蒋介石の中華民国と毛沢東等の中国共産党が【戦闘】を行った事実や、北朝鮮人民共和国が大韓民国を突如襲撃した(つまり侵略した)ことに始まる朝鮮戦争とアメリカの介入と中国共産党が参戦したことなど一切触れもしていない。










![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)
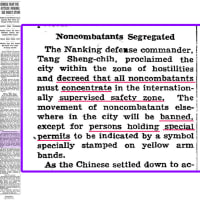

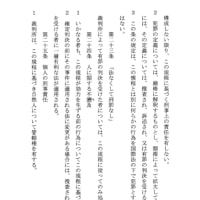


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます