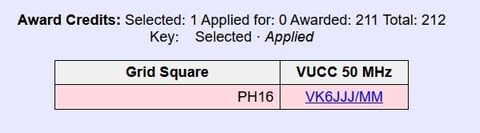TS-600はトリオ社(現KENWOOD社)のヒット商品だった。50MHz帯はAMモードがまだまだ人気の時代において、満を持して世に出した10Wのオールモード機です。
メーカー修理もできない古い機種なので、いくつもの不具合が出たが自分で修理して使っている。今までの修理記事は、旧ブログで紹介しています。TS-600は新スプリアス基準を満たすので、保証認定をとって免許状にも掲載されています。精密なVFO実装(今では当たり前)で、さらにオプションで5チャンネルの水晶振動子を入れられるようになっています。
この機器は知り合いから買ったものですが、その局は若くて亡くなったので形見でもあります。(残念ながら病死でした)水晶は、CH1に51.0MHzが実装されています。(1MHz毎のバンド毎に使えるので、正確に言うと5X.00MHzの水晶です)
52MHz以上のバンドを使おうと思ったら、オプションのバンド用水晶も必要です。52MHz台の水晶は実装してますが、53MHz台は未実装です。なぜ52MHzが必要かというと、当時のVK(オーストラリア局は)の免許は52MHz以上だったためです。52MHz以上で運用するVK局を呼ぶためには、オプションの水晶が必要でした。
オーストラリアは、50MHz帯のすぐ近く(下の周波数)にTVQ-0というTV局がいたので、TVI防止のために世界標準の50.0MHz~52.0MHzはアマチュア局には免許になりませんでした。そのため、VKが開けると50.0MHz帯でビーっという、TVのアナログ映像信号の音が聞こえました。(VKが開いたぞとの目安にもなった)TVQ-0の周波数変更に伴い、VK局も50.0MHzから運用が許されました。
53MHz以上は、一部のローカルQSO専用で使っている場合を除き、通常では使われていません。(これは今でも同じ)
今ではメインで使うことはないのですが、夏場のEスポワッチ用に使っています。地方ではEスポが出ないと誰も出ていません。春になり、Eスポが出始めました。固定チャンネル1には水晶(51.0MHz)が入っているので、1CHでワッチをしていますがなんとなく周波数がずれている感じがします。
「みんな微妙に周波数ずれてるやん、しっかりしてな」と思ったのだが、良く考えたらずれているのは自分だった。(そりゃそうだろう古い機器だし)
それじゃということで、水晶の周波数調整を行うことにします。作業自体はいたって簡単ですが、調整用のマイナスドライバーが必要です。普通の金属製接密ドライバーを使うと、発振周波数が引っ張られるのでうまくいきません。

上部のカバーを引っ張り上げます。カバーは2個のナイラッチで留まっているだけなので、手で引っ張ると簡単に開けることができます。メンテナンス性は良く設計されています。

黒いつまみは、マイクゲイン用の調整用です。その右に水晶振動子が1つあります。TS-600は、1つの水晶で送受信が共用になっています。(当時の機器では、送信用・受信用に2つの水晶が必要な場合が多かった)水晶の右にはトリマーがありますが、水晶1つ1つにトリマー1個対応しています。(黒いソケット)
チャンネル用水晶のさらに右には3個の水晶振動子がみえますが、これはバンド用の水晶です。(白いソケット)この機器は50.0MHzから52.99MHzまで使えるようになっています。
チャンネル1を調整するためには、黒いソケット右の下から5個目のトリマを調整します。

簡単な調整方法としてCALスイッチを入れると、各バンドの5X.00MHzの周波数でキャリアが確認できます。
TS-600側のトリマーをゆっくり回転させて、Sメーターが一番振れるところで止めます。幅があるので中間点を探ります。なんとS5⇒S9まで振れるようになったので、ずいぶんずれていたようです。
万一CALが発振しないようなら、他の50MHz帯トランシーバーを使って調整を行います。51.00MHzに周波数を合わせFMモードにします。アンテナは必ずダミーロードを接続し、最低出力で送信します。TS-600で受信ができなければ、少しずつ出力を上げていきます。受信できたら、トリマーでSメーターが最大に振れるように調整します。
TS-600用のチャンネル用水晶とバンド用水晶は、当時トリオ社から純正オプション部品として販売されていました。こういうオプションは、当該機器の販売が行われている間は簡単に手に入りますが、製造中止になって何年も経つと手に入らなくなります。
水晶振動子については、かつてはアマチュア向けに比較的お安い価格で1個から製作してくれる会社があったのですが、いまはほとんど無くなってしまいました。あったとしても特注品は高価で、おいそれとは手が出せなくなりました。TS-600用の水晶を頼んでみようかなと思ったのですが、費用対効果が見込めないのでやめました。