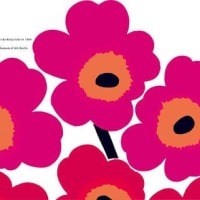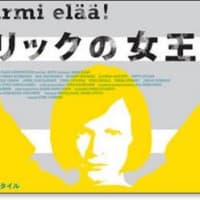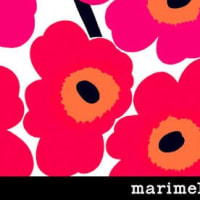漢字は、「まんが」だと言われることもある。
読み方が分からなくても、その構成を見れば、なんとなく雰囲気は分かる。
絵を見ながら文字も読みすすめて総合的にストーリーを把握するという意味で、
「まんが」的だというのだろう。
逆に、漢字や漢字の組み合わせで作られる言葉に溢れているからこそ、
日本では漫画が発展したのかもしれない。
さて、その漢字の読み方だが、学生時代までは、
「なんとなく」ニュアンスを汲み取って、理解したつもりでいられた。
それほど生活上は困らない(いや、困っていたかもしれないが)。
本を読んでいても、わざわざ「読み方」を調べることなく読み飛ばすこと20年。
その後、アナウンサーとなった私は、
たくさんの「思い込み」「勘違い」に気付くこととなった。いやあ、お恥ずかしい。
そんな新人時代から付けている、通称「ダメダメノート」
(漢字や地名の読み方、アクセント、言葉の意味などを書きとめたノート)は、
10年間でかなりの冊数となる。
(もちろん、今日も書き加えらる。「流出した」「13兆8896億円」・・・など
言いにくい言葉がいっぱい・・・)
前置きは長くなったが、今日のニュースの原稿で出てきた言葉『説諭』。
この言葉を見て、ふと懐かしくなった。
むかしむかし、重い漢和大字典で調べた記憶があるからだ。
電子辞書は便利だが、紙もので調べた記憶というのは、なかなか忘れられない。
この「説諭」という言葉、
裁判員裁判で初の死刑判決が出た横浜地裁で、裁判長が判決を言い渡した後、
被告に対して異例の「説諭」をした、という内容で登場した。
「せつゆ」と読んで、「悪い点を教え諭すこと、よく言い聞かせること」という意味で使われる。
ちなみに、「えつゆ」という読み方もあり、この読みだと「よろこび楽しむこと」となる。
読み方でほぼ反対のニュアンスだ。
(かつて、「説論」と勘違いしそうになったことがある。
「せつろん」は、「説明し論ずること」。)
テレビと違って、ラジオは音のみなので、使いなれていない言葉は
なるべく分かりやすい言い回しに変えることもあるのだが、
裁判関連のニュースではよく使われる表現なので、「説諭(せつゆ)」と読む。
あえて記者の方もこの言葉を選んだのだと思う。
そもそも、裁判官は、考慮を重ねた上に吟味された言葉で判決文までたどりつくのだろうが、
それだけは留まらない感情の発露、悩み考えた深さが出てくる部分が「説諭」なのだろう。
その重さと深さ、感情のヒダのようなものは、
「せつゆ」という言葉だからこそ、伝わる気ががする。
日常で使われている言葉や易しい表現も大切だが、
馴染みがなくとも、その言葉だからこそ持つ説得力があるのだろう。
読み方が分からなくても、その構成を見れば、なんとなく雰囲気は分かる。
絵を見ながら文字も読みすすめて総合的にストーリーを把握するという意味で、
「まんが」的だというのだろう。
逆に、漢字や漢字の組み合わせで作られる言葉に溢れているからこそ、
日本では漫画が発展したのかもしれない。
さて、その漢字の読み方だが、学生時代までは、
「なんとなく」ニュアンスを汲み取って、理解したつもりでいられた。
それほど生活上は困らない(いや、困っていたかもしれないが)。
本を読んでいても、わざわざ「読み方」を調べることなく読み飛ばすこと20年。
その後、アナウンサーとなった私は、
たくさんの「思い込み」「勘違い」に気付くこととなった。いやあ、お恥ずかしい。
そんな新人時代から付けている、通称「ダメダメノート」
(漢字や地名の読み方、アクセント、言葉の意味などを書きとめたノート)は、
10年間でかなりの冊数となる。
(もちろん、今日も書き加えらる。「流出した」「13兆8896億円」・・・など
言いにくい言葉がいっぱい・・・)
前置きは長くなったが、今日のニュースの原稿で出てきた言葉『説諭』。
この言葉を見て、ふと懐かしくなった。
むかしむかし、重い漢和大字典で調べた記憶があるからだ。
電子辞書は便利だが、紙もので調べた記憶というのは、なかなか忘れられない。
この「説諭」という言葉、
裁判員裁判で初の死刑判決が出た横浜地裁で、裁判長が判決を言い渡した後、
被告に対して異例の「説諭」をした、という内容で登場した。
「せつゆ」と読んで、「悪い点を教え諭すこと、よく言い聞かせること」という意味で使われる。
ちなみに、「えつゆ」という読み方もあり、この読みだと「よろこび楽しむこと」となる。
読み方でほぼ反対のニュアンスだ。
(かつて、「説論」と勘違いしそうになったことがある。
「せつろん」は、「説明し論ずること」。)
テレビと違って、ラジオは音のみなので、使いなれていない言葉は
なるべく分かりやすい言い回しに変えることもあるのだが、
裁判関連のニュースではよく使われる表現なので、「説諭(せつゆ)」と読む。
あえて記者の方もこの言葉を選んだのだと思う。
そもそも、裁判官は、考慮を重ねた上に吟味された言葉で判決文までたどりつくのだろうが、
それだけは留まらない感情の発露、悩み考えた深さが出てくる部分が「説諭」なのだろう。
その重さと深さ、感情のヒダのようなものは、
「せつゆ」という言葉だからこそ、伝わる気ががする。
日常で使われている言葉や易しい表現も大切だが、
馴染みがなくとも、その言葉だからこそ持つ説得力があるのだろう。