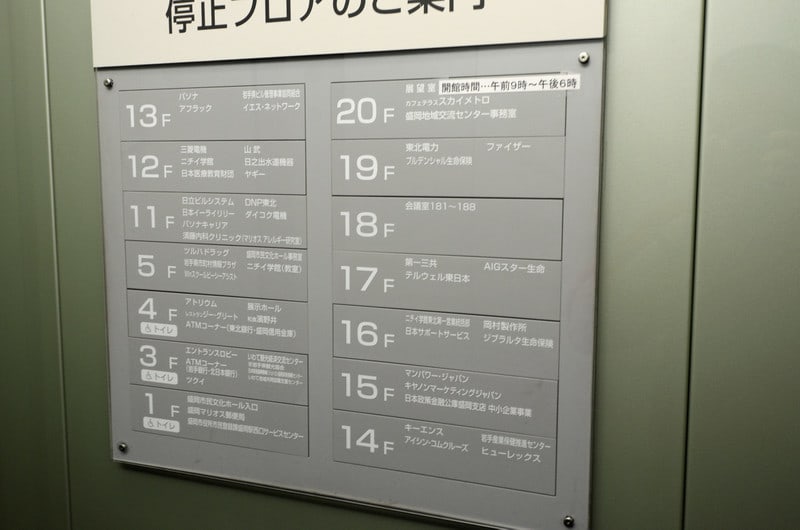NHKFMの番組を聞きながら書いています。生演奏でスタニラフ・ブーニンの演奏を聴いてしまいました。ショパンコンクールでも、将来が圧倒的に豊かだと言われていましたが、巨匠への道を進んでいるようです。
ただ今現在の苦しみを表現しているような気がします。
さて観光案内です。今回は充実しています。

上田から北山、バイパスを通って愛宕山への最短距離で向かいます。その手前で出会ったせんにんつるの花です。

三ツ割に向かうトンネルです。なんと言う事も無い案件なのですが計画からえらく時間がかかって、作り始めた所、なぜかの落盤事故。紆余曲折で出来上がりました。
このトンネルが出来た結果なのですが、盛岡の山に広がった郊外の利便性が変わりました。山の方がよくなったと思います。

バイパス沿いに、東禅寺があります。南部家の墓があるのですが質素な感じです。臨済宗です。

門前の立派な焼却炉が、いい感じです。これでも盛岡五山に数えられる別格寺院なのですが。
盛岡の寺院なのですが、よそ者にはそのランクが解りにくい所があります。

さてバイパスも秋です。この坂を越えると愛宕山に入ります。

バイパスから外れて愛宕山に向かいます。

いきなりな坂です。

凍結を考えての石畳です。にしても急な坂。

栗山大膳の墓。九州福岡黒田家家臣の墓がここにあるのは、黒田家騒動で栗山大膳が盛岡に流刑処分になったから。盛岡南部藩は、この栗山大膳をかなり厚遇したようです。
そのせいか、維新後に薩摩藩と妙に仲が良くなったり、西南の役以降九州人が岩手に来た事とは、無縁では無さそうです。

坂を上りきる前に、ナイスな家が。ベランダをガラスで囲い込むのは、盛岡では珍しいです。

愛宕山をには、盛岡で最高のホテルと言われている盛岡グランドホテルがあります。駐車場に人がいるというだけでも高級です。お殿様商売と批判された時もありますが、サービスはかなりいいと思います。

さて愛宕山展望台に向かう間には、北山地区の墓地が目に入ります。まあ墓地のど真ん中に高級ホテルがあるのですが、これはどういった事なのかと言えば、愛宕山が盛岡にとって重要な戦略拠点だからなのです。
ここを制せば、といった場所です。

墓所から少し外れると、果樹園です。ブルーベリーの紅葉がきれいです。

愛宕山の頂上に近づいてきました。きれいな雑木林ですがその人為に気がつけば、よりいっそう美しいと感じれるでしょう。実は壮大な庭です。手がかなり入ってます。

さて展望台に来ました。この展望台の礎石を探したのですが見つかりません。皇太子殿下のご成婚を記念して整備したという碑がありましたが、それ以前にこの展望台はあったと思うのですが記憶違いでしょうか。

盛岡には三カ所展望台があります。南にある展望台は私有地なので現在閉鎖されています。岩山展望台が最も有名なのですが、市内が少し遠く見えるのでイマイチです。ただレストランなどのインフラが整っているので人気スポットです。私のオススメはこの愛宕山の展望台なのですが、ちょっと木がおい茂ったようです。

ここで小学生が飛行機を飛ばそうと、必至に組み立てていました。チとアドバイスなどをしながらしばらく時間を過ごしました。

ホテルの坂を下ってゆきます。やっぱり急な坂です。

さて山岸に移ります。山岸は面白い街です。どこがどうと言われれば解らなくなるのですが、続きで。
ただ今現在の苦しみを表現しているような気がします。
さて観光案内です。今回は充実しています。

上田から北山、バイパスを通って愛宕山への最短距離で向かいます。その手前で出会ったせんにんつるの花です。

三ツ割に向かうトンネルです。なんと言う事も無い案件なのですが計画からえらく時間がかかって、作り始めた所、なぜかの落盤事故。紆余曲折で出来上がりました。
このトンネルが出来た結果なのですが、盛岡の山に広がった郊外の利便性が変わりました。山の方がよくなったと思います。

バイパス沿いに、東禅寺があります。南部家の墓があるのですが質素な感じです。臨済宗です。

門前の立派な焼却炉が、いい感じです。これでも盛岡五山に数えられる別格寺院なのですが。
盛岡の寺院なのですが、よそ者にはそのランクが解りにくい所があります。

さてバイパスも秋です。この坂を越えると愛宕山に入ります。

バイパスから外れて愛宕山に向かいます。

いきなりな坂です。

凍結を考えての石畳です。にしても急な坂。

栗山大膳の墓。九州福岡黒田家家臣の墓がここにあるのは、黒田家騒動で栗山大膳が盛岡に流刑処分になったから。盛岡南部藩は、この栗山大膳をかなり厚遇したようです。
そのせいか、維新後に薩摩藩と妙に仲が良くなったり、西南の役以降九州人が岩手に来た事とは、無縁では無さそうです。

坂を上りきる前に、ナイスな家が。ベランダをガラスで囲い込むのは、盛岡では珍しいです。

愛宕山をには、盛岡で最高のホテルと言われている盛岡グランドホテルがあります。駐車場に人がいるというだけでも高級です。お殿様商売と批判された時もありますが、サービスはかなりいいと思います。

さて愛宕山展望台に向かう間には、北山地区の墓地が目に入ります。まあ墓地のど真ん中に高級ホテルがあるのですが、これはどういった事なのかと言えば、愛宕山が盛岡にとって重要な戦略拠点だからなのです。
ここを制せば、といった場所です。

墓所から少し外れると、果樹園です。ブルーベリーの紅葉がきれいです。

愛宕山の頂上に近づいてきました。きれいな雑木林ですがその人為に気がつけば、よりいっそう美しいと感じれるでしょう。実は壮大な庭です。手がかなり入ってます。

さて展望台に来ました。この展望台の礎石を探したのですが見つかりません。皇太子殿下のご成婚を記念して整備したという碑がありましたが、それ以前にこの展望台はあったと思うのですが記憶違いでしょうか。

盛岡には三カ所展望台があります。南にある展望台は私有地なので現在閉鎖されています。岩山展望台が最も有名なのですが、市内が少し遠く見えるのでイマイチです。ただレストランなどのインフラが整っているので人気スポットです。私のオススメはこの愛宕山の展望台なのですが、ちょっと木がおい茂ったようです。

ここで小学生が飛行機を飛ばそうと、必至に組み立てていました。チとアドバイスなどをしながらしばらく時間を過ごしました。

ホテルの坂を下ってゆきます。やっぱり急な坂です。

さて山岸に移ります。山岸は面白い街です。どこがどうと言われれば解らなくなるのですが、続きで。