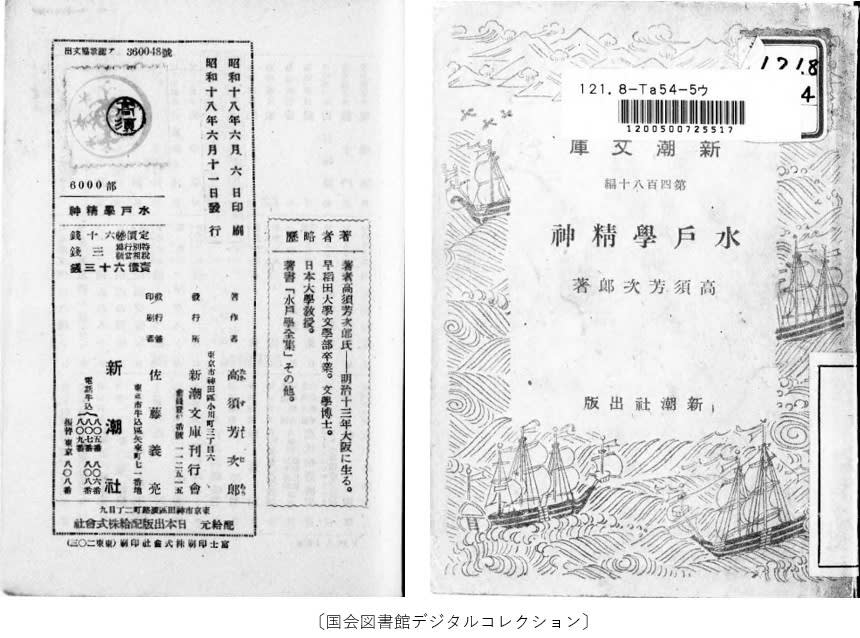
高須芳次郎著『水戸學精神』 
第六 藤田幽谷の人物と思想

(一) 天才と稱せられた幽谷
〔幽谷、東湖の父子は水戸の誇り〕
水戶政敎學の土臺をほぼ作った藤田幽谷は、大西郷を心服せしめた藤田東湖の父である。かく傑出した父、傑出した子を合せ見るといふことは、藤田家の誇りたるのみならず、また水戶の誇りである。
幽谷の生涯は、東湖ほど、花々しくはないが寧ろ質實である。その詩文も亦東湖ほど、大衆的なところがない。より多く學者的である。蓋し幽谷は、徹頭徹尾、學者であり、思想家であった。その學殖・識見は、東湖に優るとも、劣つてはをらぬ。或は、幽谷の方が一段、上にあると思はれる。
彼は、天才だったが、また努力の人でもあった。が、その實力に相應した地位を得ないで、晩年は、不遇だった。それは、彼が餘りに硬直で、一歩も自說を曲げようとしないからである。從つて、十分にその手腕を発揮しないで世を去り、東湖はどに、有名でない。けれども彼は學者として、水戸における第一人者だと云はねばならぬ實力の所有者だった。
〔よく幽谷を知りぬいた正志齋〕
在來、幽谷の俤を傳へたものとして有力なものが二つある。一つは、門下を代衣するところの會澤正志齋が書いたといふ『幽谷先生、次郎左衛門藤田君墓表』で、今一つは、東湖が執庫したといふ『先考次郎左衛門藤田君行状』である。
惟ふに、思想・學說の上からは、正志齋ほど、よく幽谷を知りぬいたものはない。それ故、正志齋が傳へた幽谷は、學者としての面目を最も鲜かに示してゐる。それから東湖が描いた父幽谷は、率直にそのブロフィルを再現して、よく眞骨頂を傳へてゐる。それは共に、簡略にちかいが、いづれも名文章たるを失はない。
〔幽谷の生い立ち、人柄〕
幽谷は説を一正、字を子定といひ、通稱は與介、後、次郎左衞門と改めた。その祖先は、小野篁から出たと傳えられてゐる。
最初、幽谷の祖先は、武蔵から常陸に移り、那珂郡飯田村に居住したが、後、水戸城下の下谷町に移り、父興左衛門は、商業を営んだ。幽谷は、幼少の時から、気象がし っかりして、聡明だったが、一向、學問を好まないで、群兒の大將株となり、日夜、遊戲にのみ耿った。
それを憂へた母根本氏は、病中、懇ろに訓戒を加へ、切に勉學を勸めたので、茲にはじめて、心眼を開き、爾來、全く讀書に沒頂した。それは、幽谷十歲の時である。
程なく、母が世を去ると幽谷は、在來の不孝を悔いて、その死を憾み、益々身を愼 むやうになつた。當時、幽谷は、青木侃齋に師事して、四書、五經を誦讀したが、それも數箇月經たぬうちに讀方を卒業し、十一歳の時には、大人らしい詩を作り、十三歲になると、立派な漢文を綴った。
この時、出來た一つが『長久保赤水七十壽序』で、内容といひ、文章といひ、到底、少年の手に成つたものとは思へない。玆に至って、彼は、神童と稱せられ、誰も彼も、 幽谷の前途に深く嘱望した。その結果、侃齋の勸めにより、當時、水戶の學界に最も重きを為してゐた立原翠軒の門に入ったのである。
東湖の傳ふるところによると、幽谷の父、與右衞門(安善)は、器量が大きく、賴母しいところがあった。それ故、彼の師、高倉某は、與右衞門をして、水戶藩士たらしめようと思ひ、一刀を授けて、この旨を傳へた。が、幽谷の父は、考へるところがあって、 禄仕することを好まず、商人として生活した。
然し乍ら、與右衛門は、決してその旧師の厚情を忘れなかったので、幽谷が長すると、水戸藩に仕へしめようと考へた。依ってこの事を少年時代の幽谷に說き、親戚のものも亦言葉を添へたが、幽谷は容易に聞き入れない。蓋しその抱負は、区々の一小吏たることを潔しとせぬからである。
が、民間の學者として立たうといふ考へは最初から幽谷の胸にあったらしい。當時、幽谷は父が度々、勧めてやまぬ儘に、表面、志を屈したやうにして、水戶に仕へるべきことを承知したが、これは、一時、父を失望させぬためであった。
父は一向、そんな事を知らず、ある日、二三の老吏を呼んで馳走し、幽谷を紹介して、周旋の勞を執らんことを依頼しようとした。が、幽谷はいつの間にか姿を晦まして何處を探してもをらぬ。そのため、父の計畫は、一旦、水泡に歸して了つたことがある。
(二) 文名一時に揚る
〔學業は著しく進み、
松平定信から文辭を徴せらるるの命に接した〕
當時、幽谷の學業は著しく進み、その才名は、水戸において、漸く知られて來たので、水戸學中興の名君といはれた文公(二四一一~二四六五)は、翠軒の言に聞いて、幽谷を抜擢し、彰考館生員に採用した。
時に幽谷は十六歳だった。その年(寛政元年)幽谷は、立原翠軒に伴はれて江戸に遊び、始めて柴野栗山(二三九六~二四六七)•太田錦城(二四二五~二四八五)・吉田篁墩(二三九~二四五八)らと交り、一段と才名を高めた。
滞在一ヶ月の後、水户に歸り、一層學問に身を入れた。
時に寛政三年の頃、當時、幕府の執政として有名だった白河樂翁(松平定信)(二四一八~二四八九)から、特に文辭を徴せらるるの命に接した。これは、十八歳の靑年としては、正に空前の榮誉だといはねばならぬ。
蓋しそれは幽谷の才器に望みをかけたからで、或は、樂翁公が、幽谷を幕臣として用ひようといふ內意があった為めとも解せらる。
それ故、この事を耳にした人々は、いづれも、幽谷のために、立身の好機が來たことを喜び、
「貴君の材能は非凡だ。區々、一藩に仕へて終るべきではない。
苟くも天下に忐があるなら、幕臣となるに越したことはなからう。
白河侯(樂翁)は新たに幕府の大老となり、人材を抜擢することに努めてをられる。
貴君の文章を求められたのも、つまり、その意味からであらう。
それは、千載一遇の秋ではないか」と云った。
が、幽谷は笑って何とも答へなかった。そこに彼の非凡性の閃きが見える。やがて彼は、『正名論』一篇を書いて、白河候に奉り、日本の國體を說き、君臣の大義を明かにすることにより、聊か侯の厚意に酬いたのである。 本來、白河侯は、幽谷の材能を愛して、これを幕臣たらしめようと思ったらしい。
が,幽谷の『正名論』のうちには、力強く、明快に天皇中心主能を高調して、ともすると、 幕府の覇政を是認しないらしい口吻があるので、躊躇した。唯幽谷の才器を賞揚するに留めたのである。
それにしても、この事は、幽谷の文名を一段高める原因となった。從って、文公も亦幽谷を愛して、度々召し出し、詩文を作らせた。彼の筆は、非常に早く、而もその出來栄えがよかつた。が、その志すところは、經國の大業にあって、詩文の末技ではなかつた。文公は、幽谷の考へを壯とし、恩遇、一脣の厚きを加へたのである。
(三) 幽谷時事を憂ふ
〔父の卒去、服喪と丹氏を娶り、新家庭に和樂〕
それから程なく、幽谷は、寛政三年(1791年)十一月下旬、その父の卒去に會った。彼は非常にこれを悲しみ、顏色もやつれるに至った。蓋し、幽谷は曩きに慈母を喪つて、風樹の嘆が深く、その遺誠を忘れないで、日夜、學問にしたしんで來た折柄、父の死を見たから、全く悲しみのどん底に沈んだのである。
彼は、哀痛の誠意を地下の父に表するため、平生、讀んでゐた『禮記』の旨により、 三年の心喪に眼することとした。その時分、世間では、父母の喪に籠ること五十日間で、平生に復するといふ制規があったが、それさへも、事實、行ふものが極く少かった。
それ故、幽谷は、さり氣なく、世俗の爲すところに從ひ、五十日間の喪に服したが、 家にゐるときは、『禮記』に記されたやうに、「苫に寢ね、塊を枕とす」の意を守り、宴席に出です、慶弔を絕ち、詩文も作らず、酒肉をも口にしなかった。
かうして朝夕、亡父の霊前に禮拜した。その哀悼の誠を現はした姿は、深く周囲の人々を動かした。
この際における感想を述べたのが『二連異稱』で、古人が固く服喪の精神を守って孝道につとめた事例を東西に亙って擧げ、喪制の得失、長短などをも論じた。これは、幽谷の没後、門下の會澤正志齋により、刊行されたのである。
その後、寛政七年、幽谷は立原翠軒に從って、京都地方に赴き、或は名所旧蹟を訪ひ、或は漣ゆるき琵琶湖上に舟を浮べた。更に歸途、富士山に登って爽かな日の出を拜し、 氣分を一新した。かうして幽谷は元氣に滿ちて、水戶に歸り、翌八年、邸宅を梅巷の東隅に賜はり、下谷から引移ったのである。
この際、先春及び困學などといふペンネームを作った。やがて寛政九年、夫人丹氏を娶り、新家庭に和樂した。
當時、江戶文化は、進步の頂點に近づき、國民は、なごやかな氣分で、平和生活を享樂してゐたが、事實、幕府の政治も、各藩政も漸く行き詰り、加ふるに、外交國難の兆候が漸く現はれてゐた。時代は、次第に艱險を加へはじめたのである。
從って爛眼な幽谷は、藩主文公の慈仁、恭儉に心服はしたが、要路に當る士が私を營んで文公の志を遮りつつあるのを憤った。率直な彼は、さうした弊害をぢっと傍觀してゐることが出來ないで、直ぐに上書しようと考へた。
が、まだ二十四歲で、地位も低いので、到底、その目的を達すべき望みがない。それ故、彼の所懐を、先づ先輩、犬久保赤水(二三七七~二四六ー)に吿げ、水戸の支藩、宍戸侯によって、文公の耳に入れようと考へた。これは、幽谷が水戶在勤時代のことである。
幽谷の衷情を諒とした赤水は、心から同情して、その時事を論じた文章を宍戸侯の手もとに差出した。ところが、侯は幽谷の論ずるところが、餘りに過激で、必す罪を得べきことを察し、それをその儘、手もとに留めて置いた。そして、一書を長久保赤水に與へ、幽谷に差控へるやう懇論すべき旨を傳へたのである。
以上の旨をそれと知った幽谷は、一層、憂憤し、再び書を赤水に與へて、時事を切論すると共に、是非、彼の主張を文公の耳に達しようとあせった。けれども、この度も亦その目的を達することが出來ない。
故に至って、幽谷はひどく失望し、煩悶した。
彼は時々、文公の講進に侍して、經史を講じたり、道義を說いたりして、度々、直言したことがある。が、幽谷の立場から、考へると、それは、区々たる章句の間に跼踳するにすぎない。本來、彼の点は經給の上にある。天下の政治を料理する點にある。けれども現在は、萬事、思ふやうにならぬので、不平の気を僅かに酒にまぎらし、時に激砍して、矯激な言動を為すことさへもあった。

(四) 幽谷と「大日本史」
〔過激な直言で咎めを受け、國許へ追ひ還された〕
が、決して自棄したのではない。
その切實な憂國の一念は、燃えて炎の如く、到底、いつまでも沈默することを許さぬ。
それ故、穴戶侯の懇諭を知りつつも、寛政九年(1797年)、封事を文公に上り、藩政の缺陷を各方面から鋭く指摘して、權を弄ぶ私臣の反省を促した。果然、宍戸侯の豫察した如く、その言葉の過激な爲めに、忽ち咎めを受けて懲罰に處せられ、すぐ職を奪われて、國許へ追ひ還されたのである。
爾来三年間、幽谷は、閉居して客を謝し、社交にも出ず、專ら讀書、講學に努めたのである。『水藩修史事略』(栗田勤著)によると、『修史始末』は、幽谷、二十四歲の時に成ったとあるから、閉居を命ぜられた年に當る。
それは閉居前になったと思はれるが、『幽谷全集』の年譜を見ても明かでない。
が、『修史復古紀略』の著者、岡崎正忠(幽谷門下)の言によると、「藤田先生江邸寓居の日錄する所なり」とあるから、確かに江戸詰の時に書いたものと思はれる。この書は、大日本史の編修經過とその中心思想とを知る上に、缺くことの出來ない重要な文献である。そこには正保二年(1645年)から寛政九年(1797年)迄一百四十二年間に至る要項が簡明に記されてゐる。
〔謹慎を命ぜられる前、
修史上の事について直言したこと〕
それから、幽谷が閉居、謹慎を命ぜられる前、修史上の事について直言したことが,やはり、『水藩修史事略』のうちにある。それは、『大日本史』の題號を定めるについて、幽谷の所信を披瀝したのであった。
蓋しそれは、水戶藩自身において、『大日本史』の題名を附することは、穩當を缺くとしたからである。彼は、そのうちで、「天朝號を建てて、日本と曰うを聞けり。未だ其の大日本と曰ふを聞かざるなり」と提言して、不可とする理由、四箇條を擧げ、且つ、不當と考へた重要點に觸れて、
「これ固より一家の私書、朝廷問はず、今先づ天闕に奏せずして、
私に力を板に鑲ばめ、公然、號して大日本史と曰ふ。
其の朝廷を蔑ろにする、豈、崔浩、圖書を作るの比にあらずや」
と直言したのである。
慈し幽谷は、朝廷に對する禮儀について深く愼重の態度、議嚴の心持を具すべき必要あることに想い至り、その題號の如きも、朝廷の御許可を仰ぎ、その思召に随順すべきを至当としたのである。
當時、その議は、未だ用ひられず、會て安積澹泊が命名した『大日本史』の題號をその儘にして置いたが、後、幽谷の言は漸く容れられ、改めて朝廷の御意を奉伺して、『大日本史』の題號を賜るに至ったのである。
以上によっても、幽谷が義公の精神を尊重して、『大日本史』の内容その他を完全なものたらしめようとして、鋭意したことが分る。
〔参考〕 
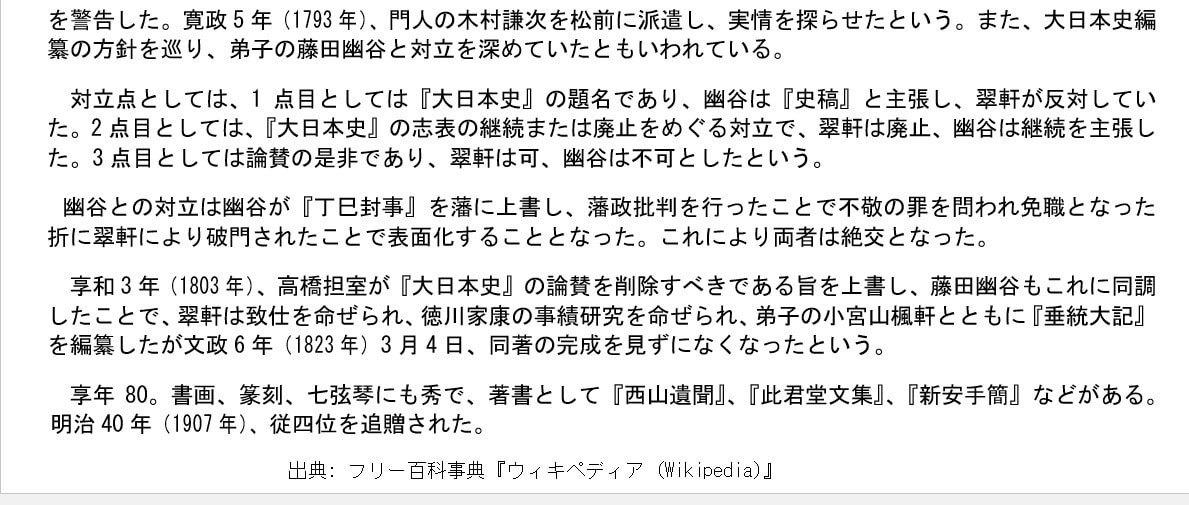


〔関連記事〕
幕末の日本に旋風を巻き起こした水戸藩の尊王攘夷論

























