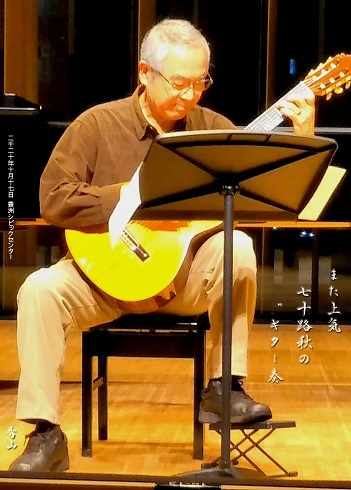1月27日に紅梅が咲き始めたのに気が付きましたので、それ以降、その隣にある白梅は何時お花を付けるか、楽しみになりました。今日、30日はまだ咲いていません・・・
コロナ禍や蝋梅近所に在るを知り

ところで、これまで蝋梅を観に埼玉県の宝登山(ほどさん)に行ったり、鎌倉、小石川植物園に行ったりしていましたが、コロナ散策コースの小名木川散策路で蝋梅に出逢いました。灯台下暗しで、こんな近くにあるとは思いもよりませんでした。これもコロナ禍で始めました健康維持散策のお蔭です。マンションが視界に入る町中で蝋梅の香りを味わえるとはちと乙な感じがします。
玉はじけ出づるマユミや玉手箱 玉:ぎょく

同じ小名木川散策路で、赤い玉手箱から深紅の宝石が飛び出してくる花のようなものに出逢いました。後で調べたら「マユミ」の実とのこと。花は小さく色は緑がかった白色で、この実からは想像できません。開花時期は5,6月で、来年が楽しみです。マユミ(真弓・檀)の花言葉は、「あなたの魅力を心に刻む」・真心・艶めき。そういえば、「真弓」さんという名の方もおられますが、その由来はこの木の名前なのでしょうか???
鴨の思ひ 推して目を追ふ飽きもせず
静から動 鴨半身の潜水漁

小名木川にはいろいろな模様の衣装を着た鴨さん達がたくさん集まってきます。黙々とそれぞれ自由に行動していますが、瞳をじっと見ていると、何かを考えながら動いているように思え始めます。何かは当然分かりませんが、不思議と見てる自分の心がゆるんで(?)いることに、時折、そんな気がします。この鴨さんは「尾長鴨」のようです。
何処でも可愛ゆチェリーセージかな 何処:いづこ

散策の途中で時折買い物もするのですが、小名木川からお店に行く途中の片側一車線の道路脇にチェリーセージがありました。大好きな花の一つで、これまで公園やお花好きの方の家のお庭で見ていましたが、無味乾燥な車道の脇のチェリーセージは一段とかわゆく、潤いを与えてくれています。ハーブの一種で、花言葉は「燃ゆる思い」、「尊重」、「知恵」。私は「可憐」を加えたい、かわゆいお子たち(動物も、鳥さんも)から微笑みかけられているような気がしますので・・・