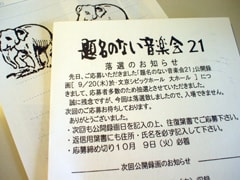東京交響楽団のコンサートへ行けることになったのだが、
行ってみると、なんと猛獣たちがラッパを吹いてるコンサートなのだった。
その名もズーラシアンブラスという、ブラスアンサンブルである。
今日はそのズーラシアンと東京交響楽団のジョイントコンサートだったのだ。

ズーラシアといえば、横浜の動物園ですが、
ズーラシアンブラスは、ズーラシアをホームとする、ブラスアンサンブル。
トランペット1・2、トロンボーン、テューバ、ホルン、指揮の6人。
で、園内のステージのほか、全国のホールで演奏活動をしているらしい。
とにかくかぶり物で演奏するという子どもターゲットに振り切れてるところがすごい。
実は親バカ母、以前brick movie好き、とこのブログに書いてしまったような気がするが、何と言ってもこのかぶりもの、着ぐるみたちには愛着を感じることこのうえなし。今日はほんとに大感激であったが、でもね、客席の子供たちもみんな起きて聴いてましたよ。
だってね、この動物ミュージシャン、キャラクターの中に「いねむりしちゃう」やつ、「暑いのがだいきらい」なやつ、ってのをあらかじめまぜてある。
クラシックのコンサートといえば客をいかにあきさせず、眠らせずといった側面がどうしてもあるだろうに、この6人は客席の子どもたちに、「起きて!」と叫ばせるのである。なんというユーモア!
ついでにこの動物たちのラインナップは
ライオン、オカピ、とら、しろくま、もう2つは難しい名前のというわけで
おそらく動物園のウリ動物と関わりがあって、それ以上の深い理由はないかもしれない。しかも動物園のかぶりものがしょぼくては話にならないから、親バカ母、さわってみたけど、実に手触りもよく、よくできたかぶりものである。見方にもよるが、この動物園主導で動物が決まっている、というのがなかなかよい。
続いて、それなのに、この動物たちが、中の人間のキャラクターと妙に一致してる……ってどうして初めて逢った動物だけ見てこんなこと言ってるのかというと、全員がそのキャラクターを演じるのが板につき、めちゃくちゃ楽しんでいるからなのだ。というのもコンサート後のサイン会に並んでヒビキの青いTシャツにサインをしてもらったのだが、シロクマは「暑い暑い」、ライオンはひたすら手を振る、とそれぞれ舞台でみせていた持ち味のまま続行していて、
「いやあ、私がそのシロクマにして、テューバでして」
「どうもどうも、オカピ・指揮者ですよ」
という具合で(言ったわけじゃないですよ、そういうキャラがにじみでている!)、さらにすごいのが、そのサイン会に列席されていた東京交響楽団の指揮者の方で、隣にいたオカピ指揮者に対して“まるで人間のようにふつうに”話しながら、かぶりもので視界が悪いのをさっと誘導したりしているのである。よほどキャラがはまっていないかぎり、そんなナチュラルなリアクションできるだろうか、あんなすごいかぶりもんに?
音楽なんて別に気脈で通じてしまうし、ミュージシャンらしいふざけた気持ちは動物に託しちゃえ! というわけで、これがなんかえらく楽しいのである。いやね、ほんとはあんなのかぶって大変だとは思います。
だけどとにかく、すごいかぶりもん現る! という感じ。
演奏がすばらしい。どうぶつになりきりがすばらしい。
そんでもって、どうぶつの芸が音楽的。
そして人間のオケである東京交響楽団に対してたかが動物という引き加減も絶妙。
(じゃないと、あんまりふざけられないし)
面白かったなあ。
いやあ、ヒビキくんはですね、もっとちゃんとコンサートとして曲目をプログラムでよく確認しながら、聴いていました。えらいなあ。親バカ母、例によってひどい脱線。