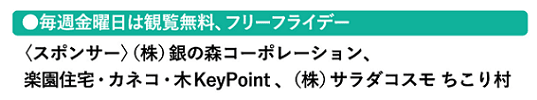ネットニュースを検索していたら、陶芸展の記事がありました。
への次郎 「加藤土師萌(はじめ)さんの遺作展をやっているって」
奥さん 「加藤さんって、人間国宝でしょ。じゃ、行かなきゃ」
ということで、岐阜県多治見市にある現代陶芸美術館にやって来ました。

前を行く女性の後をついて進むと、
美術館につながる屋根付きアーチ橋がありました。

アーチ橋から下をのぞくと、谷に沿って、

白い花のシデコブシやミツバツヅジが咲いていました。
橋を渡ってさらに進むと、美術館の入口があり、

入って地階に下りると、
焼き物販売コーナーがありました。手前が作家物で、


奥には、各窯元の製品が置かれていました。一通り見て、奥に向かうと、
ありました。作品展の入口です。

一人430円を支払って入ると、中には(作品は撮影禁止)、
美濃陶芸界の若手実力者、重鎮、六人の人間国宝の盃、抹茶茶碗、大皿・花瓶など九十数点が展示されていました。
作品群の最後に展示されていたのが、ネットニュースで紹介された加藤さんのこの作品。

(「朝日新聞デジタルニュース」より)
「黄地金襴手菊文蓋付大飾壺(おうじきんらんできくもんふたつきおおかざりつぼ)」。 高さ1.5メートル、胴径73.5センチ、重さは約120キロの大物です。
じつはこの作品、皇居に上納されたもえぎ色の「緑地金襴手飾壺(りょくじきんらんでかざりつぼ)」と色違いの姉妹品でした。
加藤さんは宮内庁から作陶の依頼を受けた際、大壺を50個作り、できがよい3個に緑地の色をつけた。さらに最上の1個を加藤さんの没後、家族が仕上げて皇居に上納。残り2つは、京都国立近代美術館などに収蔵されたそうです。
この時、家族が一つ、色違いの姉妹品を作っていたんですね。それが、この作品。

(「朝日新聞デジタルニュース」より)
ガラスケースに収められることもなく、むき出しに展示されていました。大壺の回りを二人で、何度も回り鑑賞しました。
への次郎 「迫力あるね、この作品」
奥さん 「美術作品でこの大きさ。あまり見ないね。来てよかったわ」
美術館を出て、屋根付きアーチ橋まで戻ってきました。谷の反対側をのぞくと一面に、

への次郎 「ミツバツツジ、すごい数!」
奥さん 「今年も、花の季節が始まったね」