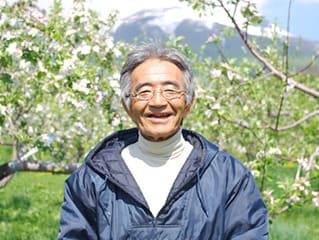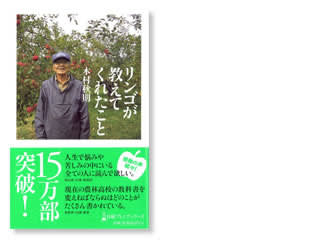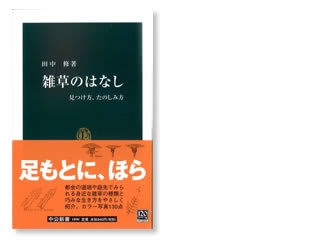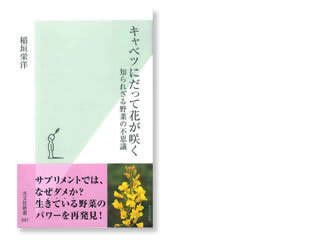地元の本屋さんで立ち読み中…
まえがき
にぎやかな都心の渋谷から電車でわずか30分。
田園都市線の住宅街として開けたわが町・川崎市宮前区土橋。
>えっ「つちはし」?
>ボクはおとなりの「小台」ですが
昭和38年、私はこの土橋で生まれた。
幼な子であった私も、仲間と野山を駆け巡り、輝くような色彩に包まれて遊び回っていた。
>ボクは昭和30年、東京で生まれました
ところが、山が削られ、親しい小径や小川が消え、茅葺き屋根の家々も消え失せた。
今や高級住宅街とさえ呼ばれるこの沿線の街並みは整えられ、
スタイリッシュになり、都心で話題の店が次々に進出し続けている。
>鷺沼には、結婚してからだから… もう30年になるか
高度経済成長の申し子として、その恩恵にあずかってきた私だが、
「何か大切なものを置き忘れてきたような気がする…」という思いは、
咽喉にささった小骨のようにうずき続けてきた。
>うまいなぁ、この言いまわし
その「何か」に真剣に向き合おうと心に決めたとき、
わが家の古い土蔵の扉に貼られた「一枚の護符」が、
私の目に映り込んできた。

>ええええっ なになになに この護符
>年末に登った「御嶽山」は「御嶽神社」のオオカミのお札じゃない?
護符の力に導かれるように、土橋を歩き回り、
村で百姓をしてきた古老を訪ねては話しを聞き、伝統行事の様子をカメラに収め続けた。
>購入! 購入! この本 即買い!
とりあえず「目次」だけでも
………………………………………
第一章/三つ子の魂百まで
取り残された土蔵の前で
新しい街の片隅から
茅葺屋根の家での暮らし
橘樹郡
地縁血縁
「大きな歴史」「小さな歴史」
竹の里
まぼろしのタケノコ栽培
お百姓の身体に宿るリズム
「オイヌさま」の謎
「土橋御嶽講」
第二章/武蔵の國へ
いざ武蔵御嶽神社へ
多摩川への畏れと感謝が生んだ「御嶽講」
日本人と川
「お山」の世界へ
雨乞い
第三章/オイヌさまの源流
「オイヌさま」の故郷
里びとを山へ導く、山びと「御師」
山の神楽
山の行者「御師」と庶民の信仰
第四章/山奥の秘儀
秘儀・太占
太占のルーツ
「太占祭」の記録
「太占」を読み解くお百姓を求めて
お百姓の底力
第五章/「黒い獣」の正体
「黒い獣」と「大口真神」
山とオオカミ
動かざる山への信仰
オオカミの頭骨を祀る家
縄文にさかのぼるオオカミへの信仰
オオカミ信仰のひろがり
武蔵國
大山塊を越えてやってきた「あにぃ」
第六章/関東一円をめぐる
「奥武蔵」へ
秩父の「わらじ親」
神と仏のあわいに
宝登山の「お犬替え」
「お犬さま」と「オオカミ」
秩父の「手締め」
東国武士と秩父
「お山」は文化の発信源
第七章/オオカミ信仰
「オオカミ神社」と「お炊き上げ」
猪狩山へ
古池耕地の人びと
手刷りの「オオカミの護符」
霊験譚
猪狩神社奥宮祭
山の祭りと海のサンマ
赤もろこし
土地の人に添う
ヨソモノの受け入れ方
「一人でやれば苦役でも……」
「鬨の声」
第八章/神々の山へ
三峰山
心直ぐなる者
遠宮「御焚上祭」と赤めし
守護不入の地
神領門前三六戸
「生まれ育った土地」の引力
オオカミ、焼畑、ヤマトタケル……
「オオカミの護符」の誕生
先祖からの「ゆずり」
「お山さま……」
第九章/神々の居場所
「神々の住まうべーら山」
………………………………………
いっきに読んでしまったぁー おすすめ!
オオカミの護符
小倉三惠子/著
新潮社