我が家ではスカパーの時代劇チャンネルに入っている。
主な録画は「暴れん坊将軍」「大岡越前」なのだけど、
ちゃだは松方弘樹主演の「遠山の金さん」を心待ちにしているらしい。
さて、暴れん坊将軍なのだが、
これは8代将軍吉宗が「徳田新之助」と名前を変えて市中を見回り、
悪人を懲らしめるという、みなさまお馴染みのストーリー。
最近これを連日ためて見ているので、あることに気付いた。
ちょっとしたことでは、上様もそんなに衣装をお持ちでないということだ。
これはこの前もお召しであった同じ着物だ!と、
続けて見ているとよく気付くのが面白い。
紫は昔から高貴な色とされていて、
上様しか身につけていないことが多い。
夏には着物も「薄様」になっていたりして、
蝉の音と合わせて、夏を演出したりしている。
また、お側ご用人の「加納五郎左衛門」(または田之倉孫兵衛)も、
茶系が中心の同じような裃(かみしも)を着けている。
大岡越前は爽やかな清潔なイメージからか青色の裃の事が多い。
さて、ここからが本題だ。
番組の後半にさしかかると、悪事が上手くいったと思い込んで、
悪人が「上首尾でござるな〜〜」などと集まって一杯やっていると、
そこに吉宗のエコーの声がかかって「悪巧みもそこまでだ!」などと言う。
その時、悪事が露見した大目付とか老中とか、どこかの藩の江戸家老とかが、
進退窮まって言うセリフに注目してみた。
まずは「もはやこれまで、上様、お命頂戴つかまつる」というのが、
今まで仕えていた臣下としては一番普通だと思う。
もちろん江戸時代は、ものすごいピラミッド社会なので、
すぐに征夷大将軍さまに盾突くのは苦しいところだけど、
こういう人は大抵のところ、尾張大納言とつるんで、
次の将軍職に尾張さんを押して、自分も出世しようという人が多い。
次に「このようなところに上様がおなりになるはずはない」と、
この上様を偽物として切って捨てようという、
これもまぁ、相手は旗本の三男坊として切られるのだという言い訳が立つ。
それと同じように「こやつは上様の名を語る不埒もの!切って捨てぃ!」という、
一旦「上様・・・」」と言って土下座しているのに、
次の瞬間には、相手を上様とは認めんぞ!という身代わりの早さ。
これも断崖絶壁の最初の手段かもしれない。
そして一番すごいのは「上様とて構わん、切って捨てぃ!」という破れかぶれのセリフ。
これはもうパニクッていて、前後の見境がない。
こんなセリフを、今日の悪人はどれを言ってくれるのかなと思いつつ、
その殺陣の場面を楽しみにしているのだ。
そして、切られた人の役目柄が上位であればあるほど、
「〜は病死と届けられ」ることが多い。
それに”いっちょかみ”(加担)していた廻船問屋とか、材木商とかは、
大岡越前によって闕所(けっしょ)になって張り付け獄門とかになるのが普通だ。
うーーーーん、時代劇も奥が深いのである。
くぅ

















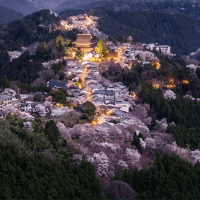









こんにちは。
コメントありがとうございます。
時代劇が好きで私なりに色々観察してたのですが、
着物なんかは着回しですもんねー。
そういう見方をするとなかなか面白いですよね!!