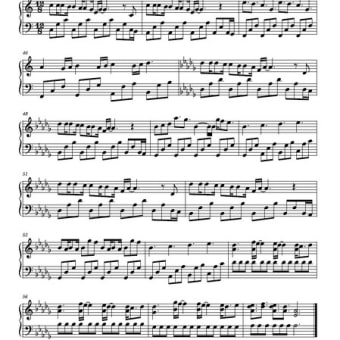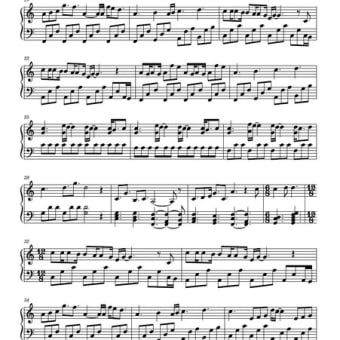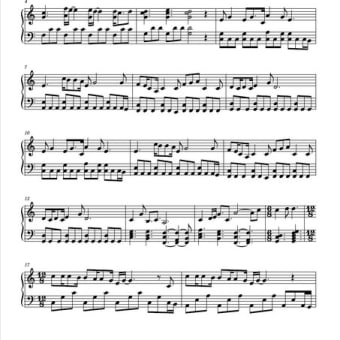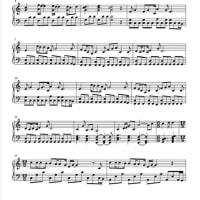やっと Kindle 版を買って、
一晩で一気に読んだ。
辻村深月さんの作品は
「かがみの孤城」を
読んだことがあって、
そのときも、日常に地味に偏在する
生きにくさの構造を腑分けして
とても上手に文章として書いているのに
感心したのだが、
今回はさらにすごかった。
amazon でも多くのレビューに
書かれているように、
まるで自分や自分の親のことが
書かれているように感じられた。
以下、ネタバレあり。
私の母親も、ここに描かれている
真実の母親のように
自分の世界だけを見ている傲慢な人間で、
私自身は、その支配の下で
真実のように善良(かつ傲慢)に、
自己愛を守りながら育ったので、
これをよくぞ書いてくれた、
という感じで読んだ。
いわゆる「毒親」についての
本や小説はあるのだが、
それは、暴力なども含んだ
「異常」に類するケースを
扱っていることが多い。
そうしたものとは違って、
この小説は、ごく普通の日常にある
見えにくい毒を、
取り上げているのがすごい。
マニエリズム的に
誇張・拡大して見せる技が
ちょっと気になったり
ご都合主義的に感じられたりも
するのだが、許容範囲だ。
* * *
ところで、ちょうどこの小説と
「世界史の構造」とを並行して読んだことで、
「傲慢」や「善良」という
心理的な?概念ではなく、
この本の内容を、柄谷さんの
交換様式論の観点から
見ることもできることに気がづいた。
それはつまり、交換様式C=商品交換が
ドミナントである現代の社会において、
人間がもっぱら商品として見られる
=値踏みされる、ということが
あたりまえになってしまったことに
由来する生きにくさが、
高い解像度で描かれている
ということだ。
我々の世代は、
高度資本主義社会の発展を
リアルタイムに経験しているので、
こうした「商品化」が進む前のことも
いちおう知っているし、
商品化が進んで、人間のほぼ全体を
覆ってしまうことへの怖れや嫌悪を
感じたこともあった。
しかし、そういう記憶も曖昧になり、
物や人を値踏みするように見ることや、
逆に、値踏みされることを予期して
それに備えることを
ごく当たり前のこととして
生きてきている、ということを
改めて突き付けられた感じがしたし、
商品化する以前の感覚を
少しは取り戻さないといけない
と感じた。
「善良さ」というのは
「私はあなたを傷つけないから、
あなたも私を傷つけないで、
踏み込んで来ないで」という
ある種の互酬的関係なのかもしれない、
などとも追う。
小説では、真実がそれらを越えるための
仕掛けとして、ボランティア活動や、
伝統的な村落共同体の文化が使われる。
そういえば、小平さんも、
長野でのボランティア活動から
いろいろなものを得たと
言っていた。
これが柄谷さんの言うところの
交換様式 D にあたるのか?
は「世界史の構造」を読み進めながら
検証してみたい課題だ。
全体的に、前半の救いの無さから、
これはいったいどういうふうに終わるのだろう?
と思って読んでいたのだが、
後半の半ば以降は、ハッピーエンドに向けて
かなりご都合主義的にものごとが進んだ。
辻村さんとしても、主人公たちが
救われる物語を書きたかったのだろうから、
これはしかたがないし、
これで良いと思うのだが、
現実にはもっと悲惨な結末も
十分あり得たと思う。
そういうことも含めて、
「わたしのおじさん」とは
また違った意味で、自分の生き方や
考え方、価値観などについて
いろいろと考えさせられる作品だった。
でも、だからといって、
ボランティア活動をしよう、
とも思わないところが、
もう根っこから腐っている感じ
ではあるのだが・・・
最新の画像もっと見る
最近の「本」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事