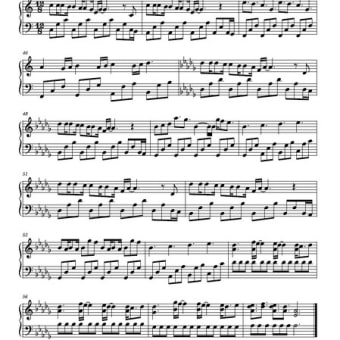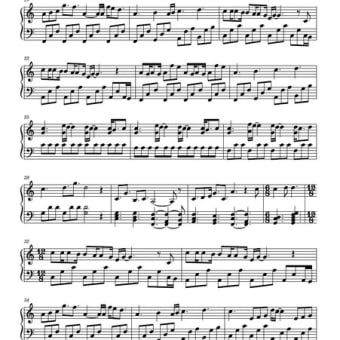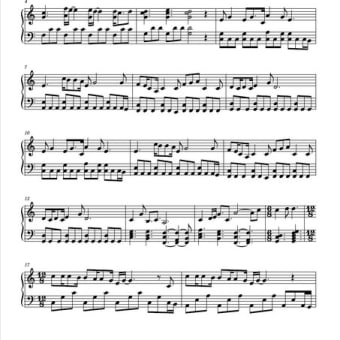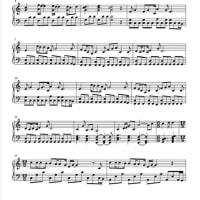なぜかお薦めされてきて以来、
宮台さんの本をいくつか読んでいる。
この新書は、2014年に出版されたものだが、
> 現代とは「社会の底が抜けた時代」である。
> 相対主義の時代が終わり、
> すべての境界線があやふやで恣意的な時代となっている。
> そのデタラメさを自覚した上で、なぜ社会と現実へコミットメント
> (深い関わり)していかなければならないのか。
> 本書は、最先端の人文知の成果を総動員して、
> 生きていくのに必要な「評価の物差し」を指し示すべく、
> 「現状→背景→処方箋」の3段ステップで完全解説した
> 「宮台版・日本の論点」である。
ということで、その論点は、現在でも古くなっていない、
というか、難点はさらに強まっているし、
内容のまとまりもよくて読みやすかった。
レビューにも、
> 宮台真司の著作は数多くあるけど、
> 一冊あげろと言われれば、この「日本の難点」だろう。
> コミュニケーション論・メディア論、若者論・教育論、
> 幸福論、米国論、日本論という5本立てで、
> まさに「日本の難点」を列挙していく。
と書かれている。まさにそういう感じ。
柄谷行人さんとも交流があったようで、
かなり似た内容もある。
柳田国男についての理解なども
共通性が大きい。
自分は、都市に生まれて、
地域にコミットするということを
徹頭徹尾やってこなかったせこい人間なので、
(だから、同じ都市民族の
如月小春さんにはとても親近感がある)
宮台さんの話は耳が痛いが、
内容やロジックには
とても共感できる。
日本は、世界に類のない地縁社会だったが、
その地縁を支えていた共同体が崩壊して
社会の底が抜けたということだが、
血縁の影響が薄い分、
地縁の復活は容易な面も
あるのではないかと思う。
たとえば、地縁に代わって
社縁が働いたから、
世界にも類のない会社人間が生まれて、
一時期、世界で戦えたと
いうこともあるだろう。
日本の、境界を超えて
集まりやすいという特徴が
完全に失われてしまう前に、
なんとか、その良い点を活かして
厚みのある社会を再生できない
ものだろうか?
世界が、超資本主義や覇権主義、
民族主義に覆われて分断されてゆく中で、
日本は、世界で最も「人間的な」
包摂的な国、社会、になれる可能性が
まだあるのではないか?
というようなことを、
今更ながら考えながら読んでいる。
ずっと昔、若い頃には
こういうことを
よく考えて<は>いたのを思い出し、
それが、いつの間にか、頽落しきっている
ことに茫然とする。
だからといって、
すぐに何かするわけでもなくて
こうやってブログを書いている
だけなのだが・・・
追記:
最後まで読んだが、
最後のほうはちょっと
よくわからなかった。
「すごい人」に感化されることが必要、
みたいな話になっているのだが、
その「すごい人」がヒットラーだったり、
麻原だったりすることもあるわけで、
ちょっと納得がゆかない。
結局また「大きな物語」
に戻ってしまった
ということだろうか?
最新の画像もっと見る
最近の「政治・経済・行政情報」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事