
第11回の問題を見ながら内容をチェックしてください。
問1 線分ACの長さが<6>とは 点Aのy座標が<6>ということになります。
このとき、点Aのx座標が<2>であるから
y = ax2 において 6 = a ×(2)2 4x = 6 a = 3/2
問2 変化の割合=(yの増加量)÷(xの増加量) より xとyの増加量を求めます
xの増加量は「変化後の値=4」-「変化前の値=1」
yの増加量は「変化後の値=a ×(4)2 」 -「変化前の値= a ×(1)2」 なので
12 ={ a×(4)2-a×(1)2}÷(4-1)
12 = 16a - a / 3 12 = 15a / 3 = 5a a = 12/5
問3 y = ax2 において a = 1/2 であるから、
点A, B の座標は A(2, 2), B(-1, 1/2) となります。 ―― ①
これを踏まえて、 △OABの辺ABの直線の式を求めます
与えられたA, B の座標より、直線の傾きは1/2
なので、直線 y = 1/2x + b において
2 = 1/2 × 2 + b b = 2 - 1 = 1
よって、 y = 1/2x + 1 ―― ②

図のように、②より 点P(-2, 0)をとると
△OABの面積=△OAP-△OBP
= 1/2×2×2-1/2×2×1/2
= 2 -1/2 = 3/2 ―― ③
△ABDにおいて、AD = t とすると
△ABDの面積 = 1/2×t×3 より
3/2 = 3/2t t = 1 ―― ④
このとき、 点Dのy座標は2より大きいので
点Dのy座標 = 2+1 = 3
∴ D(2, 3)
②の△OABの面積の求め方はほかにもありますので、工夫してみてください。
* 受験対応[英語・数学]講座




















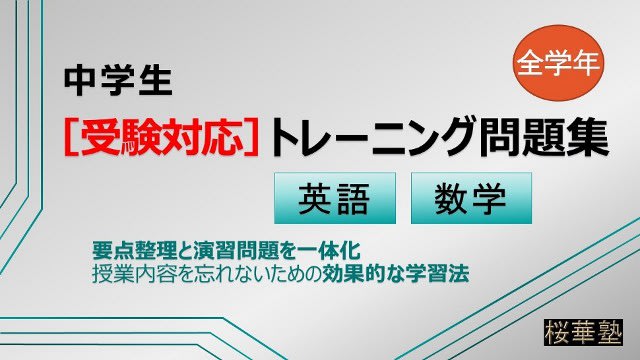
 ☆
☆ 

