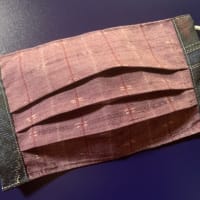前回挙げた拝見とは「内質を見る→内在する品質を見る」のお話の続きです。

お茶の内在って何でしょうか?
「内在」…あるものが、そのものの中におのずから存在すること。現象が自らその内に、その根拠・原因をもっていること。
理解出来るようになるまで訓練を要しますが、拝見では、原葉の状態(栽培)から、製造までほぼ丸裸になります。お茶を作った本人がその場にいなくても製造中に何が起きたかある程度は確認出来ますし、本人がいれば、それは更にはっきりとわかります。
例えば、良く消費者や末端小売の関係者がお茶の評価をする時に使う「爽やかな渋み」という言葉、この根拠も何らかの原因があってのことです。
自然が介在する商品であるとは言え、お茶は人の手によって植えられ、育てられれば工芸作物となり、摘採して工場に運ばれれば商品となります。
何事も人間によって作られたものですから、私達人間が拝見という行為から、作った人間が何をして、作っている最中に何が起こったかを見ることは大方可能なことです。お茶に見られるありとあらゆる現象の原因とその根拠を確認するのが拝見(テイスティング)における「内在」です。
もちろん、この他にも上記の現象をお茶の外観や茶湯の内容等項目別にし、各々を点数化させて総合評価とするもの。お茶屋さんが独自の商品を作るため、ブレンド(日本語は合組、中国語では拼配又は拼堆)の素材を探すためテイスティング、ブレンドや調整の結果を判断するテイスティングなどがあります。
しかしながら業界内や一定の組織の中では分業制になりがちなため、点数化したり、素材や商品を吟味したり調整したりするブレンダーの行為の方が一般ユーザーの目に付きやすく、その印象から入って勉強することが多いため、結局茶業の入口に立ったばかりのユーザーが、時間をかけて投資した割には案外使いどころがない…ということになりがちなのです。
習得する際に、最初に着眼すべき基本中の基本は上記のものであり、ここから入りぶれなければ、その先の枝葉が伸ばしやすくなりますので、是非テイスティングの「内在」を頭の片隅に置いていただきたいと思います。
次は品質のお話です。

お茶の内在って何でしょうか?
「内在」…あるものが、そのものの中におのずから存在すること。現象が自らその内に、その根拠・原因をもっていること。
理解出来るようになるまで訓練を要しますが、拝見では、原葉の状態(栽培)から、製造までほぼ丸裸になります。お茶を作った本人がその場にいなくても製造中に何が起きたかある程度は確認出来ますし、本人がいれば、それは更にはっきりとわかります。
例えば、良く消費者や末端小売の関係者がお茶の評価をする時に使う「爽やかな渋み」という言葉、この根拠も何らかの原因があってのことです。
自然が介在する商品であるとは言え、お茶は人の手によって植えられ、育てられれば工芸作物となり、摘採して工場に運ばれれば商品となります。
何事も人間によって作られたものですから、私達人間が拝見という行為から、作った人間が何をして、作っている最中に何が起こったかを見ることは大方可能なことです。お茶に見られるありとあらゆる現象の原因とその根拠を確認するのが拝見(テイスティング)における「内在」です。
もちろん、この他にも上記の現象をお茶の外観や茶湯の内容等項目別にし、各々を点数化させて総合評価とするもの。お茶屋さんが独自の商品を作るため、ブレンド(日本語は合組、中国語では拼配又は拼堆)の素材を探すためテイスティング、ブレンドや調整の結果を判断するテイスティングなどがあります。
しかしながら業界内や一定の組織の中では分業制になりがちなため、点数化したり、素材や商品を吟味したり調整したりするブレンダーの行為の方が一般ユーザーの目に付きやすく、その印象から入って勉強することが多いため、結局茶業の入口に立ったばかりのユーザーが、時間をかけて投資した割には案外使いどころがない…ということになりがちなのです。
習得する際に、最初に着眼すべき基本中の基本は上記のものであり、ここから入りぶれなければ、その先の枝葉が伸ばしやすくなりますので、是非テイスティングの「内在」を頭の片隅に置いていただきたいと思います。
次は品質のお話です。