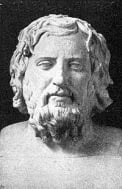ええそうです、という言葉を聞きたくてたまらないけど、
いいえ、という答えもまた大いにありうるとき、
質問をするのはたいへん勇気のいることだ。
(ヘーベル「ドイツ炉辺ばなし集」)
-------------
ヘーベル 1760~1826
ドイツの詩人、聖職者。
科学、宗教、日常道徳などを平易な語り口で表現し、
民衆の啓蒙に寄与した。
ドイツ炉辺ばなし集―カレンダーゲシヒテン ヘーベル
いいえ、という答えもまた大いにありうるとき、
質問をするのはたいへん勇気のいることだ。
(ヘーベル「ドイツ炉辺ばなし集」)
-------------
ヘーベル 1760~1826
ドイツの詩人、聖職者。
科学、宗教、日常道徳などを平易な語り口で表現し、
民衆の啓蒙に寄与した。
ドイツ炉辺ばなし集―カレンダーゲシヒテン ヘーベル