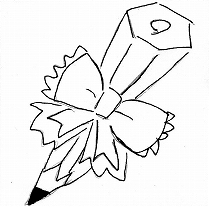本文詳細↓
できれば使いたいというと快く頷いてくれたので、深く頭を下げて感謝した。
「いえ、それがこの救貧院の役目ですから」
それまでずっと表情が乏しくて、僕たちに関心があるのかすらよく分からなかった彼女の顔が、ふわりとほころんだ。この救貧院のことを、心から誇りに思っていることが伝わってくる笑顔だった。
そのまま彼女は一礼して辞し、僕とアダムはそれぞれ椅子とベットに腰掛けてようやく一息をつけた。
「……よもや、こんなことになるとはな。ここへ来るべきではなかったかもしれん」
「どうしたんだ、いきなり。らしくない」
驚いて思わずアダムの額に指をあてて熱を測ってしまった。アダムが風邪を引いたところなんて、出会ってから一度たりとも見たことがないんだけど。
「何を言っておるか! いつまでも宿に着けぬのだから当たり前であろう! そのような宿に何の意味がある。もっと入り口近くに建てるべきだ!」
なんだ、いつも通りだ。さっきの重々しい感じは、疲れすぎただけだろうと思うことにした。
やがて呼ばれた夕食の席には、パンとスープ、いくつかの甘そうな果実が並んでいた。外はすっかり日が落ちてしまったようで、ほんの少し蝋燭の明かりから遠ざかるだけで、圧迫感のある闇が迫ってきた。