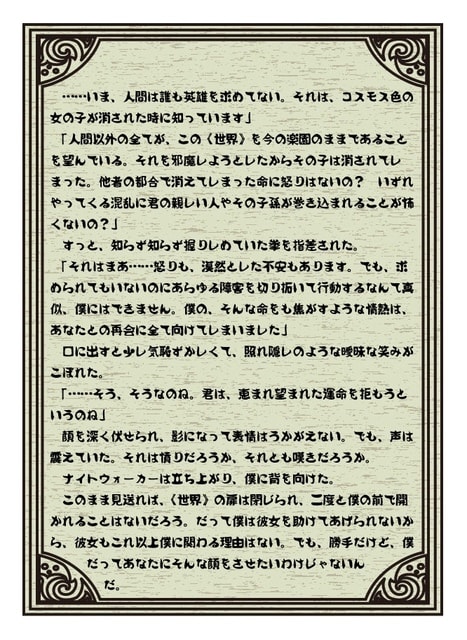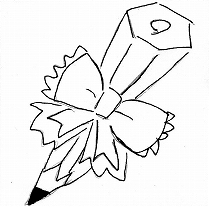1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。

本文詳細↓
それからしばらくして。
オペラリウム中の本屋の片隅に、ひっそりと置かれた本があった。
嘘のような本当のような、不思議な内容が口伝いに広がり、作者不詳のままゆっくりと人間たちの間で読み継がれていった。
タイトルは、『僕の世界見聞録(アカシックレコード)』。
これにて『とある青年の世界見聞録』完結です!
長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。コメントやいいねを下さった方々に、この場を借りてお礼を申し上げます! 本っ当に励みになりました!!
いつかこれも、きちんと製本して世に出せたらなあと思っています。もしもそんな時が来ましたら、またよろしくお願いいたします!


本文詳細↓
長い、
長い沈黙があった。
「……遠いわね。凄く遠い」
ぽつりと、彼女はそう零した。
「とても時間がかかる方法を選ぶのね。《世界》の破滅のほうが先になるかもしれないわよ」
「そうですか? 悪くない勝負だと思いますけど。少なくとも、僕が英雄役を演じるよりよっぽど早いです」
「君ほど恵まれていて、君ほど真剣になってくれる人間がそう現れるとは思えない…………のに、困ったわ」
ふわりと彼女は降りてきて、僕の両頬を包んだ。突然のことに、表情筋が熱を持ったまま硬直した。
「その先を見てみたいと思ってしまった。君の選択がどんな結果を呼ぶのか、知りたくなってしまった。君は、とてもズルい子だったのね」
泣きそうで、でも楽しそうなドキドキを隠しきれない笑顔が僕の視界を埋めた。それがとても愛おしくて、彼女の手に触れようとして――
「そうと決まれば色ボケしておる場合ではないぞ!」
アダムの木槌で思いっきり殴られた。どれだけ文句を言っても暖簾に腕押し、ぬかに釘。まあナイトウォーカーが心から楽しそうに笑ってくれたから良しとするけど。
「そうだ、あと一つだけ。人だけが忘れてしまったこの《世界》の名前って何ですか?」
「それはね。楽園の箱庭を演じるための舞台
――――――――――――――――《オペラリウム》よ」

本文詳細↓
「失望させてしまってすみません。……でもその代わりに、僕に英雄を生む手伝いをさせてください」
「…………え?」
彼女は振り返って僕をまじまじと見つめた。
「? 何を言っているのだおぬしは?」
すっかりいつもの通りに戻ったアダムも、僕の頭の上で両足をパタパタと動かした。
「僕はもう、この世界で何も知らなかった頃のようには生きられない。だから、僕を外の世界へ連れて行ってください。そこで見たこと、聞いたこと、感じたことを本にします。おとぎ話か日記か、分からないような不思議な本を」
「あの曾々祖父の真似をしようと言うのか!?」
ナイトウォーカーは首をかしげていたけど、アダムはアスキリオさんと直接会話しているだけあって、すぐに分かったようだった。
「僕はあの日あなたに会ってなかったら、ここまで絶対に来てなかった。故郷の町で死ぬまで真実を知らずに生きていた。英雄を生むには、そのためのきっかけが与えられなきゃいけないんです。
危険だからと消されてしまうかもしれないけれど、でも人間の誰か一人の手に渡ってくれれば、心に残れば、不思議に思えば、疑問に思えば、知りたいと思えば。それはきっと、いつか必要とされる英雄を生み育てる糧になる。
……そう思いませんか?」
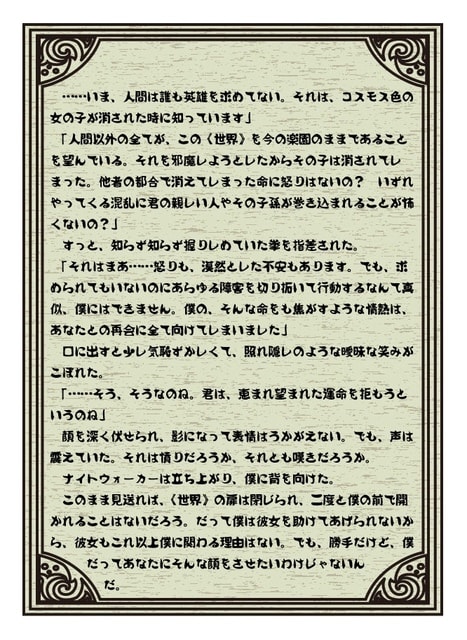
本文詳細↓
……いま、人間は誰も英雄を求めてない。それは、コスモス色の女の子が消された時に知っています」
「人間以外の全てが、この《世界》を今の楽園のままであることを望んでいる。それを邪魔しようとしたからその子は消されてしまった。他者の都合で消えてしまった命に怒りはないの? いずれやってくる混乱に君の親しい人やその子孫が巻き込まれることが怖くないの?」
すっと、知らず知らず握りしめていた拳を指差された。
「それはまあ……怒りも、漠然とした不安もあります。でも、求められてもいないのにあらゆる障害を切り拓いて行動するなんて真似、僕にはできません。僕の、そんな命をも焦がすような情熱は、あなたとの再会に全て向けてしまいました」
口に出すと少し気恥ずかしくて、照れ隠しのような曖昧な笑みがこぼれた。
「……そう、そうなのね。君は、恵まれ望まれた運命を拒もうというのね」
顔を深く伏せられ、影になって表情はうかがえない。でも、声は震えていた。それは憤りだろうか、それとも嘆きだろうか。
ナイトウォーカーは立ち上がり、僕に背を向けた。
このまま見送れば、《世界》の扉は閉じられ、二度と僕の前で開かれることはないだろう。だって僕は彼女を助けてあげられないから、彼女もこれ以上僕に関わる理由はない。でも、勝手だけど、僕だってあなたにそんな顔をさせたいわけじゃないんだ。

本文詳細↓
「ナイトウォーカー。僕はずっとあなたに会いたかったんです。あなたが何者で、どうしてあの日僕にあんなことを言い残したのか、あなたは普段どこで何をしているのか、何が好きで、何が嫌いなのか、聞きたいことがたくさんあって、同時に僕のことも知ってほしいと思っていました。
……もしあなたが何か困っているなら、助けになりたいとも、思っていました」
「なら、どうして英雄にならないなんて言うの?」
「……すみません。英雄になるなんて大それたこと、僕は望んでいなかったし、そのつもりでも生きてこなかったから」
情けないと誹る声が聞こえてきそうだけど、人生を左右する選択の場面において、『できる自信はないけれどやってみる』ことを選ぶ勇気は僕になかった。
「僕たち人間は、誰もが自分の信じる世界の中で生きています。物理的な世界が本物か偽物かなんて関係なく。たとえば、故郷にいた頃の僕の世界に、ケ・セルの山に閉じ込められた一族なんていなかったように。そんなもんです。僕らは僕ら一人ひとりの目で見て感じる世界を、世界の全てだと信じて生きている。そんな人々にこの真実を告げ、本当の自由への解放を目指して戦うなんて……。そういう『英雄』は、運命に望まれるんじゃなくて、人々に望まれて現れるんです。かつてのイルミナリスがそうだったはずです。人間を救ってくれる誰かが望まれ、彼は人間を救うために奔走し、実現させた。