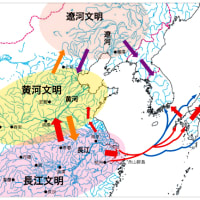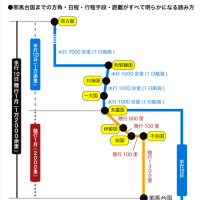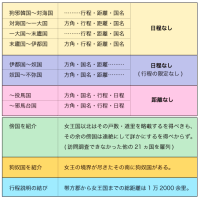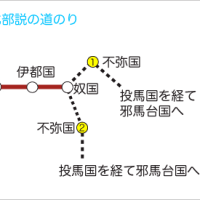● 狗古智卑狗
私は、卑弥呼と卑弥弓呼の血縁関係の有無と、狗奴国の参謀・狗古智卑狗の存在こそが、邪馬台国研究あるいは『倭人伝』解読の最大の謎と考えている。卑弥呼と卑弥弓呼が血縁縁者である可能性については先に触れたので、ここでは狗古智卑狗について触れることにする。
狗古智という名称が、古くから久々知と呼ばれた土地と関係がありそうなことは誰にも分かる。どうやら狗古智卑狗は、ククチという地名がついた高官か武官のようなのだが、この人物の存在は、私の邪馬台国探しでも謎めいた所をみせる。この部分に関しては論拠に乏しい推論に頼らざるを得ないので、「あくまでも仮説の一つ」とお断りしたうえで、 狗古智卑狗にまつわる謎を想定する。

●兄弟国家の確執
1世紀末のこと。倭奴国の王統を継いだ帥升は、筑肥山地の南側に位置する菊地川流域の豊かな土地を取るべく、先住勢力と小競り合いをくり返していた。そうして時を経た2世紀初頭に、ついに頑強な先住勢力の制圧に成功する。天然の地形に恵まれた土地を手に入れたと同時に、長年の脅威でもあった先住勢力の統一が実現したのである。倭国に屈した先住勢力は、特殊な吠声をコミュニケーション手段にしていたことから吠人(はいと・ほゆと)と呼ばれ、九州南端の地に押し込められる形で勢力圏を縮小した。これがいわゆる隼人である。
帥升は統一王になったあと、菊池川上流の山間のクマ(隈=奥まったところ)にある台地に王都を構えた。さらに、その背後に高くそびえる台地をヨナバル(与那原)と名づけ、ここに万一に備えた篭城用の城を築いた。高低差のある前後二つの台地を活用した2段構えの城である。このときから、倭国民衆はこの台地を臺(うてな)と呼ぶようになった。
うてな台地の下で、その出入り口を固めるべく配置された実力豪族が、古豪・倭奴国以来の旧臣として倭国王に仕えてきた狗古智一族である。
かくして7~80年後のこと。帥升のあと何代か続いた男王が死亡したとき、後継者をめぐる紛争が勃発した。「ゆくゆくは列島支配」という大きな利権と野望がからんでいたこともあって、新旧の勢力が幾つかの派閥に分かれて抗争をくり返し、王が不在のまま長い年月を経た。打開策に頭を悩ませた実力者たちの話し合いで、王を共立することで合意した。
ところが長年の抗争続きで、遠縁ながら王位につながる血脈の男性は、幼少の卑弥弓呼だけとなっていた。そこで苦肉の策として、姉の卑弥呼を王にすることで決着した。そうして戦後処理の話し合いの結果、100ヵ国ほどあった勢力を30カ国に整理して倭国を再編成した。
倭奴国時代から続く男王たちの倭国を支えてきた中心勢力は、奴国、弥奴国、姐奴国、蘇奴国、華奴蘇奴国、鬼奴国、宇奴国、○奴国、そして狗奴国の9ヵ国に分断された。中の狗奴国は倭奴国時代からの旧臣が多かったことから漢字語で旧奴国と呼ばれ、これが『倭人伝』に狗奴国と書かれることになる。古豪の狗奴国は、南の隼人に対するくさびとして奥まった人吉盆地を本拠地とすることになり、彼らは、彼らの故地である菊池の隈と同じにこの地を「クマ(球磨)」と呼んだ。
新たに倭国王となった卑弥呼は、戦乱で消失したヨナバルの台地を放棄して、タクマバル(託麻原)の台地に都を築くことにした。与那原の台地は男性的な台地だったが、託麻原台地はなだらかで女性的な台地である。
一旦は平和をとり戻した倭国だったが、卑弥弓呼が成長して元服したのちに紛争が勃発する。「卑弥弓呼こそ正当な王位継承者である」として、狗古智卑狗は卑弥弓呼を王に立てた。狗古智卑狗本人としても、「ククチこそわが故地」との思いがあったのである。そうして、同じく領土奪還を目論む南の隼人勢力と手を結んで、陸海両面から女王国の領域を犯すようになった。女王国側も、南境を固めるべく宇土半島に配していた諸国の防戦で何とか耐えた。
ところが狗奴国勢は、隼人たちの海上ゲリラ戦法を駆使して天草諸島域の制海権を奪い、有明海と外海との通交を遮断した。そうして陸路と海路の関門となっていた宇土(烏奴国)を攻略し、ついに浜戸川南岸一帯を手中にした。 川の北方には卑弥呼の居城がある。
危機的状況が続く中で、倭国主脳はそれまで交流のなかった魏に支援を願い出た。幸いにして、魏朝は「頼るは拒まず」の王道精神を発揮して軍事支援に乗りだしてきた。
これを知った狗古智卑狗は、「急ぐべし」と判断して大規模攻撃を敢行した。この雌雄を決する戦いで卑弥呼は戦死し宮城も焼失した。その直後、倭国からの緊急連絡を受けた魏が、本格的に援軍を投入してきた。これによって両者の形勢が逆転し、魏の軍事力と戦術を手にした女王国側が勝利することになった。これを機に、狗奴国側に加担していた隼人も女王国側の軍門に下ることになったのである。
九州において対抗すべき勢力はなくなり、以前ほど国内勢力に神経を注ぐ必要もなくなった。張政らから多くを学んで成長した女王・臺與は、卑弥呼が着手した東方への進出事業を継承し展開することになるのである。
※「くま(隈)」の本拠地が菊池にあったことは明白なのだが、その菊池から遠く離れた人吉盆地を同じく「くま(球磨)」と呼んだ。この不可思議さを解く鍵もやはり狗古智卑狗である。狗奴国は、もともと菊池の隈を本拠地とした(古豪倭奴国の後継たる)帥升の倭国の中心勢力だった。この勢力が人吉盆地を本拠地とすることとなって、故地の「くま」を称した。狗古智卑狗もまた菊池時代からの名をそのまま使っていた、というのが私の推論である。
※私は、倭奴国は九州北部に本拠地を置いていたとみている。条件としては、「博多湾を臨む・背山臨水の・大河川中流部の台地」である。最もそれらしい候補地としては、一部でいわれている「安徳台」がある。私は、在地のアマチュア研究者・島田直樹氏からの示唆でこの遺跡を知ったのだが、ここには弥生の大きな遺跡があり、貴重な出土品や建築物遺構がある。背振山を背に前面に博多湾が開ける背山臨水のロケーションと、独立した台地構造や那珂川中流に位置するという立地環境的にも、古代の王都の条件を満たしている。銅鏡を埋納する葬送儀礼が伝わる以前の遺跡として、墓から鏡が出ないのも理屈に合っている。100余国もあったという1世紀の有力国の本拠地としては、現在のところ最有力候補である。
古代の呼称や地名が現代まで残されている可能性は極端に少ないのだろうが、その他、それらしい国名と現代の土地とを立地環境や機能も考え併せて照合を試みる。
●好古都国
言語に詳しい人に聞いたところによると、「好」はhao(ハォ)、「古」はgu(ク)、都はtag(タ)またはdu(トゥ)である。du(トゥ)の語尾音はトではなくツである。博多もきちんと読めばハクタで、これがなまったのが「はかた」だろう。これらを勘案すると、博多も、古くは「ハクタ」か「ハクツ」と呼ばれていたのではないかと思われる。ということで、(井沢元彦氏の見解と同じく)好古都が博多へ変遷した可能性をる。
※「はかた」について
越智郡の伯方町は「はかた」。和泉市の伯太町は「はかた」、島根県能義郡の伯太は「はくた」と読む。博多もそのまま読めば「はくた」なのだが、「はかた」と読む。これらは、おそらくは「はくかた」(詰まって「はかた」)という地名に、後世に漢字を当てたものと思われる。そう考える理由の一つとして、宗像、直方(なおかた=のうがた)、枚方(ひらかた)、波方など、「~かた」のつく地名が各地にあり、「~かた」のつく地名には何らかの共通の意味があったものと思われるからである。
「~かた」のつく地名の意味については、これらの地名の多くが古代においては海浜あるいは気水域・河口部・深く入り組んだ入り江にあった様子からも、船の停泊に適した土地につけられた地名ではないかとみている。
博多湾には古くは幾つかの津があって、那の津、荒津、灘津、冷泉津、筑紫大津などと呼ばれていたが、「博多」という呼称そのものは『続日本紀』(797年)に博多大津(博多津)と記されているのが文献におけ初見である。その語源としては、出入りする船の停泊する潟から「泊潟」と呼ばれたというのが最も有力である。そもそも「はかた」とは、現在の博多湾に面する一帯の総称だったようである。
博多の地名については、文献に登場する以前の古くから、「泊潟=はくがた」、あいは那の津、荒津、灘津などを総称した「泊津=はくつ」という呼称が存在したものとみている。こうしたことから、(かすかにではあるが)博多湾が「はくた」あるいは「はくつ」と呼ばれていて、これが『倭人伝』に好古都と書かれた可能性も捨てきれないものがある。
●已百支国
日置(古代豪族の呼称で本拠地は玉名):已百支は「いほき・いおき」と読める。熊本平野の北西部を支配していた日置氏も「ひおき」が訛って「いおき」という。『日本書紀』にも五百城入彦と五百城入姫という人物が登場するが、私は已百支との関連を思う。この日置氏の旧領には江田船山古墳が含まれる。日置氏は、判明しているだけでも古墳時代から平安時代まで、菊池川流域の一帯を支配してきた有力者である。私は『倭人伝』に登場する已百支国とは、この日置氏の国ではなかったかとみている。
●烏奴国
宇土(古代以来の郡名):熊本県南部にあって、島原湾に突き出た天狗鼻のような宇土半島。その基部一帯には、縄文早期から古墳時代に至る遺跡が集中している。先述した通り、向野田古墳は熊本県内でも古い前方後円墳ということで知られているが、これらは、3~4世紀に九州で前方後円墳の築造が行なわれていた証しになる。
私は、『倭人伝』に登場する烏奴国がこの宇土地方にあったのではないかと考えている。その版図は、1300メートルクラスの山が並ぶ西側、宇土半島を含む浜戸川河口から半島のつけ根部分。ここは、八代・球磨川河口部との唯一の陸路の要衝でもある。先端部分は外海との玄関口に当たり、有明海への出入りに目を光らせる。その重要性と遺跡の古さなどからみても、かなり早期から有力者が配置されていたと思われる。
●呼邑国
宮崎県の西都市は、「児湯郡」にすっぽり包まれている。私は呼邑国をこの児湯郡に比定するが、この国名に関しては単なる語呂合わせではなく、相当な確信をもっている。
西都市に都万という地名があるが、これをとって投馬国につなげる説もある。イツと読むべき伊都をイトと読み、トウマと読むべき投馬をツマと読んでリンクさせるわけである。八女にある妻を投馬国に比定する説も同じく、投馬をツマと読んでいる。「邪馬台国論は自在なり」というところか。
もう一つ、西都市に大古墳群があるからこの地に大国があったということで、5万戸の投馬国に比定する生き方がある。だが、山脈の傾斜地が海側まで迫って稲作耕地が少なく、近年までヒエ、ソバ、麦づくりが盛んだった九州東側の地に、数百年にわたって単独であれだけの古墳群を築き続けた勢力があったと思われない。
「高をくくる」ということわざが示すように、その土地の石高(米の生産量)が国力や兵力の物差しになる。古墳の規模も同様で、その地の生産力・国力・民力に比例する。ところが、耕作地の少ない九州東側の西都エリアに、日本最大級ともいわれる大古墳群が存在する。立地状況的にも時代的にみても、これがこの地の一豪族によって、3~400年間にわたって継続的に造営し続けられた可能性はゼロに近い。
西都原は古くは斎殿原(さいとのはる)と呼ばれていた。斎殿原といえば、まさに大斎事の原という意味であり、西都原の古墳群は倭国の公的墓域の一つだったと見るべきだろう。私のこの見解が正しければ、朝鮮半島に出兵したことのある武将の墓があって、朝鮮半島で入手した遺物が副葬されている場合もあるだろう。また、朝鮮半島で戦死した武将の墓が造られている場合は、そこに遺体はなく副葬品だけの場合があるかも知れない。
ということで、 呼邑国がのちに大和朝廷直轄の児湯の県となり、ここに設けられた倭国の国葬センターが斎殿原で、これを、都を「と」と読む時代になって西都原と書くようになったものとみる。(ここにある古い地名の都万は現在でも「つま」と読んでいる。児湯郡と諸県郡は、ともに九州島東側南部地域における政治の中核をなしてきた)。

●華奴蘇奴国
華奴蘇奴とは『倭人伝』の中でもとくに変わった国名だが、これを「かなさな」と読めば金鑚という言葉が現実に日本にある。(埼玉県児玉郡の神川町に金鑚神社がある。ご神体は背後の御室ヶ獄に鎮座しているといわれる。山がご神体らしい)。
●火鑚(き)り:よく乾燥したタブやスギなどを台木(火鑚り臼)として、木の棒(火鑽り杵)をあてて激しくもみ合わせ火をおこすこと。
鑚(さな)は火をおこすときの「火を鑚(き)る」という文字で、金鑚は火をおこす金属の道具らしい。ほかには、鉄鍛冶用の鉄塊そのものを「サナ」とか「サナギ」といったらしい。
さては金鑚とは、鉱山か製鉄か鉄鍛冶と関連するのか。鉄となると、熊本平野と阿蘇地方は弥生の鉄鍛冶の中心地だったから、熊本平野か阿蘇地方の国名だった可能性もろう。あるいは、ベンガラの原料となる赤鉄鉱採掘と関係があるのか。こちらもまた阿蘇地方が本場だから、阿蘇地方の国名だった可能性が高くなる。
●鉱滓(スラッグ)を意味する「カナクソ」という地名
熊本県菊池郡大津町(大津北小学校の東方)に、菊池川の支流である合志川に流れ込む峠川の両岸にある集落を「多々良」という。これは踏鞴(たたら)製鉄に由来しているとの説もある。
たたら製鉄では、砂鉄を還元して鉄を製造する際に、 砂鉄中に含まれる不純物が高温で熔融して鉱滓(スラッグ)となる。峠川の川岸近くには、この鉄滓を意味する「カナクソ」とい地名が残っている。鉄滓を意味するカナクソという呼称があったのだから、鉄鍛冶用の鉄塊をサナあるいはサナギと呼ぶ名称もすでにあったことだろう。カナクソとカナサナは別物のようだが、華奴蘇奴国とは、鉄鍛冶が盛んだった阿蘇地方の国名だった可能性を思わせる。
●阿蘇の鉄素材
阿蘇中央火口丘群の活動はカルデラ生成後、そう時間を置かずに始まったと考えられている。複数のボーリング調査結果から、カルデラ内には時期と場所を異にして少なくとも三度は湖沼が生じたと考えられている。古い順に、カルデラ生成直後に比較的短期間存在した「古阿蘇湖」、一度開いた古い火口瀬を溶岩がせき止めたために生じた南郷谷側の「久木野湖」、そして阿蘇谷側にごく最近まで残っていた「阿蘇谷湖」である。
●阿蘇谷湖で出来た沼鉄鉱床
沼鉄鉱は、沼沢地・冷泉・鉱泉等に由来する多孔質の褐鉄鉱(リモナイト)を指す。でき方は、化学的な沈殿作用やバクテリアの作用により、水中の鉄分が酸化作用を受けて沈殿すると考えられている。
阿蘇市萱原付近の火口原には、日本リモナイト鉱業という会社がある。ここは、阿蘇谷湖の末期に形成されたと考えられている沼鉄鉱の鉱山であり、現在も採掘が続けられている。日本リモナイト鉱業の話によると、太平洋戦争中は製鉄のための鉱石として北九州の八幡まで運ばれていたそうである。その後は、塗料やベンガラ(沼鉄鉱を乾燥させて粉末にした黄土を焼いてつくる赤色の顔料)や、有田の陶器の釉薬としての需要が高かったという。
●沼鉄鉱を焼いて作ったベンガラ
阿蘇地方の古墳から、内側に多量のベンガラが塗られた石棺(剥落して床に敷き詰めたように見える)が発見された。これらのベンガラは、おそらくこの付近の沼鉄鉱を焼いて作られたものと思われる。そうだとすれば、阿蘇に住んでいた古代人が、この豊かな沼鉄鉱を早くから利用していたことになる。
阿蘇市萱原の近くには「赤水(あかみず)」という地名があるが、沼鉄鉱の鉄分が水に溶けて褐色になっていたためにこの地名がつけられたものと想像される。
http://www.pref.kumamoto.jp/site/arinomama/limonite.html
●巴利国
九州には原のつく地名が多く残っている。原の一字では「ハル」と読むのだが、これはもともと「人の手が入った土地」を意味する。語源は「墾(は)る」で、新しく土地をきり拓いて田畑・道路・居住地などにするという意味である。おそらくは縄文言語だと思うのだが、南西諸島や奄美列島でも「ハル」といえば田畑をさすという。
文字通り開墾するという意味だから、「◯◯原」という地名は開墾・治水が行なわれ田畑から居住地・墓地にいたるまでつけられている。これが、先の斎殿原(さいとのはる)や、前後につく文字との関係から、前原(まえばる)・平原(ひらばる)・米原(よなばる)といった具合に濁るわけである。(この訛って濁った「◯◯バル」をとりあげて、韓国語の「バル」「ボル」に直結して、韓国語と日本語の言語の共通性をいう生き方も見かけるが、甚だしい見当違いである)。
『播磨風土記』では同じく開く意味をもつ開闢(かいびゃく)の闢の文字を使って「闢(は)り」と書き、「針間」から「播磨」になったと伝えている。
四国に今治(いまばり)という地名がある。当初は「いまはり」「いまはる」など呼ばれていたそうで、13~14世紀頃の文物に今針・今治の文字が見られる。今治にもまた新しい開拓地という意味があり、開拓・治水がなされたという意味で「今墾」とも表記されているという。
名古屋市を中心とした愛知県の西地域を、かつては尾張といった。この地名は、伊勢湾から濃尾平野を支配した豪族の尾張氏に由来する。尾張は古くは「尾治」と表記されていたという。やはり開墾・治水の意味を持つ「はり」が使われていたわけである。
『倭人伝』に登場する巴利国は「はる」「はり」に由来か関連するようだから、極めて象徴的な開墾と治水がなされた国だったと思われる。ただし『倭人伝』は、「女王国の東にまた倭種の国がある」としていることから『倭人伝』のいう30ヵ国は九州の域を出ておらず、巴利国が四国や本州にあったとは考えられない。
……ほかにも弥奴国(水縄・耳納で久留米)などゴロ合わせ比定ができないわけではないが、しょせんは根拠のないゴロ合わせである。3世紀の地名の名残りが現代まで残っているとすれば、私が思い当たるのはこの程度である。
私は、卑弥呼と卑弥弓呼の血縁関係の有無と、狗奴国の参謀・狗古智卑狗の存在こそが、邪馬台国研究あるいは『倭人伝』解読の最大の謎と考えている。卑弥呼と卑弥弓呼が血縁縁者である可能性については先に触れたので、ここでは狗古智卑狗について触れることにする。
狗古智という名称が、古くから久々知と呼ばれた土地と関係がありそうなことは誰にも分かる。どうやら狗古智卑狗は、ククチという地名がついた高官か武官のようなのだが、この人物の存在は、私の邪馬台国探しでも謎めいた所をみせる。この部分に関しては論拠に乏しい推論に頼らざるを得ないので、「あくまでも仮説の一つ」とお断りしたうえで、 狗古智卑狗にまつわる謎を想定する。

●兄弟国家の確執
1世紀末のこと。倭奴国の王統を継いだ帥升は、筑肥山地の南側に位置する菊地川流域の豊かな土地を取るべく、先住勢力と小競り合いをくり返していた。そうして時を経た2世紀初頭に、ついに頑強な先住勢力の制圧に成功する。天然の地形に恵まれた土地を手に入れたと同時に、長年の脅威でもあった先住勢力の統一が実現したのである。倭国に屈した先住勢力は、特殊な吠声をコミュニケーション手段にしていたことから吠人(はいと・ほゆと)と呼ばれ、九州南端の地に押し込められる形で勢力圏を縮小した。これがいわゆる隼人である。
帥升は統一王になったあと、菊池川上流の山間のクマ(隈=奥まったところ)にある台地に王都を構えた。さらに、その背後に高くそびえる台地をヨナバル(与那原)と名づけ、ここに万一に備えた篭城用の城を築いた。高低差のある前後二つの台地を活用した2段構えの城である。このときから、倭国民衆はこの台地を臺(うてな)と呼ぶようになった。
うてな台地の下で、その出入り口を固めるべく配置された実力豪族が、古豪・倭奴国以来の旧臣として倭国王に仕えてきた狗古智一族である。
かくして7~80年後のこと。帥升のあと何代か続いた男王が死亡したとき、後継者をめぐる紛争が勃発した。「ゆくゆくは列島支配」という大きな利権と野望がからんでいたこともあって、新旧の勢力が幾つかの派閥に分かれて抗争をくり返し、王が不在のまま長い年月を経た。打開策に頭を悩ませた実力者たちの話し合いで、王を共立することで合意した。
ところが長年の抗争続きで、遠縁ながら王位につながる血脈の男性は、幼少の卑弥弓呼だけとなっていた。そこで苦肉の策として、姉の卑弥呼を王にすることで決着した。そうして戦後処理の話し合いの結果、100ヵ国ほどあった勢力を30カ国に整理して倭国を再編成した。
倭奴国時代から続く男王たちの倭国を支えてきた中心勢力は、奴国、弥奴国、姐奴国、蘇奴国、華奴蘇奴国、鬼奴国、宇奴国、○奴国、そして狗奴国の9ヵ国に分断された。中の狗奴国は倭奴国時代からの旧臣が多かったことから漢字語で旧奴国と呼ばれ、これが『倭人伝』に狗奴国と書かれることになる。古豪の狗奴国は、南の隼人に対するくさびとして奥まった人吉盆地を本拠地とすることになり、彼らは、彼らの故地である菊池の隈と同じにこの地を「クマ(球磨)」と呼んだ。
新たに倭国王となった卑弥呼は、戦乱で消失したヨナバルの台地を放棄して、タクマバル(託麻原)の台地に都を築くことにした。与那原の台地は男性的な台地だったが、託麻原台地はなだらかで女性的な台地である。
一旦は平和をとり戻した倭国だったが、卑弥弓呼が成長して元服したのちに紛争が勃発する。「卑弥弓呼こそ正当な王位継承者である」として、狗古智卑狗は卑弥弓呼を王に立てた。狗古智卑狗本人としても、「ククチこそわが故地」との思いがあったのである。そうして、同じく領土奪還を目論む南の隼人勢力と手を結んで、陸海両面から女王国の領域を犯すようになった。女王国側も、南境を固めるべく宇土半島に配していた諸国の防戦で何とか耐えた。
ところが狗奴国勢は、隼人たちの海上ゲリラ戦法を駆使して天草諸島域の制海権を奪い、有明海と外海との通交を遮断した。そうして陸路と海路の関門となっていた宇土(烏奴国)を攻略し、ついに浜戸川南岸一帯を手中にした。 川の北方には卑弥呼の居城がある。
危機的状況が続く中で、倭国主脳はそれまで交流のなかった魏に支援を願い出た。幸いにして、魏朝は「頼るは拒まず」の王道精神を発揮して軍事支援に乗りだしてきた。
これを知った狗古智卑狗は、「急ぐべし」と判断して大規模攻撃を敢行した。この雌雄を決する戦いで卑弥呼は戦死し宮城も焼失した。その直後、倭国からの緊急連絡を受けた魏が、本格的に援軍を投入してきた。これによって両者の形勢が逆転し、魏の軍事力と戦術を手にした女王国側が勝利することになった。これを機に、狗奴国側に加担していた隼人も女王国側の軍門に下ることになったのである。
九州において対抗すべき勢力はなくなり、以前ほど国内勢力に神経を注ぐ必要もなくなった。張政らから多くを学んで成長した女王・臺與は、卑弥呼が着手した東方への進出事業を継承し展開することになるのである。
※「くま(隈)」の本拠地が菊池にあったことは明白なのだが、その菊池から遠く離れた人吉盆地を同じく「くま(球磨)」と呼んだ。この不可思議さを解く鍵もやはり狗古智卑狗である。狗奴国は、もともと菊池の隈を本拠地とした(古豪倭奴国の後継たる)帥升の倭国の中心勢力だった。この勢力が人吉盆地を本拠地とすることとなって、故地の「くま」を称した。狗古智卑狗もまた菊池時代からの名をそのまま使っていた、というのが私の推論である。
※私は、倭奴国は九州北部に本拠地を置いていたとみている。条件としては、「博多湾を臨む・背山臨水の・大河川中流部の台地」である。最もそれらしい候補地としては、一部でいわれている「安徳台」がある。私は、在地のアマチュア研究者・島田直樹氏からの示唆でこの遺跡を知ったのだが、ここには弥生の大きな遺跡があり、貴重な出土品や建築物遺構がある。背振山を背に前面に博多湾が開ける背山臨水のロケーションと、独立した台地構造や那珂川中流に位置するという立地環境的にも、古代の王都の条件を満たしている。銅鏡を埋納する葬送儀礼が伝わる以前の遺跡として、墓から鏡が出ないのも理屈に合っている。100余国もあったという1世紀の有力国の本拠地としては、現在のところ最有力候補である。
古代の呼称や地名が現代まで残されている可能性は極端に少ないのだろうが、その他、それらしい国名と現代の土地とを立地環境や機能も考え併せて照合を試みる。
●好古都国
言語に詳しい人に聞いたところによると、「好」はhao(ハォ)、「古」はgu(ク)、都はtag(タ)またはdu(トゥ)である。du(トゥ)の語尾音はトではなくツである。博多もきちんと読めばハクタで、これがなまったのが「はかた」だろう。これらを勘案すると、博多も、古くは「ハクタ」か「ハクツ」と呼ばれていたのではないかと思われる。ということで、(井沢元彦氏の見解と同じく)好古都が博多へ変遷した可能性をる。
※「はかた」について
越智郡の伯方町は「はかた」。和泉市の伯太町は「はかた」、島根県能義郡の伯太は「はくた」と読む。博多もそのまま読めば「はくた」なのだが、「はかた」と読む。これらは、おそらくは「はくかた」(詰まって「はかた」)という地名に、後世に漢字を当てたものと思われる。そう考える理由の一つとして、宗像、直方(なおかた=のうがた)、枚方(ひらかた)、波方など、「~かた」のつく地名が各地にあり、「~かた」のつく地名には何らかの共通の意味があったものと思われるからである。
「~かた」のつく地名の意味については、これらの地名の多くが古代においては海浜あるいは気水域・河口部・深く入り組んだ入り江にあった様子からも、船の停泊に適した土地につけられた地名ではないかとみている。
博多湾には古くは幾つかの津があって、那の津、荒津、灘津、冷泉津、筑紫大津などと呼ばれていたが、「博多」という呼称そのものは『続日本紀』(797年)に博多大津(博多津)と記されているのが文献におけ初見である。その語源としては、出入りする船の停泊する潟から「泊潟」と呼ばれたというのが最も有力である。そもそも「はかた」とは、現在の博多湾に面する一帯の総称だったようである。
博多の地名については、文献に登場する以前の古くから、「泊潟=はくがた」、あいは那の津、荒津、灘津などを総称した「泊津=はくつ」という呼称が存在したものとみている。こうしたことから、(かすかにではあるが)博多湾が「はくた」あるいは「はくつ」と呼ばれていて、これが『倭人伝』に好古都と書かれた可能性も捨てきれないものがある。
●已百支国
日置(古代豪族の呼称で本拠地は玉名):已百支は「いほき・いおき」と読める。熊本平野の北西部を支配していた日置氏も「ひおき」が訛って「いおき」という。『日本書紀』にも五百城入彦と五百城入姫という人物が登場するが、私は已百支との関連を思う。この日置氏の旧領には江田船山古墳が含まれる。日置氏は、判明しているだけでも古墳時代から平安時代まで、菊池川流域の一帯を支配してきた有力者である。私は『倭人伝』に登場する已百支国とは、この日置氏の国ではなかったかとみている。
●烏奴国
宇土(古代以来の郡名):熊本県南部にあって、島原湾に突き出た天狗鼻のような宇土半島。その基部一帯には、縄文早期から古墳時代に至る遺跡が集中している。先述した通り、向野田古墳は熊本県内でも古い前方後円墳ということで知られているが、これらは、3~4世紀に九州で前方後円墳の築造が行なわれていた証しになる。
私は、『倭人伝』に登場する烏奴国がこの宇土地方にあったのではないかと考えている。その版図は、1300メートルクラスの山が並ぶ西側、宇土半島を含む浜戸川河口から半島のつけ根部分。ここは、八代・球磨川河口部との唯一の陸路の要衝でもある。先端部分は外海との玄関口に当たり、有明海への出入りに目を光らせる。その重要性と遺跡の古さなどからみても、かなり早期から有力者が配置されていたと思われる。
●呼邑国
宮崎県の西都市は、「児湯郡」にすっぽり包まれている。私は呼邑国をこの児湯郡に比定するが、この国名に関しては単なる語呂合わせではなく、相当な確信をもっている。
西都市に都万という地名があるが、これをとって投馬国につなげる説もある。イツと読むべき伊都をイトと読み、トウマと読むべき投馬をツマと読んでリンクさせるわけである。八女にある妻を投馬国に比定する説も同じく、投馬をツマと読んでいる。「邪馬台国論は自在なり」というところか。
もう一つ、西都市に大古墳群があるからこの地に大国があったということで、5万戸の投馬国に比定する生き方がある。だが、山脈の傾斜地が海側まで迫って稲作耕地が少なく、近年までヒエ、ソバ、麦づくりが盛んだった九州東側の地に、数百年にわたって単独であれだけの古墳群を築き続けた勢力があったと思われない。
「高をくくる」ということわざが示すように、その土地の石高(米の生産量)が国力や兵力の物差しになる。古墳の規模も同様で、その地の生産力・国力・民力に比例する。ところが、耕作地の少ない九州東側の西都エリアに、日本最大級ともいわれる大古墳群が存在する。立地状況的にも時代的にみても、これがこの地の一豪族によって、3~400年間にわたって継続的に造営し続けられた可能性はゼロに近い。
西都原は古くは斎殿原(さいとのはる)と呼ばれていた。斎殿原といえば、まさに大斎事の原という意味であり、西都原の古墳群は倭国の公的墓域の一つだったと見るべきだろう。私のこの見解が正しければ、朝鮮半島に出兵したことのある武将の墓があって、朝鮮半島で入手した遺物が副葬されている場合もあるだろう。また、朝鮮半島で戦死した武将の墓が造られている場合は、そこに遺体はなく副葬品だけの場合があるかも知れない。
ということで、 呼邑国がのちに大和朝廷直轄の児湯の県となり、ここに設けられた倭国の国葬センターが斎殿原で、これを、都を「と」と読む時代になって西都原と書くようになったものとみる。(ここにある古い地名の都万は現在でも「つま」と読んでいる。児湯郡と諸県郡は、ともに九州島東側南部地域における政治の中核をなしてきた)。

●華奴蘇奴国
華奴蘇奴とは『倭人伝』の中でもとくに変わった国名だが、これを「かなさな」と読めば金鑚という言葉が現実に日本にある。(埼玉県児玉郡の神川町に金鑚神社がある。ご神体は背後の御室ヶ獄に鎮座しているといわれる。山がご神体らしい)。
●火鑚(き)り:よく乾燥したタブやスギなどを台木(火鑚り臼)として、木の棒(火鑽り杵)をあてて激しくもみ合わせ火をおこすこと。
鑚(さな)は火をおこすときの「火を鑚(き)る」という文字で、金鑚は火をおこす金属の道具らしい。ほかには、鉄鍛冶用の鉄塊そのものを「サナ」とか「サナギ」といったらしい。
さては金鑚とは、鉱山か製鉄か鉄鍛冶と関連するのか。鉄となると、熊本平野と阿蘇地方は弥生の鉄鍛冶の中心地だったから、熊本平野か阿蘇地方の国名だった可能性もろう。あるいは、ベンガラの原料となる赤鉄鉱採掘と関係があるのか。こちらもまた阿蘇地方が本場だから、阿蘇地方の国名だった可能性が高くなる。
●鉱滓(スラッグ)を意味する「カナクソ」という地名
熊本県菊池郡大津町(大津北小学校の東方)に、菊池川の支流である合志川に流れ込む峠川の両岸にある集落を「多々良」という。これは踏鞴(たたら)製鉄に由来しているとの説もある。
たたら製鉄では、砂鉄を還元して鉄を製造する際に、 砂鉄中に含まれる不純物が高温で熔融して鉱滓(スラッグ)となる。峠川の川岸近くには、この鉄滓を意味する「カナクソ」とい地名が残っている。鉄滓を意味するカナクソという呼称があったのだから、鉄鍛冶用の鉄塊をサナあるいはサナギと呼ぶ名称もすでにあったことだろう。カナクソとカナサナは別物のようだが、華奴蘇奴国とは、鉄鍛冶が盛んだった阿蘇地方の国名だった可能性を思わせる。
●阿蘇の鉄素材
阿蘇中央火口丘群の活動はカルデラ生成後、そう時間を置かずに始まったと考えられている。複数のボーリング調査結果から、カルデラ内には時期と場所を異にして少なくとも三度は湖沼が生じたと考えられている。古い順に、カルデラ生成直後に比較的短期間存在した「古阿蘇湖」、一度開いた古い火口瀬を溶岩がせき止めたために生じた南郷谷側の「久木野湖」、そして阿蘇谷側にごく最近まで残っていた「阿蘇谷湖」である。
●阿蘇谷湖で出来た沼鉄鉱床
沼鉄鉱は、沼沢地・冷泉・鉱泉等に由来する多孔質の褐鉄鉱(リモナイト)を指す。でき方は、化学的な沈殿作用やバクテリアの作用により、水中の鉄分が酸化作用を受けて沈殿すると考えられている。
阿蘇市萱原付近の火口原には、日本リモナイト鉱業という会社がある。ここは、阿蘇谷湖の末期に形成されたと考えられている沼鉄鉱の鉱山であり、現在も採掘が続けられている。日本リモナイト鉱業の話によると、太平洋戦争中は製鉄のための鉱石として北九州の八幡まで運ばれていたそうである。その後は、塗料やベンガラ(沼鉄鉱を乾燥させて粉末にした黄土を焼いてつくる赤色の顔料)や、有田の陶器の釉薬としての需要が高かったという。
●沼鉄鉱を焼いて作ったベンガラ
阿蘇地方の古墳から、内側に多量のベンガラが塗られた石棺(剥落して床に敷き詰めたように見える)が発見された。これらのベンガラは、おそらくこの付近の沼鉄鉱を焼いて作られたものと思われる。そうだとすれば、阿蘇に住んでいた古代人が、この豊かな沼鉄鉱を早くから利用していたことになる。
阿蘇市萱原の近くには「赤水(あかみず)」という地名があるが、沼鉄鉱の鉄分が水に溶けて褐色になっていたためにこの地名がつけられたものと想像される。
http://www.pref.kumamoto.jp/site/arinomama/limonite.html
●巴利国
九州には原のつく地名が多く残っている。原の一字では「ハル」と読むのだが、これはもともと「人の手が入った土地」を意味する。語源は「墾(は)る」で、新しく土地をきり拓いて田畑・道路・居住地などにするという意味である。おそらくは縄文言語だと思うのだが、南西諸島や奄美列島でも「ハル」といえば田畑をさすという。
文字通り開墾するという意味だから、「◯◯原」という地名は開墾・治水が行なわれ田畑から居住地・墓地にいたるまでつけられている。これが、先の斎殿原(さいとのはる)や、前後につく文字との関係から、前原(まえばる)・平原(ひらばる)・米原(よなばる)といった具合に濁るわけである。(この訛って濁った「◯◯バル」をとりあげて、韓国語の「バル」「ボル」に直結して、韓国語と日本語の言語の共通性をいう生き方も見かけるが、甚だしい見当違いである)。
『播磨風土記』では同じく開く意味をもつ開闢(かいびゃく)の闢の文字を使って「闢(は)り」と書き、「針間」から「播磨」になったと伝えている。
四国に今治(いまばり)という地名がある。当初は「いまはり」「いまはる」など呼ばれていたそうで、13~14世紀頃の文物に今針・今治の文字が見られる。今治にもまた新しい開拓地という意味があり、開拓・治水がなされたという意味で「今墾」とも表記されているという。
名古屋市を中心とした愛知県の西地域を、かつては尾張といった。この地名は、伊勢湾から濃尾平野を支配した豪族の尾張氏に由来する。尾張は古くは「尾治」と表記されていたという。やはり開墾・治水の意味を持つ「はり」が使われていたわけである。
『倭人伝』に登場する巴利国は「はる」「はり」に由来か関連するようだから、極めて象徴的な開墾と治水がなされた国だったと思われる。ただし『倭人伝』は、「女王国の東にまた倭種の国がある」としていることから『倭人伝』のいう30ヵ国は九州の域を出ておらず、巴利国が四国や本州にあったとは考えられない。
……ほかにも弥奴国(水縄・耳納で久留米)などゴロ合わせ比定ができないわけではないが、しょせんは根拠のないゴロ合わせである。3世紀の地名の名残りが現代まで残っているとすれば、私が思い当たるのはこの程度である。