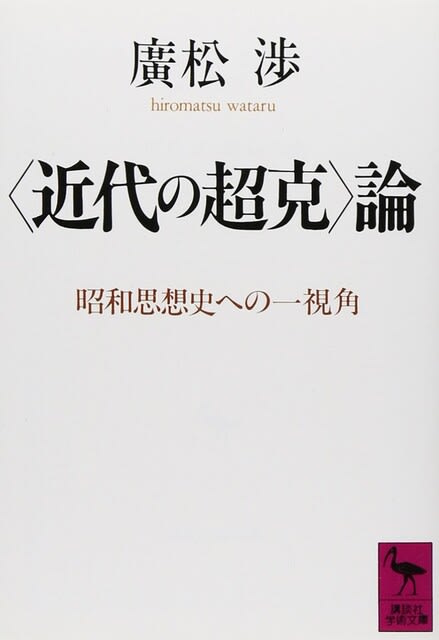京都周辺で開催されるデモ行進・街宣・イベント・裁判・選挙等の情報を共有するためのページです。
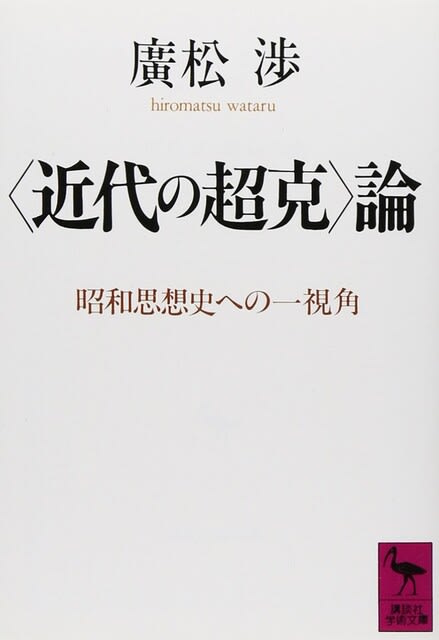
そこで審判に掛けられるのが、東洋的無によって主観と客観の二元論的対立構造を止揚せんとする、西田幾多郎と弟子からなる京都学派だ。彼らは、「西洋哲学を突き抜けた」(209㌻)と自負する西田哲学の立場から、戦前戦中にかけて「近代の超克」という思想ムーブメントに加担した。そこで、東洋的無を具現化した天皇制に西洋近代が包摂される、世界支配イデオロギーを創出する。さらには、マルクス主義すら取り込み、資本主義批判から戦争に資する統制経済と戦時体制を正当付けた。こうして西田哲学は「近代の超克」から、日本ファシズムを形作ったことが本書で示される。
どういう訳か、戦後もこれら西田哲学各派は思想としての戦争責任や検証を素通り出来た。その一部は、マルクス主義に横滑りしたことを煩悶することで贖罪代わりとし、マルクス主義陣営に宿った。恐らく廣松は、このような西田哲学の戦後的変種に、ファシズムが温存されていることを見抜いたのだろう。本書によって〈近代の超克〉に群がった西田哲学は、その派生もろとも核心部を串刺しにされる。結果として、本書では直接取り上げられていない左翼風な粉飾を施した西田哲学の戦後的変種が、戦前戦中の西田哲学と同根であり、同じような道をたどり同じ結末に至ると見通せる。
「論者たちは、成程、哲学的人間学に定位することによって、マルクス主義における“欠隙”をも埋めようと企て、その若干の論点において、戦後マルクス主義のある風潮に先駆けたかもしれない」(252㌻)
廣松の真意が、この一文に仄めかされている。「戦後マルクス主義のある風潮」は転向問題を口実に、マルクス主義の欠隙を主体性論や疎外論で埋める体で、近代の超克を延長しようとした。結果はいわずもがな、廣松の読みの正しさを証明している。今後も『〈近代の超克〉論』は、日本ファシズムの発生機序を明らかにし、成長を阻む役割を果たすだろう。と同時に、根底的な宗教批判と哲学批判を欠いた日本思想を、社会変革の理論に据える危険性についても理解させる。廣松が同時代の戦後思想家とあまり関りを持たないようにしたのは、案外これが理由かもしれない。
「近代の超克」ムーブメントには、日本浪漫派と文学界グループも関わっている。彼らは西洋近代の極致たるマルクス主義の挫折から、「原日本的古代」「日本の古典」(194㌻)に回帰し近代を超えようとした。それは結局、天皇制に収斂し日本ファシズムの推進力になり果てた。この水路は戦後になっても中途半端な迷えるマルクス主義者たちを、「原日本的古代」や「日本の古典」の実体探しに引き込み、陰謀論や謀略論、カルト宗派、エコロジー、親鸞へと導いている。心情的な原日本的古代と日本の古典に、西田哲学が理論的構図を与えたため、これらは戦後も延命できたと考えられる。
「現代的不幸」なる結論ありきに合わせるため、膨大な資料を切り貼りした本。当事者にインタビューすると、このヤリ口が使えないのでインタビューしなかった、という話でしかない。「現代的不幸」とは、高度経済成長という時代の転換点に起きる不安感のことで、著者が学問的装いでレッテル貼りするため作ったワードだ。マスコミによる数々の学生運動語りで、「純粋」の次に使い倒されている陳腐な解釈である。「現代的不幸」ということにしておけば、日本の学生運動を一過性のお祭り騒ぎか自分探しに貶めることができ、それ以上考えなくて済む。あの時代に対する苛立ちを抑えられない人が読めば、冷笑を浮かべ気持ちが収まるだろう。著者は、戦後日本社会が抱えた安保・沖縄という宿痾に、若者が落とし前をつけようとした苦闘から目を逸らしている。それは、今も果たされないままだというのに。
骨子や論拠が学生の小論文レベルであり、中身は政治的パンフレット。やたら分厚い本の割に、スラスラ読めるのはそういうこと。ページ数稼ぎにより、学術書としての体裁を取り繕おうとしているのではないか。もう一つ陳腐な学生運動解釈として、セクトの介入、もしっかり挙げられている。3・11以後という衰退の時代に、著者が社会運動へ関わろうとする動機と願望と役割が見えてくる。学生運動や社会運動を学問やノンフィクションとして取り上げたい人は、「自分探し」「純粋」「セクトの介入」を頭から外して、考察すべき。テレビや雑誌といったマスコミ報道も、「自分探し」「純粋」「セクトの介入」は、手軽で便利なのは理解するが陳腐になるので使うべきではない。見る側も、そのような切り口は飽きている。

福島原発事故収束作業は行き詰っている。溶け落ちた880トンもの核燃料デブリが原子炉圧力容器直下で鎮座し、相当分が原子炉格納容器底部にはみ出している。そして、この核燃料デブリが原子炉を支えるコンクリートを溶かしたため強度不足となり、震度6強の地震で原子炉圧力容器ごと倒壊する可能性が高い。それだけでも3・11を超える大事故だが、核燃料プールを巻き込めば放射性ダストの飛散により史上類例のない惨事となる。つまり我々は、日本滅亡と隣り合わせ運任せの日常にある。この現状を本書は、科学に基づき淡々と明らかにしてゆく。
思えば3・11から12年もの間、日本社会は福島原発事故を見て見ないふりしてきた。その象徴が東京オリンピックだ。覚えているだろうか、このオリンピックが「復興五輪」と呼ばれていたことを。今となっては噴飯もので、東京オリンピックのトの字も話題にならない。復興どころか、日本の衰退を全世界にさらけ出したからだ。我々は高度経済成長の果てに突き付けられた、この敗北をいい加減認めなければならない。にもかかわらず、まだ大阪万博や札幌冬季五輪といった昭和の戦後復興二番煎じ劇を演出し、その真打である原発再推進に執着している。小型原発や核融合など悪足掻きでしかない。
読後、原子炉倒壊を防ぐことが我が国の最優先課題だと分かる。そして福島原発事故収束作業をどうするのか、考えなければならない。原子炉倒壊を防ぐにはどうしたらいいのか。核燃料デブリを取り出せるのか否か。著者は、日本の経済成長を支えた技術者らしい修繕案を提示する。けれども、無限の熱エネルギーを渇望する非合理な社会に触れることなく、技術的合理性だけ囲い込み抜き出しても通用せず跳ね返されるだろう。何せ日本は、官民一体で放射能汚染水を処理水と言い換え海に棄てる国だ。そもそも核燃料デブリを取り出すべきなのか、仮に取り出せたとして何処に保管するのか、展望は見えてこない。今の政治経済体制の下ではどの政党が政権を担おうとも、見て見ないふりを国是とする圧力に支配される。
我々は「台湾危機」などにかまけている余裕はないはずだが、フクシマという本当の危機から目を背けるためなら何でも乗るらしい。そんな日本人の都合や俗世の権益争いなどお構いなしに、その時はやってくる。崩壊寸前の原子炉を支えるコンクリートは、日々冷却水や放射線、潮風に晒されている。また、幾多の地震によるダメージも蓄積していく。本書は福島原発1号機に焦点を当てているが、2号機3号機も1号機と同様かより酷い状態だと考えられる。あえて言えばもう時間切れであり、日本社会は文明転換の捨て駒になる覚悟を持つべきステージへ移行したのだ。
太田竜は太平洋戦争敗戦前後に、戦争由来の災害ユートピアという形で原始共産制を実感していた。貧困と革命の熱意を共有する多くの仲間によって形成される共同性と、アメリカによって帝国主義から脱落させられ革命を臨むゼネスト直前まで至った日本の姿は、強烈な記憶として刻まれた。このことが、本書から読み取れる。また、なぜ太田が最終的にオカルティストになってしまったのか、原因が見えてくる。敗戦前後の原始共産制に戻れば一からやり直せる。今度こそ正しい革命の道を選択出来る。ないものねだりな願望は、原始共産制の雰囲気が漂う辺境に敗戦前後の日本社会を投影することへ繋がる。こうして太田は、高度経済成長の渦中で大衆との接点を見失い、革命運動に躓く度次から次へと立場を変え辺境探しを繰り返すことになる。そして、いよいよ敗戦前後の原体験すら無効となった時、鬼畜米英を唱和していたであろう今は亡き樺太の豊原第一尋常小学校少国民時代まで退却し、縄文や爬虫類人を介して天皇に抱きついたのである。未来は未来へ接続することでしか創造できない、ここに至らなかった太田の悲劇というべきか。うがった見方をすれば、新たな辺境を見つけることで、太平洋戦争敗戦前後に得た興奮を再体験できたなら、太田にとっては十分なお釣りだったのかもしれない。
太田竜は戦後左翼の最重要人物であり、世界革命を目前に現出させ追い求める彼の政治的影響力は甚大であった。新左翼とカテゴライズされる全ての党派は、彼の思想から何らかのインスピレーションを受けたといっても過言ではない。にも拘わらず、見るに堪えない経緯から新左翼史の中でその存在を抹殺されている。しかし意識はしていないだろうが、今もって新左翼各党派は太田の思想的掌中にある。彼の再評価と総括がなければ前進も解放もないことは記しておきたい。憲法守れ9条守れなどと、戦後民主主義に回帰してお茶を濁しているような学生運動崩れこそ、本書との格闘が必要だと思われる。太田自身による戦後左翼総決算といえる内容であり、今だからこそ客観視でき現代と化学反応を起こすことができる。激情家の太田竜が、俯瞰目線で冷静に左翼を語った恐らく唯一の本ではないか。かなり項数を削ったと思われるが、できれば完全版を出版して欲しい。それだけの価値がある。

エピローグにおいて、戦争による破壊が徹底的に行われたことで「戦前と戦後が完全に断絶された日本国土の例は、沖縄が唯一である」(p.276)と、我々の盲点を突く。そのため沖縄では、「確固とした戦争戦争の反省と米軍軍政との権利闘争の中で強烈な民主主義的自意識が確立された」(p.277)。それに引きかえ他の日本人は、「戦後民主主義という種をばらまいても、その土壌が弱いので大きな芽が出ないのである」「土壌を入れ替えるしかないが、それは破壊を伴う作業なので、秩序や既存利益の破壊を嫌う人には受け入れがたい」(p.279)ゆえに、出口がない。皆、秩序や既存利益から甘い汁を吸う共犯である以上、今後も戦前体制の土壌である自民党政権は続き、その派生物であるシニア右翼も根絶されない。それでは希望がないと感じたのか最後の項で著者は、革新やリベラルに期待をかける旨書いて筆を置く。
だが、その結論は違うだろう。せっかく、沖縄という異なる価値観を呼び起こしたというのに。ここから求められるのは、日本の沖縄化だ。沖縄が琉球独立を選択せず「祖国日本」に復帰したのは、今の日本領内で唯一住民ともども地上戦を戦い、戦後自力で民主主義的自意識を掴み取った自分たちこそ真の日本人だからだ、という沖縄の誇りが読後に滲み出る。このことは沖縄の祖国復帰運動と、ベトナム戦争、沖縄米軍基地、日米安保体制が絡み合う中で、沖縄の在り様を規定してきたのではないか。そしてそれは、今また「米中対立」という形ではっきりと顕在している。我々日本人は再び沖縄を見殺しにするのか、今度こそ沖縄県民の思いに応え、沖縄を捨て駒にして延命しようとする日本の戦前体制を放逐し、未完の戦後民主主義を完成させるのか、迫られている。