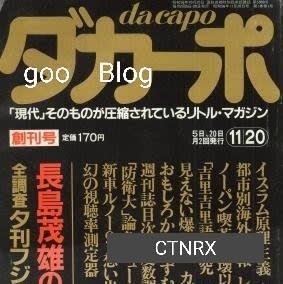
■イデオロギーの終焉
イデオロギーの終焉
(英:The End of Ideology)
先進資本主義諸国における「豊かな社会」の到来とともに、階級闘争を通じた社会の全面的変革なる理念はその効力を失ったとする論。
また、ダニエル・ベルによる1960年刊行の著作。
※“イデオロギー”については、「ダカーポ♯002」参照。
《概要》
もちろん、ダニエル・ベル以前からイデオロギーの終焉はさまざまに論じられてきたが、1960年にダニエル・ベルがはじめて『イデオロギーの終焉』のなかで理論的に整除されたかたちで唱えることになり、「イデオロギーの終焉」は世界的な流行語となった。
しかしベルは、ユートピアは終焉せず、第三世界から新たなイデオロギーの出現しうることを展望したが、古典的マルクス主義には破産宣告を行った。
ベルやシーモア・M・リプセットら、イデオロギーの終焉論者によれば、今や必要なのは不確定な観念的要素に満ちたイデオロギー的構想に基づく社会の全面的変革ではなく、信頼のおける科学的知識と技術とを用いた社会の部分的改造のつみ重ねである。
そして、そのなかでイデオロギーという概念は死語になりつつあり、資本主義国家と社会主義国家は今後、イデオロギー対立をこえた共通の方向に向かうとした。
関連項目 ー 階級闘争 ー
(共産主義における用語)
階級闘争
(ドイツ語: Klassenkampf,)
(英語: Class conflict, class struggle, class warfare)
生産手段の私有が社会の基礎となっている階級社会において、階級と階級とのあいだで発生する社会的格差を克服するために行われる闘争。
この闘争により革命が起きるとされている。
対義語として階級協調が挙げられる。
《概要》
マルクスとエンゲルスの『共産党宣言』(1848年)においては「今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である」と規定され、階級闘争は社会発展の原動力として位置づけられている。
社会がいくつかの階級に分裂して互いに和解しがたく敵対している場合に、いずれか一方の階級が他方の階級を打倒して、その政治上、経済上、文化上の特権、権利、機会を奪取し、支配権を手に入れようとして行われる闘争をいう。
階級間の対立、抗争については古くから注目され、種々の学説が生み出された。
プラトンは富者と貧者の間の闘争を哲人支配によって克服しようとし、下って19世紀初頭のフランスでは、サン・シモンは、フランス革命を進歩的知識層、保守的所有者、無産者という三つの階級間の抗争としてとらえ、産業者を中心とした社会改造を説いたが、階級闘争を理論づけるまでには至らなかった。
唯物史観の立場から階級間の対立・闘争の必然性とプロレタリアートの歴史的使命を説いて、階級闘争の理論を提出したのは、マルクス、エンゲルスである。それによると、原始共産制の段階を除き、今日までのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史であって、資本主義社会における階級間の対立・抗争は資本家による労働者の搾取(剰余価値の収取)に由来する。
つまり、富の分配の著しい不平等(貧富の差)は、生産が社会化されているのに領有が私的な性格をもつという矛盾によるが、資本家はこのような搾取の体制を維持する必要上、こうした矛盾をそのままにして労働者に貧困その他さまざまの耐えがたい犠牲を強いるため、労働者はこの桎梏(しっこく)から自らを解放しようとして、現行の生産関係を土台とする社会体制を打破し、変革していく運動を推し進めるようになる、という。
このような体制変革への条件は、資本主義体制自体のなかにあるが(生産の社会化と所有の私的性格などの矛盾)、同時に体制変革を担うべき労働者階級が孤立・分散、競争の状態を脱却して、大工業地帯に集中し、階級的利害に目覚めて組織をつくり、そのもとに団結して、真の階級意識や階級組織を備えた対自的階級Klasse für sichにまで主体的に成熟していなければならない、とされている。
階級闘争には労働組合による経済闘争、政党の指導下で体制変革を目ざす政治闘争、敵対階級の誤りを暴露し、自己の立場の正しさを主張するイデオロギー闘争がある。資本主義社会ではそれに内在する法則の作用によって、将来ますます労資二大階級への両極分解が強まり、労働者の状態は悪化し、窮乏化の一途をたどるから、階級闘争はますます激化し、革命は不可避である、と主張される。 しかし、19世紀末以降、とくに現代の先進諸国では、マルクスらの予想に反して、両極分解と窮乏化のかわりに、新中間層の増大と生活の向上・平準化をもたらし、福祉政策の拡充とともに、ベルンシュタインらの修正主義や社会民主主義の路線、階級対立の制度化などの事態を招き、そのため先進諸国における階級闘争は変質して革命性を失い、体制内部に組み込まれていく傾向がある。
関連項目 ー 市民社会 ー
市民社会
(英: civil society)
(独: bürgerliche Gesellschaft)
(仏: société civile, société bourgeoise)
資本主義社会、近代社会、ブルジョア社会。
市民階級が封建的な身分制度や土地制度を打倒して実現した、民主的・資本主義的社会。
「市民階級」「市民革命」「市民法」「市民的自由」等と共に、第二次大戦後から有力になった用語。
この言葉は本来、「市民革命 (ブルジョア革命) によって成立した社会」を意味する。
資本家や知識人らの市民階級が絶対君主制・封建制を打破し、基本的人権を確保したことで市民社会は成立した。
政治的には民主主義に、経済的には資本主義に基づく社会だとされる。
《市民革命》
またはブルジョア革命、資本主義革命、民主主義革命。
封建的・絶対主義的国家体制を解体して、近代社会(市民社会・資本主義社会)をめざす革命を指す歴史用語である。
一般的に、啓蒙思想に基づく人権(政治参加権あるいは経済的自由権)を主張した「市民(ブルジョア・資本家・商工業者)」が主体となって推し進めた革命と定義される。
代表例はイギリス革命(清教徒革命および名誉革命)、アメリカ独立革命、フランス革命など。
▼概要
この「市民」には、封建・絶対主義から解放され、自立した個人という意味および商人・資本家という意味を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。
一方で、この二義性は表裏一体をなす。
すなわち、革命をなすための市民社会の形成には資本主義の発達が不可欠であり、私的所有の絶対を原則とする資本主義社会の成立が必要だったのである。
ロシア革命もこれに分類されることがある。市民革命は、また、資本主義社会から社会主義・共産主義社会の実現をめざしたプロレタリア革命とは性格を異にする。
1848年革命、パリ・コミューンなどは一般的にプロレタリア革命に類される。
▼市民革命の前提
ブルジョアジー(ブルジョワジー)の誕生と市民社会の形成とは相支え合う要素であり、ともに市民革命の要件とされる。
ブルジョアジーが発展するためには労働力の移動、流通の自由や私的所有などが認められていなければならず、これは市民社会の成長を要件としている。
いっぽうで、市民社会がつくられるためには封建的支配者の打倒が必要であるが、それは経済力を持ったブルジョアジーの力が必要であった。
◆ブルジョアジーの誕生
個人が社会の構成要素として、一定の経済力を持ったかたちで主体的に行動することが封建制・絶対主義を覆すための前提となる。
したがって市民革命には革命の主体となるブルジョアジーの誕生が前提となる。
ブルジョワジー
(仏: bourgeoisie)
中産階級の事であり、有産階級とも呼ばれる。
特に17〜19世紀においては革命の主体になりうるほどの数と広がりを持つ階層であったが、市民革命における革命の推進主体となった都市における有産の市民階級をさす場合も有る。
貴族や農民と区別して使われた。
❒概要
この「市民」には、封建・絶対主義から解放され、自立した個人という意味および商人・資本家という意味を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。
一方で、この二義性は表裏一体をなす。すなわち、革命をなすための市民社会の形成には資本主義の発達が不可欠であり、私的所有の絶対を原則とする資本主義社会の成立が必要だったのである。
ロシア革命もこれに分類されることがある。
市民革命は、また、資本主義社会から社会主義・共産主義社会の実現をめざしたプロレタリア革命とは性格を異にする。
1848年革命、パリ・コミューンなどは一般的にプロレタリア革命に類される。
短かくブルジョワ(仏: bourgeois)ともいうが、これは単数形で個人を指す。
20世紀の共産主義思想の下で産業資本家を指す言葉に転化し、共産主義者の間では概ね蔑称として用いられたが、この資本家階級という意味では上層ブルジョワジーのみをさしている。
❒歴史
中世
古代から中世にかけての経済的な低迷が終わると中世都市に商工業を生業とするものが集まり始めた。
フランス語ではこうした中世都市の「城壁の中の住民」をさして貴族でも農民でもない存在を「ブルジョワジー」と呼んだ。これがブルジョワジーの語源で、後期ラテン語 burgus(ギリシア語 pygros、ゲルマン語 burg)から派生しできた言葉である。
近世
近世になると大航海時代の幕開きにより、港湾都市では交易によって富を蓄積する者が現れ始めた。
また絶対主義の時代には、中央集権化により特に首都が経済的な中心となり、ここにも富を蓄積するものが現れ始めた。近世における「重商政策」は彼らの成長を積極的に後押しした。
彼らが市民革命前夜における「ブルジョワジー」である。当時の権力主体であった貴族階級、聖職者と都市の労働者、民衆、農民との間に位置付けられる、都市の裕福な商人を指してブルジョワジーというようになった。
ブルジョワジーの中には巨万の富を蓄え、貴族に仲間入りするものや貴族に準ずる待遇を受けるものも現れ、新たな支配階級を形成しつつあった。
ここでブルジョワジーと呼ばれた人々は、市民革命の主体となり、それまでの貴族や聖職者が主体であった体制を革命によって転覆させた。
そのため市民革命をさして「ブルジョワ革命」とも言う。
この場合の「市民」とは「ブルジョワジー」のことで現在の「市民」という概念とは異なっている。
現在の「市民」という概念に近い言葉としてシトワイアン (Citoyen) があった。
産業革命以降
市民革命によって政治的な参加権を得たブルジョワジーの中には同時に進行していた産業革命と結びついて「産業資本家」になる者が現れた。
これによってブルジョワジーは19世紀中頃から資産階級を指す、そして貴族に代わる新たな支配階級を指す言葉として転化した(中華人民共和国では現代中国語でブルジョワジーを「資産階級」としている)。
支配階級に反抗する社会主義者から見た場合、「ブルジョワジー」、「ブルジョワ」、「ブルジョワ階級」という言葉そのものが蔑称となり、物理的に排除すべき対象となった。
これにより、かつては貴族の富裕さ、贅沢さを批判するために用いられていた「ブルジョワ」という概念は、今度は自らが富裕さ、贅沢さを批判されるために用いられることとなった。
そして、かつて貴族が敵視され、市民革命によって打倒されたように、20世紀においてはブルジョワが敵視され、社会主義革命によって打倒されるようになった。
だが、ブルジョワを打倒した社会主義体制においても、ノーメンクラトゥーラや太子党といった新たな支配階級が台頭し、その富裕さ、贅沢さが批判されるようになった。
その社会主義体制国家が再び資本主義体制に移行した21世紀現在、グローバリゼーションによって、世界全域でいわゆる「新富裕層」が台頭して新たな支配階級となり、その国の枠をも超える富裕さ、贅沢さが批判されている。
関連項目 ー フランス革命 ー
フランス革命
(仏: Révolution française)
(英: French Revolution )
フランス王国で1789年7月14日から1795年8月22日にかけて起きたブルジョア革命。
フランス革命記念日(パリ祭)はフランス共和国の建国記念日でもあり、毎年7月14日に祝われている。
フランス革命を代表とするブルジョア革命は、封建的な残留物(身分制や領主制)を一掃し、
・資本主義の発展(法の下の平等・経済的自由・自由な私的所有など)
・資本主義憲法の確立(人民主権・権力分立・自由権(経済的自由権)等の人権保障を中心とする原理、典型例としてフランス憲法) を成し遂げた。
フランス革命はアメリカ独立革命とともに、ブルジョア革命の典型的事例である。
フランスでは旧支配者(宗教家・君主・貴族)の抵抗がきわめて激しかったため、諸々の階級の対立・闘争がもっとも表面化した。
❒概要
フランス革命とは、フランスにおいて領地所有の上に立つ貴族と高級聖職者が権力を独占していた状況が破壊され、ブルジョワジーと呼ばれる商工業、金融業の上に立つ者が権力を握った変化をいう。
ブルジョワジーは権力を握ったが、貴族を排除することなく一部の貴族とは連立を続けた。
フランス革命は貴族と上層市民を対等の地位にした。
フランス革命以前は国王がフランスの5分の1の領土を持つ最大領主だった。
その国王のまわりで権力を組織していた宮廷貴族は国王に次ぐ大領主であり、減免税特権の最大の受益者であった。
財政支出の中から宮廷貴族の有力者は、巨額の国家資金を様々な名目で手に入れた。
しかし、ある段階で国家財政が破綻し、もはや支払うべき財政資金がなくなった。
権力を握っていた宮廷貴族は自分の減免税特権を温存し、ブルジョワジー以下の国民各層に対して負担をかぶせようとした。
そこで「権力を取らないことには自分たちの破滅につながる」と感じた商工業者や金融業者が、国民の様々な階層を反乱に駆り立てて、領主の組織する権力を打ち破った。
1789年7月14日のバスチーユ占領がその始まりとなった。
この時点では上層銀行家と株式仲買人を中核とする金融業者の一団が、雑多な群衆を反乱に向けて組織した。
さらにパリ駐屯のフランス衛兵が反乱を起こし、国王軍と群衆の衝突の中で、国王軍を敗北させた。
この軍の反乱には下士官を構成する下級貴族の役割が大きかった。
この革命によって宮廷貴族の減免税特権は廃止され家柄万能の時代は終わり、フランスの近代化が始まった。
❒革命以前の絶対主義
▼宮廷貴族の特権
フランス革命で倒された旧体制はアンシャン・レジームと呼ばれ、日本では絶対主義と呼ばれている。
この言葉は中世の封建制度[注 1]に比べると国王の権力が強まり、国王の絶対的権威は王権神授説によって理論化されていた。
「朕は国家なり」という言葉がその本質を表している。
フランス絶対主義はルイ13世の時代にリシュリュー宰相(枢機卿、公爵)によって確立され、ルイ16世の時代に終わった。
しかし、絶対主義という言葉で呼ばれているにもかかわらず、必ずしも国王個人が絶対的な権力を持っていたわけではなかった。
国王はフランスの領土の5分の1を持ち、最大の領主であったが、あくまで領主の一人にとどまり、最大の領主であったというだけであった。
絶対王政の期間では国王が権力を行使できない場合も多く、国王を立てて絶対的な権力を行使したのは、リシュリューやマザランなどの一群の大領主であった。
この時代に王権を動かしていた大領主の一団は宮廷貴族と呼ばれ、約4000家あった。
宮廷貴族の地位は家柄で決まっていて、宮廷貴族の上層は家柄の力で高級官僚に若いころから任命された。
これらの西洋の領主・騎士階級を日本語では通常「貴族」と呼んでいるが、実態は平安時代の「貴族(公家・公卿)」よりも江戸時代の「武士(大名・旗本等)」に近いものであり、「貴族」というよりは「西洋の武士階級」とすべきものである。
当時の宮廷貴族に要求される能力は、宮廷の作法、剣の操法、宮廷ダンスの技術、貴婦人の扱い方であり、学問とか、経済運営の能力は次元の低いものとみられていた。
宮廷貴族の大多数は大蔵大臣の仕事に向かない者が多かったため、有力宮廷貴族がパトロンとなって能力のある者を大蔵大臣として送り込み、その代わりに自分の要望通りの政治を行わせた。
これらの宮廷貴族がベルサイユに集まって、王の宮殿に出入りしていた。
宮廷貴族は収入を得るために高級官職を独占していた。
当時の官職収入は桁違いに大きく、正規の俸給よりも役得や職権乱用からあがる収入の方が多かった。
これらの役得は当然の権利とされていた。
このため4000家の宮廷貴族はその大小の官職によって国家財政の大半を懐に入れていた。
これらの官職の中には無用な官職も多く、たとえば、王の部屋に仕える小姓の官職だけに8万リーブル(約8億円)[注 6]が支払われていた。その高い俸給と副収入が貴族の収入となっていた。
また、国家予算の十分の一を占める年金支払いは、退職した兵士や将校にも支払われていたが、その年金額には大きな格差があり、退職した大臣や元帥といった宮廷貴族には巨額の年金が支払われた。
さらに王が個人的に使用できる秘密の予算もあり「赤帳簿」と呼ばれた。宮廷貴族は夫人を使って大臣、王妃、国王のところにいろいろな理由を付けて金を取りに行かせた。
これらは宮廷貴族による国庫略奪であった。
フランス革命は国庫の破綻を引き金にして引き起こされた。
国庫の赤字を作り出したものはこのような宮廷貴族の国庫略奪であった。ところが、このような不合理な支出が当時の宮廷貴族にとっては正当な権利と思われていた。
その権力を守るために宮廷貴族たちは行政、軍事を含めた国家権力の上層部分を残らず押さえていた。
宮廷貴族から見ると国家財政を健全化するために無駄な出費を削ろうとする行為は、宮廷貴族の誰かの収入を削ることになり、その権利を取り上げることは悪政と見えた。
この場合国王個人や少数の改革派の意志は問題にならず、宮廷貴族の集団的な利益が問題となった。
このように宮廷貴族は当時のフランス最強の集団であり、革命無しにはこれらの宮廷貴族の特権を奪うことはできなかった。
▼法服貴族
宮廷貴族は行政と軍事の実権を握っていたが、司法権は法服貴族に明け渡していた。法服貴族の中心は各地の高等法院(パルルマン)であり、パリ高等法院が最も強力であった。
法律に相当するものは王の勅令として出され、これをパリ高等法院が登録することで効力が発生した。
しかし国王の命令はほとんどの場合絶対であり、ときどき高等法院が抵抗運動を起こして王の命令を拒否したり、修正したりすることに成功しただけであった。
そのため立法権は宮廷貴族を含めた王権に属していた。
法服貴族の官職は官職売買の制度によって買い取らなければならず、売買代金を王が手に入れた。
彼らのほとんどはブルジョアジーの上層から来た。司法官の職を買い入れると同時に領地も買い入れ、貴族の資格を買った。
法服貴族は宮廷貴族に比べると特権階級ではなく、領地の経営と官職収入で財産を作った。彼らは支配者の中の野党的存在であった。
▼自由主義貴族
宮廷貴族の中にはオルレアン公爵ルイ・フィリップ、ラファイエット侯爵など反体制派の一派がいた。
彼らは宮廷内部の権力争奪戦で敗者になり、日陰の存在であった。
そのため進歩的な発言をするようになった。彼らの大多数は官職収入の比重が少なく、自分の領地からの収入の比重が多かった。
このため王に頼るところが少なかったため、王に服従せず自由主義派になった。
彼らは宮廷貴族の反主流派だった。
▼ブルジョアジー
フランス絶対主義下では商業貴族と呼ばれた貴族の一団があった。
これらは商業や工業を経営して成功し、貴族に列せられた者たちでブルジョア貴族と呼べる者たちであった。
この商業貴族にはせいぜい減免税の特権しかなかったが、商人や工業家にとっては社会的な名誉であった。国王は商工業を振興するという建前から、王権の側はこれに対していろいろな政策をとった。
商業貴族は「貴族に列っせられた者」と呼ばれ貴族社会では成り上がり者と見なされた。
しかし貧乏な地方貴族よりは、はるかに経済力があった。
これらの商業貴族の多くは地方行政の高級官僚となっていた。
ブルジョアジーには徴税請負人という一団も存在した。
フランス王国では間接税の徴収を徴税請負人に任せた。
その徴税の仕方は極めて厳しかった[注 11]ので、小市民から大商人に至るまで恨みをかっていた。
徴税請負人は封建制度への寄生的性格の最も強い存在であった。
徴税請負人は工業、商業の経営や技術の進歩に大きな役割を果たしたものが多かったので、本来はブルジョアジーに属する。
しかし、王権の手先として商業そのものを抑圧する立場にもあった。
そこで商人が徴税請負人を敵と見なすことが多かった。
徴税請負人は国家と直接契約することはできず、一人の貴族が代表して政府と契約した。
貴族はその報酬として年金を受け取った。
すべては貴族の名において行われ、徴税組合には貴族が寄生していた。
銀行家や商人、工業家たちは当時のフランスではブルジョアジーと呼ばれたが、上層ブルジョアジーに属する者には貴族に匹敵する個人財産を持つ者も現れた。
しかし彼らはいろいろな方法で宮廷貴族に利益の一部を吸い取られ、国王政府の食い物にされた。
ブルジョアジーは宮廷貴族の被支配者であった。
▼領主の土地支配
フランス絶対主義の時代には貴族や高級僧侶は領地のほとんどを持ち、経済的に強力な基礎を持っていた。
全国の土地が大小様々な領地に分かれていて、領地は直轄地と保有地に分けられ、直轄地は領主の城や館を取り巻いていた。
それ以外の土地は保有地として農民や商人、工業家、銀行家などに貸し与えた。それらの土地の保有者は領主に貢租を支払った。
その土地を売買するときは領主の許可が必要で、許可料を不動産売買税として支払わなければならなかった。
ブルジョアジーの中には農村に土地を保有して地主となった者もいたが、この場合も領主権に服し、貢租を領主に支払っていた。
農民で領主であった者は一人もいなかった。
農民やブルジョア地主は領主に貢租を支払いながら、国王には租税を払うという二重取りにあっていた。
▼身分制度
絶対主義下では、国民は3つの身分に分けられており、第一身分である聖職者が14万人、第二身分である貴族が40万人、第三身分である平民が2,600万人いた。
第一身分と第二身分には年金支給と免税特権が認められていた。
❒フランス革命前夜
▼国家財政の悪化
ルイ14世の晩年以来フランスの国家財政は苦しくなり、立て直しの試みも成功せず、ルイ16世の時代になって財政は完全に行き詰まり、1780年代時点の財政赤字は45億リーブル(2017年時点の日本円で54兆円相当)にまで膨張していた。
しかしルイ16世が任命した蔵相たちは宮廷貴族に十分な課税をせず、国家の資金を惜しげも無く与えた。
財政困難が深刻になり宮廷が万策尽きた結果、国王はテュルゴーやネッケル等の改革派を蔵相に任命せざるを得なくなった。
彼らは宮廷貴族などの特権身分に対して課税などの財政改革を進めようとしたが、宮廷貴族などの特権身分たちはこれに反対して、その改革を失敗させた。
宮廷貴族たちは宮廷の官職、軍隊の高級将校、将軍、元帥、行政上の高級官職を握っていた。彼らの圧力を受けて改革派大臣は追放されることが繰り返された。
▼ブリエンヌの弾圧と抵抗運動
1787年4月に財政はブリエンヌ伯爵[注 16]に任された。
彼は終身年金の創設による借款を行い、続いて土地税の代わりに印紙税を提案した。
印紙税は貴族よりブルジョワジーに対して負担が重い税だった。
パリ高等法院は印紙税の導入に反対した。ブリエンヌは国家破産に直面して4億2000万リーブルの公債増発を発表した。このときオルレアン公が、公債発行を不法だとして抗議し、国王と対立し、オルレアン公はパリから追放された。高等法院はこれに対して国王に抗議行動を起こした。
王権の側は高等法院を抑圧し、法服貴族から司法権を取り上げ、全権裁判所を新設した。
この措置は全国的な動揺をひきおこし、オルレアン公に代表される自由主義貴族の反対運動はブルジョアジーや下層市民も引き入れていった。
全国的な反対運動のために増税は成功せず、公債を買い入れる者もいなくなった。
1788年8月の初めにブリエンヌは「国庫は空になるだろう」という報告を受けた。
8月16日にブリエンヌは、現金支払いは一部だけとして、その他を国庫証券で支払うと命令した。
この命令はブルジョアジーに恐慌状態を引き起こした。
ブリエンヌはさらにケース・デスコント (fr:Caisse d'escompte)紙幣の強制流通を命じた。この結果パリでは紙幣と現金の交換を求めて取り付け騒ぎが起こった。
国庫には50万リーブルしか残らず、ブリエンヌは辞任させられた。
国王は平民の銀行家ネッケルを呼び戻して財務総督にするしかなかった。パリ高等法院は、全国三部会のみが課税の賛否を決める権利があると主張して、第三身分の広い範囲から支持を受けた。
ネッケルは三部会招集を条件として出し、国王は1789年5月1日に招集すると約束した。
これらの運動は宮廷内で冷遇されていた野党的貴族とブルジョワジー以下が合流して宮廷貴族の本流に対して反抗したものだった。
▼三部会の招集
1788年7月25日パリ高等法院は採決を身分制で行うべきだと声明を出した。
これでは第三身分が少数派になってしまうことになり、第三身分は高等法院を裏切り者として攻撃した。
高等法院は譲歩して12月5日に第三身分の代表者数の倍加を認め、第三身分と高等法院の決裂は回避された。
ネッケルは第三身分の倍加を主張し、ネッケル派の大臣も賛成した。
国王と王妃も承認せざるを得なくなった。1789年1月24日に三部会の招集と選挙規則が公布された。
各地で選挙が行われて議員が選出され、1789年5月5日、ヴェルサイユに招集された。
第一身分(僧侶)が300人、第二身分(貴族)が270人、第三身分(平民)が600人で半分が法律家で、大部分がブルジョアジーだった。
国王は開会式で三部会を独立した権力機関ではなく、国王の命令の下に財政は赤字解消に努力するものとしか言わなかった。
三部会が始まると議決方法を身分ごとにするか、人数別採決にするかで紛糾し、1ヶ月の時間が過ぎていった。
また議員の俸給一人800リーブルも財政赤字で4ヶ月支払われなかった。
❒革命の開始
▼国民議会の結成
第三身分は1789年6月18日に自分自身の名を国民議会と呼ぶことに決定した。
国民議会の権限について議決を行い、国王には国民議会の決定にいかなる拒否権もないこと、国民議会を否定する行政権力は無いこと、国民議会の承認しない租税徴収は不法であること、いかなる新税も国民議会の承認無しには不法であることを決定した。
さらに、ブルジョアジーの破産を救うべく「国債の安全」の宣言も決議された。
絶対主義の王権は破産に直面すると公債を切り捨てて、国庫への債権者を踏みにじって危機を乗り越えてきた。
これに歯止めをかける決議は、王権にとって致命的だった。
このような第三身分の動きに僧侶部会が影響を受け、多くの司祭と少数の司教が第三身分へ合流した。
貴族部会の大多数は第三身分の行動に反対した。
1789年6月20日に国王は国民議会の会場を兵士によって閉鎖するよう命令し、国民議会の集会を禁止し、国王が改めて三部会を招集するという命令を伝えた。
▼テニスコートの誓い
国民議会の議長バイイはこれに抗議して隣接する球技場になだれこみ、国王の命令に反して決議を行った。
「国民議会は憲法が制定され、それが堅固な土台の上に確立するまで決して解散しないことを誓う」ことが決められた。
これがのちに「テニスコートの誓い」と呼ばれるようになった。
6月23日に三部会が招集されたが、4000人の軍隊が出撃の準備を整えていた。
国王ルイ16世は高級貴族と近衛兵に囲まれて議場に入場すると「国王の承認しない議案は一切無効である」と宣言した。
そして身分別に議決を行うことを命令し、貴族の政治的特権と減免税特権は尊重し、維持すること、封建的特権は財産として尊重することなどを宣言した。
これによって国王と国民会議は全面的対決となった。
国王が退出すると三部会は解散の命令を受けた。
▼国民議会との対立
宮廷貴族は御前会議で三部会の解散、10億リーブルの強制借款とロレーヌをオーストリアに600万リーブルで売却することなどを決めた。
強制借款は特権身分に課税する代わりに、強制的に国民から金を借り上げようとする政策だった。
この場合、強制的に大金を政府に貸すことを強要されるのは、大商人、銀行家、金融業者、大工業家であった。このような借り上げでは返還の当てもなく、事実上の没収になってしまう。
ブルジョアジーを破産させる政策であり、三部会解散は国民議会の権力を否定し国王と貴族の絶対主義的権力を再確認する政策だった。
こうしたうわさがパリに流れると、ますます反抗的な気運が高まった。
7月11日に国王と宮廷貴族はネッケルとネッケル派の大臣を罷免した。
代わって宮廷貴族の強硬派が大臣を固めた。ブローイ公爵(元帥)が総司令官兼陸軍大臣となり、ベルサイユ宮殿を野営地に変えて、パリで暴動が起こったときの戦略として、パリ全部を守ることは不可能であるから、株式取引所と国庫とバスチーユ、廃兵院を守るにとどめることが指示された。
これはパリ市民との軍事衝突の際に国家財政の実権だけは確保するために必要な戦略であった。
▼バスティーユ監獄の占領
国民議会は軍隊の撤退を要求したが、国王は外出と集会の禁止令を出した。
オルレアン公爵の私邸パレ・ロワイヤルには王の布告を無視して大群衆が集まった。
7月12日軍隊がパリに向けて出撃を始めた。パレ・ロワイヤルでは「武器を取れ、市民よ」という演説がされ、6000人の群衆が軍隊と衝突した。
すでに軍隊では給料支払いが遅れていて、近衛兵すら不満を口にし、将校の命令に従わなくなっていた。
軍隊の中に王権に抵抗するための秘密クラブも作られた。
7月14日に再び軍隊が出動すると群衆がフランス衛兵と共に廃兵院に押しかけ、3万丁の小銃を奪ってバスティーユ要塞監獄に向かった。
群衆が占領したバスティーユに政治犯はいなかったが、要塞は大砲をのぞかせて周囲の脅威となっていたことと、武器弾薬庫を抱えていたので重要な戦略目標だった。
国王の軍隊はパリ全体で敗北し、地方都市でも国王の軍隊は敗北し、各地方で軍隊の反乱が起こった。
国王の側はこれ以上の軍事行動ができなくなった。
ブローイ元帥は反撃の機会をうかがうべきであると説いたが、すでに軍隊と共に移動する資金も食料もなかった。そこで国王は泣いて屈服した。
国王ルイ16世は譲歩することを決心し軍隊を引いて国民会議に出席し「朕は国民と共にある」と言い和解を宣言した。
軍事行動を指揮した宮廷貴族たちは群衆に処刑された。
有力な宮廷貴族たちは逃亡し、国王だけが第三身分の捕虜同然の身としてフランスにとどまった。
この勝利で権力を握ったのは最上層のブルジョアで、経済活動で最強の力を持つ者だった。
その中には貴族の資格や領地を持つ者も多かった。
これらの上層ブルジョアジーたちは士気が乱れていた兵士たちに積極的に働きかけて買収して、ブルジョアジーの軍隊に仕立て上げていた。
兵士の反乱は自然発生的に起こったのではなかった。
この時生まれた革命のスローガンは「自由・平等・財産」だった。
▼革命による財政改革
国王軍に勝利した商工業者(ブルジョアジー)の上層は、自由主義貴族と連携しながら権力の指導権を握った[71]。これ以降の政権はブルジョアジーの上層が租税徴収権を握り、財政改革を行った。
宮廷貴族に負担をかぶせ、徴税を実行し、宮廷貴族に対してなされていた財政資金を削減か打ち切り、それによって浮いた財源で商工業、金融業の救済・発展のために支出した。
❒明治維新との共通点
歴史学者の小林良彰は明治維新とフランス革命の構造が同じであると主張した。
1.フランス革命では領主の組織した権力は破壊され、商工業、金融業の上に立つ者が権力の指導権を握った。
江戸時代は領主が権力を組織していたこと、明治維新以後、商工業、金融業の上に立つ者が権力を握ったということが確認される。
この点でフランス革命と明治維新は基本的に同一の変化を引き起こした。
2.フランス革命も明治維新も市民革命である。「領主の権力からブルジョアジーの権力へ」これが市民革命の定理である。
3.どちらも財政問題が基本的原因になった。フランスの宮廷貴族は巨額の国家資金を様々な名目で手に入れ、財政破綻を引き起こした。
江戸幕府財政は大名をはじめとする領主が租税を負担せず、幕府財政資金から老中以下の幕府官僚が様々な名目で国家資金を引き出していた。
これが幕府の金庫を空にした。
4.国庫が空になると大名や宮廷貴族などの特権階級に負担させるのではなく、商人に対する幕府御用金の増加やブルジョアジーからの強制借り入れで負担をかぶせた。
その時江戸時代末期において、関ヶ原の戦い以来冷遇されていた薩長両藩と商人層の主流が結びつき、討幕派を援助しながら主導権を握っていった。
フランスでも自由主義貴族とブルジョアジーが反乱を組織した。
権力の変化と財政問題の絡み合いが日仏両国で、明治維新とフランス革命が同じ変化を持つ変革であると規定できる。
❒革命思想・制度
▼キリスト教との関係
1790年8月3日、政府はユダヤ人の権利を全面的に認めた。
1792年5月から1794年10月まで、キリスト教は徹底的に弾圧された。
当時カトリック教会の聖職者は特権階級に属していた。
革命勃発以来、聖職者追放と教会への略奪・破壊がなされ、1793年11月には全国レベルでミサの禁止と教会の閉鎖が実施され、祭具類がことごとく没収されて造幣局に集められ、溶かされた。こうして、クリュニー修道院やサント=ジュヌヴィエーヴ修道院などの由緒ある教会・修道院が破壊されるとともに、蔵書などの貴重な文化遺産が失われた。
破壊を免れた教会や修道院も、モン・サン=ミシェル修道院のように、牢獄や倉庫、工場などに転用された。
エベールらは「理性」を神聖視し、これを神として「理性の祭典」を挙行した。ロベスピエールは、キリスト教に代わる崇拝の対象が必要と考え、「最高存在の祭典」を開催した。
しかし、ロベスピエールが処刑され、一度きりに終わり定着しなかった。
その後もカトリック教会への迫害はしばらく続いたものの、1801年にナポレオンがローマ教皇とコンコルダートを結んで和解した。
なお、このような経緯を経たが、「革命は宗教を否定するものではない」とする主張もある。
▼メートル法
当時のフランスでは度量衡が統一されていなかったが、単位制度として1791年にメートル法が定められた。
メートル法は定着までには時間を要したが、今日では国際単位系として世界における標準的な単位系となっている。
▼貴族制について
革命によって貴族が一掃されたわけではなく、貴族たちの中にも革命側に加わった者や、一旦は亡命したもののナポレオン時代以後にフランスに復帰した貴族も多い。
▼奴隷制について
人権宣言が発せられた際に、すべての人間にとって普遍的で権利であるはずの人権は、啓蒙思想などによって「理性を持たない半人間」とされたフランスの植民地に住むムラート(白人と黒人の混血)や黒人(そしてインディアン、インディオ)には認められず、1791年にブークマンに率いられた黒人奴隷が大反乱を起こすまで奴隷制についての真剣な努力はなされなかった。
1793年のレジェ=フェリシテ・ソントナ(フランス語版)による奴隷制廃止宣言や、1794年のジャコバン派による正式な奴隷制廃止決議は、1791年に始まったサン=ドマングの黒人大反乱による植民地喪失の危機から植民地を防衛するためになされたものであり、決して人権宣言の理念に直接基づいてなされたものではなかったが、それでもジャコバン派による植民地をも包括した全面的な奴隷制廃止は近代西欧世界史上初となる画期的なものであった。
この後、ナポレオン・ボナパルトはトゥーサン・ルーヴェルチュールが実権を掌握していたサン=ドマングの再征服を計画し、奴隷制の復活を画策したが、解放された黒人の支持を得られなかったため、サン=ドマングは1804年1月1日に世界初の黒人共和国ハイチとして独立を達成した(ハイチ革命)。
この結果として、ハイチ革命後のフランス人の頭の中では、奴隷制の廃止が植民地の喪失とイコールで結ばれることになり、のちのフランスにおける奴隷制は1848年に第二共和政下でヴィクトル・シュルシェールが廃止を実現するまで続くことになった。
〔ウィキペディアより引用〕



















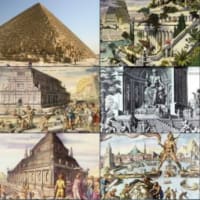

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます