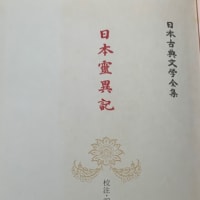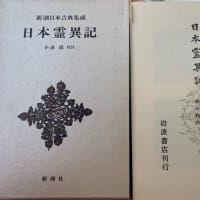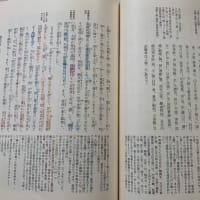昨日の続きです。
今回、こちらを参拝するまで、
鷲子山上神社を知りませんでした。
言い忘れていましたが
鷲子山上神社 わしこさんしょうじんじゃ
と読みます。
那須に行くまでの道すがらで行ったことのない
神社に行きたいな、と思ってお参りしました。
でも、行ってみたら、不思議がいっぱいです。
まず、御祭神です。
鷲子山上神社の御本殿には
天日鷲命 あめのひわしのみこと
大己貴命 おおなむちのみこと
少彦名命 すくなひこなのみこと
の三柱がお祀りされているそうです。
ただ、ホームページによると
大己貴命、少彦名命を
お祀りするようになったのは
天日鷲命をお祀りしたあとだそうですので
こちらの神社の主祭神は
天日鷲命と考えてよいようです。
大己貴命や少彦名命は古事記にも登場する
神様ですが、
天日鷲命は日本書紀と古語拾遺(こごしゅうい)
にお名前のある神様です。
古事記、日本書紀は奈良朝廷が作った資料ですが
古語拾遺というのは斎部氏(いんべし)の
作成した資料です。
古事記、日本書紀を公的資料と見るなら
古語拾遺は民間の資料といえますかね。
古語拾遺の成立は大同2年です。
お!
鷲子山上神社の開山も大同2年とありました!
ふーむ、む、む。
忌部氏は斎部氏とも表記します。
古語拾遺の編纂者は斎部広成です。
忌部氏は奈良時代以降、藤原、中臣氏の勢力に
圧されて、祭祀を掌る官職に就くことが
難しくなっていました。
このままではイカン!と忌部氏が祭祀を行う
由緒ある氏族として、自らの正統性や根拠を
説く古語拾遺を広成が作成した、
と、古語拾遺の編纂事情については
概ねこのように言われています。
開山したのは大蔵坊宝珠上人という方でしたが
この方については、よくわかりません。
神社のホームページには
お上人が諸国遍歴の中、四国の阿波より
紙漉きの技術と守護神の天日鷲命を勧請し
鷲子山に社殿を建立した、とあるのみです。
この大蔵坊宝珠上人という方が
忌部氏の出身か、忌部氏に関係する人
ということなら、わかりやすいですが…
ホームページの書き振りだと
お上人は阿波に行くまで、天日鷲命をご存知なく
そこで初めて出会ったみたいな記述なので、
もともとの忌部の縁者はどうも考え難いです。
今となっては、那珂川町が
製紙業や織物業が盛んな土地だった
みたいな様子は見当たらないんですけど…?
平安の頃は違ったんでしょうかね??
だいたい、大蔵坊宝珠上人という
名前も、なんだかなぁと思います。
大蔵
平安の大同年間に、
上人という呼称があったのか?と思います。
神社の由来や御祭神などをみると、
どうしてここに?
とか
なぜこの神様が?
どういう繋がりで??
みたいなことが、よくあります。
でも、当時にしたら、必然、当然の理由が
何かしらあったんだろうと思います。
そういうことを考えり、想像したり
片鱗を見つけたりすることも
神社をお参りした時の楽しみでもあります。
ここの鷲子山上神社も、
えーなんで?!が
いっぱいで、想像することがたくさんあって
とても面白い神社です。
神社の入り口には神社のご由緒などの
案内板があります。

全然知らずにお参りするのと
ご由緒やご祭神を知ってからお参りするのとでは
やはりちょっと違うかな、と思います!
今回、こちらを参拝するまで、
鷲子山上神社を知りませんでした。
言い忘れていましたが
鷲子山上神社 わしこさんしょうじんじゃ
と読みます。
那須に行くまでの道すがらで行ったことのない
神社に行きたいな、と思ってお参りしました。
でも、行ってみたら、不思議がいっぱいです。
まず、御祭神です。
鷲子山上神社の御本殿には
天日鷲命 あめのひわしのみこと
大己貴命 おおなむちのみこと
少彦名命 すくなひこなのみこと
の三柱がお祀りされているそうです。
ただ、ホームページによると
大己貴命、少彦名命を
お祀りするようになったのは
天日鷲命をお祀りしたあとだそうですので
こちらの神社の主祭神は
天日鷲命と考えてよいようです。
大己貴命や少彦名命は古事記にも登場する
神様ですが、
天日鷲命は日本書紀と古語拾遺(こごしゅうい)
にお名前のある神様です。
古事記、日本書紀は奈良朝廷が作った資料ですが
古語拾遺というのは斎部氏(いんべし)の
作成した資料です。
古事記、日本書紀を公的資料と見るなら
古語拾遺は民間の資料といえますかね。
古語拾遺の成立は大同2年です。
お!
鷲子山上神社の開山も大同2年とありました!
ふーむ、む、む。
忌部氏は斎部氏とも表記します。
古語拾遺の編纂者は斎部広成です。
忌部氏は奈良時代以降、藤原、中臣氏の勢力に
圧されて、祭祀を掌る官職に就くことが
難しくなっていました。
このままではイカン!と忌部氏が祭祀を行う
由緒ある氏族として、自らの正統性や根拠を
説く古語拾遺を広成が作成した、
と、古語拾遺の編纂事情については
概ねこのように言われています。
開山したのは大蔵坊宝珠上人という方でしたが
この方については、よくわかりません。
神社のホームページには
お上人が諸国遍歴の中、四国の阿波より
紙漉きの技術と守護神の天日鷲命を勧請し
鷲子山に社殿を建立した、とあるのみです。
この大蔵坊宝珠上人という方が
忌部氏の出身か、忌部氏に関係する人
ということなら、わかりやすいですが…
ホームページの書き振りだと
お上人は阿波に行くまで、天日鷲命をご存知なく
そこで初めて出会ったみたいな記述なので、
もともとの忌部の縁者はどうも考え難いです。
今となっては、那珂川町が
製紙業や織物業が盛んな土地だった
みたいな様子は見当たらないんですけど…?
平安の頃は違ったんでしょうかね??
だいたい、大蔵坊宝珠上人という
名前も、なんだかなぁと思います。
大蔵
平安の大同年間に、
上人という呼称があったのか?と思います。
神社の由来や御祭神などをみると、
どうしてここに?
とか
なぜこの神様が?
どういう繋がりで??
みたいなことが、よくあります。
でも、当時にしたら、必然、当然の理由が
何かしらあったんだろうと思います。
そういうことを考えり、想像したり
片鱗を見つけたりすることも
神社をお参りした時の楽しみでもあります。
ここの鷲子山上神社も、
えーなんで?!が
いっぱいで、想像することがたくさんあって
とても面白い神社です。
神社の入り口には神社のご由緒などの
案内板があります。

全然知らずにお参りするのと
ご由緒やご祭神を知ってからお参りするのとでは
やはりちょっと違うかな、と思います!