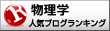背理法による私の論証は数学証明ではないと言うのかもね、だけど証明は証明であるw
1+1≠2を仮定してみたら(同義反復が出来ないとは)1+1≠2ならば1+1=2になって、それは1+1=2と同値、そしてそれは数学で否定されないから同義反復は不可能なんだよね。ここで使った排中律が論理学の物(否定されなければ肯定される)だから数学証明ではないというのかもしれませんが、それならこちらにはれっきとした言い分がございます!
ゲーデルの言う数学の不完全性というのは使われる排中律だけで決まっているのでは?
論理学では「偽でなければ真で真でなければ偽」とする完全排中律?ですけど、数学では(主として)「真ならば偽でないし偽ならば真でない」とする無矛盾排中律?を使います。前者では灰色命題があれば「真でも偽でもある」というように矛盾して、後者だと「真でも偽でもない」というように不完全です。はて論理学というのは「真でなければ偽」という後半部が無いのでそもそも排中律かどうかも怪しいですがw
ゲーデルはそのように論証してしまっているというのが現実ではなかったでしょうか?
とにかく数学や数学証明の範疇をゲーデル個人に決めつけられる覚えはないのです、私たちは数学に対する信頼を不完全性定理によって奪われる心配はございませぬ。数学では命題真偽が決定可能である限り、真命題は無矛盾であり偽命題は矛盾します。だから決定不能命題はゲーデル命題とは縁も所縁も無いことがこのようにして示されました・・。
(クルト=ゲーデル敗れたり、アメリカを母国として安らかに眠れ)
1+1≠2を仮定してみたら(同義反復が出来ないとは)1+1≠2ならば1+1=2になって、それは1+1=2と同値、そしてそれは数学で否定されないから同義反復は不可能なんだよね。ここで使った排中律が論理学の物(否定されなければ肯定される)だから数学証明ではないというのかもしれませんが、それならこちらにはれっきとした言い分がございます!
ゲーデルの言う数学の不完全性というのは使われる排中律だけで決まっているのでは?
論理学では「偽でなければ真で真でなければ偽」とする完全排中律?ですけど、数学では(主として)「真ならば偽でないし偽ならば真でない」とする無矛盾排中律?を使います。前者では灰色命題があれば「真でも偽でもある」というように矛盾して、後者だと「真でも偽でもない」というように不完全です。はて論理学というのは「真でなければ偽」という後半部が無いのでそもそも排中律かどうかも怪しいですがw
ゲーデルはそのように論証してしまっているというのが現実ではなかったでしょうか?
とにかく数学や数学証明の範疇をゲーデル個人に決めつけられる覚えはないのです、私たちは数学に対する信頼を不完全性定理によって奪われる心配はございませぬ。数学では命題真偽が決定可能である限り、真命題は無矛盾であり偽命題は矛盾します。だから決定不能命題はゲーデル命題とは縁も所縁も無いことがこのようにして示されました・・。
(クルト=ゲーデル敗れたり、アメリカを母国として安らかに眠れ)