
新日本フィルハーモニー交響楽団「トリフォニー・シリーズ」第465回定期演奏会
2010年7月30日(金)19:00~ すみだトリフォニーホール B席 3階 LB列 9番 5500円
指 揮: クリスティアン・アルミンク
ヴァイオリン: パトリツィア・コパチンスカヤ*
管弦楽: 新日本フィルハーモニー交響楽団
(コンサートマスター: 西江辰郎**)
【曲目】
リゲティ: ヴァイオリン協奏曲(1992)*
《アンコール》リゲティ: バラードとダンス(1950)* **
ホルヒェ サンチェス=チョング: クリン(1996)*
ヴェレッシュ: 哀歌~バルトークの思い出に(1945)《日本初演》
コダーイ: 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
覚えている方はどれくらいいるだろうか、ヴァイオリニストの庄司紗矢香さんが、大阪フィルハーモニー交響楽団(2009年5月)ならびにNHK交響楽団(同6月)との共演で、リゲティのヴァイオリン協奏曲の演奏が評価され、平成21年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した。何で今頃、庄司さんが「新人賞」なんだ? という疑問はさておき、コンサートには行かなかったが、NHKのテレビで放送があり、またドキュメンタリーでこの曲への取り組みについて取り上げていたので、視聴された方の多いだろう。ウワサに聞いていたリゲティのヴァイオリン協奏曲をその時初めて聴いて、衝撃的な印象を得た。馴染みにくい現代音楽であっても…どこかというか、かなり面白い。ぜひ、実演を聴きたいと思ったものである。そして、新日本フィルのプログラムのこの曲を見つけて(しかもコパチンスカヤさん!!)、ためらわずチケットを取ったのだが、時すでに遅し。ステージ近くは3階しかなかったのであった。
同時に曲目を見ればわかるように、オール・ハンガリー・プロ。しかも巨人バルトークの曲がなく、ヴェレッシュとコダーイ。ヴェレッシュに至っては日本初演。超マニアックなプログラムで期待感も高まる一方、ついて行けるかしらとかなり不安材料も…。
1曲目はリゲティ(1923~2006)のヴァイオリン協奏曲。この曲はオーケストラの構成からして特殊なので、ステージ上の椅子の配置さえ違っている。弦楽器はヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ2、コントラバス1と数が指定されていて、しかもヴァイオリンとヴィオラの各1が変則的な調弦(スコルダトゥーラというらしい)をする。しかも残りの3人ヴァイオリンもそれぞれ違ったパートを弾く。各ヴァイオリンの旋律がずれたり、音程がはずれたりと、ややこしいこと夥しい。木管楽器はリコーダーやオカリナに持ち替えたりする(これらの楽器はチューニングできない?)。
曲は1990年に初演された後、1992年に現在の形に改訂されたもの。いわゆる現代音楽のヴァイオリン協奏曲としては、最も成功したものとされ、演奏機会も多い(いや、滅多に演奏されない?)。5つの楽章から成る…といっても、形式はすでに破壊し尽くされているので、あまり意味をなさないかもしれない。そしてあまりに演奏が難しい、超難曲でもある。
第1楽章はソロ・ヴァイオリンとスコルダトゥーラのヴァイオリンとヴィオラが不思議な音響空間を紡いでいく。変則的にマリンバや打楽器がからみ、不協和、変拍子、旋律ともいえないような音の連続と重なりが続く。
第2楽章は、ソロ・ヴァイオリンに主題が明確に現れる緩徐楽章(?)のように始まり、オカリナなどが加わってくるあたりから、それぞれの楽器が一見してバラバラ勝手に演奏しているようでありながら、不協和な統一感があり、不思議なリズムが展開されていく。ソロ・ヴァイオリンも主題を演奏しつつも、ピチカートやミュートしたり、音色も多彩だ。
第3楽章は、さらに怪しげな曲想となり混沌としてくる。ソロ・ヴァイオリンが徐々に加熱してくる背景にはもオーケストラの各楽器がさらに複雑で混沌として旋律を個別に演奏するが、全体としては大きなうねりを形成し、曲の土台を作っている。
第4楽章は速度の遅い管楽器のパッサカリア(?)にソロ・ヴァイオリンの高音部だけの怪しげな主題が乗る。やがて弦楽や打楽器が変則的なリズムで加わってくると、オカリナやリコーダーを交えて、聴いたことがない音空間が展開してゆく。徐々に緊張が高まり、突然終わる。
第5楽章がこの曲の最も特徴的な曲想を見せる。弦4部が複雑にして変則的なリズムを刻む中、マリンバや打楽器が強烈なアクセントを付け、ソロ・ヴァイオリンは次々と現れる独奏的な旋律を、極度の緊張感の中で過激に刻んでゆく。やがて、超絶技巧を要求するカデンツァがあり、この曲のクライマックスを迎えると、マリンバと打楽器が鳴って唐突に曲が終わる。
ソリストとして迎えられたコパチンスカヤさんほど、この曲の演奏に適した人はいないのではないだろうか。演奏技術の正確さ完璧さを持ちつつも、アグレッシブで非常に発揮度が高い演奏をする。一旦演奏が始まると、何かに取り憑かれたように、極度の集中とパッションの迸りを見せる。それでいて、音が乱れることがなく、正確な音程と、キレイな音を出しているから不思議だ。要するに、恐ろしく個性派だが、好みの問題はともかくとして、素晴らしい演奏家であることは間違いない。
指揮のアルミンクさんも、さすがにこの手の曲の場合は、スコアとにらめっこするように、変則的なリズムと拍子を、しっかりと手を振ることで正確に指揮していた。
ナマで聴いてみて、改めて、これほど衝撃的な曲だったかと、感激を新たにした。聴き慣れていくうちに、曲の構造が意外としっかりしていることに気づいてくる。一見するとバラバラで訳の分からない曲に聞こえるのだが、一旦この構造感に気がつくと、意外にもスーっと曲が自然に耳に(脳に)入ってくるようになった。なるほど、20戦記後半の名ヴァイオリン協奏曲だというのが分かるような気がした(ホントかしら?)。
コパチンスカヤさんのアンコールは、やはりリゲティの作品で、2台のヴァイオリンのための『バラードとダンス」。1950年の作品ということなので、若い時の作品だ。コンサートマスターの西江辰郎さんとのデュオで、冷静な西尾さんに対してエキセントリックなコパチンスカヤさんが挑みかかるように弾いていた。鳴り止まない拍手に応えてアンコールの2曲目は、ホルヒェ サンチェス=チョングの「クリン」。こんな曲、誰も知らない(-。-;) キコキコ弦をこすって、踊りながら叫び声を上げていた(?)…もう、理解不能の世界だが、この人がやると何故か楽しい。会場、大喝采であった。
後半は、ステージ上を普通のオーケストラの編成にセットして…、と思ったら、指揮台の正面にツィンバロンなる楽器が置いてある。ハンガリーの民族楽器(?)で、チェンバロから鍵盤を取り外したような形をしていて、マリンバのバチのようなもので弦を直接叩いて演奏していた。
後半の1曲目は、ヴェレッシュ(1907~1992)の「哀歌~バルトークの思い出に」という曲で、1945年に亡くなった師にあたるバルトークを悼んで作曲されたものだという。ヴェレッシュはコダーイの教え子でもある。本日は、日本初演となる演奏に立ち会うことができて感激だ。14~5分の曲で、ハンガリーの民族楽器っぽい旋律(?)の哀調を帯びた現代曲で、打楽器も多用され、ppから始まり徐々に全体がクレッシェンドしていき、ffのクライマックスを経てppに戻っていく、葬送行進曲(らしい)。
2曲目はコダーイ(1882~1967)の「ハーリ・ヤーノシュ」。やっと何度か聴いたことがある曲が出てきた。前述のツィンバロンはこの曲で使用される。コダーイはバルトーク(1881~1945)と同世代の人で、フランツ・リスト音楽院などで共に民族音楽などを研究した同僚だった。「ハーリ・ヤーノシュ」はコダーイの作品としては最も有名な曲かもしれない。「ハーリ・ヤーノシュ」は音楽劇のための音楽でオペラとして上演されたこともあるらしいが、現在では6曲からなる組曲として演奏されることが多い。とはいっても、日本での演奏機会はあまり多くはなく、今回のようなハンガリーの現代音楽中心の企画プログラムならではの、採り上げ方だと思われる。いずれにしても実演を聴ける滅多にない機会だし、ツィンバロンの演奏を上から見下ろすことができ。貴重な体験となった(第3曲と第5曲に独奏的に登場)。あくまで何度か聴いたことがあるという程度しか知らないので、本日の演奏が良かったのか悪かったのか、見当が付かないが、ツィンバロンだけでなく、ビアノやチェレスタまでも加え、さらに多彩な打楽器群を駆使しての演奏には、見ていたもなかなか緊張感があって、素晴らしかったと思う。もとが音楽劇だけあって、劇的な盛り上がりを聴かせる部分では、フル・オーケストラの大音量が圧巻だった。このような曲をプログラムに採り上げ、本気で演奏してくれるアルミンクさんの情熱にBravo!!

サイン会のコパチンスカヤさんとアリスちゃん。右はアルミンクさん。
演奏会の後は、コパチンスカヤさんとアルミンクさんによるサイン会があった。コパチンスカヤさんはかわいらしい娘さんと一緒で、楽しそうだった。こうして見るとごく普通の人。演奏している時のエキセントリックな姿とは完全に別人だ。アルミンクさんもファンに日本語で挨拶しながら,丁寧に応対してくれる。新日本フィルは今後も聴く機会はあるだろうが、これまで聴いた感じでは、アルミンクさんが指揮するときは、すごくイイ感じだと思う。特に期待しているのは、来年(2011年)4月、新国立劇場のオペラ公演「ばらの騎士」で、アルミンクさん指揮の新日本フィルがピットに入ること。ウィーンの香りを是非聴かせていただきたいものである。
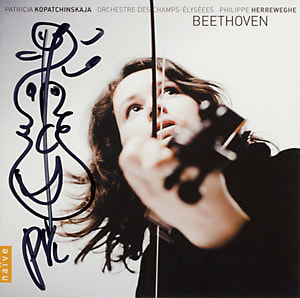
購入したベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のCDにサインしていただきました。

ついでに本日のプログラムにも。カラーページがなかったのが残念。
 ←読み終わりましたら,クリックお願いします。
←読み終わりましたら,クリックお願いします。
2010年7月30日(金)19:00~ すみだトリフォニーホール B席 3階 LB列 9番 5500円
指 揮: クリスティアン・アルミンク
ヴァイオリン: パトリツィア・コパチンスカヤ*
管弦楽: 新日本フィルハーモニー交響楽団
(コンサートマスター: 西江辰郎**)
【曲目】
リゲティ: ヴァイオリン協奏曲(1992)*
《アンコール》リゲティ: バラードとダンス(1950)* **
ホルヒェ サンチェス=チョング: クリン(1996)*
ヴェレッシュ: 哀歌~バルトークの思い出に(1945)《日本初演》
コダーイ: 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
覚えている方はどれくらいいるだろうか、ヴァイオリニストの庄司紗矢香さんが、大阪フィルハーモニー交響楽団(2009年5月)ならびにNHK交響楽団(同6月)との共演で、リゲティのヴァイオリン協奏曲の演奏が評価され、平成21年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した。何で今頃、庄司さんが「新人賞」なんだ? という疑問はさておき、コンサートには行かなかったが、NHKのテレビで放送があり、またドキュメンタリーでこの曲への取り組みについて取り上げていたので、視聴された方の多いだろう。ウワサに聞いていたリゲティのヴァイオリン協奏曲をその時初めて聴いて、衝撃的な印象を得た。馴染みにくい現代音楽であっても…どこかというか、かなり面白い。ぜひ、実演を聴きたいと思ったものである。そして、新日本フィルのプログラムのこの曲を見つけて(しかもコパチンスカヤさん!!)、ためらわずチケットを取ったのだが、時すでに遅し。ステージ近くは3階しかなかったのであった。
同時に曲目を見ればわかるように、オール・ハンガリー・プロ。しかも巨人バルトークの曲がなく、ヴェレッシュとコダーイ。ヴェレッシュに至っては日本初演。超マニアックなプログラムで期待感も高まる一方、ついて行けるかしらとかなり不安材料も…。
1曲目はリゲティ(1923~2006)のヴァイオリン協奏曲。この曲はオーケストラの構成からして特殊なので、ステージ上の椅子の配置さえ違っている。弦楽器はヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ2、コントラバス1と数が指定されていて、しかもヴァイオリンとヴィオラの各1が変則的な調弦(スコルダトゥーラというらしい)をする。しかも残りの3人ヴァイオリンもそれぞれ違ったパートを弾く。各ヴァイオリンの旋律がずれたり、音程がはずれたりと、ややこしいこと夥しい。木管楽器はリコーダーやオカリナに持ち替えたりする(これらの楽器はチューニングできない?)。
曲は1990年に初演された後、1992年に現在の形に改訂されたもの。いわゆる現代音楽のヴァイオリン協奏曲としては、最も成功したものとされ、演奏機会も多い(いや、滅多に演奏されない?)。5つの楽章から成る…といっても、形式はすでに破壊し尽くされているので、あまり意味をなさないかもしれない。そしてあまりに演奏が難しい、超難曲でもある。
第1楽章はソロ・ヴァイオリンとスコルダトゥーラのヴァイオリンとヴィオラが不思議な音響空間を紡いでいく。変則的にマリンバや打楽器がからみ、不協和、変拍子、旋律ともいえないような音の連続と重なりが続く。
第2楽章は、ソロ・ヴァイオリンに主題が明確に現れる緩徐楽章(?)のように始まり、オカリナなどが加わってくるあたりから、それぞれの楽器が一見してバラバラ勝手に演奏しているようでありながら、不協和な統一感があり、不思議なリズムが展開されていく。ソロ・ヴァイオリンも主題を演奏しつつも、ピチカートやミュートしたり、音色も多彩だ。
第3楽章は、さらに怪しげな曲想となり混沌としてくる。ソロ・ヴァイオリンが徐々に加熱してくる背景にはもオーケストラの各楽器がさらに複雑で混沌として旋律を個別に演奏するが、全体としては大きなうねりを形成し、曲の土台を作っている。
第4楽章は速度の遅い管楽器のパッサカリア(?)にソロ・ヴァイオリンの高音部だけの怪しげな主題が乗る。やがて弦楽や打楽器が変則的なリズムで加わってくると、オカリナやリコーダーを交えて、聴いたことがない音空間が展開してゆく。徐々に緊張が高まり、突然終わる。
第5楽章がこの曲の最も特徴的な曲想を見せる。弦4部が複雑にして変則的なリズムを刻む中、マリンバや打楽器が強烈なアクセントを付け、ソロ・ヴァイオリンは次々と現れる独奏的な旋律を、極度の緊張感の中で過激に刻んでゆく。やがて、超絶技巧を要求するカデンツァがあり、この曲のクライマックスを迎えると、マリンバと打楽器が鳴って唐突に曲が終わる。
ソリストとして迎えられたコパチンスカヤさんほど、この曲の演奏に適した人はいないのではないだろうか。演奏技術の正確さ完璧さを持ちつつも、アグレッシブで非常に発揮度が高い演奏をする。一旦演奏が始まると、何かに取り憑かれたように、極度の集中とパッションの迸りを見せる。それでいて、音が乱れることがなく、正確な音程と、キレイな音を出しているから不思議だ。要するに、恐ろしく個性派だが、好みの問題はともかくとして、素晴らしい演奏家であることは間違いない。
指揮のアルミンクさんも、さすがにこの手の曲の場合は、スコアとにらめっこするように、変則的なリズムと拍子を、しっかりと手を振ることで正確に指揮していた。
ナマで聴いてみて、改めて、これほど衝撃的な曲だったかと、感激を新たにした。聴き慣れていくうちに、曲の構造が意外としっかりしていることに気づいてくる。一見するとバラバラで訳の分からない曲に聞こえるのだが、一旦この構造感に気がつくと、意外にもスーっと曲が自然に耳に(脳に)入ってくるようになった。なるほど、20戦記後半の名ヴァイオリン協奏曲だというのが分かるような気がした(ホントかしら?)。
コパチンスカヤさんのアンコールは、やはりリゲティの作品で、2台のヴァイオリンのための『バラードとダンス」。1950年の作品ということなので、若い時の作品だ。コンサートマスターの西江辰郎さんとのデュオで、冷静な西尾さんに対してエキセントリックなコパチンスカヤさんが挑みかかるように弾いていた。鳴り止まない拍手に応えてアンコールの2曲目は、ホルヒェ サンチェス=チョングの「クリン」。こんな曲、誰も知らない(-。-;) キコキコ弦をこすって、踊りながら叫び声を上げていた(?)…もう、理解不能の世界だが、この人がやると何故か楽しい。会場、大喝采であった。
後半は、ステージ上を普通のオーケストラの編成にセットして…、と思ったら、指揮台の正面にツィンバロンなる楽器が置いてある。ハンガリーの民族楽器(?)で、チェンバロから鍵盤を取り外したような形をしていて、マリンバのバチのようなもので弦を直接叩いて演奏していた。
後半の1曲目は、ヴェレッシュ(1907~1992)の「哀歌~バルトークの思い出に」という曲で、1945年に亡くなった師にあたるバルトークを悼んで作曲されたものだという。ヴェレッシュはコダーイの教え子でもある。本日は、日本初演となる演奏に立ち会うことができて感激だ。14~5分の曲で、ハンガリーの民族楽器っぽい旋律(?)の哀調を帯びた現代曲で、打楽器も多用され、ppから始まり徐々に全体がクレッシェンドしていき、ffのクライマックスを経てppに戻っていく、葬送行進曲(らしい)。
2曲目はコダーイ(1882~1967)の「ハーリ・ヤーノシュ」。やっと何度か聴いたことがある曲が出てきた。前述のツィンバロンはこの曲で使用される。コダーイはバルトーク(1881~1945)と同世代の人で、フランツ・リスト音楽院などで共に民族音楽などを研究した同僚だった。「ハーリ・ヤーノシュ」はコダーイの作品としては最も有名な曲かもしれない。「ハーリ・ヤーノシュ」は音楽劇のための音楽でオペラとして上演されたこともあるらしいが、現在では6曲からなる組曲として演奏されることが多い。とはいっても、日本での演奏機会はあまり多くはなく、今回のようなハンガリーの現代音楽中心の企画プログラムならではの、採り上げ方だと思われる。いずれにしても実演を聴ける滅多にない機会だし、ツィンバロンの演奏を上から見下ろすことができ。貴重な体験となった(第3曲と第5曲に独奏的に登場)。あくまで何度か聴いたことがあるという程度しか知らないので、本日の演奏が良かったのか悪かったのか、見当が付かないが、ツィンバロンだけでなく、ビアノやチェレスタまでも加え、さらに多彩な打楽器群を駆使しての演奏には、見ていたもなかなか緊張感があって、素晴らしかったと思う。もとが音楽劇だけあって、劇的な盛り上がりを聴かせる部分では、フル・オーケストラの大音量が圧巻だった。このような曲をプログラムに採り上げ、本気で演奏してくれるアルミンクさんの情熱にBravo!!

サイン会のコパチンスカヤさんとアリスちゃん。右はアルミンクさん。
演奏会の後は、コパチンスカヤさんとアルミンクさんによるサイン会があった。コパチンスカヤさんはかわいらしい娘さんと一緒で、楽しそうだった。こうして見るとごく普通の人。演奏している時のエキセントリックな姿とは完全に別人だ。アルミンクさんもファンに日本語で挨拶しながら,丁寧に応対してくれる。新日本フィルは今後も聴く機会はあるだろうが、これまで聴いた感じでは、アルミンクさんが指揮するときは、すごくイイ感じだと思う。特に期待しているのは、来年(2011年)4月、新国立劇場のオペラ公演「ばらの騎士」で、アルミンクさん指揮の新日本フィルがピットに入ること。ウィーンの香りを是非聴かせていただきたいものである。
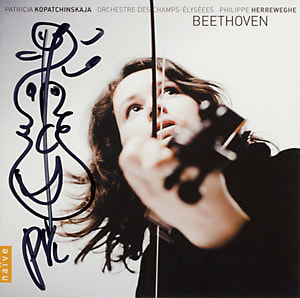
購入したベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のCDにサインしていただきました。

ついでに本日のプログラムにも。カラーページがなかったのが残念。
























