小学三年生からお坊さんへの質問
Q5 お母さんがどんなに大切なのですか?
「お母さん」は、この世で替えることの出来ないたった一人の人物です。我々のことを正直に、こころの底から心配してくれる唯一の人です。自分のことよりも子供のことを大事にしてくれる。正直に応援してくれる。励ましてくれる。・・・・・・どんな人にもこの大事な人がいます。誰にでもお母さんが一人いることは、最高に幸福なことです。
なぜお母さんは怒るのか
それはお母さんが自分の大切な仕事だと思ってやっているのです。誤解してはいけません。決してお母さんは子供のことを怒っているわけでも、嫌になっているわけでもないのです。・・・・自分の仕事を一生懸命やっているだけです。
母は自分に命を与えた神さまで、何でも教えてくれる大先生で、苦しいときは一緒にいてくれる第一の友達です。間違いを直してくれる、世の中で恥をかかないで生活できるように指導してくれる先輩でもあります。ですからお母さんがいくら怒っても誰も気にしないのです。母の怒った顔なんかは2,3秒で優しい顔に変わるものです。
しかしお母さんはうるさすぎる・・・
お母さんも普通の人間です。・・・この世で一番難しい仕事をまかされているのです。ですから、すごく心配する。まちがったか、まちがったかといつも独りで悩む。
しかし忘れてはいけません。お母さんも普通の人間です。母も失敗する、間違いもある、誤解もする、疲れる、ストレスもたまる、たまにやってはいけないこともやってしまう。普通の人間だからしょうがないのです。子供はわがままで、お母さんの弱いところは見ようとしないのです。何でも完璧にやってくれると思っているのです。それは無理な話です。
母の失敗や、怒ることなど、気にしない方が正しいのです。母の失敗だったらいつも許してあげることは子供の責任です。完璧な母はいません。・・・・・父親も同じです。
お母さんに逆らうのは悪い?
何でもかんでも母が言う通りにする必要はないのです。母は全てを知っているわけではありません。自分の生き方は自分で決めなくてはなりません。・・・・・母は絶対的に大事ですが、子供は母の奴隷ではない、ということも覚えておきましょう。
お父さんはどこに行ったの?
お父さんもお母さんに負けないほど、子供のことを心配するのです。お父さんの応援がなければ、お母さん一人では子育てはうまくいかないのです。・・・・二人は互いに協力してがんばるのです。
大人にはお母さんがいらないの?
親のありがたさは、自分が死ぬまでつづくものです。どんな大人もこれを忘れてはいけないのです。子供と違って大人は、親に甘えてはいけないのです。大人の仕事は、親の面倒を見ることです。親孝行をすることです。・・・・・たとえ歳をとっても、親は精神的な安らぎを与えてくれるのです。
(「一生役立つ ブッダの育児マニュアル」 アルボムッレ・スマナサーラ長老講義 より抜粋)
これは、親が子に言うことではないですね。これを言ってあげられるのは、第三者。先生、お坊さん。おばちゃん(まみおば)の仕事ですね 。
。
親は、自分が間違った時は「間違っちった」と、失敗したときには「失敗した~」と、分からないときは「よく分からないから調べてみるね」と、ごまかさずに正直に言うべきです。偉そうに何でも分かった風を装わないことです。そして、いつも子供のために精一杯、謙虚に努力することですね(説教や押しつけでなく)。親は子供の先生だけど、親友のように付き合えるといいですね。
お父さんもあれこれ言い訳せず、できることをして、お母さんと仲良く協力してやっていかなきゃね
そして、大人として、親を大事にしたいですね。





















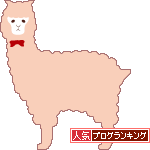
 )
)